モーパッサン
「芸術家の住まい」
« Maison d'artiste », le 12 mars 1881
(*翻訳者 足立 和彦)
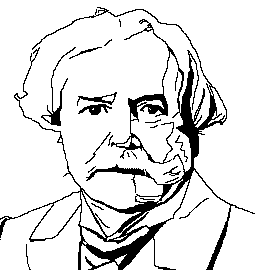 解説 1881年3月12日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois に掲載されたエドモン・ド・ゴンクール『十九世紀のある芸術家の住まい』 Maison d'un Artiste au dix-neuvième siècle についての宣伝記事 。
解説 1881年3月12日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois に掲載されたエドモン・ド・ゴンクール『十九世紀のある芸術家の住まい』 Maison d'un Artiste au dix-neuvième siècle についての宣伝記事 。エドモン・ド・ゴンクール(1822-1896)は弟ジュール(1830-1870)とともに創作を始め、『ジェルミニー・ラセルトゥー』(1865)は下層階級の庶民の生活を小説に描き、自然主義文学の先駆けとも言える作品。弟が早くに亡くなった後、エドモンは一人執筆を続ける。浮世絵などの日本美術に造詣が深かったことも有名。また日記(1851-1896)を生前から刊行。この時代についての貴重な資料であり、各種ゴシップにも詳しい。
モーパッサンが最初に日記に登場するのは1875年。その後継続的に登場するが、彼が作家として成功して以降、エドモンの言葉には辛辣なものが多い。「今晩、私は、長い間探しながら見つけられないでいた、この人物を特徴付ける定義を見出した。すなわちノルマンディー出身の若い博労のイメージであり、その典型。」(1887年2月2日)
「署名のないモーパッサンの一ページ、それはまったく、万人に属する今時の良く出来た模写に過ぎない。」(1888年1月8日)等々。
『ピエールとジャン』冒頭「小説論」でモーパッサンは「芸術的文体」を批判するが、暗にエドモンを指したものと一般に考えられている(エドモン自身がそう受け止めた)。両者の間の文体に関する見解の相違は決定的であるが、一方で「成功者」モーパッサンに対し、世間に広く受け入れられることのなかったエドモンに嫉妬があったのも確かのようだ。
「どうしてある種の人々にとっては、エドモン・ド・ゴンクールは紳士で、趣味人で、文学と戯れる貴族と映り、どうしてモーパッサンは真の文学者ということになるのだろうか? どうしてなのか教えて欲しいものだが?」(1887年3月27日)
モーパッサンの側としては、この年長の作家に対して常に敬意をもって接しているが、ゾラに対するような親しさはみられない。書評兼紹介の本記事も、その意味ではいささか儀礼的な感じがするけれど、「お宅訪問」のルポルタージュ的語りに芸を見せている。
それにしてもモーパッサン自身の「日本美術」観には多分に誤解が混じっているように見受けられるのだけれど、果たしてどうなのだろうか。
***** ***** ***** *****
本日、シャルパンティエ書店は著名な作家、エドモン・ド・ゴンクールの新著を発売する。
この書はこの大家の作品の中でも独特のもので、同じ著者の他のどんな本にも似ていない。
それは、彼を有名にしたような小説の類ではない。それは『十八世紀の女性たち』や『ルイ十五世の愛人たち』のようなあの魅惑的な歴史研究の一つでもない。『思想と感覚』のような哲学的な書物でもない。それは、彼の家具についての本なのである。
この書物の題は『十九世紀のある作家の住まい』という。実際、彼の家以上に訪れてみたくなるような住居はない。十八世紀芸術の要約であると同時に、東洋の傑作を一望にできる絵画であり、中国、日本のまばゆいばかりの工芸品について、視覚に訴えかける物語なのだ。
それというのもゴンクールは生まれついての装飾愛好家なのである。誰よりもそうなのであって、まさしくそこに彼の悪癖が存在するのだが、それは誰もが備えているような、愛すべき、出費の嵩む、身を持ち崩させるようなあの悪癖である。
見事に彼はそうなので、店内で置物を物色するように、生涯にわたって歴史の中にも装飾品を集めてきた。二人の兄弟にはこの情熱があった。小説を一本書き終えるやすぐに、熱愛する十八世紀の方へと二人揃って改めて出かけて行った。彼等はこの世紀を競売吏のように経巡り、隅々まで嗅ぎ回り、出来事や年代の配慮は教授連に任せながら、生活のあらゆる細部から風俗を再現し、小説家として歴史を作り出すのであり、それは扇、献立表、靴下留、レース飾り、靴の留め金、煙草入れ、真の生きた歴史をもって成される。同時に、売り立てや埃っぽい店内を通り抜けながら彼等が追い求めたのは、当時はあまり評価されていなかったあらゆる昔の装飾品や、大家の手に成る絵画、デッサン、版画であり、書籍、稀覯な、または一冊しかないような書物、そして古物商に訪れる偶然の機会と、疲れ知らずの忍耐とが彼等の手中にもたらしたあらゆる品々であった。
彼等の内の一人は亡くなった。もう一人は休みなく収集を続けた。彼は今日存在する中で、十八世紀フランス美術の最も美しく、最も完璧なコレクションを所有しているのである。
彼は自ら、自身の住まいの扉を公衆に開いてくれるだろう。
だが公衆よりも先にそこへ入ってみよう。さて、作家自身も在宅なので、我々は彼の姿を目にし、話しかけることも出来るだろう。
***
それはオトゥイユ、モンモランシー大通り、鉄道の環状線に面した愛らしい一軒家である。玄関から「骨董品の愛好家」の家にいることが感じられる。玄関や階段の壁がそれで覆われている。主人の書斎は二階にある。彼は机に向かって書き物をしている。それから立ち上がる。髪は長く灰色だが、灰と白との中間の特別な灰の色合いで、その陰影が幾晩もの疲れと、長時間に及ぶ頭脳労働を物語っているように見える。その髪に縁取られた顔には、稀に見られる繊細さがある。彼自身が最も美しい陶磁器について言いうるように、良き時代、良き銘柄の真に貴族らしい顔立ちである。彼はただ口ひげだけを蓄えている。背が高く、細身で、いくらか冷ややかな落ち着きを湛えている。彼の住まいはまさしく彼に相応しい額縁だ。
彼が以下のように記したのだった。「太って重々しい政治家、角ばった靴を履き、田舎者風の、あばた面、太った種で、政界のペルシュ馬とも呼びうる人物がいるものだ。」
もしこの「ペルシュ馬」の種が文人の中にもいるものなら、彼はあらゆる点においてその正反対である。
書斎に入るや否や、天井の明かりが視線を惹きつける。日本の絹で出来ていて、あまりに色彩豊かなので目がくらんでしまうほどだ。驚くべきレリーフのグリフォンが牡丹の園を駆けている。想像上の動物が四肢をよじって、光のように輝く見事な花々の中を跳ね回る。それは役者の衣装のようだ。我等が最も狂奔な女優達でさえ、これほど贅沢なものは持っていない。
至る所、壁には書物が並べられている。貴重な書物であり、彼はその詳細なカタログを我々に見せてくれるだろう。書棚の引き出しには日本ものの、値も付けられないような貴重なアルバムが眠っており、優に一財産に値する。恐らく彼は、この日本美術の持つ芸術的価値、優美さや魅力を最初に理解した者であり、今日になって芸術家はそこからインスピレーションを得ているのだ。既に1852年には「中国の扉」店で、こうした美しいアルバムの一冊を八十フランで購入していた。今日ならそれに幾らの値がつくだろうか?
さて我々は聖域へと移ろう。すなわち収集品の部屋へ。ここを支配するのは中国と日本だ。部屋の周りをぐるりと、大きなガラス戸棚の内に宝物が収められている。磁器に関してなら、枝に止まった一羽の鳥を描いた皿は、これ以上完璧な品を私は見たことがない。
ここには日本の象牙細工がある。彼は見事なコレクションを持っている。あるものは水辺を走る武士を表現していて、比類のない技術によるものだ。別のものは、葉の下にとぐろを巻いた蛇を見つめる「死」を表している。「死」は身を屈め、その動きの中に、この毒を持った生物に対する好意的な興味と優し気な関心とが感じられる。こちらには貝を齧る猿、その顔は余りにも滑稽だ。こちらにまた、驚くほど本物そっくりの鼠である。こうして見ると、彼方では、家族の中で父から子へとわたって、職人達は同じものを作り続けているようだ。だから、四世代もが鼠を作り続けた時には、ほとんど「自然より一層鼠」なるものを作り上げたとしても驚きではない。
こちらの別のガラスケースには、自分の腹を切り開くための刀が並んでいる! これらの刀の鍔は真の宝石である。事実、それらは煙管、ケースや他の細々とした品と共に、日本の装身具を成している。これらの鍔の一つは、同時に夢想と色彩の国たるこれらの国々の不思議な詩情を要約するかのようだ。片面には二匹のコオロギが見られるが、二匹の小さなコオロギは思想家のような容貌をしていて、仲良く並んで、話しながら、おしゃべりをしながら(彼等の様子からそう感じられる)、柳の枝で編んだ籠が壊れて逃げ出して来たところ。逃亡する二人の囚人なのだ。
鍔のもう一方の側は二枚の落ち葉を描いているが、冬空の下、月光を浴びながら、広大な空間の中に孤立して旋回している。
これらの繊細な風景の中には、意図をほとんど察することの出来ないような陰影や、たくさんの夢想が、夢の霧のように存在している。
こうした素晴らしい品々を展示した部屋の隣にまた別の部屋があり、それは色彩豊かな傑作である。そこを描写してみようとは思わないけれど、その特別な目的については言及しておこう。そこは作家にとっては「インスピレーションの手段」、脳を刺激するための部屋なのである。
仕事にとりかかろうと思う時、彼はそこに閉じ篭り、そこにある視覚芸術に酔いしれる。彼はそれを呼吸し、浸りきる。それから、「ちょうど良い」と感じた時、十分に燃え上がった時に、戻って机の前に座るのである。彼はそこで書きたいと思うだろうが、そうすることは出来ないだろう。それほどに目は絶えず壁の光景に奪われてしまう。
一階は十八世紀の領域である。このコレクションは唯一無二のものだ。そう言えばアルザス‐ロレーヌの展覧会に、彼から貸し出された見事なデッサン画が思い出される。ここには最も偉大な者達の中でも大家たるワットーがあり、ブーシェ、フラゴナール、シャルダンがある。クローディオンによる暖炉棚の置物には値のつけようもない。
食堂には賞賛すべきタピスリーがかけられ、一面に籠を持った貴婦人達が描かれていて、目を酔わせてくれる。
そしてまだなんと多くのものがあることか!
***
『思想と感覚』と題された見事な書物の中に、次のような考えが述べられている。
「芸術品のコレクションの中には、情熱も、趣味も、知性さえも認められず、ただ富の粗雑な勝利しか見られないものがある。」
エドモンとジュールのゴンクール兄弟によって集められたコレクションは、反対に情熱と趣味と知性の勝利である。
兄弟がパリにやって来た時にはわずかな財産しかなく、他の者ならば生きていくだけで精一杯だっただろう。だがそれでもって彼等は、まだ評価されていないが、やがては評価出来ないほどの価値を持つに至る品々を買う術を知っていた。
彼等が執筆の疲れを癒す方法は、古道具屋を漁り、ある種の版画商が屋根裏に保管している未探索のデッサンの山に目を通すことだった。はずれ知らずの嗅覚を備えていたので、大家のクロッキーを見つけ出しては、宝物のようにそれを持ち帰った。彼等にとっては、人生において人並みの満足、快楽、情熱は存在しなかった。「装飾品」こそが彼等を誘惑した。そして何か重要な品を購入した時、一月か二月の間所有熱に襲われた時には、財布は空に、手に入るはずの金も遠ざかり、二人は姿を消し、隠れて、どこか田舎の宿屋に潜んでは、慎ましく倹約して暮らしながら、次の買い物に期待するのだった。
とても長い間苦いものであった人生において、この情熱が彼等の力、避難所、そして慰めであった。
大衆を相手取った激しい戦いの内に一人は倒れた。大衆は彼等の偉大な才能を否定し、理解せずに嘲笑したのだった。そして今に至り、生き残った一方は、突然に賞賛され、喝采を受け、大家として崇められるようになった。
こうした不公正、群集の抱く無意識的な残酷さは日常茶飯である。バルザックは述べた。「このパリの公衆、彼等にあっては普通、からかいが理解にとって代わる・・・」――この言葉は驚くばかりに正しい。理解しない時には、群集とは軽蔑するものである。そして彼等は決して早すぎた者、ゴンクール兄弟のように先鞭をつける者を理解しないから、そうした者達を迎えることに同意が得られるためには、彼等は死ななければならないということになる。エドモン・ド・ゴンクールはしかしながら、自分の時代がやって来るのを生きて目にした。この洗練され、繊細で、全く新しい芸術が遂に理解されるようになった。その芸術はニュアンスの中のニュアンスを、無限の繊細さを、事物の持つ苦悩を掴みとる。
弟と彼とは探求者である。過去の探求者、生活の探求者、そして言葉の探求者である。彼等は至る所、過去に、生活の中に、言葉の内に、知られることのなかった富を発見してきた。
弟が亡くなっても、エドモン・ド・ゴンクールは仕事を続けた。彼は絶えず働き続け、それは彼自身の言に、また彼の記した言葉によれば、存在から逃れるためであった。「現実に対する人間の恐怖から三つの逃避手段が生まれた。酔いと、恋愛と、仕事と。」
本日世に出る書物の後、彼はまた小説に取り掛かるだろう。その小説が全てを忘れさせ、作家をフィクションの中に運び去り、そこに巻き込み、そこで宥め、地上から離れさせ、彼自身の世界、彼によって作られ、芸術に照らされた、創造者にとっての理想的な世界に彼を生きさせることだろう。
『ゴーロワ』紙、1881年3月12日付

