ジュール・ルメートル
「ギィ・ド・モーパッサン」
Jules Lemaître, « Guy de Maupassant »,
le 29 novembre 1884
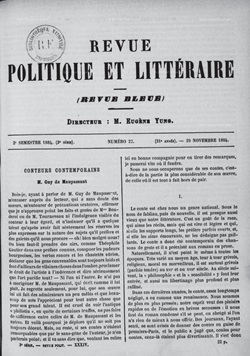 解説 1884年11月29日付、『政治文学評論』 Revue politique et littéraire に掲載された、ジュール・ルメートルによる批評。「現代の短編作家 ギィ・ド・モーパッサン氏」のタイトル。1886年に評論集『現代人』第1集に収録される(Les Contemporains, H. Lecène et H. Oudin, série 1, 1886, p. 285-310.)
解説 1884年11月29日付、『政治文学評論』 Revue politique et littéraire に掲載された、ジュール・ルメートルによる批評。「現代の短編作家 ギィ・ド・モーパッサン氏」のタイトル。1886年に評論集『現代人』第1集に収録される(Les Contemporains, H. Lecène et H. Oudin, série 1, 1886, p. 285-310.)ジュール・ルメートル (Jules Lemaître, 1853-1914) は批評家。高等師範学校を卒業し、ル・アーヴルで高校教師を務めた後、1880年代にアルジェ、ブザンソン、グルノーブルの大学で文学を教える。『政治文学評論』、日刊紙『タン』などに評論を執筆し、『ジュルナル・デ・デバ』紙に長く劇評を掲載した。主な批評は『現代人』(Les Contemporains, 7 série, 1886-1899) に纏められる。89年『反抗する女』La Révoltée 以降、自身で劇作を手がけた。
1895年アカデミー・フランセーズ入会。1899年に反ドレフュス派の団体「フランス祖国同盟」 Ligue de la patrie française 設立に参加、代表を務めた(1904年解散)。1908年創設の右翼団体「アクション・フランセーズ」にも加盟している。
 本評論でルメートルは、1880年代に入って短編小説が流行していることを示したうえで、モーパッサンは17世紀におけるラ・フォンテーヌと似ているとする。そして両者の比較から、レアリスム、悲観主義、官能性をモーパッサンの特徴として挙げている。さらに、モーパッサンは形式において「古典作家」であるとし、「彼の散文は卓越した性質を備え、実に明瞭、実に的確にして、実に無駄がない」と称えている。保守派の論客であったルメートルのこのような評価は、その後のモーパッサン評にも影響を与えると同時に、モーパッサンを早くから「若き大家」へ押しあげることに貢献した。
本評論でルメートルは、1880年代に入って短編小説が流行していることを示したうえで、モーパッサンは17世紀におけるラ・フォンテーヌと似ているとする。そして両者の比較から、レアリスム、悲観主義、官能性をモーパッサンの特徴として挙げている。さらに、モーパッサンは形式において「古典作家」であるとし、「彼の散文は卓越した性質を備え、実に明瞭、実に的確にして、実に無駄がない」と称えている。保守派の論客であったルメートルのこのような評価は、その後のモーパッサン評にも影響を与えると同時に、モーパッサンを早くから「若き大家」へ押しあげることに貢献した。なおルメートルは、1881年にアルジェリアでモーパッサンと出会っている。本評論以後も、モーパッサンの文学を高く評価し続けることになる。
***** ***** ***** *****
ギィ・ド・モーパッサン
ギィ・ド・モーパッサン
ギィ・ド・モーパッサン氏について話さなければならない時、恐らくは風紀よろしい読者に向かって弁解し、弁論家なみに用心を重ねたうえで、ボンドロワ夫人やトゥルヌヴォー氏の行いや身振りにも、彼らに向ってのこの短編作家の明白な寛大さにも少しも賛同しないことを断言し、彼にいくらか才能があることをほのめかす前に、彼の好む主題の性質と、彼が我々に呼び起こす陽気さについて、最大限に厳格な留保を付さなければならないのだろうか? ――おお! まったく我々の意に反してまでも? あるいは、尊大ぶって、よく知られた序文におけるテオフィル・ゴーティエ(1)のように、ブルジョアの羞恥心、すえたような美徳、酸化した貞操を罵倒し、礼儀正しい人というのはいつでも醜く、さらに陰では恐ろしいことまで行っているものだと宣言し、猥らさに対する芸術家の権利を主張し、芸術はすべてを純化するのだと真面目に言うべきなのだろうか? どちらでもないのである。私はモーパッサン氏に説教するべきではない。彼は彼の好むように書いている。私が彼のために遺憾に思うのは、彼の作品が生み出した称賛者が雑多な集団をなしていること、多くの愚かな者たちが、彼の偉大な才能とはまったく別のものにおいて彼を評価しているということだけなのだ。昔ながらの「俗物」が、ある種のトリュフを求めていながら、モーパッサンのそれと他のものとを区別しないのを目にするのは残酷なものである。そういう訳で、彼がいつでも慎み深いわけではないことを私は嘆くのだ。けれども、そもそも彼の短編が作者の無遠慮さのみにおいて注目に値するのであれば、私がそれについて語ることもないだろう。言うまでもなく、良き仲間としてここでそれらを読み返し、そこから考察を引き出そうと思う私は、必要な所へ急いで移ってゆこう。
我々は彼の短編のみを考慮することにする。すなわち、彼の作品の中でもっとも大きな部分であり、彼がまったく他に抜きん出ている領野である。
I
短編小説というのは我々の国民的なジャンルである。ファブリオー(2)の名、それからヌーヴェルの名で呼ばれ、我々の文学と同じくらいに古くからあった。それは民族の趣向であり、この民族は物語を愛しているが、生き生きとしていて軽薄で、長い物語を我慢できるとしても、しばしば短いもののほうを好み、感動的な話が好きだけれども、陽気であることも厭わない。したがって短編は武勲詩と同じ時代のものであり、散文による長編小説よりも前に存在した。
もちろん、いつの時代にも同じだったわけではない。中世にはとても多様で、猥らだったり、宗教的だったり、道徳的だったり、驚異の物語だったりした。16世紀、17世紀にはとりわけ猥ら(時には優しげ)であった。その次の世紀には「哲学」や「感性」が入ってくるし、より深く、より繊細な放蕩も加わったのである。
最近では、長いあいだ見捨てられていた短編小説がルネサンスを迎えている。我々は一層忙しくなり、我々の精神は短時間の快楽、短い衝撃による感動を望んでいる。可能ならば凝縮された長編、他により良いものがないなら要約された長編というものが必要となっている。新聞はそれを感じ取り、冒頭記事の代わりにコントを提供することを思いつき、公衆はどうせお話ならこっちの方が気晴らしになると判断した。そういう訳で短編作家のプレイアッド派が登場した。まずアルフォンス・ドーデ(3)、そしてポール・アレーヌ(4)。それから特殊なジャンルにおける『パリ生活(5)』誌の短編作家たち、リュドヴィク・アレヴィー(6)、ジップ(7)、リシャール・オーモンロワ(8)。そして『フィガロ』紙や『ジル・ブラース』紙の者たち、コペー(9)、テオドール・ド・バンヴィル(10)、アルマン・シルヴェストル(11)、カテュール・マンデス(12)、ギィ・ド・モーパッサン、それぞれに流儀があり、幾人かは大変愛らしい流儀を備えている。
我々の同時代人によるこれらの短い物語は、人が思うのとは違って、我々の昔の文学の短編作家たちのもの、ボナヴァンチュール・デ・ペリエ(13)、ラ・フォンテーヌ(14)、グレクール(15)やピロン(16)のものとはまったく似ていない。これら古老にお馴染みの主題がどんなものだったか、彼らの冗談のほとんど唯一の主題については人の知るところだ。そしてその種のものはいつでも人を笑わせるし、もっとも厳めしい人もほとんど抵抗できない。どうしてなのか? ある種のイメージが心地よいものであることは理解されよう。何故なら人間とは弱いものだからである。だがどうしてそれらが人を笑わせるのか? どうして恋愛喜劇の粗雑な側面が誰をも喜ばせるのか? それは、実際にそれがまさしく喜劇であるからだ。恋愛の話しぶりや感情と、その儀礼の内で容易にグロテスクたりうるものとのあいだに見られる対比は、皮肉で楽しいものだからである。そしてそれはまた、しっかりと規制され、また叱責を受けもし、予防のための法律、道徳、信仰によってすっかり包まれているような社会において、問題の本能による永遠にして打ち克ち難い反抗が我々に与えてくれる喜劇なのである。――その反抗は、もっとも思いがけない瞬間に我進んで炸裂し、もっとも尊敬すべき衣装をまといながら、突然に、もっとも確かな尊厳、あるいはもっとも安心できる無邪気さをも否定し、もっとも強大な権威、あるいはもっとも周到な用心深さの裏をかく。そして恐らくは同様に、劣った自然が社会の慣習に対して行ういたずらは、この世に生まれ出たすべての者が備えている本能的な反抗心、自由な生活への趣向をくすぐるからであろう。したがって、気難しく微妙なことを言うにしても、そうした事柄が笑わせるということは否定できないし、我々の父祖たちの安易な陽気さの中にも、いくらかの哲学が存在したのである。
この汲みつくすことない古来の資産を、今日の短編作家たちのうちに、とりわけここに名を挙げる必要のない3、4人の者の内に見いだすことができる。だが興味あるのは、モーパッサン氏の内にあって、そこに特別に付け加えられているものを探し求めることなのである。私には、彼が往年の短編作家の気質と趣味とを備えているように思われるし、フランソワ1世の治下ではボナヴァンチュール・デ・ペリエのように、ルイ14世の治下ではジャン・ド・ラ・フォンテーヌのように語ったであろうと想像できる。したがって、彼が明らかに彼の世紀、周囲の文学から受け継いだものについて見よう。そしてその後に、にもかかわらず、どのようにして、また何故に、我々は彼をこのジャンルにおける古典作家と見なすのかを述べることにしよう。
II
確かに次のように言うことで、愚かな見当違いをするということはないだろう。すなわち、我々にとってのモーパッサンの短編は、同時代人にとってのラ・フォンテーヌの短編と同じようであっただろう。それゆえ、二人の作品集を並べてみることで、時代と作家の相違についての示唆に富んだ省察を素描することができよう。
ラ・フォンテーヌの短編は、学校の座席において、「自習監督」のわずかな動きにもヴェルギリウスで本を覆えるように構えながら読まれる、禁じられた書物である。モロンヴァル校の悪童たちなら、日曜の短いミサの間にも教会の中で読み、そのことを自慢する。少なくとも彼らは読んだと信じているが、彼らが求めているのは一つのことだけだ。学校を出た後では、現代文学を貪るように読む。そしてたまたま、アンリエット・ダングルテール(17)を魅了した小さな物語が改めて掌中に収まることになれば、もう色褪せたものと感じられるだろう。だがもっと後になって、すべてを読み尽くし、食傷しないとしても冷静にはなった時に、読んでいる内容から距離を置いて、ただ知性のみの関心を惹き、感動させるような娯楽として楽しむことができるようになった時には、ラ・フォンテーヌの短編は、その時代において眺められるし、いくらか昔の愛らしい見世物のように、大変に気晴らしになりうるのだ。この陽気な世界は、ほとんどすべて人工的であるのだが、それゆえにこそ我々の気に入るのである。7、8人の人物は、イタリア喜劇のようにいつでも同じである。修道士と司祭、ラバ引きと農民、商人のお人好しの夫やフィレンツェの判事、若者、尼さん、うぶな娘、女中やブルジョアのお上さん、それぞれが自分の役割と不変の容貌を持ち、その属性にあることしかしない。何人かの夫は除いて全員が、生きることに満足し、愉快でからかい好きなユーモアを備え、そして全員が、頭巾に縁どられた顔を赤くして、この世でたった一つのことに気を奪われている。たった一つでそれ以上ではない。舞台としては修道院、庭、宿屋の一室、あるいは漠然とイタリアの宮廷。とんでもないいたずら、変装、入れ替わり、取り違えがあり、偶然と、本当らしくもないほどの信じやすさに頼った軽薄な作り話。生来の極端さや愛らしいまでの善良さが、この種のあらゆる空想において見受けられる。そしてあちらこちらに、少々の現実味、生きた現実から取られた特徴が見られるが、それらは散らばっていて、偶然に捕まえられたものだ。時々はまた、感じ取られた風景の一部、真の愛情の一筋、憂鬱の小さな影・・・、以上が全体におけるラ・フォンテーヌの短編小説である。人物と主題は人工的で単一的だが、にもかかわらずこれらの小品は、腕前と、伝達不能の優美さとによって魅力的であるのをやめない。けれども直ちに、今日の短編小説が、2世紀前のそれと何において異なるのかは予測されるだろう。
私は、素材がよく似た「お人好し」〔ラ・フォンテーヌのあだ名〕の短編一編とモーパッサンの小話一つを見つけて、二つの話を並べてみるだけで我々が探しているものが明らかになるようにしたいと思う。けれどそうしたものはまったく見つからない。それはまさしく、モーパッサン氏が物語の主題や細部を身近の生きた現実から借りているからなのである。せいぜい、「クロシェット(18)」と、あえて望むなら「野あそび」とのあいだに、いくらかの類似が見られるのを除いてはだが、それというのもどちらにおいても、永遠の「牧歌的恋愛」が問題となっており、春、青年が娘を森へと連れて行く。ラ・フォンテーヌの短編は50行である。魅力があり、偶然にも軽妙で甘美な真の詩情が見られる。思い出されることだろう、青年が
牧場、小川のほとりで、
若く美しい娘のご機嫌をとった。
歯は白く、裸足で、可愛らしい体、
イオが鈴を下げたまま
草をはみに行く間に・・・
そして「青年」は「夜が近づくと」一頭の牝牛を道に迷わせ、その鈴を塞いでしまう。そして最後の詩句は、引き伸ばされ、漠とした魅力あるものだ。
おお美しい娘たちよ、お避けなさい
森の奥と、その広大な沈黙とを。
さて、「野あそび」においては、どのようにすべてが明確となり、「現実化」するかをご覧頂きたい。思いだしてもらいたい、デュフール夫妻、娘のアンリエットはブゾンのガンゲットでブランコに乗っており、それに二人のボート乗り、そしてイル=オ=アングレの小さな森、母親の散歩は娘のそれと対になり、背景にはデュフール氏と髪の黄色い青年、将来の婿だ。それらすべてが牧歌に皮肉な現実の味わいを与えているのであり、それは代わる代わる悲しくもあれば、グロテスクでもある。ラ・フォンテーヌのヒロインが「可愛らしい体」の若い娘であることにご注意頂きたい。モーパッサン氏のヒロインは赤毛で大柄の娘である。この相違は何でもないようだ。しかしながら相違は結果において大きなものとなる。それは二種の異なる詩学を意味しているのだ。
同様に、モーパッサン氏の筆にかかれば「恋する遊女(19)」がどんなものになるか問うてみることもできよう。短編は大変可愛らしく、真に感動的で優しいものだ。だがそれはどこか知らないところで、私が思うには恐らくイタリアで起こる。「場所」はどこでもなく、人物には何の個人的特徴もない(これを批判と受け取らないでもらいたい。ただの指摘でしかないのだから)。明らかに、モーパッサン氏なら同じ主題を語りながらも、まったく違った風にそれを扱っただろう。私が推測するには、コンスタンスは、イタリアのコントの、優美で、半分だけ現実的な人物ではもはやないだろう。一人の「娘」であり、幾らかの個別的な徴を備えているはずだ。男の方は学生、あるいは画学生、または商店の店員だ。私は想像するのだが、物語はビュリエ〔当時有名だったダンスホール〕で始まり、同じように現実的などこかの一隅で幕を閉じる。そして見聞された多くの事物があり、筋の周囲には多くのディテールが配され、それは特徴的で、うっとりともさせ、ピトレスクであったり、残酷であったりするのだ。時に私は思うのであるが、『サッフォー(20)』の最初の30ページは、現代の趣味に合わせた「恋する遊女」以外の何であろうか?
我々の気に入るものとはつまり、我々の祖先の気に入ったものとはすっかり異なっているであり、第一に、モーパッサン氏にあっては短編小説はレアリストなものになった。彼の素材を見渡してみるといい。ほとんどすべての内に、通りすがりに捕えられた小さな事柄があり、それは何らかの点で興味深い、というのも愚かさや、無分別、エゴイスム、時には人間的な善良さの証拠であるからだ。あるいは、思いがけないコントラストや、事物のもたらす皮肉によって喜ばせるものであって、いずれの場合にも現に「起こった」物事か、少なくとも、生きたものに対してなされた観察があり、それが作家の精神の内で少しずつ、小話の生き生きとした形体をまとったのである。
そしてその時に、昔の短編に出てくるラバ引き、庭師や百姓、マゼやピエールの大将の代わりに、我々には農民の男や女たちがいるのであって、たとえばヴァランとっつぁんと女中のローズ、オーモンとっつぁん、オッシュコルヌとっつぁん、シコのとっつぁんやマグロワールのお上さん、さらにどれほど多くの他の者たちがいるだろう(「いなか娘」、「ひも」、「木靴」、「酒樽」等)! 境遇や顔つきの似通った立派な商人や法律家の代わりに、金物商人のデュフール氏、海軍省の第一書記であるカラヴァン氏、裁縫材屋のモランがいる(「野あそび」、「家庭」等)。陽気なお上さん、陰険な尼さんの代わりには、小柄なルリエーヴル夫人、マルロッカ、ラシュレ〔ママ〕、フランチェスカ・ロンドリがいる(「奇策」、「マルロッカ」、「マドモワゼル・フィフィ」、「ロンドリ姉妹」)。それに、ラ・フォンテーヌの修道院を、モーパッサン氏がどんなそれで置き換えたのかは言わないでおくとしよう。
このレアリスムの一つの帰結は、これらの短編が常に陽気ではなくなったということにある。悲しい短編があり、とりわけ極端にまで荒々しい短編が存在する。そのことは避けがたい。主題の多くが取られているのは、本能が一層強く、一層盲目的であるような階層であり、「環境」なのだ。それゆえに、常に笑っていることはほとんど不可能となる。古いゴーロワ流のコントから、現実の世界のどぎつい日の下へと移るや、ほとんどすべての人物は醜く、あるいは陰鬱なものとなる。そして、例えば、「美しい娘」、一般的に気軽に、愛らしく刺激的な存在として着想された
気楽な子どもたちを喜ばせる(21)
ような雅な娘と、現にそうあるような、身分と様子と言葉の内に真実があり、分類された、いや分類される以上に登録された娘との間には、どれほどの相違があることだろう! それはもはやまったく同じ人物ではない、だがすべてに勝るのである。同じことが他のすべての人物についても言える。
加えて、その自然な陽気さにもかかわらず、彼の世代の多くの作家たちと同様に、モーパッサン氏は気難しさ、人間嫌いの風を装っており、それが彼の多くの物語に、過剰なまでに苦い味わいを添えている。明らかに、欲望にまで還元された愛情(「狂人か?」、「マルロッカ」、「たきぎ」、「ポールの恋人」等)や、エゴイスム、粗野、生来の残酷さといったものの荒々しい表現を彼は好み、探究している。彼の描く農民だけを話題にするとしても、ある者たちは、祖父の遺体の上でブーダンを食べているが、その遺体は、自分たちがベッドで寝られるように長びつの中に押し込まれたのだった。別の者、ある宿屋の主人は、ある老婆の死に利益を見出し、彼女を「極上の」ブランデーで殺して陽気に厄介払いする。別の者、ある愚直な男は、女中を力づくでものにし、結婚してから、彼女が「がき」を生まないのを理由に暴力を振るうのである。別の者たち、彼らは法の外にいる密猟者、セーヌの密漁者だが、装填した銃で年老いたロバを殺して大いに楽しむ。それから私は、プロイセン人と一緒の聖アントワーヌの陽気さをお勧めしよう(「クリスマスの夜食」、「酒樽」、「田舎むすめの話」、「ロバ」、「聖アントワーヌ」)。
モーパッサン氏が好んで探し求めるのは、概念や出来事の最も皮肉な組み合わせ、最も予想外で、最も衝撃的で、我々の内の幻想や道徳的思いやりを傷つけるのに最も相応しいような感情の組み合わせであり、――滑稽と官能は、幸運なことにいつでも、こうしたほとんど冒涜的な組み合わせと混ざり合っているが、それはまさしくそれらを純化するためではなく、それらが耐えられないものになるのを防ぐためなのである。――他の者たちが戦争と、それが戦場や家族の内にもたらす影響を描いたのに対し、モーパッサン氏は、同じ題材の内からまったく彼自身の分を選り分けると、特別な世界や、一般に換言的に指し示される家の中においてまで、侵略の余波を我々に示してみせた。脂肪の塊の驚くべき自己犠牲と、彼女の恩義を受けた者たちの無慈悲な振る舞いと感情とを思い出すだろう。そして「マドモワゼル・フィフィ」の中では、ラシェルの反抗、刃物の一突き、鐘の中に隠れ、後に司祭に見送られ、抱擁を受け、最後に偏見を持たない愛国者と結婚する娘を。注意して頂きたいのであるが、ラシェルと脂肪の塊とは確かに、ミス・ハリエット、シモン少年、「洗礼」の司祭(これが全部だと私は思うが)と合わせ、コントの中で最も共感を掻き立てる人物たちである。同じように、「マダム」に連れられて彼女の姪の初聖体拝受へ赴くテリエの寄宿生たちと、そこから生まれる褪せることのないコントラストを見て頂きたい。また、ソムリーヴ大尉が、幼いアンドレに母親のベッドを嫌いにさせるために使った「手段」と、このコント(「アンドレの病気」)から生まれるまことに特別な印象とをご覧あれ。人はこのコントが「ものすごく」滑稽であるのにかかわらず、それが滑稽であっていいものか自問するのである。
これらや、まだいくつかの他の物語の内では、粗野が勝利を収め、人間を滑稽または惨めな動物のように見なす見方、人間性に対する広範な軽蔑が認められるが、その軽蔑は確かに、「人間ノ、マタ神々ノ喜ビ、モノヲ生ミ増ヤス愛ノ神(ウェヌス)(22)」が問題になるや、たちまち寛大になるのではある。そうしたものは、ほとんどの場合において、物語の速さと率直さ、それでもやはり陽気さと、完璧な自然さ、さらに(あえてよく言わないが、おのずと理解されよう)芸術家の官能性の深さそのものによって救われているのである。この官能性は、少なくともほとんどいつでも、我々を卑猥さから免れさせている。
それというのも、その二つの間には大きな相違があるように私には思われるのであって、次のことを指摘しておくのは有用であるだろうが、すなわち、卑猥さはむしろ昔日のコントに見られ、官能性は今日のものに認められる。恐らく、卑猥さとは本質的にある種の主題について「エスプリを発揮する」ことの内にある。それは学生や放埓な老人によるおふざけであり、実はそれは禁じられた何らかのもの、そしてそれに続いて規則の観念を内包しているのであって、それ故にこそ面白みも生まれるのである。官能性はこの規則を無視するか、あるいはそれを忘却する。事物を率直に享楽し、みずからそれに酔うのである。それはいつでも陽気なわけではなく、進んで憂鬱に変わってしまいさえする。それが最初の感触の内に閉じこもるのであれば卑俗なものでもあるだろうし、その時には神学者の言う「思イノ楽シミ」である。だが、一人の芸術家にあっては決してそのようには作用しないのは言うまでもない。反対に、自然かつ抗し難い運動によって、それは詩情となるのだ。存在丸ごとを震わせ、想像力を揺り動かし、終わってしまう束の間のものであるという感情ゆえに、知性そのもの、そして合理的な理性までを揺さぶるのである。少しずつ、微細な感触は汎神論的な夢想の内に開花してゆく。あるいは、繊細なものとなって最高度の幻滅に終わる。「苦サガ湧キ出デ(23)」である。したがって、官能性とは卑猥さよりも軽薄でなく、より美学的な何かなのだ。それが善いものか悪いものか、私は知らない。確かなのは、意志を挫き、破壊するものであり、内的な信仰にとって脅威となるものだということだ。
この官能性が次第に我々の世代に浸入してきているということを正直に告げねばならない。人の言うところでは、それは我々の神経が繊細なものとなり、この方面においてより多くの誘惑があるからであって、また他方では、我々の信仰は強固ではなくなり、抵抗する力を持たないからである。偉大なる精神も、成熟に至る年頃においてこの甘美な悪徳に捕われたし、とりわけ青春時代が厳格だった者の魂においてそうである。『女(24)』や『愛(25)』を読めば、ミシュレ(26)が心穏やかならざることを感じ取るだろう。現代の最も著名な者の一人(27)の最近の著作においては、女性への関心が過剰なものとなっている。『青春の泉』の中のある箇所において、自らの饗宴を断念したことについての半ば打ち明けられた後悔、取り返しのつかない何かについての痛ましい感情が見られないものかどうか、私に教えて頂きたい。つまるところは、緩叙法やニュアンスや軽妙で捉え難い文章に覆い隠されているとはいえ、影のために自らの獲物を手放したことを認めた、老ファウストの欲望と絶望の叫び声である・・・。「後になって、他の美徳と同様にこの美徳の空しさを私は目にした。とりわけ私が認めたのは、人間が貞淑であるということについて、自然は何のこだわりも持っていないということであった(28)。」学士院の一員によるこの宣言は、まさしく素朴な我々を震撼させるものである。老プロスペロの言葉にいう、自然が「こだわりを持っていない」(そして自然はそれを余りにも示している!)というのが本当であるとしても、この美徳が余りに信憑性を失われすぎないこと、およそ、それが個人によって実践されることに社会が何らかの関心を有している、そのことを私としては信じている。その美徳にはそれ自身においてでなくとも、少なくとも通常、意志の最も良く最も決定的な試練であるということによって、それなりの価値があるであろう。それというのも、この面においてみずからを克服した者は、自分自身について多くのことをなしうるからである。けれども、偉大なる思想家たちが取り乱している当今、道徳ぶった演説をぶつような愚かな真似はするまい。ただお願いしたいのは、以上のことを余談とは取らないで頂きたいということである。私が述べたり引用したりしたことすべてから、モーパッサン氏がどれほどの利益を引き出したか、どれほどの無垢さが、彼をして我々の時代の賢明なる箴言を作らせたかが、理解頂けるだろうからである。
なんであれ、純化されもはや思い出と後悔でしかないのであれば、官能性は最も繊細な懐疑論の思索とも結びつくし、芸術における悲観主義や粗暴さとさえ一層よく調和する。何故なら、満たされることなく、最終的には心を乱す痛ましいものであるという性質(「悲しき動物」・・・)ゆえに、官能性は世界をその最も高貴な側面から見ることに決して我慢できず、己を宿命的なものと感じ、自らの内にあるあの宿命性へと進んで至るものだからである。さて、モーパッサン氏は格別なまでに官能的である。自己満足をともなってそうなのであり、熱狂と興奮の内にそうなのである。彼はあたかもある種のイメージや、ある種の感触の記憶に取りつかれているかのようだ。ここでその証拠を提出するのを私がためらっているのが理解されよう。たとえば、マルロッカの物語や、嫉妬ゆえに愛人の馬を殺してしまうあの男の物語(「狂人」)を読み返されんことを。コントを紐解く中で、仮にモーパッサン氏がただ卑猥でゴーロワ的(この場合には笑いによってすべてが救われている)なことがあるとしても、よりしばしば、彼には大いなる官能性があるのを目にすることだろう。その官能性は――どのように言えばよいのか?――決してここにあると定めることはできないが、至る所に溢れ、物理的世界を己の甘美な獲物とするのである。そしてそこでは、すべては詩情によって救われている。最初の粗雑な感触に、周囲の事物、風景、線や色、物音、香り、日中や夜中という時刻、そういったものの印象が付け加わる。彼は深く匂いを味わう(「牧歌」、「ロンドリ姉妹」等を見られたし)。それは実際に、この種の感触がとりわけ官能的であり、また気持ちを和らげるものだからである。だが本当は、彼は世界全体を享楽しているのであり、彼にあっては自然のもたらす感情と愛とは互いに呼応し、混じり合っている。
このような感じ方は新しいものではないが、あれほど多くの陽気な物語の作者にあっては興味深いものだ。それはすでに彼の最初の作品、彼の詩集に認められたのであり、その詩集は偉大な息吹と、欠点にもかかわらず、大変に情熱的な詩情に満ちたものだった。3篇の主要な作品は、自然のただ中における恋愛の物語であり、死が結末をもたらしている。どのような愛か? 抵抗不可能な力、宿命的な欲望であり、それが物理的世界との交流をもたらし(なぜなら欲望とは世界の魂だからである)、それが恋人たちに、悲しみに落ち着くことを許さず、満たされることを狂おしく求めさせるので、死へと導く(「水辺にて」)。「マダム・リュノー事件簿」の著者は、ルクレーティウスの詩やショーペンハウエルの哲学を想起させるような、そうした詩句によってデビューを飾ったのだったし、それがまさしく、ほとんどの彼のコントの「下に」存在するものなのである。
したがって、ゴーロワ精神の古く永遠の源泉に、どれほど多くの新しいものが加えられているかが理解されよう。まず現実についての、とりわけ好まれるのが平凡で荒々しい現実についての観察。古来の卑猥な言葉に代わって、深い官能性があり、自然についての感情によって広げられ、しばしば悲しみと詩情が溶け合っている。これらすべてのものが、モーパッサン氏のすべてのコントに一度に現われているのではない。私は全体の印象を述べているのである。たくましい陽気さのただ中にはしばしば、生来の、あるいは獲得されたものである、フロベールやゾラ氏のと似通ったヴィジョンが見られる。彼もまた、作家たちを襲っている最近の病に侵されてはいる。私が言うのは悲観主義(29)と、奇妙な偏執のことであり、それは、世界を大変に醜く、大変に粗野なものにし、盲目的な本能に支配されているものとして示し、したがって心理学を、古き良き「人間の心の研究」をほとんど取り払ってしまい、同時に、細部や奥行きによって利益を得ようと専心するような偏執であるが、そこにおいては、それ自身においてはほとんど興味をもたらさず、もはや芸術の素材としてしか関心を惹かないあの世界にはまだ到達できていないのである。したがって、作家と彼の作品を味わい、すっかり彼の思想の中に入り込んでしまう者たちにとっての喜びとは、もはや皮肉、高慢、独善的な官能でしかない。理想と呼ばれたものに関する配慮はどこにもなく、道徳についての関心はまるでなく、人間に対する共感も一切ないが、恐らくは滑稽で哀れな人間性に対する軽蔑的な憐みだけがあるのだろう。代わりにあるものといえば、世界が感覚に触れることができる限り、そして感覚を楽しませることができる限りにおいて、その世界を楽しむ細緻な科学、事物に対しては拒み、可能な限り造形的な形態のもとに事物を再現する芸術に対してのみ完全に認められた関心、つまりは人間嫌い、からかい好きで好色な神のような姿勢である。奇妙な快楽、まさしく悪魔的であって、ポール=ロワイヤルの誰かなら――あるいは思想の別の領域においては、バルベー=ドールヴィイ氏(30)が――原罪の結果、好奇心が強くか弱いアダムの遺贈、最初の反抗の賜物を認めるだろう。私は不平ばかり漏らす理想主義者の身になって話すことを楽しんでいるし、恐らくは特徴を集めて誇張しているということもありうる。だが確かに、この高慢で官能的な悲観主義は、今日の文学の多くの底に位置するものである。このような物の見方、感じ方は過去の世紀にはあまり見られない。この神経症的な悲観主義は、我々の古典作家にはほとんど認められないのである。ではどうして、私はモーパッサン氏はその一人だと述べたというのだろうか?
III
彼は形式において古典作家なのである。彼は、古典作家たちが評価しなかったであろうようなある物の見方、感情、好みに対して、古典芸術の持つあらゆる外的な性質を結びつけた。それはまた、そもそも、フロベールの独創的な点の一つであったのだが、モーパッサン氏においては、それがより恒常的に、苦労の跡の見えない形で現われているのである。
「古典的な性質、古典的な形式」と今しがた述べた。正確にはそれは何を意味するのだろうか? それは「卓抜さ」という概念を伴うものである。それはまた明晰さ、簡潔さ、構成の技術を意味している。それはすなわち、想像力や感受性よりも、理性こそが作品の制作を司り、作家がみずからの素材を統御しているということである。
モーパッサン氏は見事なまでに自分のものを統御しているし、それ故に彼は大家なのだ。最初から彼は我々を征服してしまったのだが、その性質とは、我々の国民的精髄の特徴と思われたし、それを要求しようとは思いもしなかった場所にそれを見いだしたうえに、さらには、それが他の作家たちの疲れさせるような気どりを我々に思い出させただけに、一層に味わわれたものなのである。3、4年のうちに彼は有名になったが、これほど急速に文学的名声が確立するのを、長らく目にすることはなかったものである。彼の詩作品は1880年のものである。直ちに、「田舎のヴィーナス」の中には、血気盛んな気質の証言以外の何かがあることが感じ取られた。次に現れたのが「脂肪の塊」、あの傑作だった。同時に、ゾラ氏はある時評文の中で、その作者は文体と同じくらいにがっしりしていることを教え、そのことは我々を喜ばせた。以来、モーパッサン氏は休むことなく、楽々と、堅固な小品の傑作を書き続けている。
彼の散文は卓越した性質を備え、実に明瞭、実に的確にして、実に無駄がない! 今日の多くの者と同様に、彼は十分巧みに言葉を結びつけ、独創的な表現を見出すことができるのだが、それが彼にあってはいつでも大変に自然で、大変にふさわしく、自発的なもと感じられるので、後になってからしかそれと気づくこともない。たまたま文章が幾らか長くなり、「きっぱりと」落ち着くべきところに落ち着いている場合には、その完全さ、平衡、巧みな整いぶりにも注目してもらいたい。すでに彼の詩句は、いかに詩情が豊富で力強いにせよ、むしろ散文家の手になる詩句(いくらかアルフレッド・ド・ミュッセの詩句に似て)であった。そのことは多様な徴に見てとることができるが、たとえば韻に対する意識が低く、それに価値を持たせようという配慮が乏しい点である。また次の点もそうだが、文章は韻や詩句のシステムとは独立して動き、展開し、たえずこれから溢れ出ているのである。詩集の冒頭の詩句は以下のものである。
窓は開かれていた。部屋には
灯がともり、火事のような光を注いでいた。
強い明かりは芝生の上を駆けていた。
向こうの公園は、オーケストラのメロディーに
応えているかのようで、遠くにざわめきが起こっていた。
最初の4行の詩句は、韻の調節上は一詩節なのだが、文の終りがそれを飛び越え、新しい韻を導入している。すなわち一詩節から次の詩節への、一種の句跨ぎである・・・。詩集全体を通して、明確にするのが難しい何かが、詩人の内に散文家の天命を明かしているのである。
散文の自然さ、語彙の良質さ、文章のリズムの簡潔さにおいて古典的なモーパッサン氏であるが、彼はその笑いの質においてもまた古典的である。先ほどは、筋違いなほどにそれを暗いもののように述べ立てたのではないかと心配だ。ただ次のことを記憶に留めよう。すなわち、彼の陽気さは軽薄なものではなく、物事にはしばしば二面(他の面を数えないとしても)あるので、彼が我々を笑わせるのに慣れている一面とは、滑稽であるのと同じくらいに涙を誘うものであって、つまるところは可笑しいもの、可笑しく見えるものとは、ほとんどいつでも、よく考えてみるならば、身体的ないし精神的な歪みであり、苦しみなのである。だがこの種の笑いの残酷さは、最も偉大で、最も称賛されているような笑い話の語り手において見られるものだろう。そしてまた、これらのコントには、純粋に滑稽で、苦い後味の残らないものもたくさんある。つまり、モーパッサン氏が凡庸なままに粗野なのではないなら、彼は凡庸なままに陽気なのでもない。そして彼の笑いは事物そのもの、状況から生まれている。それは語り手の文体や、エスプリの内にあるのではない。モーパッサン氏は機知を弄さない、あるいは、軽演劇作者が言うような意味においては、恐らくはそんなものを持っていないのである。だが何ということだろうか! 辛辣な言葉もなく、凝った言葉もなく、あからさまな意図もなく、文章をひねくりもせずに、規則正しく物語を語りながら、度外れた陽気さを、涸れることない哄笑をかき立てることができる、そういう才能が彼にはあるのだ。ただただ「脂肪の塊」、「テリエ館」、「さび」、「身代わり」、「勲章をもらったぞ!」、「女主人」、「ロンドリ姉妹」の最後、あるいは「遺産」の中のルザブルと美男子マズとの事件を、もう一度お読みになられるように。さて、それらは恐らくは、まさしく小さな主題における偉大な芸術であり、大変に単純な手段によって力強い結果を得ること以上に古典の名に相応しいものはないのである。古典的という形容辞をここで用いるのも悪くないことがご理解頂けるだろう。
モーパッサン氏には、物語や人物描写において、最大限の明晰さが備わっている。単純化する見事な技術と独自の確実さをもって、彼らの容貌の本質的な特徴を見分け、際立たせて見せるのである。心理学に固執する者たちの中には言う者もあるだろう、「驚くべきことじゃない。この人物たちは全然複雑ではないのだから! それにまた、彼は人物を外面から、振る舞いや動作からしか描いていない!」と。――ああ! どうしろとおっしゃるのか? リュノー夫人やオーモンとっつぁんの魂は、実際にごく単純なのであって、モーパッサン氏が好んでいるような地域においては、思想や感情のニュアンスや対立、繊細極まる紛糾といったものにはほとんどお目にかからないのである。一体どうすればよいのか? 世の中とはこのようなものであり、我々皆がそろってオーベルマン(31)やオラース(32)やモルソフ夫人(33)になれるわけではないのだ。そして、この場が相応しいのであれば、私はここで言っておきたいのだが、恐らく、心理分析というものは、人が信じているほどに大きな謎というものでもないのである・・・。――だがミス・ハリエットはどうなんです? どうして彼女はあの画家の青年を愛するようになったのです? この愛は、あの娘の他の感情どどんな風に混ざり合ったというのだろうか! 彼女の過去、彼女の苦しみ、彼女の内面の葛藤、それこそが興味深いだろうに!――私は信じるのである、ああ! そうしたものはごく平凡なものであり、ミス・ハリエットが我々を楽しませ、我々の記憶に残るのは、まさしく彼女が一個の奇妙で滑稽で心を揺さぶる「シルエット」でしかないからなのだと。これらのコントのすべてには、必要なだけの「心理学」が存在している。それは「糸くず」の中にもある。別のジャンルで言えば、「目ざめ」の中にもそれがあり、もしも感情それ自体が稀な感興(ピエール・ロティ(34)のような何か、だがいくらか動詞が多く、形容詞は少ない)と独特な形で結びつくのをお望みであるなら、「シャーリ」の愛らしい奇想の内にその見本を見いだすことだろう。
モーパッサン氏にはまたもう一つの長所があり、それは古典作家固有のものでないにせよ、彼らの内にこそ頻繁に見られ、我々の内においてはごく稀となったものである。彼は最高度な構成の技法を持っており、それは何か本質的なもの、一個の概念や一個の状況に、すべてを従属させる技であって、結果的に、まず一切はそれを準備し、次に一切はそれをより独特でより驚くべきものにするのに貢献し、そこから効果を汲みつくすのである。それゆえに、己を律することをしない他の多くの「敏感」な者たちなら逸脱に身を任せるし、その逸脱は割れ目からでも流れ出るように流れてはそこで自足するのだが、そのような脱線は一切存在しないのである。描写や風景は、まさしく人の言う「場を確立する」のに必要なだけだ。そして描写もそれ自体見事に「構成」されており、際限なく並べられ、どれも同じ価値を持つような細部からなるのではなく、簡潔なものであり、事物から、それを際立たせ、要約するような特徴だけを選び取っている。この大変に明確な技術は、「脂肪の塊」、「家庭」、「遺産」などの十分に長い物語において詳しく検討することができるだろう。けれども「モランの豚野郎」において、最初のページがどのように哀れな男の過失を準備し、説明しているかを少しばかりご覧頂きたい。次いで、いかにすべてが、「あのモランの豚野郎」について定期的に繰り返される叫び声を、よりおかしなものにするのに貢献しているかを。いかに交渉人ラバルブによるアンリエットの誘惑に関するすべての細部が、繰り返される言葉を予想外な、味わい深いものにし、いわば次第次第に力強く皮肉な意味合いで満たしていくか、そして、最後のアンリエットの夫の口において、いかに笑いは深く、堪え難くなるものかを。――明快、単純、緊密で力強く、味わい豊かで根の深い滑稽さに満ちている、それがほとんどすべてのこれら掌編であり、それらは一気に駆け抜けて行く!・・・
今日、多少なりと騒ぎを起こしている短編作家、長編作家の中で、恐らくは最も大胆で、最も慎みのない者が、尊敬すべき古典作家の簡素な完成度に最も近い、というのは、十分に興味深いことである。「脂肪の塊」の中に、修辞学の教則本に記される優れた規則の応用を確かめることができるということも、「いなか娘のはなし」が、彼らの羞恥心に警告を与えつつも、目一杯の教訓と教義を身につけた人文主義者をも満足させるに足るものである、ということもまた興味深い。しかしながら、事実そうなのである。恐らく、モーパッサン氏を同時代の誰かと結びつけることはできるだろう。明らかに、彼はフロベールから生まれている。彼はしばしば、老ペシミストお好みのアイロニーというジャンルを、より一層の陽気さで手掛けているし、より一層軽々と、そしてそれほどに造形的ではない、確固として正確な自分の形式を所持している。ゾラ氏からは、彼ほど暗くはない不機嫌さ、さほど叙事詩的ではない様相とともに、ある種の粗暴さに対する好みを受け継いでいる。そして、彼の内にあるよく分からない何かが、所々で、書くことを知っているポール・ド・コック(35)を想起させる。私が知るある大学教授(彼はプルタルコスを「異教の告解室に陣取る伝道者ラ・ブリュイエール」と定義した)なら、モーパッサン氏を控え目で陽気なゾラ、簡単でくつろいだフロベール、芸術家で人間嫌いのポール・ド・コック、とためらわずに呼ぶだろう。だがそう呼んだところで何になろう、彼が十分に彼自身であり、感情と思想を十分に蓄えていないならば。それあるがゆえに彼は現代に生きているのである。また何になろう、彼が形式の質を保持していないのならば。それ故に彼は昔の大家を思わせるし、流行の気取り、すなわち甘ったるさ、隠語、晦渋さ、過剰、構成に対する侮蔑、そうしたものから逃れられているのである。
今や、私に言うべき必要があるだろうか、欠陥の無い一遍のソネは長い詩篇に匹敵するにもかかわらず、一編のコントは恐らくは一編の長編よりも傑作を生むに安上がりであるなどと。あるいは、もっとも、モーパッサン氏のコントの中にさえ、よく探すならば、あちらこちらになんらかの過ちや、とりわけあざとい効果、文体の行き過ぎ(「テリエ館」において、一層強烈なコントラストを得るために、「燃えるような堅信によって石畳の上に飛び出し」、「神々しい熱狂に震えている」初聖体拝受を受けた子どもたちを描いて見せた時のように――田舎において! ノルマンディーの村において! ノルマンディーの子どもたちが!)というようなことを言う必要があるだろうか? 人はすべてを手にすることはできないし、彼が『クレーヴの奥方(36)』や『アドルフ(37)』さえ書くなどとは想像もできないということを、付け加えておくべきだろうか? ――間違いなく、『山鴫物語』と同じくらいに愛することができるものが存在している。「マルロッカ」の作者よりも、彼ほどに古典的でなく、荒々しくもない作家を好むこともできるだろう。そうした作家を愛するのは、私の想像では、彼の欠点の持つ繊細さと気品ゆえのことであろう。それでもモーパッサン氏が、完全無欠とは言い難いジャンルにおいてほとんど完全無欠な作家であることに変わりはないし、それゆえに峻厳な者たちをも寛容にさせ、他の者たちには二重に気に入られるものを、彼は備えているのである。
『政治文学評論』、1884年11月29日付、673-679頁(『現代人』第1巻、1886年、285-310頁)。
Revue politique et littéraire (Revue bleue), 29 novembre 1884, p. 673-679. Repris dans Les Contemporains, H. Lecène et H. Oudin, série I, 1886, p. 285-310.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
Revue politique et littéraire (Revue bleue), 29 novembre 1884, p. 673-679. Repris dans Les Contemporains, H. Lecène et H. Oudin, série I, 1886, p. 285-310.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
訳注
(1) Théophile Gautier (1811-1872):『モーパン嬢』(Mademoiselle de Maupin, 1835) 序文において「芸術のための芸術」を主張した。
(2) 中世フランス北部オイル語圏で作られた韻文滑稽譚。
(3) Alphonse Daudet (1840-1897):南仏出身の小説家。短編集『風車小屋だより』(Lettres de mon moulin, 1866) 『月曜物語』(Contes du lundi, 1873) 等。『フィガロ』、『エヴェヌマン』といった新聞に短編小説を掲載。
(4) Paul Arène (1843-1896):南仏出身の作家。南仏に材を得た作品を発表し、ドーデやミストラルとも親しかった。ドーデ『風車小屋だより』の協力者。『ジュルナル』や『フィガロ』に寄稿。
(5) La Vie parisienne:1862年創刊の絵入り週刊誌。
(6) Ludovic Halévy (1834-1908):劇作家、小説家。アンリ・メイヤックらと共作で多数のオペレッタの脚本を執筆。ジャック・オッフェンバック作曲の『パリ生活』(1866) やビゼー作曲の『カルメン』(1875) 等。1884年アカデミー会員。
(7) Sibylle Gabrielle Riquetti de Mirabeau (1849-1932):結婚してマルテル伯爵夫人に。『パリ生活』や『両世界評論』に執筆し、1880年より Gyp の筆名で多数の著作を出版した。
(8) Richard O'Monroy (1849-1916):『パリ生活』や『ジル・ブラース』に寄稿。
(9) François Coppée(1842-1908):詩人、小説家、劇作家。高踏派の詩人として出発するが、庶民生活を素朴に表現して人気を博した。『貧しき人々』(1872)、『赤い手帳』(1874)、『物語とエレジー』(1878)、詩劇『王位のために』(1895)など。『散文による短編』(1882)などの小説も著した。1884年、アカデミー・フランセーズ会員。
(10) Théodore de Banville(1823-1891):詩人。『人像柱』(1842)、『鍾乳石』(1846)などで詩形式の完成に専念。『綱渡りのオード』(1857)出版後、『ルヴュ・ファンテジスト』や『現代高踏派詩集』で高踏派の中心のひとりとして活躍した。他の詩集に『抒情小曲集』(1856)、『流謫者』(1867)、戯曲に『グランゴワール』(1866)など。『フランス詩小論』(1871)において韻の重要さを主張、この詩の概説書は当時の文学青年によく読まれた。1880年代には多数の小説も執筆している。
(11) Paul-Armand Silvestre(1837-1901):詩人、小説家、劇作家。『新旧詩篇』(1866)、『再生』(1870)などでセンチメンタルな高踏派詩人として知られたが、1880年代に入ると艶笑譚を大量に発表、スカトロジックな内容も多く異彩を放った。短編集に『友人ジャックのいたずら』(1881)、『腕白小僧の回想』(1882)など。
(12) Catulle Mendès(1841-1909):詩人、小説家、劇作家。1860年、『ルヴュ・ファンテジスト』を創刊し、高踏派の詩人として出発。詩集に『フィロメラ』(1863)等。オペラ『グゥエンドリン』(1886、エマニュエル・シャブリエが音楽)、『イゾリーヌ』(1888、アンドレ・メサジェが音楽)でも成功を博した。小説に『童貞王』(1881)、『メフィストフェラ』(1890)など。ワーグナーを擁護したことでも有名。1866年、ジュディット・ゴーティエ(1845-1917)と結婚(1878年に法的別居、1896年に離婚)。
(13) Bonaventure des Périers (vers 1500-vers 1543):詩人、物語作者。『新笑話集』(Nouvelles Récréations et joyeux devis, 1558) は90編の短編からなり、ボッカッチョ等の影響を受け、簡潔な文体で滑稽な物語を諷刺的に綴っている。
(14) Jean de La Fontaine (1621-1695):韻文による『コント集』(Contes et nouvelles en vers)は1665年刊行。好評を受けて書き継がれた。
(15) Jean-Baptiste Joseph Willart de Grécourt (1683-1743):聖職者でありながらリベルタン流儀の生活を送り、艶笑的な詩やコントを執筆した。作品は死後に出版されている。
(16) Alexis Piron (1689-1773):詩人、劇作家。オペラ=コミックや喜劇(『作詩狂』 La Métromanie, 1738)の他、諷刺詩の才にも秀でていた。
(17) Henriette d'Angleterre (1644-1670):ヘンリエッタ・アン・ステュアート。イングランド王チャールズ2世およびジェームズ2世の妹、フランス王ルイ14世の弟オルレアン公フィリップ1世の妃。ルイ14世の愛人になった。
(18) « La Clochette »:『モークロワ氏とラ・フォンテーヌ氏の詩と散文集』(Ouvrage de prose et de poésie des sieurs de Maucroix et de La Fontaine, 1685) 所収。
(19) « La Courtisane amoureuse »:『コント集』第三部 (1671) 所収。
(20) Sapho (1884):アルフォンス・ドーデの小説、パリの社交界を描く。
(21) 「恋する遊女」の中の一行。
(22) ルクレーティウス、『物の本質について』第1巻1行(樋口勝彦訳、岩波文庫、1956年、9頁)。
(23) ルクレーティウス、『物の本質について』第4巻1129行(同前、203頁)。
(24) La Femme (1860)
(25) L'Amour (1858)
(26) Jules Michelet (1798-1874):歴史家。『フランス史』17巻の他、『民衆』(Le Peuple, 1846)や『フランス革命史』(Histoire de la Révolution française, 1847-1853) 等。
(27) Ernest Renan (1823-1892):エルネスト・ルナン。哲学者、歴史家。『キリスト教起源史』の第1巻『イエス伝』(Vie de Jésus, 1863) でイエスの生涯を実証的に記述。
(28) Ernest Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 1883, « Premiers pas hors de Saint-Sulpice », IV.(ルナン、『思い出』下巻、杉捷夫訳、岩波文庫、1953年、「第六章 サン―シュルピスの外での第一歩」、135頁)
(29) ポール・ブールジェは『現代心理論』(Essais de psychologie contemporaine, 1883)において現代人の「精神の病」の特徴としてペシミズムを挙げている。悲観主義的世界観は自然主義時代の小説家に共通して認められる。
(30) Jules Barbey d'Aurevilly (1808-1889):ノルマンディー出身の小説家。貴族主義、カトリシズム、ダンディスムを混淆する独自の世界を構築した。短編集『悪魔のような女たち』(Les Diaboliques, 1874) 等。
(31) セナンクール(Étienne Pivert de Senancour, 1770-1846) による書簡体小説 Oberman (1804) の語り手。ロマン主義の先駆けを成す作品。
(32) アレクサンドル・デュマの小説『ポーリーヌ』(Pauline, 1838) の登場人物 Horace de Beuzeval。ポーリーヌの夫、盗賊。
(33) バルザックの小説『谷間の百合』(Le Lys dans la vallée, 1836) のヒロイン。語り手フェリックスの悲恋の相手。
(34) Pierre Loti (1850-1923):海軍士官として世界中を周航する傍ら小説を執筆。『お菊さん』(Madame Chrysanthème, 1887) 他。
(35) Paul de Kock (1793-1871):小説家、劇作家。200近い戯曲、ヴォードヴィルやシャンソンを残した。
(36) La Princesse de Clèves (1678):ラ・ファイエット夫人 (Comtesse de La Fayette, 1634-1693) の小説。人物の内心のドラマを精緻な分析で描き出す。
(37) Adolphe (1816):コンスタン (Benjamin Constant, 1767-1830) の小説。恋愛の誕生からその死までを古典的な文体で綴っている。
