ポール・ブールジェ
「個人的な思い出」
Paul Bourget, « Souvenirs personnels »,
le 15 juillet 1893
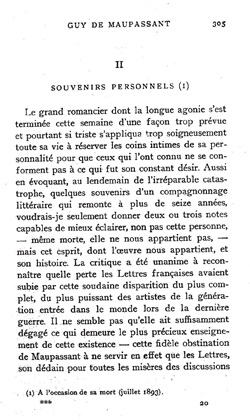 解説 ポール・ブールジェによるモーパッサン追悼文。はじめ、1893年7月15日、週刊誌『ルヴュ・エブドマデール』 Revue hebdomadaire に「ギィ・ド・モーパッサン」の題で掲載された。後に1906年『エチュードと肖像』第3巻「社会学と文学」に「ギィ・ド・モーパッサン II 個人的な思い出」として収録される(I は1884年の『ミス・ハリエット』書評)。
解説 ポール・ブールジェによるモーパッサン追悼文。はじめ、1893年7月15日、週刊誌『ルヴュ・エブドマデール』 Revue hebdomadaire に「ギィ・ド・モーパッサン」の題で掲載された。後に1906年『エチュードと肖像』第3巻「社会学と文学」に「ギィ・ド・モーパッサン II 個人的な思い出」として収録される(I は1884年の『ミス・ハリエット』書評)。ポール・ブールジェ(Paul Bourget, 1852-1935)は詩人としてデビューした後、批評集『現代心理論』(1883)で有名になり、以後多数の批評を手がける。一方で小説にも関心を向け、ゾラ流の生理学的小説に対抗して伝統的な心理分析の小説を執筆した。『残酷な謎』(1885)、『アンドレ・コルネリス』(1887)、『嘘』(1887)などの後、実証主義のもたらす精神の危機を描いた『弟子』(1889)で反響を呼んだ。1894年アカデミー・フランセーズ入会。『ピエールとジャン』以降のモーパッサンはブールジェの影響を受けていたともいわれる。
 本文に見られるとおり、ふたりの交流は1870年代に始まっており、交友はモーパッサンが亡くなるまで続いた。ブールジェはモーパッサンの親友のひとりだったと言ってよいだろう。
本文に見られるとおり、ふたりの交流は1870年代に始まっており、交友はモーパッサンが亡くなるまで続いた。ブールジェはモーパッサンの親友のひとりだったと言ってよいだろう。彼の追悼文は、ブールジェ一流の冷静な「分析」によってモーパッサンの特質をよく見抜いていると同時に、親密なモーパッサンの肖像を伝える貴重な証言となっている。
残念ながら今日、ブールジェの作品が読まれることは少ないが、彼の批評文は同時代評のなかでも、その明晰さ・鋭利さにおいて十分に見るべきものがあると思われる。
***** ***** ***** *****
個人的な思い出
個人的な思い出
十分に予測された通りでありながら、それでも大変に悲しい形で、今週、その苦しみに終わりを告げた偉大な作家は、生涯を通じて自分の人格の内密な部分を隠すことに余りにも注意を払ったので、彼を知っていた者でさえ、彼が常に抱いていた欲望に従うことができない。だから、取り返しようのない不幸のあった翌日に、16年以上前にまで遡る文学仲間についての記憶を思い返しながら、ここに二三ばかりの記録を残し、彼という人物についてではなく――死後であっても、それは我々のものではない――その作品が我々に属するところのこの精神と、その歴史についてよりよく明らかにしたいとだけ思う。このあいだの戦争の時点で社会に出た世代の芸術家のなかで、最も完全であり、最も力強かった者のこの突然の消失によって「フランス文学」がどれほどの損失を被ったかについては、批評家の意見は一致している。だが彼の存在が語ったことのなかで、最も貴重な教訓として残っているものを彼らが十分に引き出したようには思われない。――実際にただ「文芸」だけに奉仕しようという、モーパッサンが忠実に固執した姿勢であり、現代人の議論のあらゆる惨めさへの彼の軽蔑であり、常により完成された作品を作ろうとする、執拗にして疲れを知らない彼の配慮のことである。幾年もが過ぎ、今日生きる人物たちをその正しい位置に置いた時になって、この特徴こそが、情熱的なまでに完成を愛したひとりの芸術家のこの熱意こそが、ミューズの愛人たちにとってこの記憶をいつまでも愛しいものとするだろう。――古きよき時代の古きよき文体で人が述べたように。ある異なった研究と実現の方法とともに、その点によってこそモーパッサンはまさしくフロベールの弟子であるし、彼にあれほどの信頼と賞賛とを呼び起こすに値したのであったし、それはむしろ自分のライヴァルとなるに違いない一人の「大家」に対してのものだった。とはいえ彼らのあいだには相違があって、フロベールは文体家としての努力を告白し、要求したのだが、モーパッサンはそれを口にはしなかった。空しい論争を恐れるがために、彼はこの芸術に対する完璧な無関心を表明するまでに至ったのであったが、彼はそれを愛し、とても誠実に実践したのだった。彼はそこにはより実り多い飯の種しか見ていないと主張した。そうしていながら、新しい書物が現れるたびに玄人に向かって新しい努力の跡を明かし、彼のうちにある偉大な文学者としての根底的な美徳が、その最高の程度において存在することを示して見せたのである。それは、大成功への危険な誘惑のなかにあって最も良心的な芸術的誠実さであった。
宣伝の点で最初の輝かしいデビューを果たした時、彼はすでにそれを、あの賞賛すべき芸術的誠実さを備えていたし、それは同じように頑なで、同じように勇気あるものだった。「脂肪の塊」は二番目でしかなかった。最初のものは限定的なサークルの外に出ることはなかったけれども、決定的な技量を表明していた。その詩についてはすでに語ったことがある。「水辺にて」であり、1877年、『文芸共和国』に掲載された。この雑誌は当時カテュール・マンデス氏が、精神のすぐれた幅広さと、同僚としての寛容さをもって編集していた。同じこの時期に私はモーパッサンを知った。ラファイエット通りの一階にあったこの雑誌の編集室で出会ったのである。数時間前のことのようにはっきりしている記憶のなかでは、午後にこの狭い店に入ったところで、私はこの30歳にもならない青年を目にしたのだが、存在全体からみなぎるたくましさの点で彼の詩句によく似ており、四角く力強い頭、若い牡牛のような首、日々の激しい修練を受けた柔軟な、運動選手の持つような筋肉とを備えていた。大空の下で日焼けした顔の上には自信と同時に、率直さと善良さの光のようなものが漂っていた。一緒に外へ出た時の彼の姿を今も目にする。まだ寒いパリの春のあの夕暮れの一時、空気中には痛ましい悲しみのようなものがある。そして私は今でも、最初の会話がもたらした知的な興奮の火照りを感じるのだ。我々は彼の住むバティニョールの方へとあがって行ったのだった。昂揚した彼がルイ・ブイエのあまりにも知られていない一篇の詩「鳩」を朗誦するのを私は耳にする。
……戻ることも許されずに尊い寺院を追われ、
タボールから吹く火事の風に背を屈め、
偉大なるオリンポスの神々は余りにも哀れで、
幼い子供等が彼らの金の髭を引っ張り……
詩句を朗誦するに際して、彼からしか聞いたことのない一種のメロペ〔古代ギリシャ詩の節〕をモーパッサンは奏でた。彼の声ははじめ歌うようで、それから少しばかりしゃがれ、まるで美的な感動が喉元を捕えたかのようだった。当時の彼は、フロベール宅で知り合ったブイエに対して一切留保のない賞賛の念を表明していた。彼の優れた計画の一つに『メレニス』と『最後の歌』についての長い批評的考察を執筆するというものがあって、1891年の11月、カンヌに向けて出発する前に行ったことのひとつは、ある出版社を訪れて師の友人の全集を手に入れることだった。この計画が実現されなかったのは二重に残念なことである。この考察のなかで、詩の技法に関するとても新しい理論の幾つかを彼は記したことだったろう。私はそれを何度も彼の口から聞いたものだった。この最初の出会いの時から私に話していた「ラブレーにおける表現」についての考察を完成させなかったのは、同じようになんと残念なことだろう! 彼のうちでは批評家は芸術家と同等であったが、あの表現の確かさを備えている作家にあっては皆そうなのである。彼の全集が編集される際には、編むべき一巻の優れた批評集があることだろう――そしてそれは私の述べていることを証明してくれるだろう――そこには、ジョルジュ・サンド宛書簡集の冒頭に置かれたフロベールについての考察や、興味深く、また奥深い『ピエールとジャン』の序文があり、スウィンバーンについてガブリエル・ムレー氏の翻訳に関する断片があり、散逸した30ばかりのクロニックがあるだろう。ついでにこの仕事を請け負うだろう編集者に、ラウール・デュヴァル氏がオーギュスタン・フィロン氏、亡くなったアルベール・デュリュイ氏と共に創刊した『国家』紙に、1880年以前に掲載された一連の「ヴァリエテ」の記事を示唆しておきたい。モーパッサンはそこに、ヴィヨンやプレイヤッド派の詩人について幾つも記事を提供したが、それらは私の記憶に残っており、保存に値するものである。そこには優れた言語研究の証拠が見られるだろうが、一見極めて平易なこの作家は、そうしたものに取り組んだ後になってからデビューすることを自分自身に許したので、そのデビューは彼が明かした早熟さによって皆を驚かせたのであった。あの二百行ばかりの韻文の背後には、持続的で謙虚な努力の十年ばかりの月日があった。
この十年の間、それをモーパッサンがどのように――外的な面で――過ごしたかはほとんど至る所で語られた。人の言うところでは財産がなかったので、彼は役所で安月給の地位を受け入れ、余暇のあいだには書物よりもカヌー漕ぎに専念し、日曜日にはムリーリョ通りのフロベールの家に熱心に出かけ、そこで黙ったまま、トゥルゲーネフとテーヌやゴンクール、ゾラとドーデ、コペーとマンデスの会話に加わっていた――あまりに黙っているので、年長者たちは誰も彼の天職を疑ってみもしなかったという。しかしながら彼は仕事をしていたし、どれほど厳密な原則を持っていたことだろう。後に彼はそれを、彼を力づけたフロベールの助言を回想しながら語っている。しかも彼はこの仕事に対し、あの監督の行き届いた忍耐、あの虚栄のない良心を合わせ持ったのであり、彼はそれらを、最も魅力的な彼の特徴のひとつであった、高い志に対する男性的な羞恥とともに、最後まで行使したのであった。書くという技術に対して十分に堅固な原則を築いていたので、人目につかないこの修練の期間、習作でも十分に確かだった内輪の成功のもたらす安易な高揚を決して求めなかった。クロワッセの師は彼にこの原則を、受肉化され、息づいたものとして示して見せたのだが、その師の峻厳な批評だけで彼には十分だった。この師と彼とは美しい小説を書いた。この年月の間に彼らが生きた以上に稀なものを私は知らないし、素朴な善良さと雄々しさとをあふれさせながら、フロベールが弟子のなかに恐らくは自分より優れているかもしれない才能の成長するのを感じ、それを感じることに幸福を味わい、それを助けるのに一層幸福だったことを私は疑わない――最も無味乾燥な職業に閉じ込められ、反抗することもなくそれを受け入れたモーパッサンは、同年代の者たちがすでに広告のなかに身を投じているのを目にしながら、彼らの成功を羨むこともないほどに自分自身の力強さを感じ取り、完璧になりたいと望んでいた。かつての同業組合の職工にも似て、絶えず見習いとして振る舞いつづけた後にに自身の「傑作」を仕上げたのだった――そしてあの詩編がそのひとつだった。私はそれを読み返し、男性的でたくましい才能の持ち主と初めて出会った時に私を捕えたのと同じ、興奮によるかすかな震えを再確認したところだ。この詩編を再録したモーパッサンの詩集は薄いもので、二冊目が出ることはなかったけれども、「水辺にて」、「最後の逃走」、そしてとりわけ「田舎のヴィーナス」は、この異教風の野心的な三部作の著者に対し、我々の優れた抒情詩人のあいだへの地位を約束している――そしてその点でマンデスが自身の「雑誌」の屋根の下に集めた、今日すでに有名な詩人たちの集団を正当に評価しなければならない。彼らは最初から一致して、その地位を新人に与えたのだった。
この素晴らしいデビューを果たした詩人は、どうして詩を書き続けなかったのだろうか? 私が想像するところでは、まさしく先ほどお話した内省の力強さと文学者としての良心のゆえであっただろう。モーパッサンは――そしてこの点で、彼ははっきりとフロベールと区別されるのだが――決して芸術と人生とを分けて考えなかった。彼は書かれた資料を、絵画や美術品、あるいは科学書を通して得られる幻覚を信じなかった。少なくとも彼は自分にその能力があるとは信じていなかった。彼は直接的な体験をこそ力強い芸術創造の最良の条件と見なしていた。その詩集のうちに、彼は自身の魂の一部、あの汎神論的な官能性の高揚をさらけ出したが、それが自分のうちに溢れるのを、森を駆け、川を下りながら感じていたのだ。彼はそこでは社会生活に対する鋭い感性や、人間嫌いの皮肉さ、性格の細部に関する深い洞察を提示することができなかった。すでに十分なものであった生活体験を、より柔軟で、よりよく翻訳することのできる芸術形式を、小説のうちに見いだしたのであった。彼はフロベール以上に、トゥルゲーネフによってこの方向に押し進められた。フロベールはとりわけ文体の情熱家であり、彼にとってはあらゆる芸術的試みは、それが堅牢な一頁に到達した際に良いものとなった。「この頁は」と彼は言ったものだ。「大理石の石碑のようにしっかり立っている。」トゥルゲーネフは反対に、小説の未来に対して絶対的で、実のところほとんど唯一の信仰を抱いていた。彼はそこには新しい有機体、生まれたばかりの一ジャンルがあると信じたし、それは無限の多様さを備えることが出来るし、そうでなければならなかった。一方で、彼はモーパッサンを、彼が知るなかでトルストイ以来最も才能ある短編作家だと見なしていた。私は彼がこの意見を支持するのをテーヌ家のテーブルで耳にした。『女の一生』が出版されるずっと前のことである。そしてこの同じ時期に、ロシアの繊細な巨人の語る小説の未来についてのあの長い談話を、ギィ・ド・モーパッサンが熱狂的な同意をこめて私に報告してくれるのを耳にしたのだった。その時から、最初の頃と同じように男らしい辛抱強さで、同じぐらいに困難な状況のなか、彼はそれに専念したのである。従うべき相手をとり変え、役所を辞めてジャーナリスムの世界に入った。この新しい職業を彼がどんな風に理解していたかは、『ベラミ』の執筆中に彼が発した、とても簡単でとても意味深い一語に明らかだろう。彼はモーフリニューズの筆名で『ジル・ブラース』に、彼が秀でていた、とても短いながらとても悲劇的なあの短編のひとつを寄稿したのだった。私がお世辞を述べた時に、彼はこう答えた。「あれが気に入ったって?…… でもあれは下書きでしかないんだ……そうさ。」彼は続けた。「僕の習慣では、長編に取りかかる時には、クロニックのなかでエピソードの最初の大まかなデッサンを描いてみるんだ。それをふたつ、三つ、時には四つばかりやってみる……。それから長編に向けてもう一度やり直すというわけさ……」この手法が常に継続的に適応されることで、他の者なら鈍らせてしまうような試練のなかでも、自分の道具を磨き上げることが可能となったのだ。そして、一回一回のクロニックが、小説家という職業についてより深く知る機会であったのと同様に、新しく書かれる小説は、そのたびに彼にとって、新しく習得した技術を発展させるきっかけになった。彼の家に夕食に出かけたある晩――それは1885年の夏だったに違いないが――なんと最近の、なんと昔のことだろう!――彼はその時は陽気だったが、この頃からそれは珍しいことになった。『モントリオル』の執筆が始まっていた。
「40人の人物を登場させたんだ」と彼は言った。「40人だよ、ねえ、ちょっとした数だ。40人の人間が最初の2章の間に行き来する!……」
最大の賞賛の言葉でモーパッサンについて語った批評家たちは、いつも自分の「手法」を変化させようとする絶えざる彼の努力を認めていただろうか? バルザックまで遡らなければ、それぞれの本をそれぞれ特別の型に合わせて使ったことのない手法を、あるいは以前の手法を別の仕方で用いて構成しようとするような配慮は見いだすことができない。時には、『女の一生』のように、ほとんど独立した小景の連続で、それがどんな中心的な筋によって結びつけられることもないままに繰り広げられることで、タイトルとエピグラフに従って、単調な期待に疲れた一個の存在の「ささやかな真実」がよりよく理解されることになる。別の時には『ピエールとジャン』のように、緊密な一つのドラマが短い場面場面に配分され、厳密に一つの悲劇へと導かれる。古典劇と同じようにはっきりと描かれた三幕の舞台に、作家は作品を分割した。別の時には『ベラミ』において、ル・サージュ風に進めてみせる。物語はまっすぐに駆け進む。一連の、風景ではなくエピソードであって、パリの世界に焦点を合わせて、若返った冒険小説であるかのようだ。別の時には、『死の如く強し』や『わたしたちの心』のように、心理分析の小説だけれども、より力強い手で取りあげられ、鍛えあげられており、無類の独創性を備えてひとりの心理学者によって実現されたものであった。この心理学者は幻視者でありつづけることが可能だった。これらの書物のそれぞれにおいて、典型的な技法に手が加えられ、いわば捏ね直されている。こちらでは、提示は対話によってなされる。別のところでは、小説家は自分で、自分自身の名においてそれを行った。また別のところではいきなり行為のなかに身を投じた。彼の記憶のなかにはいつでも、『幻滅』のなかでバルザックが、怠惰なリュシアンに向かうダルテスに言わせた台詞があったのかもしれない。「君の主題を時には裏返して、時には尻から取りあげたまえ。とりわけ、君のプランに変化をつけるんだ。決して同じであってはいけない……」モーパッサンにあっては、表現技法のこの多様さは、それによって扱われる題材の同じように驚くべき多様さを伴っている。その外見が毎回刷新されるそれぞれの書物において、観察の領域でも同じような刷新が達成されているのは明らかである。モーパッサンは最初の頃の短い小説のなかに、一群の農民、小ブルジョア、田舎貴族、都会や田舎に住む娘たちを登場させることから始めた。それから順々に、同じほどくっきりと、ボヘミアン、修道者、ジャーナリスト、クラブに集う人間、大貴族や貴婦人たちを示すことができた。人も知る皮肉な視線で、動物的、生理学的な生活における危機を研究した後には、同じように正確に、道徳的、心理学的な生活の危機を研究するに至り、すべては自然に忠実だったが、つまり、次々に20もの場所に顔を出し、自分の周りの社会的状況を絶えず変化させたのであった。加えて、彼の書物はページごとに長い旅行の痕跡を留めている。様々な国においてすべてがよく眺められ、眺められる以上に感じ取られ、狩りについては狩人のように、漁については漁師のように、海については水夫のように、馬については騎手のように、医学についてはほとんど医者のように語った。作家としての豊穣で衝動的とも言える様相が、肖像画家のなかでも最も鋭敏な者(作者注:ジュール・ルメートル)をして、彼はリンゴの木がリンゴの実をつけるように小説を生み出すと言わしめたけれども、どんな作家も彼以上に、自分の能力を賢明かつ方法的に発展させることに適応していたことはないし、広大な世界に対して、経験することへの飽くなき欲求と、機敏な好奇心とを彼以上に備えていた者などいなかった。ただ彼が自分の方法について語ることがほとんどなかったので、誰も、彼がそれを持っているということを考えてみようともしなかったのである。有名であるということが知られないでいるための最も確かな機会であるという、逆説的な真理を証明する者たちのなかに加えるべき一個の好例である。
この疲れ知らずの労働に、あの生命体の突然の疲労の理由を帰すべきだろうか? その体はゲーテやユゴーのように、休みない80年の活動のためにあるかのように思われたのだったが。恐ろしい結末のうちに、生々しいのと同じぐらいに秘密のものであった感性の磨耗を認めるべきだろうか? それは最初の短編から最後の長編にまで、たくましい健康さの合間に覗く、奇妙に弱々しい筆づかいに認められるものだったのだが。そこには単に生理学的な故障、恐らくは遺伝的に宿命であった一撃があっただけだと考えるのがよいのだろうか? あれほどに力あふれた精神の、あれほどの正確さへの意思が難破したのであっては、すべては謎のままに留まる。確かなことは、モーパッサンは病の訪れをずっと遠くから目にしていたのであり、彼はそれに対して闘ったということだ。それというのも彼は最後の日まで働き続けたし、筆を投げ出して自殺するためにピストルを手に取ったのは、身体的にもう書くことができなくなったその瞬間においてだったのだ。1884年から最も残酷な神経発作の被害者であり、それは最も奇妙なものでもあって、彼は、彼の才能の最も良い部分を作り出したあの理性を、それから守ろうと努めていた。その証拠のひとつを記そうと思う。彼の存命中は決して記したことがなかったが、この二年ばかりの間、折に触れて思い返されるものであった。この逸話があまりに個人的なものであるのをお許し願いたい。それが真実であることの保障でもあるだろうから。我々は一緒にルルシーヌの病院へ行かなければならなかったのだが、当時そこで、モーパッサンの個人的な友人であるマルチノー博士が教鞭を取っていたのである。モーパッサンが私を誘いに来ると、私がほとんど耐え難いほどに強烈な夢の影響下にあるのを見て取った。夢のなかで私は新聞業界の同僚のひとりであったレオン・シャプロンの瀕死の様を、その死と、それがもたらす結果のすべてを、新聞紙上の彼の後任についての議論を、葬式の場での議論を、恐ろしいほど正確に目にしたので、目覚めてからも妄執のようにその悪夢に取りつかれていたのだった。私はその夢をモーパッサンに話した。彼は一瞬身を固くして、それから尋ねた。――「彼がどうなっているか知っているのかい?」――「じゃあ病気なのかい?」私は答えた。――「死にかかっている。もう一度聞くけれど、知らなかったんだね?」――「絶対に。」――そして、それは本当だった。我々は一分ばかりもの間、この予感の奇怪さに驚き佇んでいた。その予感は数日後には実現するに違いなかったのである。つけ加えておくが、私としては、その種の現象として疑うことのできない唯一のものである。しかし私が思い出すのは、モーパッサンの驚きは長くは続かなかったということだ。――「何か理由がある」と、かつての陽気さで彼は言った。「それを探さなくては。」実際に気づいたのであるが、二週間ほど前に、私はシャプロンから一通の手紙を受け取っていた。私はそれを探し、モーパッサンはそれを眺めながら幾つかの文字が震えていることを指摘した。「これは病人の文字だよ」彼は主張した。「君は自分で理解しないままにそれに気づいていたんだ。それが君の夢の元にあったんだ……説明のつかないことなんてないのさ、ねえ、よく注意しさえすればね。」――そして、私がまだ動揺していたので彼はつけ加えた。――「もし君が僕のようなのを体験したらどうだろう? 家に帰る時、二度に一度は僕は自分の幻覚を目にするんだ……ドアを開けると自分が椅子に座っている。それを目にしている時にも、それが幻覚に過ぎないことは分かっているんだ。おかしなことだろうか? もしも幾らかでも分別がなかったら怖いことだろうか?……」そしてそう言いながら、彼は目の前を眺めていた。彼の明るい瞳には明晰な思考の炎が輝き、実際に恐怖は見えなかった。何度、記憶のなかにあの時そうであった彼の姿を見ただろう。その時確かに、彼が犠牲となるはずの病はすでに始まっていたのだ! 狂気とのあの決闘は最後の10年のあいだ、秘密裡のドラマであった。そのことに彼は苦しんでいたのに違いない。最後の頃の肖像がそれを明かしているし、またかつてはとても自由で、陽気で力強く、率直であった容貌が荒廃にさらされている。この作家が耐え続け、この殉教を通して彼が成長したということ、そのことが証明しているのは、自分の芸術へのどれほどの情熱的な愛が、この芸術家の土台そのものをなしていたかということであり、彼の作品は、フランス語が存在する限りにおいて、師の作品の傍に残りつづけるであろう。彼は弟子であったが、もし長生きすれば師に等しくも、追い越すこともできただろう……。「始メラレタ仕事ハ中断サレタ」――このウェルギリウスの詩句は、なんと重たい意味を持ち、なんと人間性を湛えていることだろう!
『ルヴュ・エブドマデール』、1893年7月15日付
『エチュードと肖像』第3巻「社会学と文学」、305-319頁。
Revue hebdomadaire, 15 juillet 1893, p. 454-464.
Études et Portraits, t. III, "Sociologie et Littérature", Paris, Plon, 1906, p. 305-319.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
『エチュードと肖像』第3巻「社会学と文学」、305-319頁。
Revue hebdomadaire, 15 juillet 1893, p. 454-464.
Études et Portraits, t. III, "Sociologie et Littérature", Paris, Plon, 1906, p. 305-319.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
