「ギュスターヴ・フロベール」
« Gustave Flaubert », le 23 octobre 1876
 解説 1876年10月23日付 『文芸共和国』 La République des lettres に掲載されたギュスターヴ・フロベール(Gustave Flaubert, 1821-1880)についての論考。ギィ・ド・ヴァルモン Guy de Valmont の筆名。これは雑誌に掲載されたモーパッサンの評論の最初のものである。
解説 1876年10月23日付 『文芸共和国』 La République des lettres に掲載されたギュスターヴ・フロベール(Gustave Flaubert, 1821-1880)についての論考。ギィ・ド・ヴァルモン Guy de Valmont の筆名。これは雑誌に掲載されたモーパッサンの評論の最初のものである。『文芸共和国』はカテュール・マンデスが主幹を勤めていた雑誌。フロベールの仲介によってモーパッサンはマンデスと交流をもった。すでに3月に「水辺にて」、6月に「日射病」などの詩篇を寄稿している。
一読、フロベール礼賛に溢れた文章は、表現にぎこちなさを残しているものの、弟子による師の理解と敬愛の念を率直に語っている。
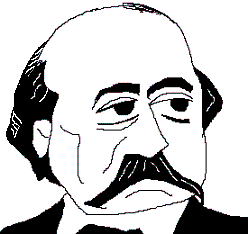 1870年代、および80年代前半のモーパッサン文学を考えるうえで、フロベールの教え、影響を無視することは出来ない。本論を通して、モーパッサンがフロベールから何を学んだかが窺えるだろう。
1870年代、および80年代前半のモーパッサン文学を考えるうえで、フロベールの教え、影響を無視することは出来ない。本論を通して、モーパッサンがフロベールから何を学んだかが窺えるだろう。フロベールの死後も、モーパッサンは師へのオマージュを繰り返し捧げる。1884年、『ジョルジュ・サンド宛書簡集』の序文として書かれる「ギュスターヴ・フロベール」は、当記事も含めたそれまでの記事の集大成であり、最も重厚なフロベール論を成すことになる。
***** ***** ***** *****
ギュスターヴ・フロベール
I
ギュスターヴ・フロベール
I
後世にその名を残す作家達の中には、時として、作品の完成度と希少性によって特別な位置を占める者が存在する。反対に、他の作家達は大量に生産し、稀なるものと凡庸なものを、見出されたものとありきたりなものとを混ぜ合わせることで、残るべきものと消え去るべきものを峻別するという面倒な仕事を、批評家や読者に強いるものである。けれども前者の者達は、苦労に満ちた忍耐強い創作によって、全体においても細部においても、絶対的であり完璧な、一個の作品を生み出す。公衆において絶対的に公正といえる成功を、こうした作者達の作品の全てが得ることはないとしても、少なくともその内の一冊は、傑作という名で文学史に残り、それはルーヴルの展示室に置かれる、偉大な画家達のああした絵画と同じようなものである。
ギュスターヴ・フロベール氏はまだ四冊しか本を執筆していないが、全てが後に残るであろう。ただ一冊のみが傑作と称されることになるかもしれないが、しかしながら他の作品も、それと同様の価値を有するのである。
誰もが『マダム・ボヴァリー』『サランボー』『感情教育』『聖アントワーヌの誘惑』を読んだ。あらゆる新聞が、あまりに頻繁にこれらの作品の分析を行ってきたのだから、ここでそれを繰り返すつもりはない。私がお話したいのは、フロベール氏の作品創造に共通する技法についてであり、そこに、今日まで公衆が気づいてこなかった事柄を求めてみたいと考える。
II
何も知ることのないままに全てを判断し、新しい未知なジャンルの書物が現れるやすぐにも、我先にとプラカードよろしく、自分の愚かしい判断を押し付けようとする人々は、『マダム・ボヴァリー』が登場した際、フロベール氏はリアリストだと声高に主張したが、彼等の了見ではそれは物質主義者のことをいうのだった。
古代についての一個の詩たる『サランボー』を、そして哲学思想の精髄たる『聖アントワーヌ』を氏が出版して以降も、何も変わるところがなかった。有能なるジャーナリストが物質主義者と命名したのであってみれば、よく考える人達の初歩的な頭の中で、彼は物質主義者としてありつづけた。
ここでは、現代小説史を語ったり、フロベール氏の最初の小説の登場が掻き立てた、深い感動の理由を逐一説明している余裕はない。最も重要な点を明らかにするだけで十分としたい。
そもそもの初めから、本当らしく見えない小説がもたらす、まったりとしたシロップを、フランス人は喜んで飲み干してきた。男女の英雄、実人生では決してお目にかかれない物事が愛されてきたのは、ひとえに、それが実現不可能であるが故だった。こうした書物の著者は観念主義者と呼ばれたが、それも単純に、可能で、現実的で、物質的な事物からは、計り知れないほどの距離を、彼等が絶えず保ってきたからである。――観念に関して言うならば、彼等には、読者ほどにもそれがあったわけではないだろう。そこへバルザックがやって来た。最初、人が注意を払ったとしても、それはわずかなものだった。――しかしながら、彼は例のないほど力強く、多作でもあった革新者であり、将来大作家の一人とされるだろう。恐らくは文章にまごつき、作家としては不完全ではあったにせよ、不滅の人物達を生み出し、歪んだ視界の中に彼等を動かすことで、現実において以上に一層印象深く、ある意味では一層真実にしたのである!――『マダム・ボヴァリー』が現れるや、世界中が震撼した。――何ゆえか? それはフロベール氏が一人の理想主義者であり、同様に、いやとりわけ、彼が芸術家であったからだ。そしてそれにも拘らず彼の書物は、真実の書物だったからである。それは読者が、自らに説明することも、理解することも、それと知ることもないままに、文体の全能の力の影響、書物の全てのページを照らし出す啓示の影響を受けたからである。
実際、フロベール氏の第一の特質は、彼の書物のどれかを開くや、すぐにも私の目には飛び込んで来るのであるが、それは形式である。それは、作家においても極めて稀なもので、公衆の目に留まることはほとんどない。目に留まらないのだが、その抵抗しがたい力は、それを信じること最も少ない者をも支配し、浸透するのであり、あたかも太陽の熱が、光を見ることのない盲者をも暖めるが如くである。
公衆は一般的に「形式」という語を、調子よく流れる文章の各所に配置された言葉の響きの良さ、堂々たる出だしの文章、音楽的な結語というように解している。だから、フロベール氏の書物の中に封じ込まれている、絶大なる芸術の存在を疑ってみることもほとんどない。
彼にあっては、形式とは作品そのもののことをいう。それは種々異なる一連の鋳型のようなものであり、それが、書物を形成する素材たる、概念に輪郭を与える。形式は概念に優美さと、力と、偉大さと、それらあらゆる特質とを付与し、それらはいわば、思考そのものの内に隠され、表現の助けを得ることによってのみ表れ出る。感覚、印象、様々な感情のように、無限に変化しながら、形式はそれらのものに密に接し、離れることがない。それらのもののどのような表明のあり方にも従いながら、形式はそれぞれの状況、それぞれの効果に即した、常に正確にして唯一の言葉、拍子、リズムをもたらし、この不可分の結合によって、文学者が文体と呼ぶものを創り出すのだが、ここでいう文体は、人が公に認めるものとは大きく違っている。
実際、一般的に人は、各作家に固有の、特殊な文章の形態をさして文体と呼ぶ。作家は唯一の鋳型に、自分が表現したいあらゆる事柄を流し込むかのようである。このような見方からすれば、ピエールの文体、ポールの文体、ジャックの文体が存在することになろう。
フロベールは彼固有の文体を持たない。そうでなく、彼は唯一の文体を所有しているのだ。すなわち、何らかの思想を表明するにあたって、彼が用いる表現や文章構成は、常に「絶対的にその思想に」適ったものなのである。作家の気質が現れるのは、正当さによってであり、言葉の特異さによってではない。
III
「文体なくして、書物はない」これが彼の格言ともなろう。実際、彼の思想によれば、芸術家の第一の関心とは、美しいものを作り出すことにある。それというのも、美はそれ自体真実であり、美なるものは常に真であるが、真なるものが必ずしも美とは限らないのである。美という語で、私は道徳的な美徳、高貴な感情ではなく、造形的な美、芸術家の知る唯一の美を言うのである。大変に醜く、嫌悪すべきものとて、解釈者のお蔭によっては、そのもの自体とは独立した美を纏うこともありうるが、一方、最も真実で、最も美しい思想も、下手に作られた文章の醜さにあっては、致命的なまでに消滅してしまう。付け加えなければならないが、公衆の一部の者は「形式」という語を憎んでさえいる。自分の理解出来ないものを、人はいつも憎むものであるからだ。
従って、フロベール氏はまず何よりも、一人の芸術家である。すなわち、非個性的な作家である。誰であれ、彼の全ての著作を読み終えた後で、私生活における彼、日々の会話の中で彼が考え、語ることを見抜けるとは思わない。ディケンズが考えたに違いない事を、バルザックが考えたはずの事を知ることは出来る。彼等は絶えず、自分達の書物の中に姿を見せる。しかし、ラ・ブリュイエールがどのような者であったか、偉大なるセルヴァンテスが言いえたことを、想像することがお出来になるだろうか? フロベールは決して「私は」「この私」という語を記さなかった。書物の中ほどで、公衆とおしゃべりしにやって来たり、舞台上の役者のように、結末に挨拶申し上げることは決してないし、序文も書かない。彼は、人間の姿をした操り人形の使い手であり、人形は彼の口で話さなければならず、彼らの口を借りて考える権利を、彼は一切自分に認めていない。操りの糸を見つけられることや、自分の声を聞き分けられることがあってはならないのだ。
アプレウスの末裔、ラブレーの子孫、ラ・ブリュイエールの後継、セルヴァンテスの息子にして、ゴーチエの兄弟たる彼は、人がどう述べようが、バルザックとの類縁は少なく、哲学者スタンダールとは尚更である。
フロベールは、同時に困難であり、簡明であり、複雑でもある芸術を持った作家である。複雑なのは、熟慮された構成の故であり、苦心によって、彼の作品には不変という特質が与えられ、簡明であるのは、その見かけにおいてであるが、あまりにも簡明かつ自然であるが故に、一ブルジョアが、自分の持つ文体についての観念をもとに、読書中にこう叫ぶようなことは決してありえない。「これこそ、まさしく、よく書かれた文章だ」
彼はバルザックのように正確に洞察し、スタンダールや、他の多くの作家のように正確に観察する。そして彼は彼等よりも正確に、より良く、そしてより簡明に表現するのだ。簡明であるというスタンダールの主張も、つまるところは無味乾燥でしかなく、よく書こうという努力にも関わらず、バルザックの努力はあまりにもしばしば、偽りのイメージ、無用な換言法、関係詞、「それが」、「それを」の氾濫に至る。一軒の家を建てるのに必要な量の百倍もの材料があり、選ぶことを知らないが故に全てを用いるといった、そうした人物の陥る困難な事態に陥るのだが、にも拘らず彼は巨大な作品を作り上げる。しかし彼が左官である以上に建築家であったなら、つまりは個性的である以上に芸術家であったなら彼が作りえたものよりも、美において劣るし、さほど強固でもないのである。
彼等の間にあるとても大きな相違は、まさしく全体的なものである。それは、フロベールは偉大な芸術家であり、他の者の多くはそうではない、ということだ。彼は、自分が掻き立てる情念の上にあって無感動である。群集の中に留まる代わりに、彼は塔に閉じ篭って、この世に起こる事柄を凝視し、人の頭に視界を遮られることのないために、より良く全体を捉え、細部の配分をより決定的に、プランをより堅固なものに、地平をより遠くにまで広げる。
彼もまた自分の家を建設するが、用いるべき材料を知り、その他のものはためらいなく拒絶する。従って、彼の作品は絶対的であり、一部でも取り去れば、全体の調和を破壊することになる。ところが、バルザックにおいては切り取ることも、スタンダールにおいても切除することが、他の多くの者においても削除することが出来る。その結果に気づくことの出来るのは、まことに鋭い者である。
IV
何人かの者のように、知性と霊感、偶然と気質があれば、一冊の本を書くのに十分だとは彼は考えないし、情報の収集は無用で、長い時間をかけての調査など忌むべきものとは考えない。それは、彼が、多くの物事を知っていた古代人達と同じ種に属するからである。93年以前にも世界が存在していたことを、1830年以前にも書くことは知られていたという事実を無視するのではなく、パンタグリュエルのように、彼は古代の全ての学者について思索した。彼は大学教授よりよく歴史を知っているが、彼等が歴史を探してみもしないような多くの書物の内から、歴史を学んだからである。彼は自分の作品のために、ほとんどの科学を研究し、それらは専門家のみに理解可能な類のものだ。背を屈めた老いた賢人達よりも、死滅した古代都市や、消滅した民族の系譜について、彼等の服装や、風俗、纏っていた布地から、好んで食した奇妙な食事に至るまでを熟知している。ラビのようにタルムード(訳注 ユダヤ律法の集成)を、司祭のように福音書を、新教徒のように聖書を、イスラムの修道僧のようにコーランを所持している。信仰、哲学、宗教と異端との連鎖を理解している。彼はあらゆる文学を読破し、多くの知られていない書物からノートを取ったが、あるものはそれが稀な本だからであり、別なものは誰も読んだことがないからであった。民衆の退廃期に生まれた、忘れ去られた才能ある作家、注釈家、伝記作家を知り、世俗の書物と神聖なる書物、聖人の生涯、教会の父祖や、慎み深い者が名を挙げられないような作者達をも知っている。憤慨と怒りに駆られたある頃に、我々に伝えるために彼が寄せ集めてみせたのは、一巻丸ごと、文体を持たない作家達の過失、文法家の犯す破格用法、偽の賢者達の誤り、それまで見過ごされてきた、ありとあらゆる虚栄と滑稽との集成であったが、それによって彼は世界を大いに侮蔑することであろう。
V
ジャーナリスト達は彼の顔を知らない。
自分の書き記したものを公衆に渡すだけで十分であると彼は考え、自分を世間の人気からずっと遠ざけ、広く流布する騒々しい宣伝、非公式の広告も、煙草屋のウィンドーに、有名な犯罪者、どこかの王子や、有名な娘達と並んで写真を掲示されるようなことも軽蔑している。
ごく少数の友人達にしか顔を合わさないが、文学者である彼等から愛される様子は、決して同僚から愛される風でなく、身内からでさえほとんど稀なほどである。その訳は、彼が自分の周囲に深い愛情の念を起こさせる点にある。けれども群集の好奇心には自分をさらさない。群集は、檻の向こうの珍しい動物と同じように、ガラス窓の向こうに有名人を見るのに貪欲であるが故に、彼の家の周囲には伝説が流布しているし、市民の誰かの家で、彼がブルジョアを食い物にしたと、真剣に非難することもありうるだろう。そうなったとしたらそれは、ともかくも、サント・ブーヴの家での有名な豚肉の夕食と、同じくらいには真実であろう。ある聖金曜日、よく知った、というよりよく唆されたジャーナリストの筆によるところでは、耐え難い「のこぎり」(訳注 単調な繰り返し・退屈)に終ったというあの夕食のことである。
最後に、常に個別の詳細をお望みの方々のお気に召すように、以下のことをお伝えする。彼は、その方々と絶対的に同じように、飲み、食べ、煙草を吸う。彼は背が高い。そして、大柄な友人、イヴァン・トゥルゲーネフと共に散歩する時には、さながら一対の巨人のように見えるのだ。
『文芸共和国』、1876年10月23日付
La République des lettres, 23 octobre 1876, p. 91-95.
Guy de Maupassant, Chroniques, éd. Gérard Delaisement, Rvie Droite, 2003, t. I, p. 51-56.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
La République des lettres, 23 octobre 1876, p. 91-95.
Guy de Maupassant, Chroniques, éd. Gérard Delaisement, Rvie Droite, 2003, t. I, p. 51-56.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
