「首飾り」
« La Parure », le 17 février 1884
 解説 1884年2月17日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois に掲載された短編小説。1885年、短編集『昼夜物語』 Contes du jour et de la nuit に収録される(マルポン&フラマリオン書店)。挿絵は P. Coustulier による。また、『ヴォルール』(1884年6月19日)、『民衆生活』(1885年5月7日)、『政治文学年報』(1889年10月6日)、『プチ・パリジャン』付録(1890年12月14日)に再録されているほか、短編集『遺産』(フラマリオン書店、1888年)、『三つの物語』(ゴーティエ書店、1892年)にも収録されている。
解説 1884年2月17日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois に掲載された短編小説。1885年、短編集『昼夜物語』 Contes du jour et de la nuit に収録される(マルポン&フラマリオン書店)。挿絵は P. Coustulier による。また、『ヴォルール』(1884年6月19日)、『民衆生活』(1885年5月7日)、『政治文学年報』(1889年10月6日)、『プチ・パリジャン』付録(1890年12月14日)に再録されているほか、短編集『遺産』(フラマリオン書店、1888年)、『三つの物語』(ゴーティエ書店、1892年)にも収録されている。モーパッサンの短編のなかでも最も有名なものの一つであり、日本語の翻訳も数多い。日本ではとくに、夏目漱石が本作品の落ちに関して厳しい評価を下していたことでも知られる。
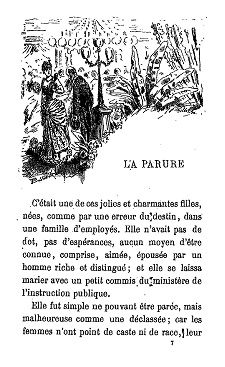 原題の la parure は 「装身具・アクセサリー」全般を指す名詞であり、動詞 parer 「~を飾る」に基づく言葉であるが、通例に倣って「首飾り」としている。
原題の la parure は 「装身具・アクセサリー」全般を指す名詞であり、動詞 parer 「~を飾る」に基づく言葉であるが、通例に倣って「首飾り」としている。作中では高額の金額が話題となるが、一説によれば19世紀当時の1フランは現在の日本円で約千円に該当するという。これに従うなら、400フラン=40万円。また4万フラン=4千万円という計算になる。一方で、当時の下級役人の年棒はおよそ1,500~2,000フラン程度だったと推定されるので、4万フランは年俸の20倍近い金額と考えれば、作者の設定した額の大きさがある程度推測できるのではないだろうか。
またロワゼルは文部省に勤める役人であるが、モーパッサン自身も1879~80年にかけて文部省に勤めていた。本作をはじめとする役人を題材とした作品には、作者の実体験が投影されていると考えられるだろう。
なお本作には、青柳瑞穂(「首かざり」『モーパッサン短編集』第2巻、新潮文庫)、高山鉄男(『モーパッサン短篇選』、岩波文庫)、山田登世子(『モーパッサン短篇集』、ちくま文庫)等の既訳が存在する。
【付記】
この訳文を、元NHK フリーアナウンサーの島永吏子さんに朗読していただきました! ぜひご一聴ください! (13/07/2021)
【朗読】思わぬ悲劇の結末が心揺さぶる名作〜モーパッサン「首飾り」
***** ***** ***** *****
首飾り
首飾り
それは、可愛らしく魅力的でありながら、運命の過ちゆえに勤め人の家庭に生まれてしまった、そういう娘の一人だった。彼女には持参金もなければ遺産の入る見込みもなく、どこかの裕福で立派な身分の男性に名を知られ、理解され、愛され、結婚してもらえるというような手段を持ち合わせてはいなかった。だから、文部省に勤めるある下級役人と結婚させられるままとなったのである。
身を飾ることができないので質素な身なりをしていたが、落伍者のように不幸だった。それというのも、女性には階級制度も家系もなく、美貌、優美さ、魅力こそが素性や家柄の代わりとなるのである。生まれながらの繊細さ、洗練された優美さに対する本能、精神のしなやかさが、彼女たちにとっての階層となるのであり、庶民の娘をもっとも高貴な貴婦人と同等の地位に置くことにもなるのだ。
自分はあらゆるぜいたく品や豪華なもののために生まれてきたと感じていたので、彼女は絶えず辛い思いをしていた。住居の貧しさ、壁の惨めさ、椅子の擦り切れ具合、布地の醜さに苦しんでいた。すべてそうした事がらは、彼女と同じ身分の女性であれば気づきさえしないようなものだったが、彼女はそれらに悩ませられ、憤りを感じていた。つましい家事を担っているブルターニュ出身の若い女中の姿を目にすると、心の内で苦々しい後悔と迷い乱れた夢とが目を覚ますのだった。東洋の壁掛けが張られ、背の高いブロンズ製の枝付き燭台に照らされる物静かな控えの間や、暖房の重たげな熱気にまどろんで、幅広の肘掛け椅子で眠る短い半ズボンを履いた二人の大柄な召使の姿を夢想した。古い絹布を張った大きな客間や、値もつけられないような高価な置物を載せた上等な家具のことを思い、そして、あだっぽく、いい匂いのする小さな客間を思い描くのだった。その小部屋は午後五時からのおしゃべりのために作られたもので、ごく親しい友人たち、女ならば誰もが憧れ、注意を惹きたいと思うような人気のある著名な男性たちが招かれるのだ。
夕食時、三日間同じままのクロスで覆った丸いテーブルを前に腰を下ろし、正面に座った夫がスープ鉢を目にして満足げに「ああ! 美味しそうなポトフだ! これ以上のものを僕は知らないね……」と断言する時、彼女は極上のディナー、艶やかな銀食器、妖精の森の中に昔の人たちや奇妙な鳥のいるタピスリーのかかった壁を思っていた。素晴らしい食器で出される美味しい料理を、こっそり囁かれ、聞く方はスフィンクスの微笑を浮かべる、そんな甘い言葉を思っていた。そうした言葉は、マスのバラ色の肉やエゾライチョウの手羽肉を食べながら交わされるのである。
彼女には衣装もなく、宝石もなく、つまりは何もなかった。それなのに彼女の好きなものはそれだけだった。そのために自分はあるのだと思っていた。それほどに彼女は、気に入られ、望まれ、魅惑的であり、追い求められることを望んでいたのだろう。
彼女には一人の裕福な女友だちがいて、寄宿女学校の同級生だったが、帰って来てからひどく苦しんだので、もう二度と会いに行きたくはなかった。何日もの間、悲しみと、後悔と、絶望と、苦悩とで、一日中泣きつづけてしまったのだった。
*****
ある晩、帰ってきた夫は誇らしげに、大きな封筒を手にしていた。
――ほら、と彼は言った。君のためのちょっとしたものだよ。
彼女は勢いよく紙を破り、印刷されたカードを取り出した。そこには次の言葉があった。
「文部省ならびにジョルジュ・ランポノー夫人(1)は、一月十八日月曜日、大臣官邸における晩餐会にご出席頂くという名誉を賜りたく、ロワゼル(2)夫妻にお願い申し上げます」
夫が期待したように感激する代わりに、彼女はいまいましそうに招待状をテーブルの上に投げると、呟いた。
――これをわたしにどうしろと言うの?
――だって君、君が喜ぶと思ったんだよ。君はふだん外出しないから、それはとっても良い機会じゃないか! 手に入れるのにとっても苦労したんだよ。みんなが欲しがっているからね。とっても人気があるし、平役人にはあまり回ってこないんだ。そこに行けばお偉方みんなに会えるよ。
彼女はいらだたしそうな目で彼を見ていたが、我慢できずに声をあげた。
――そこへ行くのにどんな格好をしていけって言うつもりなの?
そんなことは思ってもみなかったので、彼は口ごもった。
――それは、劇場に行く時のドレスがあるよ。とてもいいと、僕は思うよ……。
妻が泣いているのを見て、彼は驚き、動揺して口をつぐんだ。二粒の大きな涙が、目の端から唇の端へとゆっくり流れ落ちていく。彼はたどたどしく言った。
――どうしたの? どうしたの?
けれど、たいへんな努力をして苦しみを抑えると、濡れた頬をぬぐいながら彼女は落ち着いた声で答えた。
――なんでもないの。ただ、わたしには着ていくものがないし、だからこのパーティーには行けないわ。招待状は同僚の中で、わたしよりもいい服を着ている奥さんのいる人にあげてちょうだい。
彼は残念がり、また口を開いた。
――ねえ、マチルド。申し分のない衣装で、また別の機会にも役に立つような、そんなに気取っていないものだったら、幾らぐらいかかるかな?
数秒の間、彼女は考えた。自分のための計算をするとともに、倹約家の下役人が即座に却下したり、恐れをなして声をあげたりしない範囲で、彼に要求しうる金額に思いを馳せた。
それから、彼女はためらいがちに答えた。
――正確には分からないけれど、四百フランあればなんとかなると思うわ。
彼は少しばかり蒼ざめた。それというのも、ちょうどそれだけの額を貯めていたからだった。そのお金で一丁の銃を買って、日曜日にヒバリを撃ちに行く何人かの友人たちと一緒に、次の夏に、ナンテールの野原(3)で狩猟パーティーを開こうと思っていたのだ。
けれども彼は言った。
――分かった。四百フラン出そう。せいぜい素敵なドレスを手に入れるんだよ。
*****
パーティーの日が近づいていた。ロワゼル夫人は悲しげで、不安がり、心配を抱えているようだった。もっとも衣装はすでに整っていた。ある晩、夫は彼女に言った。
――どうしたの? ねえ、三日ほど前からすっかり様子が変だよ。
彼女は答えた。
――アクセサリーも、宝石も、身につけるものが何もないのは困るわ。すっかり貧乏人みたいでしょうね。この夜会には行かないほうがましな気がするわ。
彼は口を開いた。
――自然の花をつけたらいいじゃないか。今の季節にはとてもシックだよ。十フランもあれば、二、三輪の立派なバラが手に入るだろう。
彼女は全然納得しなかった。
――駄目よ……、お金持ちの女たちの中で貧乏に見えること以上に屈辱的なことなんて何もないわ。
そこで夫が叫んだ。
――なんてバカなんだ! 友だちのフォレスティエ夫人(4)に会いに行って、宝石を貸してくれるように頼めばいいじゃないか。それぐらいのことは頼める付き合いがあるんだろう。
彼女は喜びの声をあげた。
――本当ね。考えつかなかったわ。
翌日、彼女は友人の家を訪ね、自分の窮状を訴えた。
フォレスティエ夫人は鏡付きの衣装戸棚のところへ行くと、貴重品用の大きな箱を手に取り、戻ってくるとそれを開いて、ロワゼル夫人に言った。
――どうぞ、選んでちょうだい。
彼女はまず幾つかのブレスレット、次に真珠の首飾り、それから金や宝石で出来た見事な細工のヴェネツィアの十字架を目にした。鏡の前で首飾りを試しては、ためらい、それでも外して元に戻す決心がつかなかった。毎回、彼女はたずねた。
――他にはないの?
――あるわよ。探しなさいよ。どれがあなたの気に入るか、わたしには分からないもの。
ふと、黒い繻子の箱の中に見事なダイヤの首飾りを見つけると、彼女の心臓は抑えられない欲望でどきどきしはじめた。それを取る腕は震えていた。ローブ・モンタント(立ち襟のドレス)の上から首の回りにそれを付けると、自分自身の姿を前にして、彼女はうっとりとして動けなくなった。
それから、おずおずと、不安で胸を一杯にしながら彼女はたずねた。
――これを貸してもらえるかしら。これだけでいいんだけど?
――もちろん、いいわよ。
彼女は友だちの首に飛びつき、興奮のままに抱きしめると、その後、宝物を持って逃げるように帰って行った。
*****
パーティーの日がやってきた。ロワゼル夫人は成功を収めた。彼女は誰よりも愛らしく、エレガントで、優美さに富み、顔には微笑みを浮かべ、喜びに溢れていた。男たちはみな彼女を眺め、その名をたずね、紹介されようと手を尽くした。官房の補佐官はそろって彼女とワルツを踊りたがった。大臣も彼女に注目した。
踊る彼女は陶酔と興奮に満たされ、快楽に酔い、もう何も考えず、自分の美貌の勝利と成功の栄誉の中にいた。賛辞と、賞賛と、掻き立てられる欲望と、女たちの中心にあってあまりにも完璧で甘美なこの大勝利とから成る幸福の雲のようなものの中にいたのだった。
午前四時ごろに彼女は出発した。夫は、真夜中ごろから、人気のない小さな客間で、妻が大いに楽しんでいる他の三人の紳士と一緒に眠っていた。
彼は彼女の肩に、持ってきた外出用のコートを着せかけた。普段の生活で着ている質素なコートなので、そのみすぼらしさは舞踏会の衣装の優美さと釣り合わなかった。彼女はそれを感じて、高価な毛皮にくるまった他の女たちに気づかれないように、急いで逃げ出そうとした。
ロワゼルが彼女を引きとめた。
――待ちなよ。外に出たら凍えるよ。僕が辻馬車を呼んでこよう。
だが彼女は彼の言うことを少しも聞かず、足早に階段を降りていった。二人は通りに出たが、馬車は見つからなかった。それで二人は探しながら歩きはじめ、遠くを過ぎてゆく御者を目にしては、大声をあげて呼びかけた。
セーヌ川まで降りてきた時には、打ちひしがれ、寒さに体が震えていた。ようやく河岸に一台の古いクーペ(二人乗りの四輪箱型馬車)が見つかったが、日中は惨めさを恥じているかのように、パリでは日が暮れてからしかお目にかからないようなあの夜専用の馬車の一つだった。
二人は馬車に乗って、マルティール(殉教者)通り(5)の住まいの戸口で降りると、部屋まで悲しげに上っていった。彼女にとっては、これでおしまいだった。彼のほうでは、十時には庁舎に出なければいけないと考えていた。
彼女は肩を覆っていた外套を脱ぐと、栄光に包まれた自分の姿をもう一度見ようと鏡の前に立った。だが、突然に彼女は叫び声をあげた。首元に首飾りがないのだ。
すでに半分服を脱ぎかけていた夫が問いかけた。
――どうしたんだい?
彼女は狂乱の体で彼のほうに振り返った。
――わたし……、わたし……、フォレスティエ夫人の首飾りがないのよ。
彼は驚いて飛びあがった。
――なんだって!…… どうして!…… そんなはずがない!
二人はドレスの襞やコートの折り目の間、ポケットの中、いたるところを探した。まったく見つけられなかった。
彼はたずねた。
――舞踏会を出た時にまだ身につけていたのは確かかい?
――ええ、官邸の玄関で触ってみたもの。
――でも通りで落としたんだったら、僕らはその落ちる音を聞いたはずだ。辻馬車の中に違いない。
――ええ。きっとそうね。番号を覚えてる?
――いや。君のほうは見なかったかい。
――いいえ。
打ちひしがれて、二人は顔を見合わせた。しかたなく、ロワゼルは再び服を着た。
――僕は、と彼は言った。徒歩で来た道をぜんぶもう一度辿って、見つからないかどうかみてくるよ。
そして彼は出ていった。彼女は夜会服姿のままじっとしていた。寝に行く力もなく、椅子の上で打ちのめされたまま、火もつけず、頭は空っぽだった。
夫は七時頃に帰ってきた。何も見つからなかった。
彼は警察に出向き、新聞社に行って褒賞を約束する広告を出し、辻馬車の会社に行き、つまりは一抹の希望のあるところ全てに顔を出した。
このぞっとするような災難に怯えきったまま、彼女は一日中待ちつづけていた。
ロワゼルは夜に帰ってきた。顔はげっそりとして蒼ざめていた。何も見つけられなかった。
――友だちには、と彼は言った。首飾りの留め金を壊してしまったから修理に出さないといけないと伝えるんだね。それで、どうにかするだけの時間を稼げるだろう。
彼の言う通りに彼女は手紙を書いた。
*****
一週間後には、一切の希望が消えてしまったのだった。
五歳は老け込んだロワゼルは宣言した。
――あの宝石の代わりの品を返すことを考えねばならないね。
翌日、首飾りの入っていた箱を手に取ると、二人は、箱の内側に名前の記されていた宝石商に赴いた。宝石商は帳簿を調べた。
――この首飾りをお売りしたのは、奥様、私ではございません。こちらでは宝石箱だけを納めさせていただきました。
そこで二人は宝石商から宝石商へとまわり、悲しみと不安とに二人とも気分を悪くしながら、記憶を頼りに、よく似た首飾りを探した。
パレ=ロワイヤルにある店で、自分たちが探しているのとまったく同じと思えるダイヤモンドの首輪が見つかった。値段は四万フラン。三万六千まで値下げするという。
二人は三日の間、他の人に売らずに待ってもらうように頼んだ。そして、もしも二月末までに最初のものが見つかったら、三万四千フランで引き取ってもらうという条件をつけた。
ロワゼルには、父が遺してくれた一万八千フランがあった。残りは借金することになる。
彼は金を借りた。ある者に千フラン、別の者に五百を、こちらに五ルイ(百フラン)、あちらで三ルイ(六十フラン)を。彼は手形を切り、額のかさむ契約を結び、高利貸しやあらゆる種類の金貸しを相手に取引をした。余生のぜんぶを巻き添えにし、契約を履行できるかどうか分かりもしないままに署名すると、将来についての不安、自分の身に降りかかる陰鬱な貧窮、あらゆる物理的欠乏と精神的苦痛とに恐れおののきながら、新しい首飾りを求めにゆき、店のカウンターに三万六千フランを置いた。
ロワゼル夫人がフォレスティエ夫人に首飾りを返した時、彼女は気分を害したような様子で言うのだった。
――もっと早く返してくれてもよかったんじゃない。わたしだって必要になったかもしれないんだから。
彼女は宝石箱を開けなかったが、そのことを恐れてびくびくしていたのだった。もし取り換えに気づいたら、あの人はどう思っただろう? なんと言っただろう? わたしのことを泥棒女だと思ったのではないかしら?
*****
ロワゼル夫人は恐ろしい窮乏生活を経験した。もっとも、彼女は一気に、勇ましく、決意を固めたのだった。このぞっとするような額の借金を払わなければならない。きっと払ってみせよう。女中には暇を出した。引っ越しをして、屋根裏部屋を借りた。
彼女は家事というたいへんな仕事、台所仕事という忌わしい労働を身をもって知った。皿を洗い、脂まみれの陶器や鍋の底でバラ色の爪をすり減らした。汚れた下着、シャツや布巾を石けんで洗い、ひもに吊るして乾かした。毎朝、ゴミを出しに通りに降りて、水を運び上げる時には、各階ごとに立ち止まって一息ついた。庶民の女のような恰好で、八百屋、乾物屋、肉屋へと買い物かごをぶらさげてゆき、値切ってはののしられても、わずかのお金をちびちびと倹約した。
毎月手形の支払いをし、別のものを書き換え、猶予を得なければならなかった。
夫は、晩にはある商店の会計処理をし、夜にはしばしばし一ページ五スーの代書を行った。
そしてこんな生活が十年間続いた。
十年後、二人はすべてを返済することができたのだった。高利の利率も積み重ねた利息も含めたすべてをである。
ロワゼル夫人は今では年老いたように見えた。彼女は力強く、厳しく、無骨な、貧民の家庭の女になった。髪に櫛も通さず、スカートは歪んで、手は赤く、大声で話し、じゃぶじゃぶと水で床を洗う。だが時折、夫が事務所にいる時に、窓辺に腰を下ろして、昔のあの夜会のことを、彼女がとても美しく、大いに歓待されたあの舞踏会のことを思うのだった。
あの首飾りをなくしていなかったらどうなっていただろう? そんなこと、誰に分かるだろう? 人生とはなんと奇怪で、変わりやすいものだろう! 破滅したり、救われたりするのに、なんとわずかなもので足りることだろう!
*****
ある日曜日、週日の仕事の疲れをいやすためにシャン=ゼリゼ通りをひと巡りしに出かけた時、ふと、子どもを散歩させている一人の女性に気がついた。変わらずに若く、美しく、魅力的なフォレスティエ夫人だった。ロワゼル夫人は感動を覚えた。話しかけにいこうか? ええ、もちろん。すべて支払ってしまったんだから、ぜんぶ話してしまおう。どうしてそうしてはいけないことがある?
彼女は近づいていった。
――こんにちは、ジャンヌ。
相手には彼女がまったく分からず、こんな風におかみさんに親しげに呼びかけられたことに驚いていた。彼女は口ごもった。
――でも……、奥様!…… 私には分かり…… お間違いじゃありませんこと。
――いいえ。わたし、マチルド・ロワゼルよ。
女友だちは叫び声をあげた。
――ああ!…… かわいそうなマチルド、なんて変わってしまったの!……
――ええ、あなたに会わなくなってから、とっても辛い日々だったわ。とっても貧しくて…… それもあなたのせいなのよ!……
――わたしの…… どういうことなの?
――大臣のパーティーに行くためにわたしに貸してくれたあのダイヤの首飾りのことを覚えているでしょう。
――ええ。それで?
――それで、わたしはそれをなくしちゃったの。
――なんですって! だってあなたは返してくれたじゃない。
――わたしがあなたに返したのはそっくりの別物だったの。それで十年かけてわたしたちはその支払いを済ませたの。財産のなかったわたしたちにとって、それが簡単ではなかったって分かるでしょう……。 やっとのことで終わって、わたしはとっても満足しているのよ。
フォレスティエ夫人は動きを止めていた。
――わたしのと取り換えるために、ダイヤの首飾りを買ったって言うの?
――ええ。ねえ、あなた、気づかなかったんでしょう? とってもよく似ていたものね。
そして彼女は誇らしいと同時に素直な喜びを感じて微笑みを浮かべた。
フォレスティエ夫人は、すっかり心を動かされ、彼女の両の手を取った。
――ああ! かわいそうなマチルド! でもわたしのは偽物だったのよ。せいぜい五百フランのものだったんだから!……
『ゴーロワ』紙、1884年2月17日付
『昼夜物語』、マルポン&フラマリオン書店、1885年所収
Le Gaulois, 17 février 1884.
Contes du jour et de la nuit, Marpon et Flammarion, 1885.
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, éd. Louis Forestier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1974, p. 1198-1206.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
『昼夜物語』、マルポン&フラマリオン書店、1885年所収
Le Gaulois, 17 février 1884.
Contes du jour et de la nuit, Marpon et Flammarion, 1885.
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, éd. Louis Forestier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1974, p. 1198-1206.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
訳注
(1) Ramponneau の名は、18世紀の有名な居酒屋店主 Jean Ramponneau (1724-1802) を想起させ、諷刺的な意味を持ちうるものとなっている。
(2) Loisel の名は l'oiselle と同音であるが、oiselle には「雌鳥」から派生して「うぶで愚かな娘」の意味が含まれる。
(3) Nanterre はパリ西部の郊外の町。ナンテールの平原は19世紀当時、狩猟家に愛好された。
(4) Mme Forestier の名は長編小説『ベラミ』にも見られる。本作発表時はちょうど『ベラミ』執筆中でもあった。なお forestier には「森林の」「森林を管理する人」の意味があり、ロワゼルの名と意味的関連が認められるかもしれない。この点を含めた本作の詳細な読解として次の論考がある。柏木隆雄、「対訳で楽しむ『首飾り』」、『ふらんす』、2006年、4月号―7月号。
(5) Rue des Martyrs : パリ北部モンマルトル地区、9区から18区にかけて実在する通り。
