永井荷風とモーパッサン
Nagai Kafû et Maupassant
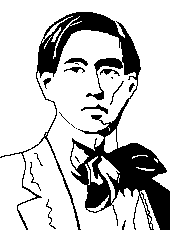 日本の作家の中で最もモーパッサンに親しみ、彼の文学を理解したのは永井荷風(1879-1959)だったかもしれない。『ふらんす物語』初版に収められた「モーパッサンの石像を拝す」に、このフランスの作家へ向けた熱烈なオマージュが読まれることは有名だ。
日本の作家の中で最もモーパッサンに親しみ、彼の文学を理解したのは永井荷風(1879-1959)だったかもしれない。『ふらんす物語』初版に収められた「モーパッサンの石像を拝す」に、このフランスの作家へ向けた熱烈なオマージュが読まれることは有名だ。
「そもそも、私がフランス語を学ぼうという心掛けを起しましたのは、ああ、モーパッサン先生よ。先生の文章を英語によらずして、原文のままに味いたいと思ったからです。一字一句でも、先生が手ずからお書きになった文字を、わが舌自らで、発音したいと思ったからです。」
(「モーパッサンの石像を拝す」、『ふらんす物語』、岩波文庫、257頁)
1903(明治36)年、アメリカに渡った荷風はフランスへの憧憬を一層に募らせ、1907(明治40)年7月、遂に待望のフランスの地を踏むのだが、アメリカ滞在中にモーパッサンの著作に親しんだことが『西遊日誌抄』から伺い知れる。該当の記述を抜き出してみる。
*****
1905(明治38)年
8月3日 毎日炎暑甚しけれど華盛頓(ワシントン)の市街は到処メエプルの老樹に蔽はれ馬車の往来烈しからず辻々にはまた必ず美しき花壇の設けあり。夕暮その腰掛にいこへば街燈の光に心静けく読書し得べし。モオパッサンが紀行『水上』を読む。
1906(明治39)年
4月2日 西区卅二丁目辺の裏通は仏蘭西の移民町なり。仏蘭西の酒場ありて娼婦多くつどふ。揚代三弗より五弗位なりとぞ。この移民町にはまた仏蘭西の貸本屋ありてドオデ、モオパッサンなぞの小説もそなへたり。また内々にて如何はしき絵も売るなり。この夜亭主と懇談す。
6月9日(土曜日) 新緑愛すべし。人なき公園の樹下に坐し携へたるモオパサンの詩集を読みて半日を過しぬ。夕陽のかげ、新緑の梢にやうやゆ薄くなり行く頃あたりの木立には栗鼠の鳴き叫ぶ声物淋しく、黄昏の空の色と浮雲の影を宿せる広き池の水には白鳥の姿夢の如くに浮び出せり。何ら詩中の光景ぞや。余は頭髪を乱し物に倦みつかれしやうなる詩人的風采をなし野草の上に臥して樹間に仏蘭西の詩集よむ時ほど幸福なる事なし。笑ふものは笑へ余は独り幸福なるを。
6月22日 モオパサンが短篇集『メイゾン・テリエー』を読む。
7月16日 モオパッサンの作『ベルアミイ』を読みはじむ。
8月23日 心漸く日常の平和を保ち得たり。朝銀行に赴くべき列車の中にてモオパサンを読む。小波先生その著『笑の国』を送らる。
9月17日 病よからず臥床の中にてモオパッサンの『イヴェット』を読む。
10月3日 空よく晴れたれば始めて外出し手袋を買ふ。風甚だ寒ければなり。図らず書肆ブレンタノの前を過ぎたれば入りてモオパッサンの『ロンドリ姉妹』を購ひ、それよりイデスの家を訪ひ晩餐を共にす。
(以上『断腸亭日乗』(上)岩波文庫より)
ちなみに「西遊日誌稿」の1908(明治41)年3月30日(28日にリヨンからパリ着)に
「午後パルクモンソーにモーパッサンの像を見る。」
とある。
「ああ、モーパッサン先生よ。私は今、巴里の停車場へ着くと、直ちに、案内記によって馬車を走せ、先生が記念石像の下に、身を投げかけています。」(「モーパッサンの石像を拝す」)」には、多少の潤色が見られるようだ。
荷風はパリに2ヶ月滞在の後、イギリスから帰国の船に乗ることになる。
*****
次に当時の書簡を見る。『断腸亭尺牘』として作者生前に発表されたものとその他のものを合せて時系列に並べて引用する。出典は新版の『荷風全集』第27巻、岩波書店、1995年より。
明治37年2月27日 生田葵山 宛 タコマ発 封書
作物が出来ないので一時は実に云はれぬ程煩悶したがいくら煩悶しても感興が湧かねば駄目だとあきらめて近頃は専心読書に耽つていさゝか素養するつもりである。此間仏国小傑作集と云ふ六冊本でフローベル、ゴーチヱー、メリメー、モーパツサン、バルザツク、ドーデの短篇をあつめた新刊を読んだが、まだ日本の文壇には訳されないでゐる好いものが沢山ある。[...]
劇を見ると劇作者になつて見たい気がすると貴兄は云はれたが全くさうだ。余はオペラを見ればオペラを作りたしローマンスに接するとローマンスに筆を取りたくなる。さうかと云つてフローベルなぞの自然主義に触れると又其れも書いて見たい。思想混乱して遂には何が何やら分らなくなつてしまふ。
明治37年某月 木曜会 宛 タコマ発 封書
○近頃読んだものゝ中で抱一庵の泰西奇文、文藝でモーパツサンの「兄弟」鳥渡面白かつた。
明治37年4月26日 生田葵山 宛 タコマ発 封書
僕は矢張自然主義で行きたいと思つて居る。然しゾラは余りに科学を尊び過ぎて居る。彼は藝術なるものを認めない。――彼は人から自分をアーチストと云はれる事を快しとしなかつた。と云ふに至つては余りに極端だと思ふ。此間一寸読んだのだが彼は沙翁のハムレツトを冷笑した。そして自分の作ラツソンモワルが劇となつて舞台に出るのを見て此れこそ真に自然的のドラマだと喜んだと云ふ。ゾラはあまり極端だよ。然しモーパツサン、ドーデーあたりの筆つきは僕の模せんとする所だ。僕には到底僕の性格上トルストイや何かの様な沈痛陰鬱な作品は書けやう筈がない。仏蘭西的の華やかな悲劇が僕には一番適して居ると自ら思つてゐるのだ。[...]
あゝ!幸福。僕は幸福なのであらう。僕もたしかにさう思ふ。然し君!僕はさう思ひながらも常に悲しい方面ばかりの空想に耽つてしまふ。僕には幸福と云ふものゝ定義解釈を施す能力がない。何でも構はん・・・「心の行く処に満足し得た時が幸福だ」と云ふモーパサンの言が真の幸福の定義であらう。
明治38年4月13日 生田葵山 宛 米国ミシガン州発 封書
僕は君が近来ドラマチツクの方面に移つて行かれる事をば余り賛成しない。僕一個の意見では君は依然として叙情的の作家で行つた方が適当だと信じて居ます。ツルゲネフとモーパツサンとを比較して見たなら誰でも一目してその特徴の異なる処を発見する。僕は重ねて君が其の特徴のある処に向はれん事を望みます。
明治39年6月28日 西村恵次郎 宛(ニューヨークより絵葉書)
御無沙汰、酷暑で閉口して居ます。御近作はありますか。モーパツサンの長篇 Une vie を読んで居ます、木曜会へよろしく、巌谷先生の番地を知らしてください。荷風 六月廿八日
明治40年1月1日 西村恵次郎 宛(ニューヨークより絵葉書)
葵山君の人相、モーパツサンのバガボンドとゴルキーとを一ツにした様なもので感伏した。
明治40年7月9日 西村恵次郎 宛(ニューヨークより)
僕はとにかくフランスに居られるだけ長く居て、此の十年近く一度は見たいとあこがれて居たフランスを研究しやう。リオンは南部であればゾラ、ドーデの故郷にも近い。巴里を過ぎる折には一度はナヽの様な女が歩いた往来の敷石にも接吻しやう。
今月の十八日朝十時にフランス舩ブレタンユと云ふので、紐育を去り、行先はフランスのアーブル(モーパツサンの著作に能くある港だ)それからノルマンデーの野をセーン河に添ふてパリーに入り、それから南へ下るのだ。誰れも伴はない、何時も一人旅。
明治40年12月11日 西村恵次郎 宛 リヨンより
此頃はオペラと音楽会へ通学するので、殆ど創作する時間がないので困つて居る。其れ故しばらくは筆をやめて、読書しやうと思つて居る。モーパツサンも已に再読三読し了つたので、何か外にモデルとするやうな作者をめつけて居るが、まだどうも僕の趣好に合ふやうなのがない。目下はゾラの門下から出て、印象派に這入ったHuysmans(ユイスマン)の作(La-bà)だの、其の短篇、パリーのスケツチなぞを読んで居る。其れから、Henri de Regnier(レニヱー)と云ふ人の作をも見た、此れ等の人の作物は、文章が難解で、作意が充分に云現はしてないから、非に骨が折れる。フランスの文壇ではゾラの自然派から一進歩んだ印象派の作物が今の処では最も進歩したものであるらしく思はれる。此の辺の消息は早稲田文学なぞに屡ゝ論じられて居る処だから、日本の文壇も同じ調子で進んで居るものだと信じて居ます。
たしか十一月の新小説であつたと思ふ、花袋氏の「蒲団」を読んだ自分は非常に敬伏しましたよ。すつかりロシヤの自然派式で、然も日本人の頭から出た純粋な明治の作物だと思ふ。
明治41年2月20日 西村渚山 宛 仏蘭西里昴市発 封書
フランスに来てフランスの生活を見ると今更のやうにモオパツサンのいゝ処が分るので此頃は又々それを読返してゐる。[...]
小説は君の云ふ通り要するに藝術である。藝術を外にした小説は小説とは云へない。木の葉一枚を描くのも聖女の像を描くのも藝術としては同一の価値がある。其の哲学的と云ひ理想的と云ふ内容の如何は其の人々の趣味に過ぎない。僕はゲーテもミユツセをも詩人としては上下の差がないと信じて居る。ゴンクール兄弟の純藝術主義で自分は進んでゆくつもりだ。[...]
さて自分は自分一家の思想作物についてはどうしても形式的になつて行く傾があると思つてゐる。自分は形式の作家で満足する。藝術の価値はその内容にあらずして寧如何にしてその内容の思想を発表したかといふ手際にある。水夫が檣の上で大洋の月に対する情懐は大なる詩であるが其れを発表する事の出来ぬ水夫は即水夫で詩人ではない。自分は文章詩句をある程度まで音楽と一致させたいと思つて居る。言辞の発音章句の朗読が直に一種神秘な思想に触れる様にしたい。即ヴヱルレーンやマラルメの詩のやうにしたいと思つて無論此の両詩人の詩は絶えず読返して居る。モーパツサンの短篇中で「夜」だの其れから「水の上」の如きものはたしかに此の境まで進んで居るし又ピヱールロツチのものでは Fantôme d'orient (「東方の幽霊」嘗て己が愛したるトルコの少女の墓を弔ふ文)の書始め又は Le passage de Carmencita(昔馴染のチリーの婦人が老衰して行くさまを書いた短篇)の如きも此の実例であらうと思ふ。結構も思想も単純で強ひて其の主意を云へば悲しいとか哀れだとか云ふ一語で尽きて了ふが読んで居ると丁度音楽をきくと同様で口で説明の出来ない一種幽艶な悲愁を感ずるのだ。モーパツサンの方は暗夜の中に何か風の音でもきくやうな陰惨を感ずる。
明治41年4月17日 西村渚山 宛 巴里発 封書
○自分は今巴里の書生町(Quartier latin)の宿屋に泊つて居る書生町の書生生活(Bohemian life)を日々目撃すると自然と思出すのはゾラとモーパツサンとの差別である。ゾラは「クロードの懺悔」を書いて書生町に居る女郎の生活を描いた。モーパツサンのは短篇中にHermite(隠者)Reveillon(聖誕祭の前夜)など其他沢山あつたと思ふ。ゾラのものは如何にもゾラ式で精密極まる写実にも係らず人物や景色が実際の生きたものよりは要するに「ゾラの書いた人物や景色」であると云ふ感じを脱し得ない。此れに反してモーパツサンの短篇になると直に自分が目に見る生きた人生で簡単な物語の中に無限の悲しみが含れてゐる。君も既に御存じかも知れぬが Hermite(隠者)の一篇は昔書生町に居た男が幾年かの後或晩書生町を散歩してとある料理屋に入りその時出来心で女を買う。女の部屋へ泊りに行くと暖炉の上に一枚の女の写真があつた。何心なく見るとこれこそ昔書生時代に自分が馴染んだ女で今買つた女は誰あらう自分の落し胤であつたと云ふだけだが此の一篇などは書生町の一部の生活が驚く程鮮明に深刻に反映してゐる。又 Reveillonと云ふ一篇はある男がクリスマスの前夜に独身生活の淋しさに往来を歩いて居る女郎を呼び自分の部屋につれて来て晩餐を食う。すると突然女は病気になる。女は実はポテレンになつてゐたので食事最中に産気がついて其の夜男の部屋で子を産むといふ滑稽談である。此等は僅か二三頁の小篇で巴里街頭を彷徨する哀れな女郎生活の一面が十二分によく現はれて居る。自分は毎日散歩する毎にモーパツサンの魔筆に感服してゐる。
○モーパツサンの墓は書生町からは程遠からぬ巴里の南端モンパルナスの墓地にある。二三日前に参詣した。又その記念碑は巴里の貴族富豪町の公園モンソーの池のほとりにある。
*****
ところで荷風が読んだモーパッサンは、時期から見て恐らく最初の全集(挿絵入り)であるオランドルフ版だったと考えられる。もっとも入手したのが古本(貸本)であったならば、オリジナルの版だった可能性も無いわけではない。いずれにせよ『イヴェット』『ロンドリ姉妹』などは作品集のタイトルであり、所収の短編を一通り読んでいることは確かであろう。
当然、日誌や書簡に記された以外の書物も手にとっていた可能性があるので、モーパッサンの著作を「ほぼ読み盡したと推定されよう」(伊狩章「永井荷風とモーパッサン」、「国語と国文学」1954年、6月号、国書刊行会『日本文学研究大成 永井荷風』1988年に再録)と考えることも出来よう。
(「モーパッサンの石像を拝す」には、愛人イデスが「わかれに臨んで私に先生の著作の大半を買ってくれました」とある。また「モーパツサンも已に再読三読し了つた」(明治40年12月11日)の言葉に、モーパッサンへの傾倒ははっきりと記されている。)
さて、以上のようにモーパッサンに入れ込んだ荷風であってみれば、彼の作品にモーパッサンの影響が現れるのもごく自然なことかもしれない。実際、欧米滞在の経験に基づく『あめりか物語』『ふらんす物語』の二作品にモーパッサンの影響が見られることに関して、評者の意見は一致していると言ってよい。『あめりか物語』の「様式や素材の上にはモオパッサンの感化が感ぜられるものが多い」という吉田精一の意見などはその典型(『永井荷風』吉田精一著作集5、桜楓社、1979年、47頁。)
ただし、その影響が具体的にどういうものであったかについては、そもそも「影響」とは曖昧なものでもある故に、明確に指摘することは難しいようだ。(前記伊狩論文は反対にモーパッサンの直接的な「影響」を過剰に重視しているきらいがある。)
ところで伊狩氏も既に指摘する通り、モーパッサンの影響は『あめりか物語』に顕著であるが、それに比して『ふらんす物語』にはむしろモーパッサンの影が薄い、というのが一般的な見解であると言っていいだろう。「モーパッサンの石像を拝す」の熱烈な告白とは裏腹に、『ふらんす物語』の時点では既にモーパッサンからの離反が見られるとするならば興味深いが、それはどのようなことを意味するのだろうか。
そして、もしもモーパッサンの「影響」が偏に『あめりか物語』のみに顕著であるならば、それは一過性の「モーパッサン熱」の成せるところのものであったということだろうか。言い換えればモーパッサンの「影響」は表面的なものに留まったのか、どうか。
永井荷風とモーパッサンとの関係を、いま少し詳しく考察してみたい。
*****
そこでまず確認しておきたいのは書簡である。『西遊日誌抄』にモーパッサンの名前が頻出するのは1906(明治39)年だが、荷風は渡仏後もモーパッサンを再読している。実際に目にしたパリをモーパッサンの作品の中に確認し、その「魔筆に感服」している。その限りで「モーパッサンの石像を拝す」の告白も決して突飛ではないということだ。
翻って、『あめりか物語』がとりわけモーパッサンの短編を想起させるとするならば、その理由は色々考えられるが、まずは短編の形式が挙げられよう。吉田精一のいう「様式」である。
『あめりか物語』の諸編は、アメリカ滞在中「日頃旅窓に書き綴りたるもの」から成っており、「旅行記」という要素を強く持っている。そのことは作者自身と思しき一人称の「語り手」の登場する作品の多い点にもはっきりしている。中でもとりわけ、語り手が直接に自己の体験を語るのではなく、友人・知人が自身の体験を、あるいはさらに第三者の体験を回想の形で語るという形式が目につく。また三人称で記述されても「雪のやどり」「一月一日」等、やはり第三者の語りによって物語が構成されている作品もあり、これらの語りの形式はモーパッサンが多用したものであった。この形式の類似がもっとも顕著な特色である。
それが直接にモーパッサンを範としたものであるかどうかを断定することはできないが、そう考えることは十分に妥当であるだろう。しかしここで強調しておきたいのはむしろ、『あめりか物語』における伝聞の語りの形式には必然性がある、ということだ。
既に述べたように滞米報告の様相の濃い諸作において、語り手(=作者)は「異国に於ける異国人」(「春と秋」)であり、彼はアメリカ社会を客観的に概観する立場に立っている。物語の中心にいるのは、既にアメリカ社会の中に生きる在米日本人であり、またアメリカ人だ。その限りで語り手の存在はほとんど「透明」であり、彼は聞き語りの役を務めているだけなのである。
その語りに変化が見られるのは「おち葉」「支那街の記」「夜あるき」「六月の夜の夢」など作品の末尾に並べられる作品で、ここでは語り手「私」が前面に姿を現し、彼の直接の体験が詠嘆を伴って綴られる。そのスタイルは『ふらんす物語』にも引き継がれるわけであり、同時にモーパッサンとの類縁が薄くなるように感じられる由縁でもある。
言い換えれば、アメリカに滞在することになった一青年が、はじめは傍観的に外から眺めていたものが、次第に社会の中に深く入って行く中で、自身の思想や感情を明確に意識し、これを率直に表明することを憚らなくなるまで、という過程を描くのが『あめりか物語』である。そしてそこに芸術家として作者が自立してゆく様を辿るならば、作品集全体が一個の成長物語の様相をも呈する。「今日ではもう形式や流派はない。自分は自分のみだ。人生を忠実に現はすより外にたよる処はない。」(明治41年4月17日 西村渚山 宛)との断言に作家の個性の確立を認めることが出来るだろう。
『あめりか物語』『ふらんす物語』を携えて帰国した荷風は、その評判によって新世代の作家の代表と目されるに至るわけだが、彼がこの二作によって芸術家としての自負を得たことは間違いなく、中村光夫に倣えば、彼は「その青春の自己表現をほとんど完成した」のであり、「彼の表現はこの二つの「物語」で或る完璧な定型を得てしまつたので、今日から読みかへして見れば、荷風の生涯にわたるさまざまの制作の原型がここに集約されてゐることに人々は気付く筈」ということになる(『荷風の青春』、『中村光夫全集』第四巻、筑摩書房、1971年、88頁)。
話を戻せば、伝聞という語りの形式が『あめりか物語』前半の作品に頻繁に採用されていることをして、単にモーパッサンの「模倣」とするのは適当ではないだろう。それがその時点においてもっとも適切な形式であったからこそ採用されているのであるならば、それは決して受身的な「影響」の結果ではないのである。
次に内容(「素材」と言い換えてもよい)について見ると、『あめりか物語』の諸編の多くが男女の関係を語り、情緒的恋愛よりもむしろ、退廃的な官能への耽溺や、愛欲がもたらす悲劇を主題としているという、著しい傾向を認めることができる。ここにも確かに「モーパッサン的」と思わせる様相がある。実際、伊狩章がモーパッサンの「翻案」として挙げている作品およびその原作(?)にも同様の傾向が認められる。そこから「モーパッサンの文学を流れるエロティズムは、江戸文学伝来の荷風の好色趣味とも相通ずるものがあった」(大西忠雄「モーパッサンと日本近代文学」、『日本近代文学の比較文学的研究』清水弘文堂、1971年、193頁)といった見解が引き出される。
だが注意したいのは、ここでもことは一方的な「影響」ではなく、荷風自身のより意識的な「選択」が働いている点を見落とさないことである。
その「選択」は例えば、「西遊日誌抄」に登場するモーパッサンの書名にも現れている。
そこには『水の上』『詩集』『メゾン・テリエ』『ベラミ』『イヴェット』『ロンドリ姉妹』の名前が読まれるが、旅行記『水の上』をひとまずおけば、他はいずれも遊女や「色男」の物語である点は注目に値する(『詩集』の詩篇の多くも恋愛を率直な言葉で歌っている)。書簡には名の挙がる『女の一生』や『兄弟』(ピエールとジャン)はこのリストから意図的に排除されているようだ。一方、書簡の中で詳しく語っている「隠者の話」« L'Ermite »「クリスマスの夜食」« Un réveillon » もまた娼婦を扱った話であるなど、徹底しているといってよい。
あえて断るまでもなく、モーパッサンが「娼婦もの」(とそれに類する物語)ばかりを書いているから、このような結果になったわけでは、もちろんない。荷風の意図的な選択の結果、このような作品が並んでいるのである。
帰朝後の永井荷風がやがて自らの主題を花柳界、公私にわたる娼婦の世界に限定してゆくのは人の知るとおりだが、その源泉は『あめりか物語』を越えて渡米以前にまで辿ることができる。『地獄の花』やゾラの影響のいわれる『夢の女』の時点から既に、裏町の「ひかげの花」は彼にとって特権的な主題であった。その限りで言えば、『あめりか物語』の主題に見られる顕著な偏向をモーパッサンの「影響」と見るのは正しくない。荷風は「素材」においてもまた、モーパッサンの中から自分にとって意義あるもの(だけ)を極めて意識的に選び取っているのであり、そこに見られるのは積極的、そして選択的(すなわち限定的でもあるよう)な受容の実態なのだ。
渡米以前、ゾライズムを推奨していた頃に既に定まっていた性向、アメリカで実際に目撃した下層社会の悲惨な現実、それを傍観的に観察する「異国の異国人」たる立場。そのような幾種もの、青年永井壮吉をとりまく状況が、彼のモーパッサン文学の受容のありようを明確に条件づけ、また限定していわけだが、その条件の中において彼の選択は見事なまでに狂いがない、ということに我々は驚かされるのである。
『あめりか物語』にモーパッサンの影が濃いとすれば、その理由は以上のようなものであるだろう。
ところで、『あめりか物語』から『ふらんす物語』に見られる語り手(=作者)の成長を、ゾラ、モーパッサンからロチやアンリ・ド・レニエ、あるいはボードレール、ヴェルレーヌへの移行とする見方が存在する。しかし興味・関心をひく作家の変化が、直接の影響として作品の性質の変化を生んだと考えるのは適当ではない。その証拠に、例えば書簡に見られるように、フランスへ移って以降にモーパッサンを一層愛読している事実は確かに存在している。ゾラ、モーパッサンの自然主義作家による「客観的」描写から、デカダン派、象徴派の「主観的」叙述への移行といったような記述は事実を単純化しすぎており、なにより永井荷風自身も、決してそのような区別をしていたのではなかった。
事実はむしろ逆であって、ここでも荷風はその時の自分にとってもっとも意義ある作家・作品を意識的に選択しているのだ。作者の側の立場と心情の変化が、それに呼応する文学作品を(モデルとして)招来する。『あめりか物語』後半、そして『ふらんす物語』にはボードレール、ヴェルレーヌ、レニエ、そしてミュッセの詩が頻繁に引用され、その傾倒ぶりは作家のナイーヴさを露見させているが、しかし彼が自分の書くものについて自覚的であったことに変りはない。
同時に作家荷風にとっては、モーパッサンをとるかレニエ(あるいはボードレール、ヴェルレーヌ)をとるかの二者択一的な選択が問題となっていたはずがないのも自明のことだ。明治38年の時点で荷風は次のように書簡に記している。「どうか勉強して帰国するまでに仏蘭西文学の大概を窺ひたいと思つて居る。」(4月13日生田葵山宛て)実際に滞米、滞仏の期間を通して荷風が目を通した書物の数は相当数に及び、19世紀後半のフランス文壇の事情に精通するに至っている。
荷風における「モーパッサンの影響」を指摘するのが容易でないのは、彼が偏にモーパッサンだけを摂取したのではないのに多くを拠るわけだが、言い換えれば彼は個別の作家の影響を超えて、広くフランス近代小説を規定する精神を理解し、またこれを消化することが出来たほとんど唯一の作家であった。そしてその上で彼が辿り着いたのは、既に引いた「今日ではもう形式や流派はない。自分は自分のみだ。人生を忠実に現はすより外にたよる処はない」という芸術家永井荷風を決定する決意の表明であった。この言葉が優れて世紀末のフランスと通底するものであるということは強調されていいし、フロベールの教えを受けてオリジナリティの重要性を説いてやまなかったモーパッサンの声もまた、そこにこだまのように響いている(荷風が『ピエールとジャン』の冒頭におかれた「小説論」を読まなかったとはとても考えられない)。
だから「影響」のあり処は本当は「様式や素材」に求めるべきではなく、もっと深いところを見なければならない筈のものであるだろう。
*****
とは言え、話を広げすぎると収拾がつかなくなるので、ここで視点を変えて、永井荷風はどのようにモーパッサンを捉えていたのかを、改めて問題にしたい。
書簡や「西遊日誌抄」、また『あめりか物語』『ふらんす物語』の記述から窺うならば、パリの下町の庶民の生活の実態を、簡潔な言葉で巧みに描き出した作家というのが、まずもってモーパッサンのイメージであっただろう。その点は「直に自分が目に見る生きた人生で簡単な物語の中に無限の悲しみが含れてゐる」の言葉に見事に要約されている。中でもとりわけ娼婦(女郎)に焦点が当てられているのは既に見たとおりである。
しかしそれだけのことであるならば、「モーパッサンの石像を拝す」の激越な調子は生まれなかったかもしれない。彼にこの激しい告白をさせるに至った理由はどこにあるのだろうか。
そこでまず考えるべきなのは、荷風がフランスという国に抱いていた憧れの強さだ。その点にはすでに多くの論考があるけれども、芸術家として大成するためには是が非でもフランスを目にしなければいけないという思いは「西遊日誌抄」に繰り返し述べられている。そして、フランス、とりわけパリとは、ゾラやモーパッサンが作品に描いた国であり、街であった。
「私は、どんな事をしても、フランスへ渡って、先生のお書きになった世の中を見たい、もし、この志がとげられなければ、私は例え、親が急病だといっても日本へは帰るまい、と思いました。」(「モーパッサンの石像を拝す」、『ふらんす物語』、258頁)
「自分はいうまでもなく、モーパッサンの作物―― La Passion, Mon oncle Jules または、Pierre et Jean なぞいう小説中に現れているこの港の記事を思い浮べて、大家の文章と実際の景色とを比べて見たいと、一心に四辺を見廻していたのである。」(「船と車」、『ふらんす物語』、10頁。)
「フランスはフランスの藝術あって初めてフランスである」(「船と車」、18頁)のであり、荷風にとっては、中でもモーパッサンとフランスとは密接に結びついて分かちがたい。換言するなら、この時、モーパッサンは憧れのフランスのシンボルともいうべき存在であったのである。「私は今、巴里の停車場へ着くと、直ちに、案内記によって馬車を走せ、先生が記念石像の下に、身を投げかけています。」(「モーパッサンの石像を拝す」)という一文は明確にそのことを告げているだろう。「モーパッサンの石像に拝する」とは、そのまま「パリの街に拝する」のとほぼ同義であり、その象徴的な表現であったのだ。
もっともその限りでは、「巴里を過ぎる折には一度はナヽの様な女が歩いた往来の敷石にも接吻しやう」との言葉にもあるように、モーパッサンだけが唯一絶対の作家ではないとも考えられる。
「フランス人の作家」モーパッサンがさらに重要な意味を持ったのは、芸術家としての彼の思想ゆえであり、また彼の人生そのものが荷風に強く訴えるものであったからに他ならない。
ここはどうしても「モーパッサンの石像を拝す」を、初版の形で読まなければいけない。次の引用が文章の末尾である。
私は先生のように、発狂して自殺を企てるまで苦悶した藝術的の生涯を送りたいと思っています。私は、先生の著作を読み行く中に、驚くほどの思想の一致を見出します。私等が今日感じた処を、先生は已に三、四十年前に経験しておられたのです。
先生は人生が単調で、実につまらなくて、つまらなくて堪えられなかったらしいですね。愛だの、恋だのというけれど、つまりは虚偽の幻影で、人間は互に不可解の孤立に過ぎない、その寂寞に堪えられなかったらしいですね。老年という悲惨を見るに忍びなかったらしいですね。「要なき美」 Inutile Beauté で論じられたように、私も神が作った人間の身体組織には不満足ですよ。紀行「水の上」 Sur l'eau の中で説明された通り、私も無限を夢みるためには、ヱテールの蒸発気を嗅いで、筆を走らせる時があるでしょう。
私はこれから、先生の遺骸を埋めたモンパルナスの墓地に参詣しましょう。私のささげる一束の花を受けて下さい。ああ、崇拝するモーパッサン先生。(262頁)
ここで青年荷風の過剰な感傷を笑うまい。重要なことは彼は確かに、モーパッサンの内に芸術家としての理想を見出していたということである。現世に幻滅する一方で芸術に人生を捧げ、最後は狂気の内に幕を閉じるという生涯。そこには明確に世紀末のデカダンな芸術家観が窺える。
事実はどうあれ、ここで荷風はそのような芸術家像を自己の理想として表明しているのであり、この一文の重点は実際のモーパッサン以上にはるかに、そのような自己イメージの提示にある。詳細に読めば「モーパッサンの石像を拝す」は、モーパッサン自身についてはほとんど実のあることを語っていないことが分かるが、代わりにあるのは、偏に自己の苦悩と理想の、過剰な感傷に誇張された吐露ばかりなのである。
従って、二重三重の意味において、モーパッサンは永井荷風にとっての「理想像」であった。言い換えれば、彼は自己のあるべき姿をモーパッサンの内に投影していることになる。「モーパッサンの石像を拝す」はつまり、帰国時点での芸術家永井荷風のマニフェストとして書かれていると言えよう。
その限りにおいて荷風のモーパッサンの理解の程度を疑ってみることも出来るのだが、しかし忘れないでおきたいことがある。
それはこのようにモーパッサンを「作家像」において捉えた作家は、当時の日本人に他にはいなかった、ということだ。
日本においてモーパッサンを最も積極的に受容したのは、恐らくは田山花袋であろうが、英訳の短編集によってモーパッサンを知った花袋にとって何より衝撃だったのは、モーパッサンのいわゆる「露骨なる描写」、当時の言葉で言う「性欲」「肉欲」を道徳に捕われずに赤裸々に描く、その大胆さにあった。彼に代表される日本の自然主義文学者達は、多かれ少なかれモーパッサンを「発見」したわけだが、しかし彼等が荷風のように「作家モーパッサン」について、どれだけの理解をしていたかは疑わしい。
同時代にあって荷風が突出しているのは、彼がフランス語の原文で読んだ点にももちろんあるが、フランス語が出来た彼は、より広く作家についての情報を得ることが出来たという点も見逃せない。具体的には、彼がモーパッサンの最初の伝記たるメイニヤルの『モーパッサンの生涯と作品』 Edouard Maynial, La Vie et l'œuvre de Guy de Maupassant (1906)を読んでいたことは疑いない。
そのことを記憶に留めた上で、荷風におけるモーパッサン像をもう少し考えるなら、興味をひくのは書簡において『水の上』『夜』について語っている箇所だろう(明治41年2月20日 西村渚山宛)。
ここで言う『夜』は、恐らく旅行記『放浪生活』の中の「夜」と題された一章である。後に荷風は、この章と『水の上』の中の「4月8日」の章を合せて訳し「モオパツサンの扁舟紀行」と題して『珊瑚集』に収めているのである。
荷風がこの両者を訳出した理由は明確だ。いずれにおいてもモーパッサンは多数の詩作品を引用している点で関心を惹いたに違いなく、また『珊瑚集』の趣旨にも適っていた。
ここでは詳述を避けるが、問題の書簡で荷風はヴェルレーヌ、マラルメの名を挙げて象徴主義芸術について語っており、その延長にモーパッサンの二編について言及している。とりわけ「夜」の断章はボードレールの「コレスポンダンス」やランボーの「母音」を引いてモーパッサン自身が象徴主義芸術について言及している重要な箇所だが、荷風がモーパッサンの散文芸術を象徴主義との関連で理解し、またそれを味わっている、という事実は強調されてよい。当時にあって、これは実に革新的なことだ。
もっともモーパッサンの、そして荷風自身の「象徴主義芸術」理解の程度は疑ってかかるべきである(cf. 松浦寿輝「荷風と「世紀末」」新版全集、月報12)。しばしば「印象主義」の語を用いている荷風の象徴主義の理解は、むしろロマン主義的な叙情への傾向の強いものであったし、またモーパッサンの側でも、デカダンの究極としての象徴主義を病的なものとして、十分に評価しているとは言い難い。
だがそれでも「音楽」としての散文芸術の理想を詠い、その実践としてモーパッサンを捉えている荷風の先進性は十分に評価されるべきだし、日本の自然主義作家と最も隔絶している点もそこにこそ認められるだろう。
そして、たとえば「巴里の別れ」においてモーパッサンとボードレールの名を並べることに荷風が違和を感じていない理由もそこにある。要するに、荷風は決して、モーパッサンをゾラと同じ「自然主義作家」の範疇に限定してはいない。デカダン派ともサンボリスムとも近しい、世紀末に生きた一人の芸術家としてモーパッサンは彼の内に存在しえた。モーパッサンを「再読三読」した彼であったればこそ、そのような理解の仕方が可能だったのである。
そこで元に帰って『ふらんす物語』である。憧れの土地フランスに辿り着いた感動がこの作品集の全体を覆っているといってよく、その限りにおいて『あめりか物語』に見られた客観的・没主観的な語りは影をひそめている。一般のモーパッサンのイメージとはかけ離れて見える理由はそこにあるわけだが、しかしそのような(直感的な)判断自体が、どこまで正当なものであるかを疑ってみることは不可能ではない。
とりわけ荷風が最初に読んだモーパッサンの作品『水の上』を想起するならば、一人称の叙述によって周囲の景観と同時に自己の主観を余さず語る『ふらんす物語』の各編にも、モーパッサンの文章との類縁を見て取ることは無理ではない。なかでも巻末に収められた帰国途上の情景を綴った「黄昏の地中海」や「砂漠」は、同じ旅行記である点からも『太陽の下』『水の上』のモーパッサンを思い出させるに十分だ。
もちろんそのように言う時にも、やはり安易に「影響」如何を議論するべきではないし、そうなればたとえばロチの名前なども挙げた上で検討することが必要となるだろう。ここで強調したいこととは、読者が「モーパッサン的」だと判断する時に前提となっている「モーパッサン」像とは、そもそもどのようなものであるのかを問い返すことであり、それ以上ではない。
『あめりか物語』『ふらんす物語』あるいは『新橋夜話』や『腕くらべ』『おかめ笹』さらには戦後の『勲章』などの短編の内に、批評家がモーパッサンの影を見て取る時、そこにはいつもある一定の、そして実際のところ限定的なステレオタイプともいえる「モーパッサン」像が存在している。
それがまったく間違っているのでは勿論ない。だがそれが既成の限定的なモーパッサン像であることを自覚しない限りにおいて、永井荷風におけるモーパッサン受容如何の議論は決して進展することも深化することもありえないだろう。それは広く日本におけるモーパッサン受容についてもまったく同じことである。
ことを皮肉に言い換えるならば、「永井荷風におけるモーパッサン」を論じてきた者達は、果たして荷風以上にモーパッサンを理解していたことがあっただろうか。そのような疑問さえ浮かんでくるのである。
かような偉そうな物言いはただちに自分に返ってくることを十重に自覚しなければなるまいが、その上でこの小文にひとまずのまとめをつけることにしよう。
『ふらんす物語』とモーパッサンの関係は簡単ではないが、忘れてならないのは『あめりか物語』との間でさえ、ことは簡単ではないということのほうであろう。「模倣」「翻案」による受容から、やがて離反へと向かうといった単純な図式が「受容」の本質を取り逃がす原因となりかねない。第一に荷風を取り巻く状況の変化があり、彼のモーパッサン理解もまた変化・深化してゆく過程がある。だから『ふらんす物語』においてモーパッサンからの離反が見られるか、という問いの立て方自体に慎重になることが大切なのだ。
より広く、永井荷風におけるモーパッサンの「影響」が表面的に留まったかといえば(以上見てきた事情からも)そんなことはなかっただろうと、現時点の私は考える。しかし結果的によく消化されたものほど原型を留めないのであるなら、「影響」の有無を客観的に測定することは不可能だと諦めるべきであろう。より重要なことは「影響」とは異なった形で、両作家の関係を捉えなおす道を探すことであるように思われるが、今はまだそこまでの問いに答える術を持たない。
(ただ確かに言えることは、帰朝後の荷風はフランス文学について多数の評言を残しているが、そこにおいてモーパッサンの存在はむしろ影をひそめるということであり、『ふらんす物語』新版以降、「モーパッサンの石像を拝す」の文章が削除された事実とも符合している。そのことは恐らく、慶応大学教授、「三田文学」主幹としての荷風が「反自然主義」の立場に否応無く置かれる事情と関係があるだろうし、より直接には彼がフランスにおける「現代文学」の趨勢を象徴主義に見て取っていたという事実が持つ意義が大きい。モーパッサンはいわば「時代遅れ」のものとして意識的に閑却されるに至るのは疑いない。ただそのことをしてモーパッサンの「影響」がなくなったとするほどには、事は簡単ではないだろうと思われるのである。)
「永井荷風におけるモーパッサン」を問うことは、同時に自分自身の内にあるモーパッサンの姿を問い返すことに繋がるということを心に留め、今一度両作家の作品を読み返すことにしたいと思う。
(19/03/2007)
追記 1
| 荷風 | モーパッサン |
| 酔美人 | アルーマ Allouma |
| 春と秋 | 父親 Le Père |
| 長髪 | |
| 雪のやどり | 流れながれて L'Odyssée d'une fille |
| 夜半の酒場 | メゾン・テリエ La Maison Tellier |
| 林間 | 身がわり Le Remplaçant |
| 夜の女 | メゾン・テリエ La Maison Tellier |
| 寝覚め | みれん Regret |
| 一月一日 | ボーイ、もう一杯! Garçon, un bock ! |
| 悪友 | 旧友パシアンス L'Ami Patience |
| 祭の夜がたり | ロンドリ姉妹 Les Sœurs Rondoli |
このうち、
翻案 「酔美人」「悪友」「祭の夜がたり」
モーパッサンを粉本 「夜半の酒場」「雪のやどり」「夜の女」
構成や題材を借用 「春と秋」「林間」「寝覚め」「一月一日」
で、「長髪」は佐藤春夫が「モオパッサンの感化」を指摘するも、特定の作品が源泉ではない、とする。また『ふらんす物語』中「祝杯」に「いなか娘のはなし」からの暗示が濃い、との指摘も見られる。
ここではそれぞれの妥当性は問わないが、例えば「酔美人」を「アルーマ」の「翻案」と断じてしまうのはいささか誇張の感があるようだ(翻案というのは実に定義の曖昧なものだけれども)。
追記 2
以下、『あめりか物語』『ふらんす物語』中、モーパッサンに関する言及箇所の引用。いずれも岩波文庫、2002年より。なお「モーパッサンの石像を拝す」は全文になるので割愛。
[...]その中に、作者も題目も忘れ果てている一篇の短い翻訳小説の趣向が、この場合大いに熟慮参考すべきものであると気付いた。
何でも、磁石力の理論から説き起して、或る男が久しい間或女を恋込んでいたが、どうも迫って見る機会がない、一夜計らずも恋の成立ッた夢を見たので、男は驚き目覚めたが、もう如何にしても思に堪えやらず、折好くも出合せた女の姿を見るや、前後の思慮もなく、矢庭に駆寄って物もいわずに、女の手を握り締めると、不思議や女は久い以前から已にその男の情婦であったように柔順に男の心に従ったとやら。俊哉は篇中の主人公に対して非常に羨しくもまた妬しくも感じたが、さて、この主人公が得た女というのは、一体どんな性質の女であったのかしら。菊枝とは人種が違っているとすれば、深い参考の材料にはなるまいが・・・
(「春と秋」、『あめりか物語』102頁。)
(文中に明記されていないが、「マニェチスム」Magnétismeという作品。1882年ジル・ブラース初出後、1899年オランドルフ版全集『ミロンじいさん』に収められた。翻訳については不明だが、あるいは荷風は原文で読んだものか。)
仏蘭西のモーパッサンは早くもこの退屈極る人生に対して、堪え難い苦痛を感じ「水の上」なる日記の中に、
(厭うべき同じき事の常に繰り返えさるるを心付かぬものこそ幸なれ。今日も明日も同じき動物に車引かせ、同じき空の下、同じき地平線の前同じき家具に身を取り巻せ同じき態して同じき勤めする力あるものこそ幸なれ。堪えがたき憎しみ以て、世は何事の変るなく、何事の来るなく、すべてこれ懶く労れたるを、見破らぬものこそ、ああ幸なれや・・・。)
といっているではないか。されば、饑えたるものの食を求むる如く、この変化なき人生の事件を知ろうとするアメリカ人の如きは、最も幸福というべき者であろう。
(「市俄古の二日」、『あめりか物語』261頁。)
(『水の上』の一部を、荷風は後に翻訳し、「モーパッサンの扁舟紀行」と題して『珊瑚集』に収めている。)
――ああ、造花の巧を集めたこれらの名山霊水は、久しい間世の人に驚かれ、敬われている事、もしミルトンが失楽園、ダンテが神曲にも譬え得べくば、かの名も無き村落の夕暮の景色は、正に無名詩人が失恋の詩ともいうべきか。トルストイはベートーヴェンの音楽よりも、農奴の夕の歌に動され、ジョージ、エリオットは古代の名画よりも小さな和蘭画を愛したといえば、自分が常に、博士や学者が考究の玩弄物になっているクラシックの雄篇大作よりも、ツルゲネフ、モーパッサンの小篇に幾多の興を覚ゆる事、敢て自分が浅学の故ばかりでもなかろう。
(「夏の海」、『あめりか物語』269頁。)
自分はいうまでもなく、モーパッサンの作物―― La Passion, Mon oncle Jules または、Pierre et Jean なぞいう小説中に現れているこの港の記事を思い浮べて、大家の文章と実際の景色とを比べて見たいと、一心に四辺を見廻していたのである。
しかし、多分夜のためであったか、自分は遺憾ながらも、それかと思うような景色には一ツも出会さぬ中に、船は早や岸辺近く進んで来た。
(「船と車」、『ふらんす物語』10頁。)
幾年以来、自分は巴里の書生町カルチヱー、ラタンの生活を夢みていたであろう。
イブセンが「亡魂」の劇を見た時は、オスワルドが牧師に向って巴里に於ける美術家の、放縦な生活の楽しさを論ずる一語一句に、自分はただならぬ胸の轟きを覚えた。プッチニが歌劇 La Vie de Bohème に於いては、露地裏の料理屋で酔うて騒ぐ書生の歌、雪の朝に恋人と別れる詩人ロドルフが恨の歌を聞き、わが身もいつか一度はかかる歓楽、かかる悲愁を味いたいと思った。モーパッサンの小話、リッシュパンの詩、ブールヂヱーの短篇、殊にゾラが青春の作「クロードの懺悔」は書生町の裏面に関するこの上もない案内記であった。
(「羅典街の一夜」、『ふらんす物語』242頁。)
南の墓地はモンパルナスと呼びて、モーパッサンの眠る処、またボードレールの墳墓のみならず「悪の花」の記念碑もあれば、夙に詣でて知る処たり。モーパッサンの墓は、猶太人の共同墓地を横ぎりて後、一度フランスの音楽を味いたるものの忘るべからざるセザールフランクの墳墓に近く、いとささやかなる石の柱にその名を止めたるのみ。記録家の伝うる処によれば、後の人文豪の名を慕いて、その亡骸を西の方名士の墓多きラシェーズに移さんとしたれども、虚名を憎みて、翰林院の椅子をすら辞退せし文豪の志を思い、世に残りし母人これを許さざりしがためなりという。
[...]吾はただ一人、黒き喪の姿したる若き女の、遠からぬ新塚の前に跪けるを見たるのみ。暗き石、曇れる空、鳩の声。寂々たるこの周囲の対照して、若き女の美しく、哀れ深きは、さすがに吾をして、礼なく近きて、道聞く事をためらわしたりといえども、また同時に、巴里の浮世の計り難きは、墓辺に偽り泣きて物に打れ易き感情家を誘いし女もありしという、モーパッサンが小篇を思わしめたり。
許し給え。若き喪の人よ。われの余りに、空想多き事を。
(「橡の落葉(墓詣)」、『ふらんす物語』266、269頁。)
(後者の引用は短編「墓場の女」 Les Tombales に触れている。1891年1月ジル・ブラース初出、同年の新版『メゾン・テリエ』に所収。)
すべては皆生きた詩である。極みに達した幾世紀の文明に、人も自然も悩みつかれた、この巴里ならでは見られない、生きた悲しい詩ではないか。ボードレールも、自分と同じように、モーパッサンもまた自分と同じように、この午過ぎの木陰を見て、尽きぬ思いに耽ったのかと思えば、自分はよし故国の文壇に名を知られずとも、藝術家としての幸福、光栄は、最早これに過ぎたものはあるまい!
(「巴里のわかれ」、『ふらんす物語』305頁。)
