夏目漱石とモーパッサン
Natsume Sôseki et Maupassant
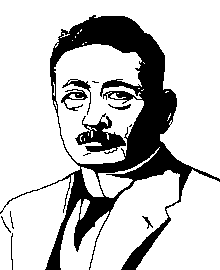 夏目漱石(1867-1916)とモーパッサンの関係はいたって簡明に要約できる。すなわち「嫌い」だった。あるいは、まったく「馬が合わなかった」。――とても簡単だ。
夏目漱石(1867-1916)とモーパッサンの関係はいたって簡明に要約できる。すなわち「嫌い」だった。あるいは、まったく「馬が合わなかった」。――とても簡単だ。漱石は蔵書に感想を書き込む習慣を持っていたが、漱石山房蔵書にはモーパッサンの英訳が3冊存在する(他に、仏語原書が2冊、ただし書き込みは無い)。
百聞は一見に如かずということで、まずは漱石の寸評を読んでみることにしよう。河盛好蔵に倣って(「モーパッサン盛衰記(二)」、『文学界』、46(7)、1992年、p. 242-248. )以下に引用する。
なお出典は新版の『漱石全集』第27巻、岩波書店、1997年、p. 208-213.
*****
944 Maupassant (G. de) : A Woman's Soul (The Lotus Library. 1907)
(前扉および見返しに。○印は漱石自身による)
○完全ナル芸術的作品ニアラズ
○作者ハ Jeanne ノ一生ノ運命ヲ描ケリ。一生ノ運命ニハ continuity ナキコト多シ
○一生ノ運命ハカヽル小冊ニテ書キ了セベキモノニアラズ。モシ書キ了セントセバ冒頭ヨリ其心組ニテ掛ラザル可カラズ。作者ハ普通ノ小説ト同ジク筆ヲ著ケ始メタリ。
○従ツテ簡ナルベキ筈ノ処却ツテ密ニ密ナルベキ筈の所(後半)ハ却ツテ粗ナリ。前半ノクダクダ敷ニ反シテ終リノ方ノ如何ニ急ギ足ナルカヲ見ヨ
○事件ニ連続アリ。事件ニ中心ナシ。河ハ平面ヲウネリ行クニ過ギズ。途切レヌト云フ迄ナリ。此故ニツゞクト雖局部局部ノ見所ガ違フ。即チドレガ主眼ナルヤヲ弁ゼズ。此点ニ於テ興味散漫ニ傾ク。モシ主人公ノ一生の運命ソノモノガ興味[ノ]中心ナリト云はゞ夫迄ナリ
○Jeanne ノ夫ハ下女ト通ジ。其上有夫姦ヲ犯ス。Jeanne ノ父モ母モ不品行ナリ。コトサラニ斯ル人物ヲ集メテ小説ヲ作ル必要ヲ認メズ
○characterization トシテハ人物ノイヅレモガ入神ナラズ。是ガ物足リヌ大源因カモ知レズ
○作者ハ只事件ノ推移ニヨリテ Jeanne ノ運命ノミヲ描カントアセリ過ギタルニハアラザルカ。
(他に本文中に good, too much 等の書き込みがあるが割愛する。)
945 Maupassant (G. de) : Guy de Maupassant (Little French Masterpieces. 1904)
The Horla [同書三‐五九頁] (引用者注 「オルラ」)
愚作ナリ [(p. 59): 同作品末尾の余白に]
Little Soldier [同書六三‐七八頁] (「豆兵士」)
是モ愚作ナリ [(p. 78): 同作品末尾の余白に]
A Coward [同書八一‐九九頁] (「ひきょう者」)
是モ愚作ナリ [(p. 99): 同作品末尾の余白に]
Vain Beauty [同書一〇三‐一四六頁] (「あだ花」)
面白イ。然シ要スルニ愚作ナリ。モーパサンは馬鹿ニ違ナイ。コンナ愚ナコトヲ考ヘツク者ハ軽薄ナル仏国ノ現代ノ社会ニ生レタ文学者デナケレバナラナイ。毫モ真摯ナ所ガナイ。シカモ毫モ滑稽ナ所ガナイ。只人ヲ釣リ込ンデ読マセル技術ト之ヲ釣リ込ム夫婦ノ関係アルノミデアル而シテ其夫婦ノ関係タルヤ、馬鹿気テ居テ毫モ人生ノ大問題ニワタラナイ。西洋ノ夫婦ハ夫婦ヲ大事ニスルト公言シナガラ其口ノカハカヌ内ニコンナ軽薄ナイタヅラヲ到ル所ニ演ジテ居ル。英国デモサウデ[ア]ル。仏国ハ尤モ甚シイ。日本ナラバ噺家ノヤリソウナコトダ。何等ノ趣味モナイ考モナイ寄席ヘ行ツテ手ヲパチ々々叩く連中が歓迎スルノミデアル。文学ハコヽニ至ツテ堕落デアル。此技術アル文学者ガ堕落シタノハ尤モ厭ナ感ジデアル。容色ノイヽ女デオキやンナノト同様デアル。
英国ノ貴夫人抔ト云フ者ハ之ヲ読ンデ拍手スル連中バカリデアル。要スルニ高尚ナ趣味モ何モ分ラナイノデアル。 [(p. 146): 同作品末尾の余白に]
The Piece of String [同書一四九‐一六四頁] (「ひも」)
○モーパサンは何時でもこゝ迄かくからいけない。こゝまでかけば不自然ニナツテ、折角ノ話ヲ打壊して仕舞ふ。[p. 164. ll. 4-9: 同作品最後の部分に対して]
Moonlight [同書一六七‐一七八頁] (「月光」)
是ハヨシ [p. 178 : 同作品末尾の余白に]
The Necklace [同書一八一‐二〇〇頁] (「首飾り」)
○此落チガ、嫌デアル。コヽニ至ツテ今迄ノイヽ感ジガ悉ク打チ壊サレテ仕舞フ。ナゼモーパサンはかうだらう。此一節ガナケレバ夫婦ノ辛苦シタノハ全ク義理堅イ美徳デ軽薄ナル細君モ此出来事ノ為メニ真正ナル人間トナツタノダカラ、読者モ非常ニ同情ヲモツテ読ンデ行カレルノニ、此結末ノ一節ノ為メニ夫婦ハ丸デ馬鹿ニサレテ仕舞フ。ツマリ毫モ利目ノナイ美徳ヲツクシテ居タノデアル。天下ニ何ガ愚ダト云ツテ、人ニ馬鹿ニサレナガラ善ヲ骨ヲ折ツテ汲々為シツヽアル程愚ナコトハナイ。換言スレバ其人ノナス善行ガ善行トシテ寸毫ノ結果モ生ジナイ程愚ナコトハナイ。モシ運命ガ相手(此話ノ場合ノ如キ)デアルナラバ読ミ了ツテ馬鹿々々シイ感ジガスル。モシスレカラシのワル者ガ相手ナラバ読ミ了ツテ其相手ガニクラシクナル。相手ガニクラシクナルノハ、夫婦ニ同情ヲ増ス訳ダカラ少シモ構ハナイ。相手ガ運命デアルトキニハ夫婦自身ガ馬鹿々々シク感ズル程読者モ馬鹿[々々]シク感ズル。
モーパサンは何ヲ苦シンデ此夫婦ノ美徳ヲ殺シテ仕舞ツタノカ分ラナイ。ツマリ仏国ノ現代ノ社会ニ生息シテ其冷刻ナ、皮肉ナ空気デ自身ガ臭クナツテ居ルカラデアル。 [p. 200. ll. 5-7 : 同作品の結末部分に対して。]
Tallow-Ball [同書二〇三‐二九一頁] (「脂肪の塊」)
是ハ立派ナル作物ナリ。
但シ後段ノ食物ヲ馬車中ニ食フ人々ガ売春婦ノ恩ヲ忘レテ、一片ノ肉ヲモ与ヘザル所ハ、著者得意ノ所ニシテ却ツテ不自然ナリ。其前迄ニテ沢山ナリ [(p. 291): 同作品末尾の余白に]
946 Maupassant (G. de) : Pierre and Jean (A Century of French Romance. 1902)
[見返しに]
名作ナリ。Une Vie の比ニアラズ。[Une Vie は、邦訳『女の一生』の原題]
○ original [(p. lxii. ll. 11-23) : 同書の冒頭に掲げられた the Earl of Crewe による解説 'Of “The Novel”' 中の次の部分に対して。There is an unexplored side to everything, because we are wont never to use our eyes but with the memory of what others before us have thought of the things we see.]
*****
三連発、もとい四連発の「愚作ナリ」は強烈で、取り付く島もないという感がある。漱石先生が読んだのは仮にも「モーパッサン傑作集」で、有名な短編ばかりを取り揃えていてこれなのだから、どうにもしょうがない。
一見、気ままな読者の放言のように見えるけれど、漱石の批評の観点は一貫していると言っていい。つまり「作家は、何を、どう書くべきなのか」という、書く側としての問題意識が、各評言の背後には常に存在する。これは普通の意味での(読む側からの)「批評」ではなく、作家漱石の文学観の如実な反映と捉えるべきだろう。
「作家は、何を、どう書くべきか」という問いは、(大雑把に言って)「どう書くか」という技術的な面、すなわち美学的問題、および「何を」書くべきかという主題の選択、つまり道徳的問題の両方を含む。前者に関しては「技術アル」と、漱石はモーパッサンをある程度評価しているから(もっとも『女の一生』に関しては相当厳しい)、後者、すなわち作家としての道徳的態度が、日仏二人の作家では決定的に違っている、それが酷評の基本的な理由と言えるだろう。「どの批評も感情的で大づかみだが、共通しているのは作者の倫理性を評価の基準にしていることである」と、秋山勇造も述べる通り(『埋もれた翻訳―近代文学の開拓者たち』、新読書社、1998年、p. 306-307)だ。
要するに、「モーパサン」は不道徳で「堕落」している。それというのもフランス社会が「堕落」しているから悪い。エゴイスムがまかり通って他者に対する「同情」が無い。「軽薄」なことばかりで「人生の大問題」が何も書かれていない。「モーパサンは馬鹿ニ違ナイ。」――ということで、ここまでばっさり断罪した日本の作家は他にはないのではなかろうか。漱石先生が『ベラミ』をお読みにならなくて、つくづく良かったと思う。読んでたらえらいことになったに違いない。
さて問題は「道徳」にある。モーパッサンはそんなに不道徳だったのか、を問題にする前に、漱石先生のお言葉をもう少し聞いてみたい。次は講演「文芸の哲学的基礎」から。これも長くなるけれど、大胆に引用しよう。
(なお、漱石の評言に関しては、大島 真木、「芥川龍之介と夏目漱石 ― モーパッサンの評価をめぐって」、『比較文学』、有精堂出版、1982年、p. 145-167. また、伊狩 章、「夏目漱石と自然主義 ―モーパッサンの評価をめぐって―」、『新潟大学国文学会誌』、28号、1985年、p. 1-18.でも詳しく検討されている。)
出典は同じく新版の『漱石全集』第16巻、岩波書店、1995年、p. 109-113.
(前段までにおいて漱石は、文芸の理想には真・善・美・壮の四種があること、現代文芸の理想はもっぱら「真」に偏重していることを説いている。)
*****
第十八回 現代文学者の理想(三)――真に対する理想の偏重
次にこんな事を書いたら、どうなりませう。一人の乞食が居る。諸所放浪してゐるうちに、或日、或時、或村へ差しかゝると、しきりに腹が減る。幸ひつそりとした一構へに、人の気はいもない様子を見届けて、麺麭と葡萄酒を盗み出して、口腹の慾を充分充たした上、村外れへ出ると、眠くなつて、うとうとして居る所へ、村の女が通りかゝる。腹が張って、酒の気が廻つて、当分の間外の慾がなくなつた乞食は、女を見るや否や急に獣慾を遂行する。――此話しはモーパサンの書いたもににあるさうですが、私は読んだ事がありません。私に此話をして聞かした人は頻りに面白いと云つて居ました。成程面白いでせう。然し其面白いと云ふのは、矢張りある境遇にあるものが、ある境遇に移ると、それ相応な事をやると云ふ真相を、臆面なく書いた所にあるのでせう。然し此面白味は、前の唖の話と違つて、只真を発揮した許りではない。他の理想を打ち壊して居ます。其打ち壊された理想を全然忘れない以上は、折角の面白味は打ち消されて仕舞ふから役に立たんのみか、他の理想を主にする人からは散々に悪口される場合が多いだらうと思ひます。かう云ふ場合に描出の約束は成立しさうにもない。約束が成立しない以上は、此作物の生命はないと云ふより、生命を許し得ないと云ふ方がよからうと思ひます。一般の世の中が腐敗して道義の観念が薄くなればなる程此種の理想は低くなります。つまり一般の人間の徳義的感覚が鈍くなるから、作家批評家の理想も他の方面へ走つて、こちらは御留守になる。遂に善抔はどうでも真さへあらはせばと云ふ気分になるんではありますまいか。日本の現代がさう云ふ社会なら致し方もないが、西洋の社会がかく腐敗して文芸の理想が真の一方に傾いたものとすれば、前後の考へもなく、すぐ夫を担いで、神戸や横浜から輸入するのは随分気の早い話であります。外国からペストの種を輸入して喜ぶ国民は古来多くあるまいと考へる。私がかう云ふとあまり極端な言語を弄する様でありますが、実際外国人の書いたものを見ると、私等には描出法がうまく行はれない為めに不快を感ずる事が屡あるのだから仕方がありません。
*****
とまずはここまで。ここで話題になっているのは(注釈にもある通り)、「浮浪者」 Le Vagavond という短編。ここで注意しなければならないのは、漱石はこの作を自分で読んだわけではないことだ(伊狩論文によれば、漱石に話をしたのは佐藤紅緑)。漱石の要約が間違っているのではないが、ただ省略が余りに多すぎる。作品の勘所はむしろ前後にあるので、単に人間の本性を描いただけではない。
詳述は避けるけれども、主人公は不況の世の中、方々に仕事を探した挙句に、どこにも職を見つけられなかったという経緯を持っている。本来なら彼は「善き労働者」たりえた人物なのだ。
さらに重要なのは、村長、警官が一度、彼を不審者として捕らえるが、何の罪も見出せないので放免するというエピソード。食べ物があるならいっそ牢獄に入れてくれという嘆願は無視され、肝心の仕事探しや貧窮の現状については、誰も彼の訴えを聞こうともしない。そして村の外に放り出して、戻って来るなと警告するだけなのである。彼がその後に、空腹の余りに罪を犯すかもしれない、というような予測は誰にも簡単に出来る。
そして実際に罪を犯した彼を、警官や村長は、今度は堂々と捕まえることが出来るのを喜んで逮捕するのである。
従って、モーパッサンが本当に「臆面もなく描いた」ものとは、「正しい」人間の見せる(利己的な)他者への無関心であり、彼等がマイノリティに属する者に対して示す抑圧と排除の構造であるはずだ。ここには「罪」の原因はそもそもどこにあるのか。「悪人」とは一体誰のことなのか、を問い返す視線がある。
そのような視線が「倫理的」なものでないと考えることは、果たして正当だろうか。作者に「善抔はどうでも真さへあらはせばと云ふ気分」があったかどうか、というのがここで提起される問題だが、しかし読んでいない漱石にそんな批判を向けても仕方ないので(人聞きでこんなに酷評するというのは随分な話だ)、続けて話を聞いてみよう。
*****
大変に虚栄心に富んだ女房を持つた腰弁がありました。ある時大臣の夜会か何かの招待状を、ある手蔓で貰ひまして、女房を連れて行つたら唯喜ぶだらうと思ひの外、細君は中々強硬な態度で、着物がかうだの、簪がかうだのと駄々を捏ねます。折角の事だから亭主も無理な工面をして一々奥さんの御意に召す様に取り計らひます。夫で御同伴になるかと云ふと、まだ強硬に構へてゐます。最後に金剛石とかルビーとか何か宝石を身に着けなければ夜会へは出ませんよと断然申します。さすがの御亭主も是には辟易しましたが、遂に一計を案じて、朋友の細君に、かう云ふ飾り一切の品々を所持して居るものがあるのを幸い、たゞ一晩丈と云ふので、大切な金剛石の首輪をかり受けて、急の間を合せます。所が細君は恐悦の余り、夜会の当夜、踊つたり跳ねたり、飛んだり、笑つたり、した揚句の果、とう々々貴重な借物をどこかへ振り落として仕舞ました。両人は蒼くなつて、あまり跳ね過ぎたなと勘づいたが、是より以後跳方を倹約しても金剛石が出る訳でもないので、已むを得ず夫婦相談の結果、無理算段の借金をした上、巴里中をかけ廻つて漸く、借用品と一対とも見違へられる首飾を手に入れて、時を違へず先方へ、何知らぬ顔で返却して、其場は無事に済ましました。が借金は中々済みません。借りたものは巴里だつて返す習慣なのだから、如何な見え坊の細君も茲に至つて翻然節を折つて、台所へ自身出張して、飯も焚いたり、水仕事もしたり、霜焼をこしらへたり、馬鈴薯を食つたりして、何年かの後漸く負債丈は皆済したが、同時に下女から発達した奥様の様に、妙な顔と、変な手と、卑しい服装の所有者となり果てました。話はもう一段で済みます。
第十九回 現代文学者の理想(四)――真に対する理想の偏重
ある日此の細君が例の如く笊か何かを提げて、西洋の豆腐でも買ふ積で表へ出ると、不図先年金剛石を拝借した婦人に出逢ました。先方は立派な奥様で、当方は年期の明けた模範下女よろしくと云ふ有様だから、挨拶するのも、一寸面はゆげに見えたんでせうが、思ひ切つて、おやまあ御珍らしい事とか何とか話かけて見ると案の如く、先方では、もうとくの昔に忘れて居ます。下女に近付はない筈だがと云ふ風に構へて居た所を、しよげ返りもせず、実は是々で、あなたの金剛石を弁償する為め、こんな無理をして、其無理が祟つて、今でも此通りだと、逐一を述べ立てると先方の女は笑ひながら、あの金剛石は練物ですよと云ふたさうです。夫で御仕舞です。是は例のモーパサン氏の作であります。最後の一句は大に振つたもので、定めてモーパサン氏の大得意な所と思はれます。軽薄な巴里の社会の真相はさもかうあるだらう穿ち得て妙だと手を拍ち度くなるかも知れません。そこが此作の理想のある所で、そこが此作の不愉快な所であります。よくせきの場合だから細君が虚栄心を折つて、田舎育ちの山出し女と迄成り下がつて、何年の間か苦心の末、身に釣り合はぬ借金を奇麗に返したのは立派な心掛で立派な行動であるからして、もしモーパサン氏に一点の道義的同情があるならば、少くとも此細君の心行きを活かしてやらなければ済まない訳でありませう。所が奥さんの折角の丹精が一向活きて居りません。積極的にと云ふと言過ぎるかも知れぬけれども、暗に人から瞞されて、働かないでも済んだ所を、無理に馬鹿気た働きをした事になつて居るから、奥さんの実着な勤勉は、精神的にも、物質的にも何等の報酬をモーパサン氏もしくは読者から得る事が出来ない様になつて仕舞ます。同情を表してやりたくても馬鹿気てゐるから、表されないのです。それと云ふのは最後の一句があつて、作者が妙に穿つた軽薄な落ちを作つたからであります。此一句の為めに、モーパサン氏は徳義心に富める天下の読者をして、適当なる目的物に同情を表する事が出来ない様にして仕舞ました。同情を表すべき善行をかきながら、同情を表してはならんと禁じたのが此作であります。いくら真相を穿つにしても、善の理想をかう害しては、私には賛成出来ません。
*****
これが先の書き込みにもあった「首飾り」へ与えた(多少)有名な漱石の批評である。あえて筋の要約も全部引用したのは、そこに話者の主観が微妙に入り込んでいることを確認するため。例えば肝心要の「先方の女は笑ひながら、あの金剛石は練物ですよと云ふたさうです」という言葉。手近な翻訳では次のようになっている。
フォレスティエ夫人はすっかり驚いて、彼女の両手を取った。
「まあ! おきのどくなことをしたわ、マティルドさん! だって、あたしのはまがいものだったのよ。せいぜい五百フランぐらいの品だったのよ!・・・」
(新庄嘉章 訳、『モーパッサン全集』第2巻、春陽堂、1965年、p. 832.)
漱石先生の抱く嫌悪感が、かように微妙に誇張を与えているのは疑いない。モーパッサンはここで漱石の言うほどに「意地悪」なわけでもない。それがまず一点目。
二点目は、漱石が見落としている次の事柄。
なるほど主人公夫婦は借金返済のために勤勉に働く。だがそもそもにおいて、彼等は借り物の首飾り過って無くしてしまったことを隠すために、代わりの宝石を探してそれを返す。過失を隠蔽する、という行為は「道義的」に見て問題ないことだろうか。
この点を強調して考えるなら、話の結末はいわば「自業自得」ということになり、なにも漱石先生(また一般に読者)がそんなに憤慨しなくてもよいはずなのだ。
それがそうはならないのは何故なのか。それは、一般に読者(また漱石)が、主人公に「道義的同情」を抱いて読み進めるからだ。また実際、作者は夫婦が勤勉に働く様子を丁寧に描写しているから、読者が人物に共感を抱くのはごく自然な心理であるだろう。しかし、作者は主人公を100パーセントの善男善女としていないことを、見落としてしまうのは、いささかナイーヴに過ぎる。
そしてそこから三点目。もし一般に読者がこの結末に憤慨するとすれば、その理由は漱石の説明する通りであるだろう。だがその時に読者は、「善行は報われるべきである」という理念を、半ば無批判に抱いているということになる。それ自体は悪いことではないかもしれない。しかし人間誰しも生きていれば、「善行は必ずしも報われるとは限らない」のが「現実」(すなわち漱石の言う「真」)であると知るものではないだろうか。
現実はそうでないと知りながら、文芸作品の上においては「善行は報われるべきである」あるいは「報われなければならない」と考えるのは、一体何故なのか。
もしもモーパッサンが「此細君の心行きを活かし」た結末に作品を纏めたならば、読者の「道義的同情」は満足されるだろう。だがしかし真に倫理的であるということと、「道義的同情」を示すということは、同じことであるのか、どうか。
またモーパッサンが「善行は必ずしも報われない」という「現実」を示した時、彼が本当にその「善行」自体を無意味なものとしているのかどうか。
道徳的であるかどうかを判断する前に、我々はそもそも「道徳」とは何であるのか、と問うべきであり、モーパッサンの作品はそのような問いを読者に要求している。文芸の根源を文字通り「哲学的」に考察することから始める漱石にあっても、こと「道義」(ないし「善」の理想)に関しては根源的な追求が成されずに終わっているのは何故なのだろうか。そのことは例えば「徳義心に富める天下の読者」というような表現にも現れているようだ。これがただの「おためごかし」でないとするならば、漱石は「性善説」に立っているということにでもなるのだろうか。
(ところで大島氏は「モーパッサンは別に道徳的な考えがあってこの作品を書いたわけではない」としている。しかしここでも、その「道徳的な考え」とは何を指すのかを問わなければならない。)
「首飾り」の一編が優れているのは、読者が普段疑うことのないままに抱いている「道徳」の観念そのものを揺さぶり、これに疑義を呈するところにある。「此作の理想」は決して「軽薄な巴里の社会の真相はさもかうあるだらう穿ち得て妙だ」というようなところにはない。
モーパッサンにあって文芸の理想が「真」にあったのは確かであろう。だがこの「真」の深さを漱石は見誤っているし、「真」が「善」を損なっているとするのは、やはり早計だと考えざるをえない。
同情心故に「首飾り」の結末に憤慨した漱石は、いささか冷静さを失っているというべきではないだろうか。
という訳で、以上、モーパッサン擁護派の言い分である。同様の反論は幾らでも出来るので、例えば『女の一生』に対する批判についても、逐語的に論駁することも不可能ではないけれど、ここにその必要を認めない。
漱石の批評が関心を惹くのは、一に漱石自身の文学観を間接的にも見て取ることが出来る点にあり、二に、モーパッサン文学の核心が「道徳」と密接な関わりにあることを、改めて我々に教えてくれるところにある。もちろんそこでは時代を考慮する必要もあるだろう。
モーパッサンの「不道徳」さに憤慨した漱石に対し、続く世代の花袋や荷風は、まさしくその「不道徳」さの中に、封建的道徳の根強い明治の社会に対する「反抗」の可能性を見てとったのだった。今日的視点からすれば、彼等はいずれもモーパッサンを「誤読」していると言い得るのだけれども(しかし「正しい読解」が存在する訳ではない)、それがどのように「誤読」であったのかを突き詰める時には、モーパッサン文学について、また明治という時代の日本について、そして我々自身の視点のあり方について、多くのものを学ぶことが出来るように思われる。
まだ他にも言いたいことはたくさんあるけれど、ここまでにしておこう。最後に『ピエールとジャン』についての一言、「名作ナリ」に関して、秋山氏の言葉が面白いので引いておく。
モーパッサンについて語ること、それはその人の「道徳観」を露見させずには済まない、危険な行為なのかもしれない。
「思いがけない遺産が弟のジャンにころがりこんできたことから、兄のピエールが母の姦通に気づいて苦悩するという物語で、フランス古典悲劇を思わせるこの長篇小説の緊密な構成と、母親の秘密を知りはじめてからのピエールの心理の動きを捉えた見事な描写に漱石は感服したのか、それとも、破局が来たのち、「母親がピエールに向けた瞳の奥には、打たれながら赦しを乞う犬のように控えめな、やさしい、悲しげな、哀願するような表情があった」という、人間を痛罵嘲笑しながら、同時に涙するこの作者の心の奥底をのぞかせる描写に感動して、愛人との間に出来た子供を何食わぬ顔で愚かな夫に育てさせているという不道徳この上ないこの物語に、漱石の道徳観も腰砕けになったということだろうか。」(前掲書、p. 307.)
(2007.01.25.)
