『カルネ・ド・ヴォワヤージュ』 出版
Maupassant, Carnets de voyage
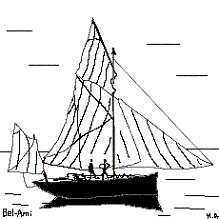 旅は一種の扉であって、人はそこから既知の現実を出て、夢にも似た未探索の現実へと入って行く。
旅は一種の扉であって、人はそこから既知の現実を出て、夢にも似た未探索の現実へと入って行く。駅! 港! 汽笛を鳴らし最初の蒸気を吐き出す列車! ゆっくりと、防波堤の内側を進む大型船、その腹はけれども我慢できずに喘ぎ、彼方へと逃れて行く、水平線へ、新しい国々へと向かって! そうしたものを、期待に震えることもなく、魂の内に長旅への震え立つような欲望が目覚めるのを感じることもないままに眺めることが誰にできるだろう?
(『太陽の下へ』序文)
Guy de Maupassant, Carnets de voyage, édition critique préséntée par Gérard Delaisement, Paris, Rive droite, 2006 が出版されたことをまずは無条件に褒め称えたい。
その上で、本『カルネ・ド・ヴォワヤージュ』について幾らかコメントを加えよう。
とは言いながら、本当は冒頭に付された130ページにわたる「エチュード」を読んでから紹介するつもりだったのだが、なかなか終わらないのでひとまずの報告としておきたい。(2006年7月12日)
モーパッサンに『カルネ・ド・ヴォワヤージュ』という作品は存在しない。訳せば「旅行記」のとおり、本書は、モーパッサンが遺した3冊の旅行記『太陽の下へ』 (Au soleil, 1884)、『水の上』 (Sur l’eau, 1888)、『放浪生活』 (La Vie errante, 1890) を合わせ、研究者が注釈を施したものである。
さて本出版、何故に偉いのかと言えば、近来モーパッサンの旅行記は書店で入手不可能だったからだ。もっとも folio に『水の上』は収められており、これは注釈のしっかりした良書。だが『太陽の下へ』、『放浪生活』は廉価のポッシュ版で出たことはあるが、いずれも短命に終わっている。率直に言って、研究者が一致して参照出来るような校訂のしっかりした版は、これまで一度も世に出たことがなかったのである。
短編・長編のほとんどが複数の書店から出版され、学生向きの注釈書も毎年のように新しいものが出るという現状にあって、これは一体どういうことなのだろうか。
そういう疑問を抱きもするのだが、モーパッサンはもっぱら「小説家」としてのみ現在クラシック入りを果たしているのであって、それ以外の作品(詩、演劇、評論)は、専門家の関心を惹くに留まっている。それが現状であると言わざるをえない。最高権威のプレイヤッド叢書が短編集2巻、長編1巻のみの収録に留まっているのが、その紛れもない証左であると言えるだろう。
そうした状況において、その他のマイナーな著作は長らく忘却の内にあったと言っても過言ではない。一方で、幾人かの誠意あるモーパッサン研究者は、彼が未刊行のままに遺した膨大な時評文の収集、出版を行って来たのだが、その中心人物こそが、本書編纂のドゥレーズモン氏である。モーパッサンのクロニック研究は彼を抜きにしては語れない。(また近年、ルーアン大学は、フロベールに次いで地元作家モーパッサン研究に力を入れており、極めて詳細な注釈を施した『詩集』の出版が行われた。これも偉業である。)
そのドゥレーズモン氏は2003年、自身の半世紀にも亘るモーパッサン時評文の研究成果の精髄として『クロニック』 (Chroniques, Rive droite, 2003, 2 tomes) を出版した。本『カルネ・ド・ヴォワヤージュ』は言わばそれを補完するものであって、『クロニック』への参照は無数と言っていい。
それもそのはず、3冊の旅行記はいずれも新聞雑誌に既出の時評文を、作者が再編集することによって成立しているからだ。研究者人生の到達点とも言うべき本出版が、氏にとってもどれほど感慨深いものであったか、想像に難くない。
要するに『クロニック』『カルネ・ド・ヴォワヤージュ』の合わせて3巻は、現在以降モーパッサン研究を志す人間にとって、文字通り必携の書である。
と褒め称えておいた上で、しかしながら上記の書に関してはいずれも不満を抱かずにいられないのだが、つまるところ、この本には恐ろしく使い勝手が悪いという難点がある。
『クロニック』2巻は上下巻を合わせて総ページで数える(2巻目は911ページから始まる)。注釈は下巻に纏まっているので、常に重たい2冊両方を見なければならない。おまけに注釈の側は、対象となっているページ数を記していないので、注から元の記事の該当箇所を探すのには一々手間取る。些細な愚痴だが、しかし編集上の手抜きとしか思えないのは残念なところだ。
更に付け加えて言えば、ドゥレーズモン氏の注釈には、実のところ色々問題がある。どうにもこの先生、ご存知のことは滔々と語ってくださるのだが、ご存知でないことは無視される嫌いがあっていけない。引用の出典などもさらりと黙殺されてしまうと、こちらとしてはがっかりしてしまうことが多い。アマチュアリズムが抜けきらず、真に科学的な批評校訂に成り切れていない憾みが残るのだ。(それと比較するわけではないのだが、プレイヤッド3巻編集のルイ・フォレスチエ氏の仕事は、批評校訂のお手本のような優れたもので、今後これ以上の版を出すのは不可能だし、その必要もないものである。)
しかし不満を言っても仕方ない。現状最良の版であることは確かである以上、研究者の長年の地道な努力と、無事出版に漕ぎ着けたエネルギーに、敬意を表してやまないのである。
さて、いささか専門過ぎる話を並べてしまったが、モーパッサンの旅行記とは何なのかについて記しておかなければならない。
冒頭に掲げた引用は最初の旅行記『太陽の下へ』の序文の一節。ボードレールさながらの「旅への誘い」を歌った一文だけれども、ボードレールと異なり、モーパッサンは実際に自ら進んで旅に出た。1881年のアルジェリア旅行(当時、植民地紛争が激しかった中、ルポルタージュの先駆けと言っていい)を皮切りに(『太陽の下へ』)、とりわけヨット「ベラミ」号購入以後は、地中海沿岸を飽くことなく航海し(『水の上』)、そしてイタリア、シチリアへと足を進めた(『放浪生活』)。年を追うごとに(病気の進展にともなって)喧騒を嫌い、人間から逃れるかのように海上へ漕ぎ出したモーパッサン。彼のヨットを操る技術は本職の水夫顔負けだったというが、ある時期以降、彼が「幸福」を感じえたのは、まさしく「水の上」だけであったのではないかと思えるほどだ。デカダンの風潮の流行る19世紀末、これほど旅に情熱を傾けた作家は他にいなかった。
「旅行記」の第一義は、見知らぬ国の風土、風俗習慣を読者に伝えることにあるだろう。『太陽の下へ』ではフランス植民地を駆け巡りながら、現地人の風習を詳しく語る一方で、フランスの植民地政策がいかに現地の実情をふまえない拙劣なものであるかを鋭く批判する。コート・ダ・ジュールの奇観を印象深く語った『水の上』の幾ページ、シチリアやヴェネチアの心奪われる美景を『放浪生活』において、モーパッサンは実に見事に語っている。
「見ること」に作家の全てがかかっていると断言する作者にとって、旅行記とは、自らの観察、印象をいかに忠実に描き、そして生き生きと浮かび上がらせるか、その文体練習に最適な場であったと言えるだろう。またモーパッサンは決して固定したものとして景観を捉えない。常に移ろいゆく相のもとに捕まえられた一瞬の「印象」を、叙述する以上に遥かに「喚起」する描き方。モーパッサンの描写を「印象主義」と比較するのは、決して誤ったことではない。
そしてドゥレーズモンも詳しく語る通り、モーパッサンは単に「眺める」だけでなく、そこにある全てを、五感の全てを使って「感じ」とり、そしてそれをまた読者の感覚にも強く訴える言葉で記した。様々な香りを敏感に嗅ぎ取り、南国の灼熱の太陽に打たれる。彼以上に感覚的であった作家は、フランス文学史上においても稀であるだろう。
もっとも、研究者の力説とは裏腹に、モーパッサンの旅行記が今日広く読まれないのには理由が無いわけでもないだろう。春陽堂版翻訳全集解説、大西忠雄氏なども「平凡な旅行記」と手厳しい評価を下している。
明確な筋も物語も存在しないこれら3冊の旅行記は、その「内容」だけに関心を向ければ、退屈に感じるのも無理はない。彼の小説を読むように、彼の旅行記を読んではいけないのである。
例えば『放浪生活』に、夜明けの海上、今や太陽が姿を現さんばかりの情景を叙述した箇所がある。刻一刻と変化してゆく空の色合い、一時に溢れ出す太陽の光線の様を詳しく語ったこの場面、一見何の変哲もない情景描写の内にこそ、モーパッサン旅行記の眼目がある。さながらモネの絵画のように、時間とともに移ろう光と色彩の微妙な変化を、簡潔にして流麗な文章においてあますことなく描き出すその作者の筆致を、純粋に美学的快楽を求めて味わうこと。それが出来る者にとっては、モーパッサンの旅行記は実に豊穣な喜びを与えてくれることだろう。
忙しい現代においてモーパッサンの短編が広く読まれやすいのが事実であるとすれば、ゆったりとした心の余裕を必要とする彼の旅行記に、受け入れられにくい理由が存するのも無理はない。
だがそこに、「芸術家」モーパッサンの優れて繊細な美的感覚が見て取れることを強調しておきたい。しばしば卑俗な、あるいは好色な短編作家としてのみ思われがちなモーパッサンの別の一面は、3冊の旅行記の中にしっかりと存在しているのである。
他にもまだまだモーパッサン旅行記の魅力はあるが、取り急ぎここまでに留め、まずは謙虚にドゥレーズモン氏の言葉に耳傾けることとしたい。かつて悲観主義的な瞑想によって日本でも広く読まれた『水の上』も版が絶えて久しい。改めて『カルネ・ド・ヴォワヤージュ』を手に取られる人の、一人でも多く生まれることを望みたい。
(12/07/2006)
