『マダム・トマサン』とはなにか
Qu'est-ce que Madame Thomassin ?
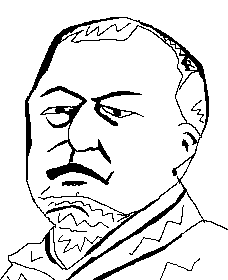 1883年1月13日、土曜日、クリュニー劇場 Théâtre Cluny において、一幕の小品『マダム・トマサン』 Madame Thomassin が上演された。作者の名前はウィリアム・ビュスナック William Busnach。『ナナ』、『居酒屋』の演劇版の共作者でもあった彼は、多作な劇作家であり、ゾラをはじめとする自然主義文学者達とも近しい関係にあった。
1883年1月13日、土曜日、クリュニー劇場 Théâtre Cluny において、一幕の小品『マダム・トマサン』 Madame Thomassin が上演された。作者の名前はウィリアム・ビュスナック William Busnach。『ナナ』、『居酒屋』の演劇版の共作者でもあった彼は、多作な劇作家であり、ゾラをはじめとする自然主義文学者達とも近しい関係にあった。芝居の筋は簡単である。トマサン夫人が急死し、葬式を控える夫と女中のジュリー。二人は悲しみを打ち明けあい、夫婦ともどもの親友だった、青年アンリとも悲しみを分かち合おうとトマサン氏は考える。アンリはトマサンを迎えに来て、二人は近くの教会へ赴くが、やがてアンリが一人戻って来ると、トマサン氏用の聖書を探すという。実は彼がトマサン夫人に宛てた恋文を、見つからない内に取り返そうとしてのことだった。だが手紙の見つからない内に、トマサン氏が葬儀の途中で戻って来る。アンリは改めて外へ出るが、その際に、ジュリーが聖書に挟まれた手紙を見つけ、トマサン氏は妻の裏切りを知る。
そこへ戻って来たアンリをトマサン氏は非難する。アンリはトマサン夫人は過ちを後悔して自殺したのだと告げ、自らも毒をあおごうとするが、トマサン氏は阻止し、アンリに街を出るように命じる。ジュリーは妻とアンリとを許すように言うが、トマサン氏は、妻は許してもいいが、アンリは許さないと告げ、幕となる。
本来、ヴォードヴィルや笑劇を演目にするクリュニー劇場において、このような芝居は観客の期待を裏切るものであり、役者の力不足もあったためか、初日、観客は大いに笑ったという。そして芝居は4回の上演で、打ち切りとなった。
ところでその上演の最中に、次のような噂が流れた。「この作品の本当の作者は、ギ・ド・モーパッサンであるらしい」
Guy de Maupassant en collaboration avec William Busnach, Madame Thomassin, pièce inédite, édition de Marlo Johnston, Publication des Universités de Rouen et du Havre, 2005, 153p. において、マルロ・ジョンストンはこの未刊の戯曲に関する資料を収集し、検閲用提出台本を発見、当時の新聞雑誌に出た劇評と合わせてこれを出版した。ビュスナックとモーパッサンとの関係、その後のモーパッサンと劇作との関わりについて等、詳しく検証されている。研究者の熱意と努力は賞賛に値するだろう。
後年のビュスナック自身の証言にも、作者はモーパッサンだったとの言葉があり(しかしモーパッサン自身は否定している)、本作品執筆にモーパッサンが関わっている可能性は極めて高いが、草稿が未発見なこと、モーパッサンやゾラはじめ、メダニスト達の書簡・証言の中にこの作品への言及が見られないこと等、確実な物的証拠に乏しいのも確かである。
一方、作品の構成・テーマから見れば、モーパッサンの発案である可能性は濃厚であるように見受けられる。死後の手紙の発見という情景も『女の一生』はじめモーパッサンの好んだものだ。だが、それもモーパッサンの独創ではなく(なにより『マダム・ボヴァリー』という先例がある)、不倫、浮気という題材は、自然主義作家達が頻繁に取り上げたものでもある。
従って、今現在、本作品をモーパッサンのものと断定するには慎重にならなければならないが、もしそうであったなら、この小品は、モーパッサンと劇との関係を考える上で、極めて重要な鍵となるであろう。
1870年代のモーパッサンは、少なくとも二本の一幕劇、および三幕『レチュヌ伯爵夫人』を執筆したが、これらはいずれも韻文で綴られ、貴族趣味、社交界の洗練された趣味を取り入れたものであり、反自然主義的姿勢を鮮明に表している。
1880年、『脂肪の塊』以降、モーパッサンはしばらく劇作から離れる。だが劇への関心を捨てた訳ではなく、後にやはりビュスナックに『ベラミ』の演劇化を託し(未完に終る)、『ピエールとジャン』を舞台に乗せる計画もあった(詳細はジョンストンの書を参照)。そしてジャック・ノルマンとの共作という形で、『ミュゾット』(1891年、ジムナーズ座)、作者一人で何度も改稿を繰り返した『家庭の平和』(1893年、コメディー・フランセーズ)が作られることになる。
これら80年代の作品(その計画)は、小説を原作にしていることもあり、いずれも散文で書かれ、レアリスムの様相の濃いものである。自然主義演劇との関連を考えることも十分に可能である。だが注意すべきは、脚本執筆に対するモーパッサンのためらい、慎重さであり、このことは小説と演劇とではその製作姿勢・技法に相違があることを、彼が明確に自覚していたことを意味する。彼が脚本化を他者に委託し、あるいは共作の形を取り続けたのはそれ故である。そして実際のところ、フロベール、ゴンクール、ゾラ等の演劇が多く舞台で失敗に終った事実は、彼等の美学的理念と、劇場という現実の場、具体的な観客の存在との間に、解消しきれぬ齟齬があったことを語っている。
仮に『マダム・トマサン』がモーパッサンの手になるものだったとしたら、彼がこれを劇作家ビュスナックに託し、彼の意見をいれて上演に適うよう修正を施した可能性は極めて高い。その上でさらに自らの名前を隠し、芝居の成功の可否を陰から窺っていたということも、十分に想像されることであろう。
そして実際の上演が失敗に終れば、そのまま名前を隠し続け、演劇に対し、一層慎重な姿勢をとることになったかもしれない。以上のことは憶測に過ぎないが、可能性としてはありえることだろう。
そのように考えた時、70年代の韻文劇が、あるいはある程度の成功を収めつつ(『昔がたり』、ただし上演は79年)、多くは上演に至らないという苦い経験を経た後、なおモーパッサンが演劇に対し、関心と、恐らくは野心とを抱いていたことを示す証拠として、『マダム・トマサン』が存在することとなる。
そしてここにおいてモーパッサンは、『脂肪の塊』以降培った短中編作家としての才能を発揮し、散文で、レアリスムの手法に則りながら、現代ブルジョア家庭にみられる(ささやかな)ドラマを描き出す。「明確な筋をもたない」という当時の劇評は、翻って、劇的な、すなわち空想上の物語ではなく、本当らしい、現実にありえる物語こそが、現代の芸術の目標であるという、モーパッサンの美学を明確に示すものであろう。寝取られ亭主たるトマサン氏は、同時に滑稽であり悲惨でもあるという存在だ。初演時の観客が笑ったとしても故のないことではなく、モーパッサンの描く人物達は常に悲劇・喜劇の両面を合わせ持つ。見る者の視点次第で、どちらともとれるのである。
モーパッサンの試み、ひいては自然主義演劇の理念が広く世に浸透するには、今少しの時間が必要だったかもしれない。アンリ・ベックの『烏達』がコメディー・フランセーズで演じられたのは、『マダム・トマサン』の少し前であった。恐らく別の劇場で上演されたなら、本作品が異なった受け止められ方をした可能性も高い。
短い小品であるが、『マダム・トマサン』は興味深い作品である。モーパッサンに関心のある方に、是非とも上記の書を手に取ってもらいたい。価格は15ユーロ。(27/03/2006)
