モーパッサン、翻訳の歴史
Histoire de la traduction japonaise des œuvres de Maupassant
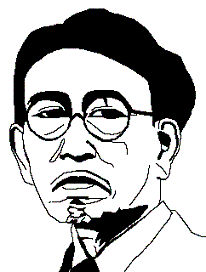 『翻訳と歴史 文学・社会・書誌』22・23合併号「モーパッサン特集」(ナダ出版センター、2004年9月)をこの度入手した(労を取ってくれたT氏に感謝)。新着ニュースではないけれど、ここに紹介するとともに、モーパッサンの翻訳史に関して私見を述べてみたい。
『翻訳と歴史 文学・社会・書誌』22・23合併号「モーパッサン特集」(ナダ出版センター、2004年9月)をこの度入手した(労を取ってくれたT氏に感謝)。新着ニュースではないけれど、ここに紹介するとともに、モーパッサンの翻訳史に関して私見を述べてみたい。明治28(1895)年から平成16(2004)年までのモーパッサン翻訳文献リストを作成した、榊原貴教氏の尽力にまずは敬意を表したい。本号はその成果をもとにした氏の報告文、および主要作品の翻訳作品年表とから成っている。
榊原氏によれば、これまでに翻訳されたモーパッサン作品の総数はおよそ3500点。主に約240の作品が3400ほどの翻訳によって(繰り返し)伝えられてきたという。もちろん、その多くは短編小説であるし、同じ訳者の翻訳が何度も再録された場合もあるが、いずれにせよ相当な数であるのは疑いない。明治30年代よりこれまで110年ほどの間、モーパッサン作品がよく読まれたことを示す数字だけれど、その内実は幾らか詳しく検討する余地があるようだ。
モーパッサン・ブームとも呼ぶべき翻訳が溢れた時期は少なくとも二回。最初は明治30年代から大正始めまで、主に雑誌に短編が数多く掲載された。最初は主に英訳からの重訳であり、その際に偽作が相当数紛れ込んだ事実がある。作家が小遣い稼ぎに手頃な短編を翻訳をしたという時代でもあった。
二度目は終戦直後。こちらは主に短編集が多数出版された。榊原氏によれば当時流行した「エロ・グロ」の流れを汲むものでもあったろうという。戦後のブームの頂点は昭和25年頃だというが、当時試みられた全集はいずれも中途で挫折。最初で最後の完結した全集が昭和40-41(1965-66)年の春陽堂版であった。それ以後も翻訳の出版は継続するが、その内容は限定的なものとなって今に至っている。
明治期のモーパッサン移入は当時の文学者に少なからず影響を与えた。氏によれば「日本文学研究はモーパッサンの影響を負の遺産として切り捨て」てきたと手厳しいが、比較文学研究者による、田山花袋を始めとした自然主義作家、並びに永井荷風(右画像)に関しての研究論文は必ずしも少なくない。田山花袋がいかにモーパッサンを「正しく」理解しなかったか、を始めとして、西洋文学の受容という観点からは、これまでむしろ批判的に検討されることが多かったようだ。私見によれば、誤解は誤解として了承した上で、モーパッサン受容の実態を、より客観的に検討し直す余地があるのではないだろうか。
それはともかく、当時「モーパッサンはもうたくさん」という冗談が聞かれたというぐらい、一時期の文壇にモーパッサンがよく読まれた事実は確かにあり、正宗白鳥の証言などはその点で貴重なものであろう(『モウパッサン』、文藝春秋社、1948年)。榊原氏は夏目漱石の道徳的見地からの批判が、後のモーパッサン評価に影響を及ぼしたのでないかという。恐らく、トルストイのモーパッサン論の影響も無視出来ないであろう。
とまれ漱石は道徳観の欠如に怒り、田山花袋は「露骨なる描写」に瞠目した。『東京の三十年』に読まれるモーパッサン発見の興奮は今となっては微笑ましいようなものだが、『布団』以後の日本の自然主義に、モーパッサンが決定的な役割を果たしたことは疑いなく、同書における『死の如く強し』を始め、彼の小説・随筆中にモーパッサンへの言及はその後も数多い。白鳥、独歩などにもモーパッサンの陰は見られ、永井荷風(とりわけ『あめりか物語』に影響が濃い)はモーパッサンを読むためにフランス語を学び、フランスの地を目指したほどであった。
明治の話はこれぐらいに留めよう。自然主義への反発が、同時にモーパッサンへの反発を含んでいた可能性は高く、後の世代においては、芥川龍之介が比較的よく読んだのを除いて、モーパッサンの影は日本文学史上に薄くなるようだ。
戦後の一時期は、モーパッサンに限らず多くの外国語文学の翻訳が世に出た。戦時中の事情を鑑みればごく当然の反動でもあっただろう。そしてこの時期以降、フランス文学が人気を集めた時期は確かにあった。今は昔の感は深いけれども。大学の授業でモーパッサンがよく使われたのもその頃のことだ。
戦後の盛んな出版ブームの後は、ある特定の作品が繰り返し出版されるようになる。とりわけ文学全集の隆盛時は、毎年のように新しい文学全集が出版され、『女の一生』『ベラミ』『ピエールとジャン』『我らの心』のどれか(そして「脂肪の塊」と幾つかの短編)は必ず含まれた。春陽堂版の全集は、それまでの翻訳事業の集成であり、当時の仏文学界の中心人物の結集による成果であった。
昭和40年代に新潮文庫に青柳瑞穂訳の三巻が入り、これは以後継続的に読まれ続け、モーパッサン作品への入り口として最も貢献したものであるだろう。岩波、角川なども一時期は多くの文庫を出していたが、次第に数を減らしてゆく。
1970年代を最後に文学全集の出版は事実上途絶える。以後、手軽に読める翻訳は、長編では『女の一生』、短編では「脂肪の塊」「テリエ館」、そして前記の新潮文庫三巻にほぼ限定されることになった。『ベラミ』や『ピエールとジャン』も、時期を空けて重版を見るに留まる。もっとも近年にも作品集の出版は見られ、岩波文庫も改めて短編集を出版した。
現状を鑑みる時、「かつてのモーパッサン・ブームは何であったのか」という榊原氏の感慨に同意したくもなる。全ては時代の読者の趣向であるのかもしれない。それでもあえて言うならば、ある時期までの仏文学者/翻訳家の世代以降に、モーパッサンを専門とする研究者が十分に育たなかったという事実がある。そのことは翻訳事情にも多少の影響を及ぼしているだろう。それだからと言うのではないが、翻訳の数の多さに比して、果たして明治末の頃から今日に至るまでの間に、日本におけるモーパッサン受容がどれほど進展したのか、という問いに対しては、いささか懐疑的にならざるを得ない。
とは言え、モーパッサンの作品が絶えず読み継がれて来た事実に変わりはない。昭和以降、文学者よりもむしろ一般の人々に親しみをもって読まれて来たという事情は、フランス本国にも共通する点であるように思われる。
***
榊原氏は、「春陽堂版全集以降に4回以上刊行された翻訳」の一覧を挙げている。モーパッサン作品の中でも最も読まれたものは何であったか。まずは回数とともに作品名を挙げてみる。(五十音順。長編は『』、中短編は「」で記す。)
「雨傘」 29
「オトー父子」 18
「オルラ」 23
『女の一生』 88
「帰郷」 30
「狂女」 31
「首飾り」 65
「酒樽」 29
「脂肪の塊」 50
「シモンの父」 27
「ジュールおじ」 36
「死んだ女」 13
「たれぞ知る?」 9
「手」 15
「トワーヌ」 16
「母親」 17
『ピエールとジャン』 40
「ひも」 25
「ふたりの友」 36
「マドモアゼル・ペルル」 24
「水の上」 25
「山の宿」 32
上位五位を挙げれば、『女の一生』、「首飾り」、「脂肪の塊」、『ピエールとジャン』、同数で「ジュールおじ」と「ふたりの友」の順。
全22作中、長編は『女の一生』(最高の88)『ピエールとジャン』(40)の二作。『女の一生』は文字通りモーパッサンの代表作となっている。その他は短編で、多くは20から30の翻訳があるが、榊原氏も特筆するように「首飾り」65回は特別に多い。この短編はフランスでは特別に重視されることの少ないものである分、一層特徴的である。上記六作を眺めていると、日本人読者の趣向が窺われるようにも思われる。いずれも哀切な物語であり、古い言葉で言えば「人情の機微」を語ったものだ。
そこで、ここに挙がっている短編をごく簡単に三種に分類してみよう。それは感動的なもの(あるいは悲話)、滑稽譚、そして怪奇小説である。
感動的小話
「狂女」、「シモンの父」、「ジュールおじ」、「ふたりの友」、「マドモアゼル・ペルル」
滑稽譚
「雨傘」、「オトー父子」、「首飾り」、「酒樽」、「トワーヌ」、「ひも」
怪奇小説
「オルラ」、「死んだ女」、「たれぞ知る?」、「手」、「水の上」、「山の宿」
遭難して亡くなったはずの夫が十数年の後、既に再婚した妻のもとに帰って来る「帰郷」は前二項のどちらに入れるか難しい。中編「脂肪の塊」もまた単純な分類には入れがたく、子どもの復讐を果たす「母親」も、どちらにも当てはまらないので、もとより粗雑な分類である。悲劇と喜劇は常に背中合わせであり、モーパッサンの作品は多くの場合、両面を備えているところに特色がある。上位五位の作品である「首飾り」や、「ひも」なども、むしろ結末の悲哀さに重点を置いて読まれてきたものかもしれない。
最も多く翻訳されてきたこれらの作品が語っているのは何だろうか。ここから窺われる作者のイメージは、滑稽譚で笑わせ、時にはほろりとさせる一方で、怪談も語ってみせる巧みな短編作者、というところだろうか。確かに、このようなモーパッサン像は明快である分、幾らかなりと還元化、簡略化されたものではある。だがそれだけに、日本人の抱くモーパッサン像をよりよく示していると言えるだろう。残念ながら(?)「エロ・グロ」の面も格別に好まれたわけではないようだ。
榊原氏も指摘するように(とりわけ近年)怪奇小説、あるいは幻想小説に対する好みは根強い(原作では「幻想小説」は全体の一割程度でしかないので、翻訳傾向は明らか)。「死んだ女」のようなモーパッサンには例外的な作品が含まれているのが興味深い(もっとも、これは明治期に翻訳が多い作品)。それはそれとして、作者自身は決して「幻想小説」をそれ自体一つのジャンルとして捉えるようなことはなく、彼の描く「恐怖」は日常の生活の内に潜むものであって、その限りでその他の作品と隔絶している訳ではない点に留意しておきたい。「オルラ」が幻想小説の傑作であるのは確かだが、ここに描かれる「幻想」はポーやホフマン、あるいはラヴクラフトとは性質を異にする。ジェイムズの『ねじの回転』は同時代に書かれ、類似する点の多い作品だが、これもまた単純な怪奇小説ではないように。
かつて正宗白鳥は、(適度な)悲観的内省が読者に受けるのだと述べたが、このリストの上では、作者の根深いペシミスムはいささか陰を潜めているようだ。もっとも「感動小話」に分類した作品の多くは悲劇的結末のものであるし、「首飾り」「ひも」などの笑いも苦いものであろう(『女の一生』『ピエールとジャン』もまたしかり)。モーパッサンのペシミスムは彼の世界観を根底から決定づけるものである。(かつてよく読まれた)旅行記『水の上』に見られる強烈なペシミスムの表明は、一つの世界観のあり方として、今日なお多くを語るものであるように思われる。
かつて大学の授業でよく読まれたという「初雪」が入っていないのはいささか意外な感がある。長編『ベラミ』も知名度の割に、翻訳は少ない部類に入るらしい。
と、リストを眺めながら思うところを記してみた。もとよりこれらの作品だけが読まれてきたのではないのだから、断定的に結論を下すことは出来ないけれど、日本におけるモーパッサン受容を考える上で、本リストが貴重な資料であることは間違いない。
***
この百年、モーパッサンは十分に読まれ、理解されてきたかどうか。
その答えは見方次第で如何ようにも変化しようし、そもそも決して簡単な問いではない。榊原氏作成の全リストに目を通すことがまずもって不可欠でもあるだろう。
しかしながら3500という数が確かに語っていることは、例え限定的にであれ、たくさんの人が『女の一生』をはじめとするモーパッサンの作品を読んで来たという厳然たる事実だ。
改めてそのことを確認すると同時に、これからもなおモーパッサンの作品が読まれ続けることを願いたい。そして本サイトがその一助に与れば(更には新しいモーパッサン像を発見してもらえれば)、とささやかに期待する次第でもある。
(06/05/2006)
追記 榊原貴教氏ご自身より『翻訳と歴史 文学・社会・書誌』22・23合併号「モーパッサン特集」をお送りいただいたことをここに記し、御礼の言葉とさせていただきます。手違いがあって管理人の手元に届くまで2年以上かかってしまい、申し訳ありません。ありがとうございました。
(13/12/2006)
