ステファヌ・マラルメ
「追悼」
Stéphane Mallarmé, « Deuil », le 22 juillet 1893
 解説 1893年7月22日、ロンドンで発行される週刊誌『ナショナル・オブザーバー』The National Observer に掲載された、ステファヌ・マラルメによるモーパッサン追悼文。『メルキュール・ド・フランス』Mercure de France 9月号に再録。
解説 1893年7月22日、ロンドンで発行される週刊誌『ナショナル・オブザーバー』The National Observer に掲載された、ステファヌ・マラルメによるモーパッサン追悼文。『メルキュール・ド・フランス』Mercure de France 9月号に再録。ステファヌ・マラルメ (1842-1898) は詩人。パリ出身。1860年代、ポーやボードレールの影響のもと、トゥルノン、アヴィニョンで英語教師を勤めながら詩を執筆し、高踏派の詩人らと交流した。普仏戦争後にパリに出た後も、定年まで高校に勤務を続ける。
1884年、ヴェルレーヌ『呪われた詩人たち』、ユイスマンス『さかしま』による紹介で広く知られるようになり、青年詩人たちの指導者的立場に立つ。「火曜会」には、マラルメを慕う芸術家たちが集った。作品に『半獣神の午後』(1867)、『パージュ』(1891)、『詩と散文』(1893)、『ディヴァガシオン』(1897)、『賽の一振り』(初出:1897 ; 1914)など。また、エドガー・アラン・ポーの詩篇の翻訳 (1888) がある。
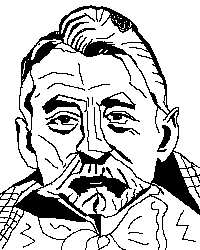 若き詩人だった1870年代のモーパッサンは、高踏派との交流のなかでマラルメにも知り合っている。後年にも一緒にボートに乗るなどの交流があったことを、従者フランソワが書き記している(『新ギィ・ド・モーパッサンの親密な思い出』)。だが、モーパッサンがこの詩人から何らかの影響を受けた形跡は見られない。
若き詩人だった1870年代のモーパッサンは、高踏派との交流のなかでマラルメにも知り合っている。後年にも一緒にボートに乗るなどの交流があったことを、従者フランソワが書き記している(『新ギィ・ド・モーパッサンの親密な思い出』)。だが、モーパッサンがこの詩人から何らかの影響を受けた形跡は見られない。一方でマラルメは1893年3月8日の『エコー・ド・パリ』のアンケート「ギィ・ド・モーパッサン」に回答を寄せると共に、モーパッサン死去の際に追悼文を執筆し、「文学的ジャーナリスト」の才能を(多少の留保をしながらも)賞賛している。
前衛詩人マラルメの語る(難解な)言葉のうちに、彼独自のモーパッサン像が浮かびあがってくると同時に、彼一流のジャーナリズム観が窺える点でもこの小文は興味深いものであろう。
***** ***** ***** *****
追悼
追悼
モーパッサンの完全な死(人の知るように、18か月前から、壁に覆われた精神病院の個室の扉が、この作家の前に閉ざされたのであった。以後、白いままに残されたページのように)は人々の心を動かし、公の感情を解放させることにもなった。ただし、あちこちで新聞雑誌は、この死を雑報記事の中に含めたのではあったが、それというのも、ずいぶん前から、この作者の死が到達すべき何もなかったからだ。また、闇の最初の愛撫が、まだ若い作家の額から一切の思考を奪い去ってしまった時、永遠の敷居を越えるためのこの準備期間が、文学者たちの間で、無意識の内に、会話の声を潜めさせたようでもあった。彼の死後も、一時停止が、期待とともに続いているのである。しかしながら、その時期より、結末に関する時期尚早の噂が流れ、ある新聞は、敬意を表する意味でだが、半ば死亡したこの友人について、威厳ある多様な権威者たちの意見を聞くことを提案したのだった(1)。その回答が示したのは、渦中の者は不幸から利益を得るのを拒む権利を持つのだから、哀れみの感情を措くとすれば、ある不和なのであった。こちら、年長者側においては、統一的、全員一致の、彼の才能に相応しい格調を備えた、崇拝の念であった。だがむしろ、別の世代にあっては、軽蔑だったのである。ブールジェの重要な意見を私は思い出すが、彼の言葉には純粋なエッセンスが浸透している故に、いつでも重要なのである。彼は、恐らくは、モーパッサンにはフロベールよりも優れた面があったことを示唆しており、それは、子の内における親の再生のようなもの、あるいは師の芸術が、弟子によって青春時代に再び浸った、ということであった(2)。私としては、ギュスターヴ・フロベールは、数人の絶対なる者の内に選り分ける。ただ少なくとも、双方ともの持つ明敏さは、一方の者が秀でているのを認めるべきだろう。彼はとても思いがけずにやって来たが、文学に関する能力を十分に備えていたので、奇跡的にももはや同じではなく、生まれつきヴィジョンと言葉とを備えたフォーヌであった。天性に結びついた神秘的な完成度に従い、純潔さを保ったままに、誰もが難渋した道を踏みしめた。確かに彼の子だった。高度を上げてゆく飛翔には欠けながら、一国家の文学的土壌が、彼に愛情を誓い、誇りにさえ思っている。彼は直接に生まれ出たのであり、誰に対しても善良であった。私はゾラを評価するが、洞察力に溢れ、感動的でもある墓前での演説の中で、彼は完璧なひらめきによって、ラ・フォンテーヌと『寓話』を挙げたのだが、それは我らの同時代人の、引き締まっていて自由な、数多くの短編小説に伴うだろう不滅性の例えとしてであった(3)。彼ら、土地の神々にあっては普通のことだが、ある事象がここに明らかになる。すなわち、読むことの出来る者なら誰もが、彼らの作品を読み、そして続けて、全てを読むことが出来るのである。素朴なものを自らの位置にまで一気に高めると、より遠くにまで導くのである。それは文芸に対し、原初の、学ぶことの出来ない機能の持つ美徳を回復させることであり、その美徳が、フランス的な意図であるかのように、私を打つのである。
我々の内にあっては、〈プレス〉の語の意味を、習慣どおりに、ジャーナリスムに限定しよう。以下、どのような訳でプレスが、最近になって、文学作品に位置を与えるのを望むようになったかである。伝統的なフイユトン は一階において、長い間、判全体の質量を支えてきたのだった。ちょうど往来において、まばゆいばかりの壊れやすい商店、宝石が輝き、布地のニュアンスに染められたショーウインドーの上に、何階もある重い建物がどっしりと構えているようにである。今日、よりよいことに、本来の意味でのフィクション、あるいは、想像的な物語が、商品の豊富な「日刊紙」を横切って飛び回り、中心を占める場で勝利の声を上げ、頂上にさえ至っている。土台となる、あるいは最新の事柄に関する記事は、そこから立ち退いて、二次的なもののように見えている。幾らか美しくもある示唆、あるいは教訓のようなものさえが、そこに見て取れる。すなわち、今日とは単に昨日の代わり、明日を予告するものではなく、一般的なものとして、刷新された新しい完全さの内に、時間の外に出るものである、ということだ。四辻において、まるで印刷されるようにおおっぴらに叫ばれるプラカードの粗野な言葉が、こうして、どこかの風吹く空の下で、塵となって、政治的文書などの上で、この反映を受けたということ……わたしは満足である。これはここ数年、行われていることだ。才能ある者、あるいは力ある者が直ちにこの現象を助けたのは、ただそこに居合わせ、公衆を丸め込むに相応しく、同時に彼の本能にも適っているような主題が泡立つ中で、準備が出来ていたからであり、その者が『脂肪の塊』、『ロンドリ姉妹』、『トワーヌ』、『ミス・ハリエット』あるいは『メゾン・テリエ』、多くの中で幾つかの成熟した傑作しか引かないとしても、そうした作品の散文作家となったことだったろう。この新聞の革命に由来する危険とは、凡庸さが横溢するということだ。だが少なくとも、誰よりも、ギィ・ド・モーパッサンの寄与がそれを救った。短くも決定的な彼の記事の中で、完全に、あるいは限定的に、最も難しい愛好家をも満足させないようなものはなかったのである。
このような事件にある種の者たちが無関心なままなのを、私は心得ている。なぜなら、彼らが想像するのは、人々の味わう快楽の中で、多かれ少なかれ稀で高尚なものであり、唯一、計り知れないほどに高尚で稀なもの、〈ポエジー〉の名で知られるものに関しては、状況は維持されているからである。ポエジーは、いつでも除外されたままであるだろうし、ここではない何処かへの飛翔のためのポエジーの身震いは、性急に書かれた、新聞の大きな紙面を我々の手の内に広げることで、それ以上ではないが、パロディー化されているのである。この紙面は、この場合、必要かつ贅沢な事物によって補完され、洗練されるだろうから一層、夢と、何らかのものの間に割って入るぞ、という主張を発しているのではないか?――幾らかは。
この懸念に対し、先見の明があり、鋭い精神を持つ者たちが、意見を求められた際に固執する、モーパッサンに対する態度のありようを私は認めるのであるが、この作家は私には、無傷で独自の性質を持った、この時代の文学的ジャーナリストの中で最も優れた者であるように思われるのだ。今日の、異常なほどの過剰生産、それに対し〈プレス〉は聡明にも手段を譲り渡しているが、それを評価するならば、大変に決定的で、入念に仕上げられようとしている何物か、という概念が優勢である。すなわち、確かに、一時代前のように、〈現代大衆詩〉、あるいは少なくとも無数の『千一夜物語』の創立のための巨大なコンクールであり、そこでは、突如発明されたこの読者大衆が目を覚ますのである。祭りのように、あなたも、今から、このとんでもない達成の機会に、参加したまえ! そうでなければ、この大変な加熱ぶりは、明らかに、日々の消費量を超えてしまうだろう。
この先日の悲しい午後、葬儀のミサの続く間、私はこうした多くのことを思っていた。最大限の未来を考慮し、突然の荘厳な運命から、その意味を引き出すためであるかのように。我々が敬意を表していた、打ちのめされたこの同僚を直接に評価するには、大変な不調が生じるので、全体の中で、彼の人となりと作品とを立ち上がらせることにも専心せずに。実際、私は、特別な特徴を追うに際して、最後の数年を示す大きな作品を省略しなかっただろうか(ただ題名だけでも雄弁に語る、『女の一生』から『ピエールとジャン』、『死の如く強し』を経て、運命を告げる『オルラ』まで)。劇場への逃避を含めて、無限に同じように延長される一連のリストである。
最初の様式を想起しながら、同じように私は自分に問いかけた。その様式とは恐らくは古典となるだろうが、短編作家のものであり、それを長編作家は充実させ、また不安に陥れさせたのだった――もしもあるジャンルに、相容れない性質を持つ反対のものを要求するとするならば、この面白く、明晰で、喜びのようにたくましい、資質(唯一望むべきもの、それで十分)において、喜びのように限定的な、この才能に、欠けていたものは何であり、それは何故だったろうか?という風に。それは、苦悩に満ちた、あるいは感知しがたい彼岸であり、何らかの高揚であっただろうが、悲劇的にも、そうした色調は、宿命によって余りに早くに、彼の存在そのものに付与された。宿命は、最も健康な者、最も率直な精神を、一撃一撃と、病人に、次いで死者へと変えたのであった。
『ナショナル・オブザーバー』誌、1893年7月22日付(『メルキュール・ド・フランス』1893年9月号)
The National Observer, 22 July, 1893 (Mercure de France, septembre 1893, p. 17-20).
The National Observer, 22 July, 1893 (Mercure de France, septembre 1893, p. 17-20).
訳注
(1) 「ある新聞」:『エコー・ド・パリ』 L’Écho de Paris は1893年3月8日に別冊でモーパッサン特集を組んだ。
(2) Paul Bourget, « Guy de Maupassant », L’Écho de Paris, 8 mars 1893 において、ブールジェは以下のように記している。「フロベールとモーパッサンの間では、後者の方に天才のあの神秘的な魔法を付与したいし、その点で弟子は、作品全体において、師を凌駕しているように思われる。」
(3) ゾラはモーパッサンの墓前での追悼演説の中で、モーパッサンの短編は、「ラ・フォンテーヌの寓話や、ヴォルテールの短編」のように古典に属するのではないかと述べている。また別の箇所では、モーパッサンの祖先として、ラブレー、モンテーニュ、ラ・フォンテーヌの名を挙げている。
