「ブヴァールとペキュシェ」
« Bouvard et Pécuchet », le 6 avril 1881
 解説 1881年4月6日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois 別冊に掲載されたフロベール『ブヴァールとペキュシェ』 Bouvard et Pécuchet についての書評記事 。
解説 1881年4月6日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois 別冊に掲載されたフロベール『ブヴァールとペキュシェ』 Bouvard et Pécuchet についての書評記事 。ギュスターヴ・フロベール(Gustave Flaubert, 1821-1880)の愛弟子として、ここでモーパッサンは師の遺作の理念について詳しく語っている。『ブヴァールとペキュシェ』についての解説として今日なお遜色のないもので、弟子の理解の確かさと深さをありありと示すものである。
モーパッサンの懸念通り、出版当時、この作品は正当には理解されなかった。未完のままに残された本作はフロベールの栄光に何ら新しいものをつけ加えないと判断され、むしろ期待していた読者を裏切るものと映った。誰もが『ボヴァリー夫人』(1857)と『感情教育』(1869)をフロベールの頂点と見なすなか、『ブヴァール』こそが最高の作品であると主張したのは、当時ほとんどモーパッサンひとりだけだった。
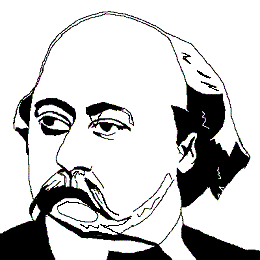 文中「愚かさについての書類」として言及される、フロベールが遺した膨大なメモは、今日『ブヴァールとペキュシェ』第2部をなすと考えられているもの(『紋切形事典』を含む)。フロベールの姪カロリーヌの委託を受け、モーパッサンは原稿を預かり、編集に取りかかる。しかし、膨大な引用だけを出版することは不可能であり、フロベールの遺志に背くことになるとして、断念することとなった。その代わりとして1884年フロベール『ジョルジュ・サンド宛書簡集』の序文「ギュスターヴ・フロベール」において、モーパッサンはこの「書類」の内容を詳しく語っている。これは長らく、フロベールの遺稿に関する唯一の貴重な情報源だった。
文中「愚かさについての書類」として言及される、フロベールが遺した膨大なメモは、今日『ブヴァールとペキュシェ』第2部をなすと考えられているもの(『紋切形事典』を含む)。フロベールの姪カロリーヌの委託を受け、モーパッサンは原稿を預かり、編集に取りかかる。しかし、膨大な引用だけを出版することは不可能であり、フロベールの遺志に背くことになるとして、断念することとなった。その代わりとして1884年フロベール『ジョルジュ・サンド宛書簡集』の序文「ギュスターヴ・フロベール」において、モーパッサンはこの「書類」の内容を詳しく語っている。これは長らく、フロベールの遺稿に関する唯一の貴重な情報源だった。師の遺業を顕揚し、フロベールの人と作品に正当な位置を与えることにモーパッサンは終生心を尽くした。「文学にすべてを捧げた」人物としてのフロベール像に、幾らかなりと「神話化」の意図を読みとることは不可能ではないとしても、モーパッサンの師への尊敬と愛情の念を疑うことはできないだろう。
***** ***** ***** *****
ブヴァールとペキュシェ
ブヴァールとペキュシェ
ギュスターヴ・フロベールの最後の小説『ブヴァールとペキュシェ』がアルフォンス・ルメール書店から発売されたばかりだ。
この優れた作家の全作品の中で、これは間違いなく最も深く、最も調べられたもので、最も広大なものである。だがそれゆえに、恐らく最も理解されないものとなるだろう。
以下にこの風変わりな百科全書的な書物の思想と展開がどのようなものかを述べるが、本の副題は「人間の知についての研究における方法の欠如」ともなるだろう。
パリで雇われたふたりの書記が偶然に出会い、密接な友情で結ばれる。ひとりが遺産を相続し、もうひとりは貯金を持ち寄る。ふたりはノルマンディーに農園を買い、それはふたりの生活全体の夢であるのだが、そして首都を去る。
さて、彼らは人類のあらゆる知識にわたって一連の研究と実験を始める。そしてそこにおいて、この作品の哲学的構想が展開するのである。
彼らはまず園芸に、次いで農業、化学、医学、天文学、考古学、歴史、文学、政治、衛生学、動物磁気、魔術に取り組む。ふたりは哲学に辿り着き、抽象概念に没頭し、宗教にはまり、うんざりすると、ふたりの孤児の教育を試み、また失敗すると、幻滅し、絶望し、以前のように筆写を再開するに至る。
したがってこの書物は、あらゆる科学の点検であり、科学はふたりの十分に聡明で、凡庸で、単純な精神に現れるがままに示される。それは同時に巨大な知の積み重ねであり、とりわけ、あらゆる科学的体系についての驚くべき批判であって、それぞれの体系が対立し合い、お互いに滅ぼし合うのだが、それは著者たちの永遠の相互矛盾、事実間の矛盾、認められ、異論のない法則同士のもたらす矛盾によるものなのだ。それは人類の知の非力さについての物語であり、一本の糸を手に博識の無限の迷宮の中を散策することになる。その糸とは優れた思想家の大いなる皮肉であり、彼は絶えず、あらゆるものに永遠の普遍的な愚かさを確認するのだ。
何世紀にもわたって確立された信仰が10行の内に提示され、発展させられ、そして別の信仰との対立によって分解され、その別の信仰も同じように鮮明に、生き生きと提示され、解体される。頁から頁に、行から行にわたって、ひとつの知が立ち上がり、すぐにまた別のものがそびえ立つと、前のものを倒し、自分もまた隣のものに打倒される。
『聖アントワーヌの誘惑』で古代の宗教と哲学についてなしたことを、フロベールは改めて、あらゆる現代の知に対してなし遂げた。それは科学のバベルの塔であり、そこではあらゆる多様な教義が、相反しながらもそれぞれは絶対的なもので、各々自分の言葉を話し、努力の空しさ、断言に含まれる虚栄、常に「一切のものの永遠の惨めさ(1)」を証明している。
今日の真理は明日には錯誤となり、すべては不確かで、変わりやすく、比率は分からないままに多くの真と誤りとを含んでいる。真も誤りもないのではない限りの話だが。この書物の教訓はブヴァールの以下の台詞に含まれているように私には思われる。「科学は領域の一部分からもたらされた資料に従って作られる。人の知らない残り全部には恐らく適応しないのだろう。そちらのほうが一層広いのだが、発見することはできないんだ(2)。」
***
したがって、著者と公衆との間に誤解があってはならないし、出来事を求める読者が「これが小説だって? でも筋がないじゃないか」などと言うようなことがあってはいけない。それは確かに小説であるが、哲学的小説なのであって、かつて書かれたなかで最も驚くべき書物なのだ。間違いなく、批評家たちは驚かせてくれる事柄を要求し、「万人のための芸術」の名において、知性ある者だけのためのこの芸術を攻撃するだろう。小説というイメージ豊かな形式を純粋な哲学的議論に供する著者の権利に、異議が申し立てられることさえあるだろう。そんな風に考える者たちには残念なことである。彼らは理解することがないだろうから。この書物は、人間のうちにあって偉大なもの、奇妙なもの、繊細なもの、そして「興味深い」すべてのものと関わっている。それは「概念」の歴史であり、「概念」はあらゆる形態、あらゆる現われ方のもとに、あらゆる変化を伴って、その弱さと強さのうちに描かれる。
ここで興味深いこととして指摘しておくべきは、ギュスターヴ・フロベールは、次第に抽象度を増しつつ高められていく理想へ恒常的に傾倒していったということである。理想という語でもって、ブルジョアの想像力を魅了するロマンチックなロココ趣味を言うのではない。それというのも、理想とは大部分の人間にとっては「本当らしくない」ものでしかないからだ。他の者にとっては、それはごく単純に概念の領域を指している。
ギュスターヴ・フロベールは、軽率な者たちがどう述べてきたにせよ、常に最も頑固なイデアリストだった。けれども、彼には同時に激しい真実への愛があったので、それがなければ芸術は存在しないが、先ほど述べたように、理想と本当らしくないものとを混同する者は皆、彼を狂信的な物質主義者だとしてきたのである。
我々の間ではそんな風に人は理解するものである。
一般に小説と呼ばれるものにおいては、人物が動き、愛し合い、戦い、滅ぼし合い、死に、絶えず動いている。この書物においては、人物はほとんど諸概念の代弁者でしかなく、概念は彼らのうちに生き、存在する者のように、動き、結ばれあい、争い、滅ぼし合う。そして、人間性を擬人化するこのふたりの哀れな老人の頭の中に信仰が行列する様から、特別な滑稽さ、並外れた滑稽さがあらわになる。ふたりは常に誠実で、常に熱心であるが、経験は変わることなく最も確立された理論にも反する。最も微細な道理が、最も単純な事実によって覆される。
科学についてのこの驚くべき建造物は、人間の非力さを証明するために建てられたもので、一個の仕上げ、一つの結論、明々白々たる正当な論拠を備えるはずだった。その巨大な論告文書のうちに、著者は雷のごとく強烈な証拠を貯え、偉人たちから集められた愚かな言行についての資料を積み重ねたのだった。
ブヴァールとペキュシェがすべてにうんざりし、写筆を再開した時、ふたりは自然と以前に読んだ書物を開き、自分たちの研究の辿った自然な順序を繰り返し、自分たちが知識を得た書物から選ばれた一節一節を、細心の注意を払って書き写していった。その時、愚かさ、無知、明白で奇怪な矛盾、とんでもない誤謬、恥ずべき断言、最も卓越して了見の広い知性が犯したありえないような過失が、恐ろしいような連続をなし始めた。何か一つの主題について書いた誰かは、しばしば愚かな言葉を吐いた。この愚かな言動を、フロベールは倦むことなく発見し、収集した。そしてひとつのものを別のものと、また別のもの、また別のものと関連づけ、彼は巨大な束を築き、それはあらゆる信仰、あらゆる断言の意気を挫くものとなった。
この「愚かさについての書類」は、今日ノートの山をなしている。恐らくは来年、公衆にゆだねられることになるだろう。
***
ギュスターヴ・フロベールの半生は『ブヴァールとペキュシェ』についての考察に過ぎ、彼は最期の10年間をこの力仕事の実践に捧げたと言えるだろう。飽くことを知らぬ読書家、疲れ知らずの研究者として、休みなく資料を積み重ねた。ついにある日、作品に取りかかったが、仕事の巨大さに驚いたのだった。「狂ってしまわなければならない」としばしば彼は述べた。「このような書物を企てようとするには。」とりわけ超人的な忍耐と、根を張った意志とが必要だった。
彼方、クロワッセにおいて、窓が五つある広い書斎の中、彼は自分の作品を前に昼も夜も呻き声をあげた。休息も、慰めも、快楽も、気晴らしもなく、精神を驚くほどに緊張させ、絶望的なゆっくりさで彼は進んでゆき、毎日、読むべき新しい本、取り組むべき新しい調査を発見するのだった。そしてまた文章が彼を苦しめた。とても簡潔で、とても正確で、同時に彩りのある文章は、二行の内に一巻の書物を、一段落の内にひとりの賢者の思考のすべてを閉じ込めなければならなかった。同じ性質の思想のひと山をまとめて取り上げ、霊薬を準備する化学者のように、それらを溶かし、混ぜ合わせ、付随物を取り除き、主要な思想を純化し、そして驚くべき坩堝からは、50語の内に哲学の一体系を包摂する絶対的な公式が現われ出るのだった。
一度、彼は疲れ、ほとんど意気阻喪して止まらなければならなかった。そして休息として、『三つの物語』と題された甘美な書物を著したのだった。
それから彼は再び仕事に取りかかった。
だがその企ては人のなしうるものではなかった。このような書物はひとりの人間を食い尽くす。それというのも我々の力には限界があり、我々の努力は無限ではありえないからだ。フロベールは二三度、友人たちに宛てて記している。「人間の完成が書物のそれより先なのではないかと恐れている――麗しい章末となることだろう。」
そんな風に書き続けたので、ある朝、彼は仕事に討たれて斃れた。あまりにも高くに登ろうとした野心の大きすぎたタイタンのように。
そして、私は神話との比較をしたのだから、以下に『ブヴァールとペキュシェ』の物語が私の精神に目覚めさせるイメージを語ろう。
私はそこに古代のシシュポスの寓話を見いだす。現代のブルジョアたる二人のシシュポスは、絶えずこの科学の山峰の登攀を企て、理解というこの岩を押し上げてゆくが、それは絶えず転がり、落ちてゆく。
だが二人は最後には、息あえがせ、意気阻喪し、歩みを止め、そして山に背を向けると、自分たちの岩に腰をおろすのである。
『ゴーロワ』紙、1881年4月6日付、別冊
Le Gaulois, supplément, 6 avril 1881.
Guy de Maupassant, Chroniques, éd. Gérard Delaisement, Rvie Droite, 2003, t. I, p. 183-186.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
Le Gaulois, supplément, 6 avril 1881.
Guy de Maupassant, Chroniques, éd. Gérard Delaisement, Rvie Droite, 2003, t. I, p. 183-186.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
訳注
(1) « l'éternelle misère de tout »:『感情教育』(1869)、第3部第1章のなかの言葉。
(2) 『ブヴァールとペキュシェ』、第3章。
