モーパッサン
「書簡に見るギュスターヴ・フロベール」
« Gustave Flaubert d'après ses lettres », le 6 septembre 1880
(*翻訳者 足立 和彦)
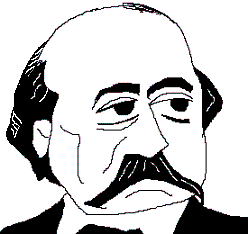 解説 1880年9月6日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois に掲載された、師フロベールについての一文。8月23日同紙掲載の「一年前の思い出」に続いて、フロベールについて語っていることになる。ここでは彼の書簡を引用しながら、文学に一生を捧げた芸術家として、フロベールの精神的肖像を描いている。
解説 1880年9月6日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois に掲載された、師フロベールについての一文。8月23日同紙掲載の「一年前の思い出」に続いて、フロベールについて語っていることになる。ここでは彼の書簡を引用しながら、文学に一生を捧げた芸術家として、フロベールの精神的肖像を描いている。文学の師であると同時に精神的父でもあったフロベールの死が、モーパッサンに与えた影響は計り知れない。この時期に二回続けてフロベールを話題にしている事実も、モーパッサンの思いの強さを語っている。ただ芸術だけに生きた作家というフロベール像はいささか堅苦しく感じられ、今は亡き先達を「聖別化」しすぎているきらいがあるかもしれない。しかしそれが、モーパッサンの見た偽らざるフロベールの姿であったのだろう。
後半に登場する「デビューしたての若者」とはモーパッサン自身のことである。モーパッサンの引用には原文どうりでない箇所が見受けられる。
***** ***** ***** *****
自分の芸術に対する敬意と文学的尊厳の念を、ギュスターヴ・フロベール以上に遠くまで推し進めた者は存在しない。唯一の情熱、文芸に対する愛が、最期の日まで彼の人生を満たしていた。彼は熱狂的に文芸を愛し、その愛し方はほとんど絶対的なもので、ライヴァルも存在しなかったし、この天才の抱く愛情は四十年以上も持続し、一度たりと衰えることはなかった。
書かない時には、彼は読書し、ノートを取った。
どんな文学も、ほとんどどんな作家もと言えるだろうが、彼にとって無縁なままではありえなかった。
友人たるご婦人方に宛てた彼の書簡には次のように書かれている。
「美しく、魅力的なあなたに向かってどう言えばいいでしょう? 私は医学理論と教育論の歴史を研究しています。その後には他の課題に移ることでしょう。たくさんの書物をむさぼって、ノートを取っているのです。こんな風にして二年か三年が過ぎることでしょう。その後で、私は書き始めるのです(1)」
別の書簡にはこうある。
「あなたの友人はこの冬、自分でも理解できないほどに仕事をしています。この一週間、全部で十時間しか眠りませんでした。もうコーヒーと冷水の力に頼ってしか立っていられなかったのです。つまり、私は恐ろしいような興奮に捕らわれていたのでした。もう少しで、この善良なる男もくたばるところでした(2)」
そしてまた別の書簡。
「・・・たくさん仕事をしています。毎日水浴びをして、誰の訪問も受け付けず、どんな新聞も読まず、(今がそうであるように)規則的過ぎるほどに朝陽が昇るのを眺めていますが、それというのも夜の間に仕事をぐっと前に進めるのです。窓を開けたまま、上着を脱いで、静かな書斎の中でうなっている様は、まるで憑かれた者のようです(3)」
実際、彼は熱狂的に仕事をする種族に属していたのである。
ほとんど一年中、熱愛するクロワッセの領地に居て、午前九時か十時から、彼は仕事に取り掛かった。昼食を終えるとすぐに、広い庭を一周することもなく仕事を再開したもので、そして夜の間中、セーヌ河を上り下りする船員達は、遠くから「フロベールさん」の四つの窓明かりを灯台のように利用するのだった。
教室で幼い子供達に読ませ、年長の者達に暗記させるためには、偉大なる芸術家のこの見事な生涯を書き記す必要があるだろう。彼はただ自分の芸術のためだけに生き、そのために死に、彼が言ったように、自分の心臓を黙らせたのであり、あらゆる欲望を退け、官能の炎さえも消し去ってしまったのだった。誰よりも金銭を軽蔑し、それを稼ぐのを潔しとせず、利益に関する議論に汚されるように思い、社交界の気晴らしや、娯楽、喜びや快楽に対する荒々しい軽蔑の念に溢れ、書物からもたらされる以外のどんな幸福も決して知ることがなかった。しばしば興奮に喘ぎながら、よく響く声で大家の作品の数章を朗誦したのだった。
何をして、どこに行こうとも、彼の精神は常に文芸のことしか考えてはいなかった。人々も、会話も、物腰も、彼にはもはや描くべき効果でしかなく、凡庸な会話が一晩中続くようなサロンから退出した時には、まるでめった打ちにされかのように衰弱し、打ちのめされ、自分自身が愚かになってしまったと彼は断言したものだが、それほどに、他人の肌の内にまで入って行くことの出来る能力を備えていたのである。
過剰なまでに敏感で、心を動かされやすく、絶えず高ぶっている彼は、皮を剥がれた者に自らを譬えたもので、些細な接触でさえ、痛みに震えるのであった。そして彼が受けた大きなショックとは、恐らくは人間の愚かさに由来するものだった。それはいわば彼の個人的な敵、悲痛の種、彼の人生が受けるべき刑罰だった。そして彼は、獲物を追う狩人のように執拗にそれを追い求め、最も偉大な者達の頭脳の奥底においてまでそれを捕らえた。彼にはそれを発見するに猟犬のような鋭敏さがあり、新聞の中や、一冊の美しい書物の中においてさえ、彼の素早い視線はそれの上に注がれるのだった。時にはそのためにあまりにも憤慨することになったので、彼は種を丸ごとを破滅させたいとさえ望んだだろう。そして、「ブルジョワ」に対する彼の憎しみというのも、愚かさに対する憎しみに他ならなかったのである。
ある日には、おぞましい書物を数え挙げた後で、彼は記している。「これは全て、我が同胞たちに対して、彼らが私に催させた嫌悪感をぶつけるというだけの目的なのです。最後には私は、自分の考え方を述べ、恨みをぶちまけ、憎しみを吐き出し、苦汁をまき散らし、憤りを洗い落とすことでしょう(4)」けれども、たとえ巷の愚かさを激しく憎んでいたとしても、彼はどれほどに知性を熱愛し、崇拝していたことだろう! ルナン氏を不器用に批判した、ある親しい新聞に対して彼は気を悪くしたことがある。ヴィクトール・ユゴーの名前だけで、彼の目には涙が浮かんだ。そしてこの文学者は、それが誰であろうとも、科学者、「学者」に向かって、自分の前で誰かが口を出すのを許しはしなかっただろう。彼はクロード・ベルナールを褒め称え、ベルトゥロ氏(5)を友人に持っていた。
芸術的に高い道徳によって生涯を導かれ、彼はしばしばそれを打ち解けた言葉で、教訓として若い者達に助言したものだった。以下、あるデビューしたての若者に宛てた手紙の一節である。
「今から貴君のことを話そう。君は女性たちが「単調」だと嘆いている。とっても簡単な治療法があるが、それはそれらを利用しないことだ。
「出来事は変化に乏しい」それは現実主義的な不満である。しかしそもそも君は、それについて何を知っているのか? 問題はそれらをもっとよく見ることにある。君はかつて事物の存在を信じたことがあるというのか? すべては一個の幻影ではないのか? 真実であるのは「関係」だけだ。つまりは、我々が事物を認識するあり方だけである。
「悪徳はしみったれている」――しかし全てのものがしみったれている。
「文章には十分な言い回しが存在しない」――探したまえ、そうすれば君は見つけるだろう。
結局、親愛なる友よ、君は随分とうんざりしているようだし、君の憂鬱は私を悲しませる。何故なら君は自分の時間をもっと気持ちよく使えるはずだからだ。「必要」なのは、青年よ、分かってくれたまえ、もっと働くことが「必要」なのだ。君はいくらか怠惰なのではないかと私は疑うに至ったよ。女が多すぎるし、ボート漕ぎが多すぎる、「運動」が多すぎる。そうだよ君、医者の諸君が主張するほどには、文明人は運動を必要とはしないものだ。君は詩を作るために生まれてきた。作りたまえ! 「他のもの一切は空しい」まずは貴君の快楽と健康からだ。そんなものは頭の中で相手にしなければいい。それに、君の健康は君の使命を追うのに十分のはずだ。以上の指摘はある哲学による、いやむしろある深遠なる衛生学によるものだ。
君は地獄に生きている。私はそのことを知っているし、心の底から君を気の毒に思う。しかし、午後五時から午前十時まで、君の時間の一切をミューズに捧げることができるのだ。彼女こそはまだしも最高の娼婦だ。さあさあ、我が親愛なる者よ、顔を上げるのだ。悲しみを掘り下げたところで何になる? 強い人間として、自分自身と正面から向かい合わなければならない。それが強い人間になる手段だ。まったく、もう少し誇りを持ちたまえ! 君に欠けているもの、それは原則というものだ。なんと言っても、それが必要なのだ。あとはどの原則かを弁えるだけだ。芸術家にとっては、たった一つしかない。すべてを芸術に捧げること。彼にとって、人生は一個の手段と考えなければならないし、それ以上ではない。そして彼が真っ先に馬鹿にしなければならない人間、それは自分自身に他ならない・・・(6)」
そして、また別の個所。
「けれど、哀れな親愛なる者よ、君が仕事をする時間のないことを気の毒に思う。まるで一行の美しい詩句が、君を忙殺する真面目腐った無駄話よりも、公衆の教育に十万倍も「有用」ではないかのようだ! 単純な思想というものは、人々の脳に理解させることが難しいものだ!(7)」
そしてまた、別の手紙。
「L氏は私を困惑させる。一人の人間の将来について判断を下すのは大変に重大なことに思われるので、私はそのことを差し控える。他方、書くべきかどうかを尋ねるというのは、激しい天性のある印とは思われない。愛するべきかどうか知るために他人の意見を求めたりするだろうか?・・・待っている間に、その者は働けばよい。すべてはそれ次第だ・・・(8)」
次が、彼がしばしば繰り返した興味深い格言である。
名誉とは、名誉を傷つけるものである。
称号とは、堕落させるものである。
職務とは、人を愚かにする。
そして彼は付け加えたものだ。「それを書いて壁に貼っておきたまえ」
彼は自分の精神をあまりに高い位置に置いていたので、どんな下劣な関心も彼には届かなかった。芸術が、彼の関心を惹く唯一の話題だったし、その他のことについて彼と話すのはほとんど出来ない相談だった。
彼は今世紀随一の文体家であったし、そうであり続けるだろう。執拗なまでの労働者、一徹なまでの推敲家、しばしば彼は一週間かけて、一行の文章から不愉快な一個の動詞を取り除いたのだった。
彼は言葉の「宿命的な」調和というものを信じていたし、不可欠と思われる一個の表現が、しかしながら彼の思うようには響かない時には、すぐにも別のものを探したものだし、「本当の」、「唯一の」表現を手にしていないのだと確信していた。彼にとって文体とは、型にはまった構成のある種の優美さにではなく、言葉の絶対的な正確さと、表現と表明すべき思想との間の完璧な一致の中にこそ存在した。そこから、『感情教育』の大変に正確で簡潔な文体と、『聖アントワーヌの誘惑』の見事な文章との間の、あの決定的な違いが生まれているのだ。
ある友人に宛てて彼が記したバルザックについての文章が、この観点からして興味深い。
「この偉大なる人物は詩人でも作家でもなかったが、だからといって彼が大変に偉大な人物であることには変わらない。今日では、彼を尊敬する気持ちは昔よりぐっと少なくなったが、それは、より一層に完成というものに餓えるようになったからだ。だが恐らくは私の方が間違っているのだろう(9)」
以上がごく簡単な彼の生涯についての概観であるが、しかしそこから道徳的教訓を引き出すことができよう。
一人の芸術家が作品に取りかかる時には、彼はいつでもある秘密の、芸術とは無縁の野心を抱くものである。人が真っ先に追い求めるのは栄光であり、輝かしい栄光が、生きたまま彼を崇拝の対象とし、人々を振り向かせ、手を叩かせ、女達の心を虜にする。女性達に気に入られること! それもまたほとんど全ての者にとって熱狂的な欲望である。才能の全能ぶりによって、パリにおいて、巨大なハーレムの中のスルタンのようになれるということ。右に、左に、社交界のサロンや劇場のボックス席の中で、我々が絶えず餓えているあの生きた肉体の果実を摘み取ること。まったく障害を知らずにいること。そして、従僕が自分の名前を響き高く呼び上げた時、輝く視線を自分の上に注いでいる魅惑的な被造物すべての中から、選ぶべき一人を探し出すこと。
他の者達は金銭を追い求めた。それ自体のためであったり、それがもたらしてくれる満足のためであったり。すなわちは、豪奢な生活と食卓の上の甘美な料理。
ギュスターヴ・フロベールは文芸をあまりにも絶対的な形で愛したので、この愛に満たされた彼の魂においては、他のどんな野心も場を占めることはできなかった。
ほとんどいつでも一人、田舎に暮らし、パリでは大変に親しい友人以外にはほとんど顔を合わせることもなく、彼は他の多くの者達のようには、社交界でのああした勝利や、民衆の人気を求めもしなかった。彼は文学的であれ政治的であれ、どんな祝宴にも決して出席しなかったし、どんな徒党、どんな党派にも自分の名前を加えなかったし、称賛を得るためといっても、どんな凡庸な者、どんな愚か者の前でも身を屈めたりすることはなかった。
彼の肖像写真は決して売りに出されなかった。彼は芝居の初演にも、社交界の人士が通う場所にも姿を現さなかった。彼は一種の羞恥心から自分の姿を隠しているようだった。「私は公衆に自分の作品を差し出している」と彼は言っていた。「これ以上に自分の顔をさらすことはできないさ」
感じやすく、ほとんど感傷的でさえある性質ながら、しかし彼は愛からも身を遠ざけた。
何人かの女性達が、彼の忠実なる友人であった。別の何人かは、恐らくは彼の愛人だった。だが彼は心を文学に与えたのであり、決してそれを取り返すことはなかった。
彼はただ芸術のためだけに生きた。この節度を越え、高揚した愛情に人生を費やし、孤独な恋人のように熱にうかされた夜を過ごし、腕を振り上げ、叫び声を上げ、神聖な熱狂に打ち震え、そして彼は最後には、ある日のこと、仕事に斃れたのである。すべて偉大な情熱の持ち主が、自らの悪徳によって死を迎えるのと同じように。
『ゴーロワ』紙、1880年9月6日付
訳注
(1) 1872年10月5日付、レオニー・ブレンヌ宛。
(2) 1877年2月15日付、レオニー・ブレンヌ宛。
(3) 1876年7月8日付、レオニー・ブレンヌ宛。
(4) 1872年10月5日付、レオニー・ブレンヌ宛。
(5) Marcellin Berthelot (1827-1907):化学者、科学史家、政治家。1865年よりコレージュ・ド・フランスで有機化学を講じた。
(6) 1878年8月15日付、モーパッサン宛書簡。
(7) 1879年4月25日付、モーパッサン宛書簡。
(8) 1876年8月10日付、モーパッサン宛書簡。
(9) 1876年11月30日付、モーパッサン宛書簡。

