『エラクリユス・グロス博士』(1)
(1-10章)
Le Docteur Héraclius Gloss, vers 1875
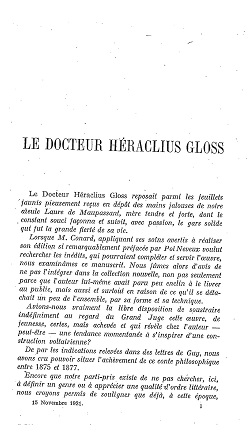 解説 生前未刊行のままに残されたモーパッサンの中編小説。
解説 生前未刊行のままに残されたモーパッサンの中編小説。1875年10月6日母親宛て書簡の中に「『エラクリユス』の中の女中と猿の章をどんな風にまとめればいいか全然分らなくて、すっかり困っています」とあることから、およその執筆時期が推測されるが、詳細はまったく不明。
1921年『パリ評論』Revue de Paris に、2回に分けて(11月15日、12月1日)初めて掲載された。原稿はモーパッサンの甥、ジャン・オソラが所持していたもので、最初の全集コナール版出版時には、「形式と文体」が他の作品と異なるゆえに掲載が見送られたという。なお原稿はその後の全集出版(シュミット版、1957)の際に失われてしまった。
この「哲学的コント」はヴォルテール的だと評されるが、他にもラブレー、ラ・フォンテーヌ、あるいはポー、ホフマンの影響が指摘される。なによりフロベールの『聖アントワーヌの誘惑』そして『ブヴァールとペキュシェ』が源泉にあったことは間違いないだろう。
形式・内容ともに後のモーパッサンとは大きく異なるこの作品は、ぎこちない文体のためもあって「習作」の色が濃いものである(学校で学んだ古典へのレフェランスが多い点も特徴的)。また、諧謔的な一人称の語りが頻出する点も、後の散文と相違を見せている。
一方、後半の展開においては「狂気」(および「分身」)のテーマが前面に現れるが、ペシミスムの濃い結末とともに、後の散文に引き継がれる要素が既に認められるのも確かである。
恐らく本邦初訳の、この若いモーパッサンが著した「哲学コント」を、ぜひともご一読いただきたい。
***** ***** ***** *****
エラクリユス・グロス博士
エラクリユス・グロス博士
Ⅰ
エラクリユス・グロス博士は
精神面では、どのような人物だったか
エラクリユス・グロス博士は
精神面では、どのような人物だったか
エラクリユス・グロス博士は、とても博識な男だった。彼の署名のあるものは、どんな小さな論文さえも一度も街の書店に並んだことはなかったが、学識深いバランソンの街の住民皆が、エラクリユス博士をとても博識な男と思っていた。
どうして、何について、彼は学者だったのか? 誰もそれを言うことは出来なかっただろう。ただ、彼の父も祖父も、市民から博士と呼ばれていたことだけが分かっていた。彼はその肩書きを、名前、財産と一緒に相続したのであった。彼の家では、父祖代々エラクリユス・グロスと名乗るように、父祖代々、学者だったのである。
さらに、自ら署名し、どこかの有名な大学の先生方が連署した学士免状を持っていなかったにしても、だからといってエラクリユス博士が、とても堂々とした、とても博識ある人物であることには変わりがなかった。広い書斎の四面の壁を覆い尽くす、本の詰まった四十の棚を目にするだけで、彼以上に碩学の学者が、バランソンの都市に名誉を与えたことはなかったと確信するのに十分だった。最後に、学部長と学長の前で、彼の人柄が問題になる度に、二人がいつも謎めいた微笑を浮かべるのが見られた。人の伝えるところでは、ある日、学長が大司教の前でラテン語で彼を大変に賞賛したという。その話をした証人はさらに異論の余地のない証拠として、自分の聞いた数語を引用した。
「泰山鳴動スレバ鼠一匹」
しかも学部長と学長は毎日曜、彼の家で夕食を摂るのだった。だからエラクリユス・グロス博士が十分に博識ある男ではないなどと、あえて疑ってみる者はいなかったのである。
Ⅱ
エラクリユス・グロス博士は
身体面では、どのような人物であったか
エラクリユス・グロス博士は
身体面では、どのような人物であったか
幾人かの哲学者が主張するように、一人の人間の精神と肉体の間には完璧な調和が存在する、というのが本当であれば、また、顔の輪郭から性格の根本的な特徴が読み取れるというのが本当であれば、エラクリユス博士は、この主張に否定を与えるようには出来ていなかった。彼は小柄で、活発で神経質だった。彼の内には鼠が、テンが、バセット犬が住み、つまり、彼は探求者、何でもむしばむ者、狩人、疲れ知らずの者の家系の出だった。彼を見ても、彼が研究したあらゆる教義がこの小さな頭の中に入りうるとは思いもしなかったが、分厚い本の中に入り込んだ鼠のように、彼自身が知識の中に入り込み、それを齧りながら生きている様は、すぐに想像されるのだった。とりわけ奇妙なのは、彼の容姿が極端に痩せていることだった。友人の学部長は、恐らくは多少の根拠をもって、彼は何世紀もの間、二つ折り版の本のページの間に、バラとスミレと並んで挟まれたまま忘れられていたに違いない、何故なら彼はいつも小奇麗で、いい匂いをさせているから、と主張していた。とりわけ顔立ちは剃刀の刃のように尖っていたので、金の眼鏡の蔓は額から大きくはみ出て、船のマストの帆桁のようだという強い印象を与えた。バランソンの大学長はしばしば言ったものだった。「あれが博識のエラクリユス博士でなかったら、間違いなく、見事な紙切りナイフを作ったことだろう」
彼は鬘をかぶり、きちっとした身なりで、決して病気に罹らず、動物を愛し、人間を憎まず、鶉の串焼きを熱愛していた。
Ⅲ
何にエラクリユス博士は
日中の十二時間を
使っていたか
何にエラクリユス博士は
日中の十二時間を
使っていたか
博士は目を覚まし、石鹸で顔を洗い、髭を剃り、パターつきの小さなパンを、バニラ風味のショコラに浸してお腹に詰め込むと、すぐに庭へ下りてゆくのだった。都会の常として庭はさほど広くないが、快適で、木陰があり、花が咲き、静かで、あえて言えば瞑想的であった。つまり、真実を求める哲学者の理想の庭とはこのようなものに違いない、というものを想像するなら、エラクリユス・グロス博士が速足で三四周する庭を理解するに遠くないだろう。それから彼は二度目の朝食として、日課の鶉の串焼きに身を委ねるのである。このちょっとした運動は、彼の言うところでは、目覚めに素晴らしいとのことであった。眠りによって麻痺した血液の循環を活性化し、脳の体液を追い出し、消化管を準備するのである。
その後、博士は食事を摂る。それから、カフェを飲み終えるや、彼はそれを一息に飲み干すのだが、テーブルで始まった消化ゆえの眠気に身を任せることは決してなく、大きなフロックコートを羽織り、外へ出かけるのだった。そして毎日、大学の前を通り、ルイ十五世様式の大型の懐中時計の時間を、大学の時計台の高い文字盤のと見比べた後、彼はヴュー・ピジョン(古鳩)小路に姿を消し、夕食までそこから出て来ることはなかった。
一体、エラクリユス・グロス博士は、ヴュー・ピジョン小路で何をしていたのか? そこで彼がしていたのは、ああ!……彼はそこで哲学的真実を探していたのだ。それは以下のようであった。
暗く、汚れたこの狭い通りに、バランソンの全ての古書店が店を並べていた。ヴュー・ピジョン通りを形成する五十のバラックの、地下室から屋根裏にまで積まれた、思いがけない書物の題名だけを全て読み上げるのにも、何年も必要なことだったろう。
エラクリユス・グロス博士は、通りを、家々を、古書店を、そして古書を、彼個人の所有物のように眺めるのだった。
しばしば起こったことだが、ある骨董屋の店主が、眠りに就く頃になって、屋根裏で物音がするのを聞きつけ、過去の時代の巨大な長剣を構えて忍び足で上って行くと、彼はそこに見つけるのだった……エラクリユス・グロス博士を ―― 体半分、古書の山に埋もれ、一方の手には蝋燭の残りを持ち、指の間には蝋が溶け落ち、もう一方の手では古代の手稿をめくっている。恐らくは、そこから真実を湧き上がらせようと期待して。そして哀れな博士は、鐘楼の鐘がとっくに九時半を鳴らし、惨めな夕食を摂らねばならないことを知って大変に驚くのだった。
それは、真剣に探していたからなのだ、エラクリユス・グロス博士が! 彼は古代、現代のあらゆる哲学を深く知っていた。彼はインドの宗派を、アフリカの黒人たちの宗教を研究した。北方の未開人、南方の原始的な民の中に、彼がその信仰を調査したことないような、どんな少数民族も存在しなかった。ああ! ああ! 彼が研究し、調査し、探索し、瞑想すればするほど、一層彼は決心がつかなくなるのだ。「友よ」と、ある夜、学長に言った。「新世界を求め、果敢に海を横断したコロンブスたちは、我々よりもどれほど幸福であろうか。彼らはただ前に進めばよかった。彼らを妨げる困難は、物質的な障害に由来するものばかりで、勇敢な人間ならばいつでも克服出来る。一方で我々は、不確実の海の上を絶えず揺られ、北風に捕まる船のように、荒々しく仮定に押し流されるかと思えば、突然、逆風の如くに、対立する教義に出会い、希望もなく、出立した元の港に連れ戻されるのだよ」
ある夜、学部長と哲学談義をしている時には、彼にこう告げた。「君、真実は井戸の中にあるとはよく言ったものだ……バケツ(seaux)は何度も降りて行っては、それを汲み上げようとするが、決まって澄んだ水しかもたらさないのだ。……ご推察の通りだよ」と彼は抜け目なく付け加えた。「どんな風に私がその文字(Sots:馬鹿)を書くかは」
それが唯一の、彼の口から聞かれた言葉遊びであった。
IV
何にエラクリユス博士は
夜中の十二時間を
使っていたか
何にエラクリユス博士は
夜中の十二時間を
使っていたか
エラクリユス博士が、夜、家に帰る時には、普通、出発した時点よりも大変に太っているのだった。それは、ポケット一つ一つが、その数は十八あったのだが、ヴュー・ピジョン小路で買い求めたばかりの、哲学に関する古代の書物で一杯になっているからだ。冗談好きな学長はこう主張していた。もしこの瞬間に化学者が彼を分析したら、博士の構成要素の三分の二を、古い紙片が占めていることを発見しただろうと。
七時に、エラクリユス・グロスは食卓に就き、食べながら、自らが所有者となったばかりの古い書物に目を通した。
八時半に博士は厳かに立ち上がる。その時の彼は、日中の敏捷、快活な小男ではもはやなく、深刻な思想家なのであって、その頭は高尚な瞑想の重みに傾げられ、重すぎる荷物の下の担ぎ人夫のようであった。家政婦に対し、威厳に満ちた「誰にも面会しないので」の言葉を投げつけた後、彼は自分の書斎に消える。一度そこへ入ると、書物に溢れた机の前に座り、そして……彼は夢想するのだった。その時に博士の思考の中を覗ける者があったら、何と奇妙な光景があったことだろう!!……最も相反する神々、最大限に種々雑多な信仰から成る怪物じみた行列、教義と仮定との幻想的な交錯。あたかも一個の闘技場であり、そこであらゆる哲学の闘士たちが、巨大なトーナメントにおいてぶつかり合うのである。彼は東洋の古代唯心論とドイツの唯物論を、使徒たちの道徳とエピクロスのそれとを、寄せ集め、組み合わせ、混ぜ合わせた。彼が教義の組み合わせを試みるのは、実験室で科学物質の化合を試みるのに似ていたが、表面に、あれほど望んでいる真実が泡立つのを見ることは、決してなかった。――そして、よき友人である学長が主張するところでは、人が永遠に待ち焦がれるこの哲学的真実とは、まことに賢者の石に似ているのである……ただし躓きの石に。
真夜中に博士は眠りに就く。――眠りの中で見る夢は、前日までと全く同じものであった。
V
かくして、全てを期待する先は、学部長は
折衷主義、博士は啓示
そして学長は消化
かくして、全てを期待する先は、学部長は
折衷主義、博士は啓示
そして学長は消化
学部長、学長と彼が、広い書斎に集ったある夜、大変興味深い議論が繰り広げられた。 「友よ」と学部長が言った。「折衷主義をとり、エピキュリアンになることが必要なのだよ。良いものを選び、悪いものは除きたまえ。哲学とは、地上を覆いつくす広大な庭である。東洋のまばゆい花を、北方の蒼ざめた花を、田園のスミレを、庭に咲くバラを摘みたまえ、それで花束を作り、匂いを嗅ぐがいい。その香りは、想像しうる中で最高に甘美なものではないにしても、少なくとも大変に心地よく、ただ一種の花よりも遥かに馥郁たる香りであることだろう。――それが世界一香り高い花だとしてもだ。」―― 「一層多様であるのは本当だろう」と博士が答えた。「だが一層馥郁としているというのは違う、もしあなたが、それ自身の内にあらゆる花の香りを、集め、凝縮しているような花を見つけるに至ったなら。何故なら、あなたの花束においては、ある種の香りが互いに打ち消しあうのを、そして哲学においては、ある種の信仰が互いに矛盾するのを、あなたは防げないだろうからだ。真実なるものは一つだ――あなたの折衷主義では、ばらばらの断片的な真実しか得ることはないだろう。私も以前は折衷主義だったが、今では排他的なのだ。私が望むのは、偶然のおおよそ、ではなく、絶対的な真実である。私の信じるところでは、知性ある人間は皆、予感を抱いているのであり、自分の道の先にそれを見出した者は叫ぶことだろう。『ここにあった』と。美についても同じことだ。だから私も、二十五になるまでは愛したことがなかった。たくさんの女性を可愛らしいとは思ったが、彼女たちは私に何も訴えてこなかった。――私が垣間見ていた理想の存在を構成するためには、彼女たちのそれぞれから何かをとってこなければならなかっただろうし、更に言えば、それはあなたが先ほど話した花束に似ていたろう。そんな風なやり方では、金や真実のように分解不可能な、絶対的な美を得ることは出来なかっただろう。ある日、遂に、私はその女性に出会った。彼女がそうであると私には分かった。――そして私は彼女を愛した」博士は幾らか感動して口を閉ざし、学長は学部長を眺めながら、繊細な微笑を浮かべた。一瞬の後、エラクリユス・グロスは続けた。「全てを期待しなければならないのは、啓示なんだよ。啓示こそが、ダマスカスへの途上で使途パウロを照らし、キリスト教への信仰を与えたのだ……」――「……それは真実のものではなかった」と、笑いながら学長が口を挟んだ。「何故って、あなたはそれを信じてはいないのだから――つまり、啓示は折衷主義以上に確かだというわけではないことになる」――「失礼だが、我が友よ」と博士は答えた。「パウロは哲学者ではなかった。彼は、おおよその啓示を受けたのだ。彼の精神には、抽象的なものである、絶対的真実を理解することは出来なかったのだろう。だかそれ以来、哲学は進歩したし、何らかの状況、一冊の書物、恐らくはたったの一語が、それを理解するに十分なほどに賢明なる人物に、それを明かすこととなるだろう。それは突然にその人物を照らし、それを前にしては、夜明けを迎えた星のように、あらゆる迷信が消え去るだろう」――「アーメン」と学長は言った。「だが翌日には第二の、その翌日には第三の者が啓示を得るだろう。そして頭の中で、彼らは互いに自分の啓示を投げつけ合う、幸いにも、それほど危険な武器ではないけれどもね」――「だが、それではあなたは何も信じないのか?」博士が叫んだ。気を悪くし始めていたのだ。「私は『消化』を信じている」厳かに、学長は答えた。「私は気にもとめずにあらゆる信仰、あらゆる教義、あらゆる道徳、あらゆる迷信、あらゆる仮定、あらゆる幻想を飲み込む、ちょうど、素晴らしい夕食において、等しい喜びを感じながら、ポタージュ、オードヴル、肉料理、野菜、アントルメ、そしてデザートを食するように。その後で、自分の寝床に哲学的に横になると、我が静かなる消化が、夜のためには快適な眠りを、翌日のためには人生と健康を、もたらしてくれることを疑わないのさ」――「もし言うことを聞いてくださるのなら」学部長が急いで言った。「比喩をそれ以上展開させないでおきましょう」
一時間後、賢人エラクリユスの家から出た時に、学長は突然笑い出して言った。「あの可愛そうな博士ときたら! もし真実が、愛する女のように彼の前に現れたら、かつて地上に現れた中で、誰よりも騙された人間ということになるだろう。」そして、自分の部屋に帰ろうとしていた酔っ払いは恐怖に襲われたのだが、それは学部長の力強い笑い声を聞いてのことで、その笑いは、学長の鋭いファルセットに、深いバスでもって合わせていたのであった。
VI
かくして博士のダマスカスへの道は
ヴュー・ピジョン小路だと判明し、
またいかにして真実は彼を照らしたか
輪廻転生論者の
手稿という形態の下に
かくして博士のダマスカスへの道は
ヴュー・ピジョン小路だと判明し、
またいかにして真実は彼を照らしたか
輪廻転生論者の
手稿という形態の下に
千七百――数十年、三月十七日、博士はすっかり興奮して目を覚ました。夜の間、古代風の服装をした白髪の大きな男が、指で彼の額に触れながら理解出来ない言葉を呟くのを、何度も夢に見たのであり、この夢は賢明なるエラクリユスにとって、大変意味深い予告であると思われた。これは何についての予告なのだろうか?……何において意味深いのであろうか?……博士は正確には分からなかったが、にも拘らず、彼は何事かを待った。
朝食の後、彼はいつものようにヴュー・ピジョン小路へ赴き、そして昼の鐘が鳴る時、三十一番地、衣装屋、古家具商、古書店にして、暇な時には古い靴の修繕屋、すなわち靴職人であるニコラ・ブリコレの店に入った。霊感によって動かされたように、博士は直ちに屋根裏へ上がり、ルイ十八世紀様式の棚の三段目に手をやり、そこからぶ厚い原稿を引き出したが、羊皮紙にはこう題が付されていた。
我が十八度の輪廻転生。
人の呼ぶキリスト暦
百八十四年以来の我が存在の歴史。
この奇妙な題の後に続けて、以下のような序文があり、エラクリユス・グロスは落ち着きなくそれを解読していった。
「この手稿は私の転生の忠実な物語を綴っているのだが、筆者によって、上記の通り、キリスト暦百八十四年、ローマの都市より始められたものである。
魂の再出現の入れ替わりについて、人間たちに光明を与えるべきこの説明文書に、本日、千七百四十八年四月十六日、我が運命の変遷が、私を投げ置きしバランソンの街において、我が名を記す。
見識があり、哲学的な問題に関心のある者には、このページに目を通すだけで、自らの内に最も明るい光が差し込むに十分であるだろう。
そのために、以下に読まれる私の歴史の内容を、数行で要約しようと思うが、読むためには、ラテン語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語を知っていさえすればよい。それというのも、人間として私が再出現した別々の時代に、こうした様々な民族の内で私は生きたからである。次いで、どのような概念の連鎖、どのような心理的用心、どんな記憶手段によって、私が輪廻転生という結論に誤ることなく到達したかを、説明しよう。
百八十四年、私はローマに住み、そして私は哲学者だった。ある日、アピエンヌ通りを散歩している時に、ピタゴラスは、生まれたばかりの偉大なる日の、まだ不確かな夜明けのようなものであったかもしれない、という考えが頭に浮かんだ。その時から、私には一つの欲望、一つの目標、一つの持続的な関心しかなかった。自分の過去を思い出すことだ。ああ! どれほど努力しても空しく、以前の存在については何も蘇って来るものがなかった。
さてある日、中庭に置いたジュピターの像の台座の上に、若い頃に彫った何本かの線が、偶然に目に入った。そしてそれが突然に、長い間忘れていた出来事を思い出させたのだ。それは一筋の光線のようだった。そして、もしも何年か、時にはたったの一晩が、記憶が消えてしまうに十分であるならば、尚更のこと、前世において成されたことは、中間段階の動物として生きた、長いまどろみの期間がその上を過ぎたのであれば、我々の記憶から消え去ってしまうに違いない、ということを理解したのであった。
その時、私は自分の歴史を石版に刻み、運命がいつの日か私にそれと再会させてくれることを、それが私にとって、我が像の台座の上に見つけ出された言葉のようであることを期待した。
私の望んだことが実現した。一世紀後、私が建築家であった時に、ある古い家を解体して、その場所に宮殿を建てるように命じられたのである。
私が指揮していた労働者たちが、ある日、土台を掘り返していて見つかったという、表面を文字で覆われた、ひびの入った石片を運んで来た。私はそれを解読にかかった。――そしてこの文字を記した者の生涯を読みながら、瞬間的に、忘れていた過去が素早い閃光のように私に訪れた。少しずつ、魂の中に光が差し、私は理解し、思い出した。この石を彫ったのは私だったのだ!
しかしこの一世紀の空白の間、私は何をしていたのだろうか? 私は何者だったのだろうか? どんな姿の下に私は苦しんでいたのか? それを教えてくれるものは何もなかった。
しかしながら、ある日になって、ある手がかりを得たのであるが、あまりに些細で曖昧なので、その話をするのは難しい。隣人の老人が私に語ってくれたのだが、五十年前(ちょうど私の生まれる九ヶ月前)、ローマで、元老院議員、マルクス・アントニウス・コルネリウス・リパの身に起こった事件を、人々は大いに笑ったという。彼の妻は可愛らしく、また大変背徳的とのことだったが、フェニキアの商人たちから一匹の大きな猿を買い、それをとても愛した。元老院議員コルネリウス・リパは、自分の半身である者が、この人間の顔をした四足動物を愛するのに嫉妬し、それを殺した。この話を聞きながら、私はまことに漠然と認識したのであるが、その猿、それが私だったのだ。この姿のもと、失墜の記憶のようなものに私は長い間苦しんだのであった。だが私は、それ以上、はっきりとした正確なことは何も見出さなかった。とは言え、私は以下の仮定に辿り着いたのであり、それは少なくとも大変本当らしいものであった。
動物の形姿とは、人間の姿をしていた時に犯した罪に対して課される、償いのための苦行である。動物には、優れた存在であった時の記憶が与えられ、失墜したのだという感情によって懲罰を受ける。
苦しみによって浄化された魂だけが再び人間の姿をとることが出来るが、その時には自分が経てきた動物時代の記憶を失う。何故なら、その魂は再生したのであり、過去についての認識は不当な苦しみとなるばかりだからである。結果として、人間は動物を保護し、尊敬を払わねばならない。罪を償った罪人に敬意を払うようにであり、自分が動物の姿のもとに再出現した時に、今度は他の者が守ってくれるためにである。このことは、ほとんど、キリスト教道徳の言うあの文句と同じことである。「自分がされたくないことを、他人に向かってしてはならない。」
私の輪廻転生の物語を通して、その都度の存在時に、どのように運良く私が記憶を取り戻すことが出来たか、青銅板、次いでエジプトのパピルス、最後にずっと後になって、今日も使用しているドイツの羊皮紙の上に、毎回改めて、どのように私がこの物語を書き写してきたか、お分かりになるだろう。
後に残されたのは、この教義から哲学的結論を引き出すことである。
あらゆる哲学は、魂の運命という解きがたい問題を前にして立ち止まって来た。今日優勢を占めるキリスト教の教理の教えるところでは、神は正しき者を天国に集め、悪人は地獄に送られ、悪魔によって火に焼かれるという。
だが現代の良識はもはや、族長の顔を持ち、雌鶏が雛を抱くように、翼の下に善良なる者の魂を庇う神を信じはしない。それに理性はキリスト教の教理に反論する。
何故なら、天国はどこにもありえないし、地獄もまたどこにも存在しえないのである。
それと言うのも、無限の空間といえども、我々の世界と同じようなたくさんの世界で満ちている。
それと言うのも、この世の始まり以来引き続いた世代の数を、我々のと同様に人の住む、無数の世界の上に繁殖した世代の数とかけ合せることで、魂の数はあまりにも超自然的で不可能なものとなり、乗数も無限であるのだから、神は間違いなく、どんなに強固であれ理性を失い、悪魔もまた同様の状態に陥るだろうし、それでは手に負えない混乱を来たすだろう。
それと言うのも、正しき者の魂の数は無限であり、同様に悪人の魂の数も、空間も無限であるならば、無限に広がる天国と、無限に広がる地獄が必要となるだろうが、つまりはこういうことになる。天国は至る所にあり、地獄も至る所にある、すなわち、どこにもありはしない。
さて、理性は輪廻の信仰に反論しない。
魂は蛇から豚、豚から鳥、鳥から犬へと移り、最後に猿や人間へと辿り着く。それからまた、魂はいつでもそれぞれの過ちを新たに繰り返し、それは、優れた世界へ魂を移住させるに至った、地上での浄化の頂点にあってさえ同じである。従って、魂は絶えず動物から動物へと、一つの領域から別の領域へと移動を続け、不完全なものからより完全なものへと向かい、最後に至高の幸福をもたらす星へと辿り着くが、そこで新しい過ちによって再び、至高の苦しみの領域へと投げ落とされ、また転生を繰り返すことになるのである。
従って、普遍的、宿命的な図像である円というものが、我々の存在の変遷を内に閉じ込めると共に、世界の進化を支配しているのだ。
VII
かくしてコルネイユの一行の詩句は
二通りの仕方で
解釈されうる
かくしてコルネイユの一行の詩句は
二通りの仕方で
解釈されうる
エラクリユス博士はこの奇妙な資料を読み終えるや、驚きに硬直したままだった。――それから、交渉もせずにその本を購い、十二リーヴル十一スーを払うと、古書店主はそれが、ポンペイの発掘で発見されたヘブライ語の手稿であるかのように扱った。
四日四晩、博士は書斎を離れなかった。そして、忍耐と辞書の力によって、どうにかこうにか、原稿の内のドイツとスペインに渡る部分を解読するに至った。それというのも、彼がギリシャ語、ラテン語、少しばかりのイタリア語を知っていたにせよ、ドイツ語、スペイン語はほとんど全く知らなかったのである。最後に、とんでもない誤読をしていないかと心配して、友人の学長に、彼はこの二ヶ国語を知悉していたので、自分の翻訳を読み直してくれるように頼んだ。学長は喜んで引き受けた。だが、真剣にそれに取り掛かることが出来るまでには丸三日かかったのだが、博士のものに目を通す度に、大変長く激しい笑いに襲われたので、二度ほどは失神しかけたのであった。異常な哄笑の理由を尋ねられたので、「理由だって?」と彼は答えたのだった。「まずもって三つある。一、優れた同僚であるエラクリユスの笑った顔。二、彼の滑稽な翻訳が、原文におおよそ似ている様子は、まるでギターが風車に似ているようなものである。そして三、原文そのものが、想像できる限りで最も滑稽なものであること。」
おお、頑固な学長! 何物も彼を説得出来ないのだ。太陽が自らやって来て、彼の髭と髪を焼いたとしたら、彼はそれを蝋燭だと思うのだろう!
エラクリユス・グロス博士について言うならば、その顔が光輝き、照らし出され、変身を遂げていたということを、殊更述べるまでもない。――彼はポーリーヌのように絶えず繰り返していた。
「私は見て、感じて、そして信じる。私は覚めた人間だ。(je suis désabusé.)」
そして、その度に、学長は口を挟み、désabusé の語は二語に分かれ、最後にsが付かなければならないと指摘したのだった。
「私は見て、感じて、そして信じる。私は騙された人間だ。(je suis des abusés.)」
VIII
かくして人は、同一の理由から
王よりも王党派になることも
法王よりも信心深くなることも出来るし
同様に、ピタゴラスよりも
輪廻転生論者になることも出来る
かくして人は、同一の理由から
王よりも王党派になることも
法王よりも信心深くなることも出来るし
同様に、ピタゴラスよりも
輪廻転生論者になることも出来る
長い幾日、幾晩をも広大な海の上をさ迷った後、壊れそうな筏の上に捨て置かれ、マストも、帆も、羅針盤も、そして希望もないままの遭難者が、突然に、待ち焦がれた岸辺を見出した時の喜びがどれほどのものであろうとも、エラクリユス・グロス博士を浸した喜びに比べれば、何物でもなかった。彼は、余りに長い間、不確かさの筏の上で、諸哲学の波のうねりに揺すられた後に、遂に勝利し、啓示を得て、輪廻転生の港へ入ったのだった。
この教義の真実さが大変に強く彼を打ちつけたので、彼は一度に、その最も極端な帰結までを含めて受け入れたのだった。彼にとって曖昧なものは何もなく、数日の内に、瞑想と計算とによって、これこれの年に亡くなった一人の人間が、次に地上に再び現れる正確な時期を確定するに至った。おおよそ、一つの魂が劣った存在の内に転生する期日が分かり、人間としての最後の期間に成された善と悪との推定総量に従って、その魂が蛇の、豚の、役馬の、牛の、犬の、象の、あるいは猿の体の内に入る時期を割り当てることが出来た。同じ一つの魂は、前に犯した罪が何であれ、定期的な間隔を空けて、また優れた外観のもとに再び現れるのである。
従って、懲罰の程度は、常に罪障の程度に比例するのだが、種々の動物内への追放の長短に渡る期間の長さではなく、その魂がある卑しい動物の肌の下に留まる期間が、長さの程度はあれ延長されることに拠るのである。動物の階梯は、下の階層では蛇か豚から始まり、猿にまで至る。猿は「言葉を奪われた人間である」と博士は言った。――それに対し、優れた友人たる学長はいつも答えるのだった。同じ理屈から言って、エラクリユス・グロスは言葉を授けられた猿でしかないと。
IX
メダルとその裏側
メダルとその裏側
驚くべき発見の後の数日間、エラクリユス博士はとても幸福だった。彼は深い歓喜の内に生きた。――困難を克服し、謎を究明し、大きな希望を実現したという輝きに溢れていたのである。輪廻転生は天のように彼を包んだ。突然にヴェールが引き裂かれ、未知のものに向けて視界が開かれたように、彼には思われたのである。
食卓で自分の脇に犬を座らせると、彼は火の傍で重々しく顔を向かい合わせた。――無知な動物の目の中に、前世の謎を捕らえようとしながら。
しかしながら、彼の至福の内には二つ黒い染みがあり、それは学部長と学長の存在だった。
エラクリユスが輪廻転生の教義への転向を促す度に、学部長は怒って肩を聳やかし、学長は最も無礼なからかいでもって、博士を悩ませるのであった。それはとりわけ容赦のないものだった。博士が自分の信仰を披瀝するとすぐにも、悪魔的な学長は彼に同意してみせる。彼は偉大な使徒の言葉を聞く信者を真似しながら、周囲の人たち全員の、最もありそうにもない過去の動物遍歴を想像してみせるのだ。「だから」と彼は言ったものだ。「大聖堂の鐘撞きのラボンド親父は、最初の転生の時からメロンだったに違いない。」――それ以来、ほとんど変化することなく、自分が耳にしながら育った聖堂の鐘を、朝晩鳴らし続けるばかりなのである。彼の主張によると、サント・ウラリー教会の第一助任司祭、ロザンクロワ神父は間違いなく、かつては胡桃を平らげるカラスであったのだが、それというのも、その衣装と属性を保持し続けている(訳注:胡桃noixには「間抜け」の意味がある)からだ。それから、最もひどい役割の入れ替えを行い、薬剤師のボカイユ先生は、退化したトキでしかないと断言した。何故なら、彼は道具を使って薬を注入するように強制されているのだが、それはごく単純なものなので、ヘロドトスによれば、神聖な鳥であるトキは、長い嘴だけを使って自分自身で服用していたというのである(訳注:浣腸のこと)。
X
かくして曲芸師は、賢明なる博士よりも
ずる賢い
者となりうる
かくして曲芸師は、賢明なる博士よりも
ずる賢い
者となりうる
にも拘らずエラクリユス博士は気落ちすることなく、一連の究明を続けた。以後、彼にとっては全ての動物に謎めいた意味が存在した。動物の内に、その姿のもとに純化してゆく人間しか見ないのを止め、贖罪の外皮を見るだけで、昔の過ちを見抜くに至った。
ある日、バランソン公園を散歩している時に、木造の大きなバラックを認めると、そこから凄まじい唸り声が漏れている一方、手足を自在に曲げて見せる道化役者が、恐ろしい猛獣使い、アパッチ族のトマホークや「轟く雷」が働く様子を見るように群衆を誘っていた。エラクリユスは感動し、要求された十サンチームを払って中へ入った。おお、偉大なる精霊たちに護られる幸運よ! バラックの内に入るや目に入ったのは大きな檻で、そこに書かれた三語の文字が突然に燃え立ち、彼の目を眩ませたのだった。すなわち「森の人」。突然に博士は精神を大きく揺すぶられ、神経の震えを感じ、感動に足をよろめかせながら近寄った。その時、尻をついておとなしく座り、仕立屋やトルコ人のするように足を組み合わせた、巨大な猿を彼は目にしたのだった。そして転生の最終段階にある人間の、この素晴らしい見本を前にして、エラクリユス・グロスは喜びに蒼ざめ、深い瞑想の中に沈んだのである。数分の後、森の人は、恐らくは自分をじっと見つめる街の人の心の内に、抑え難い共感の念が急速に花開いたのを見抜いたのだろう、生まれ変わった兄弟に向かって恐ろしいしかめ面をして見せたので、博士は頭髪が逆立つのを感じた。それから、幻想的なアクロバットを演じて見せ、それは人間としての尊厳とは全く相容れないもので、全く堕落したものでさえあったが、この四本足の市民は、博士の鼻先で無作法極まりない哄笑に身を委ねたのだった。しかしながら博士は、前世の罪の犠牲者のこの陽気さを少しもショックには思わなかった。反対に、そこに一層の人類との共通性、類縁関係のより大きな見込みを見出し、そして科学的好奇心は余りにも激しいものになったので、自由に観察するために、このしかめ面の先生を幾らででも買い取る決意をした。彼にとってなんという名誉だろう! 偉大なる教義にとってのなんという勝利だろう! もしも彼が遂に動物の内の人間性の部分と関係を築き、この哀れな猿を理解し、自分のことを理解させるに至ったならば!
ごく自然に、動物小屋の主は、この寄宿者について最大限の賛辞を呈した。猛獣の見世物師としての長い経歴の間に目にした中でも、あれは最も賢く、穏やかで、行儀のいい、愛らしい動物です。そして自分の言葉を補強するために格子に近づき、手を差し出すと、すぐに猿はからかうようにその手を噛んだ。更にまたごく自然に、彼は信じられないような値段を要求し、エラクリユスは交渉もせずにそれを支払った。それから、巨大な檻の下に身を屈める二人の担ぎ人夫の後について、勝利を得た博士は、我が家へ向けて足を進めたのであった。
