「メヌエット」
« Menuet », le 20 novembre 1882
 解説 1882年11月20日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois に掲載された短編小説。1883年、短編集『山鴫物語』Contes de la bécasse に収録される(ルーヴェイル&ブロン書店)。
解説 1882年11月20日、日刊紙『ゴーロワ』 Le Gaulois に掲載された短編小説。1883年、短編集『山鴫物語』Contes de la bécasse に収録される(ルーヴェイル&ブロン書店)。『民衆生活』(1883年11月11日)、『政治文学年鑑』(1887年8月28日)、『エコー・ド・ラ・スメーヌ』(1888年12月2日)、『アントランシジャン・イリュストレ』(1890年11月13日)、『家庭生活』(1891年4月3日)、『プチ・パリジャン』付録(1891年6月14日)、『マガザン・リテレール』(1891年)、『プチ・ジュルナル』(1891年7月4日)に再録。
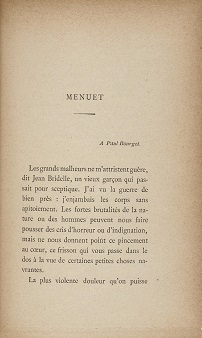 メヌエットはフランス起源の3拍子の舞踏であり、17, 18世紀の宮廷で流行した。
メヌエットはフランス起源の3拍子の舞踏であり、17, 18世紀の宮廷で流行した。すぎ去った過去に対する哀惜の念は、初期の戯曲『昔がたり』の頃からモーパッサンにとって親しい主題であり、『女の一生』の後半部においても取り上げられている。
一方、18世紀の雅で放埓な貴族文化をモーパッサンは愛好し、時評文などにおいては、19世紀を席巻する卑俗なブルジョア文化と対比的に引き合いに出すことが多い。本作では、個人と時代との二重の意味での「過去」の象徴として、メヌエットを踊る老夫婦の存在が語られている。
なお本作には、青柳瑞穂(『モーパッサン短編集』第2巻、新潮文庫)、高山鉄男(『モーパッサン短篇選』、岩波文庫)等の既訳が存在する。
***** ***** ***** *****
メヌエット
メヌエット
ポール・ブールジェ(1)に
大きな不幸を目にしても、僕はほとんど悲しまない、と、懐疑主義者として通っている独身男のジャン・ブリデルは言った。僕は戦争を間近に見たが、哀れみも感じずに死体をまたぎ越したものだった。自然や人間たちが示す激しい暴力性というものは、僕たちに恐怖や憤慨の叫び声をあげさせはする。しかし、心を締めつけるようなあの苦しみ、些細ではあるが痛ましい事柄を前にした時に背中を駆け抜けるあの震えを、それらが感じさせることはない。
確かに、人が感じうる最も激しい苦しみは、母親が子どもを失うことや、子が母親を失うことである。その苦しみは激しく、耐えがたい。それは心を動転させ、胸を引き裂く。だが人は、出血多量の大怪我から回復するように、そうした不幸からも回復するものだ。ところが、ある種の出会い、ふと垣間見て窺い知ることになったある種の事柄、ある秘密の悲しみ、ある種の運命の悪戯といったものは、たくさんの苦しい思いをかき乱し、我々の眼前で神秘の扉を乱暴にいくらか開いてみせ、複雑で癒しがたい心の苦しみの存在を知らしめる。そうした苦しみは、軽いものに見えるぶん一層深く、ほとんど見分けられないほどなだけに一層ひりひりと焼けつくようで、作り物めいて見えるゆえに一層執拗なものであって、我々の魂の内に悲しみの跡、苦い後味、失望の感覚を残していくのだが、それらを厄介払いするには長い時間がかかるのである。
他の者たちがきっと全然気づきもしなかっただろう二、三の事柄が、細くて深く癒しようのない刺し傷のように僕の中に入って来たことがあった。それらの事柄は、今でもこの目にありありと見えるかのようなのだ。
そうした瞬間的な印象によってもたらされ、今でも残っている感動というものは、諸君には理解できないだろう。そのうちの一つだけを話してみよう。それはとても古いものだが、昨日のことのように今でも生き生きとしているのだ。ただ僕の想像力ばかりが、僕の感動の犠牲となったのかもしれない。
僕は今、五十歳だ。その頃は若く、法律を勉強していた。少しばかり寂しく、いくらか夢見がちで、憂鬱な哲学に浸っていたので、騒がしいカフェ、喚き散らす仲間たち、愚かな娼婦たちもそんなに好きではなかった。僕は早くに目覚めた。もっとも大事な感覚的な喜びの一つは、午前八時頃に一人でリュクサンブール公園の「苗床」(2)を散歩することだった。
諸君は、あの「苗床」を知らないだろうか? それは忘れられた前世紀の庭園のようなもの、老婦人の優しい微笑のように愛らしい公園だった。密生した生垣が、規則的に並ぶ小道を隔てていて、その小道は、きちんと剪定された葉の作る壁に挟まれて静かだった。園丁の大きなはさみが休むことなく、枝でできたこの隔壁をまっすぐに揃えていた。ところどころで、花の咲いた花壇や、散歩する中学生のような灌木の隊列、見事なバラの集まり、果樹の連隊などに遭遇するのだった。
この魅惑的な木立の一隅全体が蜜蜂の住処になっていた。藁でできた彼らの家は、花壇の上に上手に間隔を空けて置かれており、太陽に向かって大きく開かれたドアが、指ぬきほどの大きさの入口となっていた。だから、道を行く間中ずっと、ぶんぶんと音を立てる金色の昆虫に出会うのだった。それはまさしくこの平和な場所の女王、回廊を成すこの静かな小道の真の散歩者だった。
僕は、ほとんど毎朝そこへやって来た。ベンチに腰を下ろして読書したものだった。時々は本を膝に置いて、夢想に耽ったり、自分の周りでパリの町が息づくのを聞いたり、この古風な生垣に囲まれた無限の休息を味わったりするのだった。
だが、やがて僕は、開門時からこの場所に通ってくるのは自分一人ではないことに気がついた。そして何度か、茂みの先で、奇妙な小柄な老人と鼻を突き合わせたのである。
彼は、銀のバックルのついた短靴、先を折り返したキュロット(半ズボン)、ミドリヒョウモンのようなオレンジ色のフロックコート、ネクタイ代わりのレース、ノアの洪水を思わせるような、毛が長くつばの広い、信じられないような灰色の帽子、という出で立ちをしていた。
彼は痩せていた。とても痩せて骨ばっており、顔を歪めて微笑んでいた。まぶたが持続的に動く下で、目は生き生きと動き回っていた。彼はいつも金の握りの立派なステッキを手にしていた。それはなにか大切な記念の品であるに違いなかった。
この人物は最初僕を驚かせたが、その後、たいへんに僕の興味を掻き立てた。僕は葉っぱの壁越しに彼の様子を窺い、遠くから彼の後を追いかけ、茂みの曲がり角では足を止めて見つからないようにした。
するとある朝、自分が一人きりだとすっかり信じ込んで、彼は不思議な動作をし始めたのである。まず前に小幅に数歩、次いで膝を折ってお辞儀。それからか細い足で今なお軽快なアントルシャを跳ぶと、次にはうやうやしく回転し始め、飛び跳ね、滑稽な様子で身をくねらし、公衆を前にするように微笑むと、愛敬を振り撒き、腕を丸め、操り人形のような哀れな体をねじり、虚空に向かって軽やかな挨拶を投げる様は、微笑ましくも滑稽だった。彼は踊っていたのだ!
僕は驚きで石のように固まったまま、彼と僕とのどちらが狂っているのかと自問した。
彼は急に動きを止めると、舞台上の俳優がするように前に進み出た。それから後ろに下がりつつ身をかがめた時には、口元に優美な微笑を浮かべており、女優のような投げキスを、刈り込まれた二列の木々に向かって震える手で送ったのである。
それから、彼は重々しい様子で散歩に戻ったのだった。
この日以降、もう彼から目を離すことはなかった。そして毎朝、彼は信じられないようなその練習を繰り返すのだった。
僕は彼に話しかけたいという激しい欲望にとりつかれた。覚悟を決めると、彼に挨拶をして、僕は口を開いた。
――今日はとてもいい天気ですね。
彼はお辞儀をした。
――ええ、まったく昔のような天気ですよ。
一週間後には僕たちは親しくなり、僕は彼の来歴を知るに到った。彼はルイ15世が国王だった時代(3)にオペラ座のダンスの教師をしていたのだ。美しいステッキは、クレルモン伯爵(4)の贈り物だった。ダンスについて話しかけられると、彼のおしゃべりはもう止まることがなかった。
そうしてある日、彼は僕に打ち明けた。
――私はラ・カストリ(5)と結婚したのです。よろしければあなたにご紹介しましょう。でも、彼女はここには午後にしか来ないのです。あなた、この公園は私たちの悦びであり、私たちの人生です。昔のもので私たちに残っているのは、これだけなのです。この公園がなかったら、私たちはもう生きていけないでしょう。この庭は古くて上品ではありませんか? ここでは、若かった頃と変わらない空気を吸えるように思えます。妻と私はここでずっと午後を過ごすのです。でも、私は朝からやって来ます。早くに目を覚ますのでね。
昼食を済ませると、僕はすぐにリュクサンブール公園に戻った。やがて友人の姿が目に入った。彼はうやうやしく、黒服を着たすっかり年老いた小柄な女性に腕を貸しており、僕は彼女に紹介された。それがラ・カストリ、王子たちに愛され、王その人に愛され、世界に愛の香りを残していったかのようなあの雅な世紀全体に愛された、偉大な舞姫だった。
僕たちは石のベンチに腰を下ろした。五月のことだった。小奇麗な小道には花の香りが漂っていた。心地よい日光が葉を通り抜け、僕たちの上に光の滴をまき散らしていた。ラ・カストリの黒いドレスは光に濡れているかのようだった。
公園に人気はなかった。遠くで辻馬車の走る音が聞こえていた。
――では、教えてくださいませんか、と僕は老ダンサーに言った。メヌエットってどんなものだったのでしょうか?
彼は身震いした。
――メヌエット、それはダンスの女王であり、女王様がたのダンスなのです。お分かりですかな? 王様がたがいなくなったら、もうメヌエットは存在しません。
そして彼は仰々しい調子で、情熱に溢れる称賛の言葉を長々と述べたのだが、僕には全然理解できなかった。僕は、ステップ、動きのすべて、どんな姿勢を取るのかを説明してほしかった。彼は混乱し、自分の無力さに苛立ち、神経質になって悲嘆に暮れた。
すると突然、ずっとおとなしく厳かな様子をしている昔の連れ合いに向かって、彼は言った。
――エリーズ、ねえ、君、よかったらこちらの方に、それがどんな風だったか、一緒にお見せしようじゃないか?
彼女は気遣わしげな視線を四方に向けた。それから一言も言わずに立ち上がると、彼に向かい合う位置に立った。
そして、僕は忘れがたいものを目にした。
二人は子どものように気取った様子で行ったり来たりし、微笑みあい、体を揺すり、お辞儀をして、飛び跳ねた。その様子は、古い機械仕掛けによって踊る二体の古い人形のようだった。その仕掛けはかつて大変に巧みな職人が当時の流儀で作り上げたものだが、今ではいささか壊れているのだった。
僕は二人を眺めていた。異様な感興に心は乱れ、言葉にならない哀愁に魂が震えていた。痛ましいと同時に滑稽な亡霊、一世紀も時代遅れの幽霊を見ているようだった。僕は笑いたくもあり、泣きたくもあった。
突然、二人は動きを止めた。ダンスの動作を終えたのだった。数秒の間、二人は向きあったまま留まり、驚くような仕方で顔をしかめた。それから、二人は咽びながら抱きあったのだった。
三日後、僕は田舎にむけて出発した。二人には二度と会わなかった。二年後にパリに戻って来た時には、「苗床」は壊された後だった。親しい昔の庭園、その迷宮のような小道、その過去の匂い、その優美な茂みの曲がり角を無くして、あの二人はどうなったのだろうか?
死んでしまったのだろうか? それとも、希望のない亡命者のように、現代の通りをさ迷っているのだろうか? あるいは滑稽な亡霊となって、月夜に、墓地の糸杉の木に囲まれ、墓石の間の道に沿って、幻想的なメヌエットを踊っているのだろうか?
二人の思い出は僕に取りつき、つきまとい、僕を苦しめ、まるで傷のように僕の内に残り続けている。何故だろうか? 僕には何も分からない。
きっと、諸君はそれを滑稽だと思うのだろうね?(6)
『ゴーロワ』、1882年11月20日付
『山鴫物語』、ルーヴェイル&ブロン社、1883年所収
Le Gaulois, 20 novembre 1882.
Contes de la bécasse, Rouveyre et Blond, 1883.
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, éd. Louis Forestier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1974, p. 636-640.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
『山鴫物語』、ルーヴェイル&ブロン社、1883年所収
Le Gaulois, 20 novembre 1882.
Contes de la bécasse, Rouveyre et Blond, 1883.
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, éd. Louis Forestier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1974, p. 636-640.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
訳注
(1) Paul Bourget (1852-1935). 詩人として詩集『不安な生』(La Vie inquiète, 1875)、『告白』(Les Aveux, 1882) などを出版。1883年、『現代心理論』(Essais de psychologie contemporaine)で批評家として注目され、後に活動の場を小説に転じる。モーパッサンとは1870年代に雑誌『文芸共和国』La République des lettresを縁に出会い、以後も交流があった。
(2) 現在モンテーニュ高校のある場所に存在した。オスマンによるパリ改造の一環で1867年に壊された。
(3) ルイ15世(1710-1774) の在位は1715-1774年。
(4) Louis de Bourbon-Condé (1709-1771) を指すか。聖職者としてはサン=ジェルマン=デ=プレ教会の司祭を務める。文芸に嗜み、放埓な生活を送った人物。
(5) La Castris. モーパッサンの創作。有名なダンサー、ガエタノ・ヴェストリス(Gaetano Vestris, 1729-1808) の名をモデルにしたものと思われる。
(6) 『ゴーロワ』初出には、末尾に以下の段落があった。「我々はこの懐疑主義の独身男性が語った物語を、それほど滑稽だとは思わなかったのだった。/ギィ・ド・モーパッサン。」
