「クリスマスの夜」
« Nuit de Noël », le 26 décembre 1882
 解説 1882年12月26日、日刊紙『ジル・ブラース』 Gil Blas に掲載された短編小説(1面最終段から2面にかけて、筆名モーフリニューズ Maufrigneuse )。1883年、『マドモワゼル・フィフィ』増補改訂版に収録される(アヴァール書店)。
解説 1882年12月26日、日刊紙『ジル・ブラース』 Gil Blas に掲載された短編小説(1面最終段から2面にかけて、筆名モーフリニューズ Maufrigneuse )。1883年、『マドモワゼル・フィフィ』増補改訂版に収録される(アヴァール書店)。「クリスマスの夜食」 réveillon はクリスマス・イヴ(または大晦日)の夜食を指す。初出時、作者は時節を考慮してクリスマスという題材を選んでおり、アクチュアリティーが重要な意味を持つ新聞という媒体の要請を考慮していることが窺える(前日の25日には『ゴーロワ』紙に「クリスマス物語」を掲載している)。
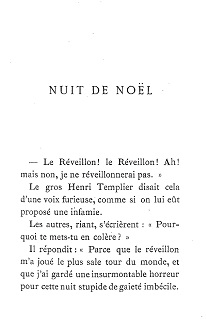 この作品は一種の艶笑譚と呼べるだろうが、この種の作品は、王党派よりの『ゴーロワ』よりも、自由な気風が売りの『ジル・ブラース』に主に掲載された。新聞の傾向による主題の選択も、この時期のモーパッサンが意識していたことである。
この作品は一種の艶笑譚と呼べるだろうが、この種の作品は、王党派よりの『ゴーロワ』よりも、自由な気風が売りの『ジル・ブラース』に主に掲載された。新聞の傾向による主題の選択も、この時期のモーパッサンが意識していたことである。軽い小話ではあるが、結末に語り手の置かれた状況には滑稽さと惨めさが入り混じっており、モーパッサンの短編に特有の余韻を残す作品となっている。また「私生児」という主題は、「親殺し」をはじめ、モーパッサンの作品に繰り返し登場する。
なお、本作には青柳瑞穂による既訳(『モーパッサン短編集』第2巻、新潮文庫など)が存在する。
***** ***** ***** *****
クリスマスの夜
クリスマスの夜
「クリスマスの夜食! クリスマスの夜食! ああ! まったく、僕はクリスマスに夜食なんかとらないね!」
太ったアンリ・タンプリエは激しく怒った声で言った。まるで誰かが卑劣なことに誘いでもしたかのようだった。
他の者たちは笑いながら、大声で叫んだ。「どうして君は怒りだしたんだい?」
彼は答えた。「なぜと言えば、クリスマスの夜食というやつは、僕に対して世界一ひどいいたずらをしてくれたんで、愚かしい陽気さに溢れたこの馬鹿馬鹿しい晩に対して、今でも耐えがたい嫌悪を抱えているという次第さ」
「いったい、どんな?」
「どんなだって? 君らは知りたいと言うのか? けっこう、聞きたまえ」
*****
2年前のこの今の時期、ずいぶん寒かったことを君らも覚えているだろう。路上の貧民を凍え死にさせるような寒さだった。セーヌ川が凍った。歩道は、ブーツの靴底越しにも足を震えさせるほどだった。世界中がくたばりかけていたね。
その時、僕はある大きな仕事をやりかけていたから、クリスマスの夜食の誘いを一切断って、自分の机の前で夜を過ごすほうがいいと思っていたんだ。僕は一人で夕食をとり、それから仕事に取りかかった。けれど十時頃になると、パリ中を駆け巡っている陽気さへの思い、なんだかんだと僕のところまで届いてくる通りの騒ぎ、壁越しに聞こえる隣人たちの夜食の準備の音が、僕の気持ちを乱した。もう自分が何をしているのか分からず、馬鹿げたことを書き散らす有様だ。それで、今晩はもう何か良いものを生み出せるというような望みを諦めなければならないと分かったんだ。
僕は少しばかり部屋の中を歩いた。椅子に座り、また立ち上がった。確かに、外の陽気さに何やら影響を受けていたのだろう。僕は観念した。
呼び鈴を鳴らして女中を呼ぶと、彼女に言ったよ。「アンジェル、二人分の夜食を買いに行ってくれないか。牡蠣、冷えたウズラ、ザリガニ、ハムにケーキ。シャンパンを二本つけてね。食卓を準備したら、休んでいいよ」
彼女はいくらかびっくりしながら言うことを聞いてくれた。すっかり支度が整うと、僕はオーバーを引っかけて外へ出た。
解決すべき大きな問題が残っていた。誰と一緒にクリスマスの夜食をとるというのか? 女の友人たちはすでにあちこちに招待されている。一人捕まえるためには、前もって手を打っておかなければならなかっただろう。そこで、僕はついでに慈善事業を行ってやろうと思ったんだ。僕は独りごちた。パリには、お腹一杯に夜食をとることができず、気前の良い独身男を求めてさ迷っている貧しくて綺麗な娘たちがたくさんいる。そうした恵まれない女の一人に対して、クリスマスの救いの神となってやろうじゃないか。
僕はうろつき、歓楽街に入っていって、質問し、追いかけ、自分の好みに合うのを選ぶことにしよう。
そして僕は町を駆け巡りはじめたんだ。
たしかに、アヴァンチュールを求めている哀れな娘たちにはたくさん出会った。けれども彼女たちときたら、消化不良を起こさせそうなほどに醜いか、一度立ち止まったら立ったまま凍えてしまいそうなほどに痩せているんだ。
諸君もご存知のように、僕には弱点があって、発育のいい女が好きなんだ。肉付きがよければよいほど、僕はその女を好むという始末。巨人女にはすっかり理性を失ってしまうんだよ。
突然、ヴァリエテ座(1)の正面で、好みにぴったりのシルエットが目に入った。まず頭、それから前側には二つのこぶがあって、一つは胸のそれでとても美しく、その下のもう一つのこぶは驚くべきものだった。まさしく脂肪太りしたガチョウのお腹だ。僕は身震いし、呟いた。まったく、いい娘じゃないか! もっとも、まだ一点、確認すべき点が残ってはいる。顔だ。
顔、それはデザートのようなもので、残りの部分はといえば……、ロースト肉というわけだね。
僕は歩みを速め、さ迷える女に追いつくと、一本のガス燈の下で急に振り返った。
彼女は魅力的だった。年若く、髪は褐色、大きな黒い目をしている。
僕が話を持ちかけると、彼女はためらいもせずに承諾した。
十五分の後には、アパルトマンの僕の部屋で、二人はテーブルについていた。
入ってくる時に彼女は言った。「ああ! ここはいい気分ね」
それから彼女は周囲を見回したが、凍りつくようなこの晩に、食卓と寝床を見つけられたことに満足している様子がはっきりと見てとれた。彼女は見事で、たいへんに可愛らしいことに驚かされたし、僕の心を永遠に魅了するほどに太っていた。
彼女はコートを脱ぎ、帽子を取った。席に着くと食事を始めたが、調子が良いようには見えなかった。時折、少しばかり蒼ざめた顔が震えると、まるで抑えた悲嘆に苦しむかのようだった。
僕は彼女に尋ねた。「何か心配事でもあるのかい?」
彼女は答えた。「なあに! みんな忘れちゃいましょうよ」
そして彼女は飲み始めた。一気にシャンパンを飲み干すと、またグラスを満たしてはそれを空け、それを繰り返した。
やがて、少しばかり赤味が頬にのぼってきた。彼女は笑い出した。
僕はと言えば、すでに彼女にぞっこんで、口いっぱいにキスをし、彼女が路上の娘たちのように愚かでも、ありきたりでも、粗野でもないことを知ったのだった。僕は、彼女の人生の細部について尋ねた。彼女は答えた。「坊や、あんたには関係ないことよ!」
ああ! それが一時間後には……。
ついに、ベッドに行く時間になった。僕がテーブルを持ち上げて、暖炉の火の前に立てかけている間に、彼女はさっさと服を脱ぐと、布団の下に潜り込んだ。
我が隣人諸君はとんでもない大騒ぎをしており、狂ったように笑ったり歌ったりしていた。僕は独りごちたものだったよ。「この綺麗な娘を探しに行って、まったく賢明だった。決して仕事なんかできなかっただろうから」
激しいうめき声がして、僕は振り返った。僕は尋ねた。「どうしたんだい、子猫ちゃん?」彼女は返事をせず、苦しそうなため息を発しつづけている。ものすごく苦しんでいるようだった。
僕はまた口を開いた。「具合が悪いのかい?」
突然、彼女は叫び声をあげた。引き裂くような叫び声だ。僕はろうそくを手に急いで近寄った。
彼女の顔は苦しみに崩れていた。彼女は腕をよじり、息をあえがせ、喉の奥から、瀕死の喘ぎにも似て、聞く者の心を弱らせるあの種の音の無いうめき声を発していた。
僕はぎょっとして尋ねた。「いったい、どうしたんだ? 言ってくれ、どうしたの?」
彼女は答えずに唸り声をあげ始めた。
突然、隣人たちが静まった。僕の家で起こっていることに耳をそばだてている。
僕は繰り返した。「どこが痛むんだい、言っておくれ、どこが痛むんだい?」
彼女は口ごもった。「おお! お腹が! お腹が!」
僕は一気に布団をはぎ取った。そして僕は目にした……。
諸君、彼女は産気づいていたんだ。
それで僕はすっかり取り乱してしまった。壁まで走って行くと、拳で力一杯に叩きながらわめいた。「助けて、助けて!」
ドアが開いた。人々が一団となって飛び込んできた。正装をした男たち、肩を露わにした女たち、ピエロ、トルコ人、近衛騎兵などに仮装した者たち。この侵入に僕はすっかり仰天してしまい、事情を説明することもできやしなかった。
彼らは何らかの事故、恐らくは何かの犯罪があったものと信じ込んでいたので、何が何だか理解できないでいた。
ようやくのことで僕は言った。「これは……、これは……、この……、この女が……、子どもを生むんです」
すると、皆がそろって彼女を調べ、各人が意見を述べた。なかでもカプチン会修道僧の格好をした男が、自分は詳しく知っていると言い張り、自然の摂理の手助けをしたがった。
彼らはぐでんぐでんに酔っぱらっていた。彼らが彼女を殺してしまうんじゃないかと思ったよ。それで僕は帽子もかぶらずに階段を駆け下りると、隣の通りに住んでいる年寄の医者を呼びに行ったんだ。
医者と一緒に戻って来ると、建物中の者が起きていた。階段のガス燈にも火が入れられていて、すべての階の住人が僕のアパルトマンに押しかけてきていた。テーブルに着いた荷揚人足姿の四人が、僕のシャンパンとザリガニを片付けていたよ。
僕の姿が目に入ると、とんでもない叫び声があがった。牛乳屋の恰好をした女が、タオルに包まれたぞっとするような小さな肉の塊を僕に見せた。その塊はしなびて、皺くちゃで、うめき声をあげ、猫のようにわめいていた。女は僕に言った。「女の子ですよ」
医者は産婦を検診し、状態は芳しくないが、それというのも夜食の直後にことが起こったからだと断言し、直ちに看護人と乳母を送ろうと告げて去って行った。
二人の女は、一包みの薬を持って一時間後にやって来た。
僕は肘掛椅子で一晩を過ごした。あまりに仰天していたので、後のことなど考えられもしなかった。
朝になると、医者がまたやって来た。病人の様子はとても悪いらしかった。
彼は言った。「あなたの奥様は……」
僕はさえぎって言った。「妻ではありません」
彼は続けた。「愛人でも、私には関係ありませんがね」 そして彼は必要な手当て、食事、治療法を並べ立てた。
どうすればいいのか? この不幸な女を病院に送り込む? そんなことをすれば、建物中はおろか、この地区のすべての人間から、僕は不作法者扱いされたことだろう。
僕は彼女を家に置いた。六週間、彼女は僕のベッドに寝ていた。
子ども? ポワシー(2)のある農民のところへ預けたよ。今でも、月に五十フランかかっている。最初に財布を出してしまったから、死ぬまで出しつづけなきゃならない破目になったのさ。
そしてやがては、その子は僕を父親だと思うんだろう。
だが何よりも不幸なことには、あの娘は回復すると……、僕を愛してしまったんだ……、狂ったように僕を愛しているんだよ、あの乞食女は!
*****
「それで?」
「それでさ、彼女は野良猫みたいに痩せてしまった。僕はこの骸骨みたいな女を外に放り出したが、彼女は路上で僕を見張り、僕が通り過ぎるのを隠れて見ていて、僕が夜に外出すると呼び止めて手にキスをするんだ。そんな風にうるさくつきまとうんで、僕は気が狂いそうだよ。
以上が、僕が金輪際クリスマスの夜食をとったりしない理由だ」
『ジル・ブラース』、1882年12月26日付
『マドモワゼル・フィフィ』増補改訂版、1883年所収
Gil Blas, 26 décembre 1882.
Mademoiselle Fifi, Havard, 1883.
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, éd. Louis Forestier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1974, p. 695-699.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
『マドモワゼル・フィフィ』増補改訂版、1883年所収
Gil Blas, 26 décembre 1882.
Mademoiselle Fifi, Havard, 1883.
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, éd. Louis Forestier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1974, p. 695-699.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
訳注
(1) Théâtre des Variétés:1807年の開場以来、モンマルトル大通り7番地に今も存続している劇場。
(2) Poissy:パリ西方約30キロに位置する町。
