「最後の逃走」
« La Dernière Escapade », 1876
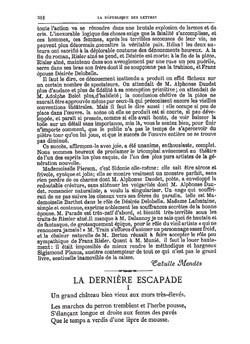 解説 1876年9月24日付『文芸共和国』La République des lettres に掲載された長篇詩。Guy de Valmont ギィ・ド・ヴァルモンの筆名。同誌には先に「水辺にて」や「日射病」が発表されていた。後に1880年『詩集』 Des vers に収録される。
解説 1876年9月24日付『文芸共和国』La République des lettres に掲載された長篇詩。Guy de Valmont ギィ・ド・ヴァルモンの筆名。同誌には先に「水辺にて」や「日射病」が発表されていた。後に1880年『詩集』 Des vers に収録される。この詩は『詩集』より前、1878年3月19日付『ゴーロワ』紙 Le Gaulois の「月曜の詩人たち」の欄に再掲されている。この際にはギィ・ド・モーパッサンの本名で発表された。
当時、モーパッサンは海軍省から文部省への転勤を計画していた。フロベールから時の文部大臣アジェノール・バルドゥーに推薦してもらう際、文学者であることを強調するために、この『ゴーロワ』への発表を画策したらしい。いわば宣伝効果を狙っての新聞掲載だった。
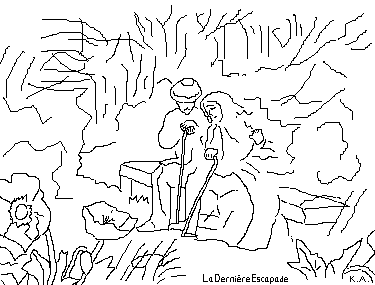 母親宛て書簡89信に掲載の経緯が述べられており、「現実の中に詩を理解する」という言葉で、この作品の趣旨が説明されている。
母親宛て書簡89信に掲載の経緯が述べられており、「現実の中に詩を理解する」という言葉で、この作品の趣旨が説明されている。以下、『ゴーロワ』掲載の際に付された「前書き」を引用する。この詩篇が当時の読者にどのようなものとして映ったかが推察されるだろう。
*****
 我々は二か月前より文学的試みを続けており、『ゴーロワ』紙上に「月曜の詩人たち」の欄が生まれたのであった。
我々は二か月前より文学的試みを続けており、『ゴーロワ』紙上に「月曜の詩人たち」の欄が生まれたのであった。あらゆる方面から寄せられる惜しみない共感がこの試みを迎え入れ、読者にお目にかけるにふさわしい作品が目に入る限り、我々にこの試みを継続するように促している。
今日までは短い詩篇や、詩人のインスピレーションに従って切り取られた一部分を掲載してきたが、その詩人たちの筆は、人の言う希望を与える以上の成果を既に成し遂げている。最も正当に有名となった作家が、署名することができた名誉として、我々の掲載した頁を眺める日が来るだろうことを、我々は自らの誇りとするのである。
多大な興味をもって読まれてきた詩句のどれにも、我々はどんな紹介も特別な推薦の言葉も付さずに掲載してきた。我々は読者の趣味にどんな影響も与えないように特別に取り図ってきたし、各作品の長所それだけに、作者の評判を認めさせる配慮を一任してきたのである。
今日、我々はこの規則を逸脱する必要を認め、以下にお読みになる「最後の逃走」と題された詩作品を特別に推薦することにする。
欠けるところなく響きよく、思想に富み、表現は明晰で正確なこの詩句の、男性的な様相に我々は強く打たれた。とりわけ、レアリストの息吹に完全に心を捕えられたのであるが、それが詩句を生気づけ、一幅の絵画のように生き生きと感動的なものに仕立てているので、通常は詩に対して最も反抗的な者も含めた読者全員の注意を、我らが「月曜の詩人」の上に喚起したい。
「最後の逃走」を執筆した詩人は、我々の感覚では、今日の若い世代の中で最も力強い作家の一人であり、我々はためらうことなく、芸術家としての美しく輝かしい将来を彼に予言するものである。
ゴーロワ紙
***** ***** ***** *****
最後の逃走
最後の逃走
I
高い壁を備えたとても古い大きな城。
階段の踏み石はぐらつき、草が生え、
石畳の割れ目に沿って長く真っ直ぐに伸び、
時が敷石を癩のような苔で緑に覆った。
両側には二本の塔。一方は尖った帽子をかぶり、
空に向かって細くなる。もう一方は首を斬られていた。
その頭は、ある夜、風によって運び去られたのだ。
けれど一本の蔦が、崩れた頂きまで這い上り、
その上に髪の毛のように逆立っている。
一方で、塔の横腹に染み通った
天の水が、日々執拗に穿ち続け、
足元まで大きなひび割れを開けた。
そこに生えた一本の木が、壁の穴に育った。
古びた暗い客間をぼんやりと覗かせている、
窓はうつろな眼のように陰欝である。
この重たげな建物全体が、老いて、黒ずみ、萎れ、
亀裂が額に皺のようなものを印し、
足元は砕け、白結晶に侵食され、
屋根は天に向けて荒廃した瓦を見せ、
見捨てられた事物の荒涼とした様子を見せている。
周囲には暗く深い、大きな庭園が広がっている。
庭は昇りくる太陽の下に眠っている。そして時折、
聞こえるのは、通り過ぎる葉々のざわめき、
それは浜に寄せる穏やかな波の音のよう、
遠く青空の下に海が輝く時に。
木々は枝を伸ばし、あまりに入り組んでいるので
太陽は、火の雨を降り注ぎながらも、
暗がりの小道にまで染み通ることはない。
生い茂ったこれら巨人の下に、灌木は息絶える。
天蓋はカテドラルのように大きく育った。
そこに漂うのは古代の、墓場のような匂いと、
訪れる人の無い場所の湿っぽさ。
けれど、遠く巨木の尽きる先
長い芝生の上に立つ、階段の高い所に、
召使達が現われ、腕に支えている
二人の老人はすっかり腰が曲がり、小幅に歩いて来る。
緑に覆われた踏み石の上にゆっくりと
こわばった足のためらいを引きずって、
杖の先で道を探ってゆく。
とても年老いている、―― 男と女、―― 顎を揺らしながら、
額はとても重たく、肌は大変に萎びているので、
どんな力が、彼らの骨の髄に、この執拗な生命を
注ぎ込んだのか誰にも分からない。
二人は置いて行かれ、大きな椅子に座り込むと、
二つ折りになるほど屈み、手と頭を震わせている。
老年に鈍った視線を下げて、
すぐ近くの地面を、じっと見つめる。
二人にはもう思考もない。長い微かな震えだけが
この老齢の内に住んでいるかのよう。
もし彼らが死んでいないなら、それは長い習慣のため
二人で、いつも互いに寄り添って生きて来た。
それというのも、何日も前からもう話もしていなかった。
II
けれども平野の上に火の息吹が立ち上る。
木々の脇腹が樹液に震え出す、
揺り動かされる額の上に、太陽が通り過ぎて行くので。
到る所、潮のように熱気が上ってくる。
そしてあちこちの草地では、黄色い蝶の
金の群れが漂い、踊るかのように見える。
遠くでは花開いた野原が音を立てる、
持続的な音が地平を満たす、
というのも、芝生の奥底に狂乱する
バッタの一団が耳を聾するほど声を嗄らしているから。
燃え立つ生命の熱気が駆け抜けた。
熱い光の中、生き返って、すっかり白く、
失われた過去の最初の日々のように。
古城がその石の微笑みを取り戻す。
その時、二人の老人が少しずつ活気づく。
彼らは目をしばたたく。そしてこの火の浴場の中、
乾き切った肢体がゆっくりと緩んでゆく。
冷え切った肺が日光を吸い込む。
そして彼らの精神が、目覚めた後のように混乱したまま、
耳にするざわめきに、ぼんやりと驚く。
二人は立ち上がる、手を杖に押しつけて。
男は少しばかり、昔からの女友達の方を向き、
一瞬眺めた後に言う。――「とてもいい天気だ」
彼女は、まだ眠っている頭を持ち上げ、
よく見知った地平を見渡しながら、
彼に答える。「ええ、麗しの日々が戻ってきましたわ」
二人の声は雌山羊の鳴き声に似ている。
春の陽気が老いた唇に皺を作る。
彼等は震える、新木の香りが
時折、荒々しく体を通り抜けて行くから
強すぎるワインが頭に上ってくるかのように。
とても穏やかに二人は頭を揺らし、
空気中にかつての息吹を再び見出す。
彼は、突然に、声に嗚咽を交えながら
――「こんな日に、君はやって来た
最初の待ち合わせ、広い並木道を」
そして二人はもう何も言わなかった。だが苦い思いが
若かった頃の遠い思い出へと遡っていった
海原を越え、二艘の船が
同じ航路をとって引き返してゆくように。
彼は続けた。――「すっかり遠ざかって、もう戻っては来ない。
我々の石のベンチは、庭の奥、向こうだろうか?」
女は一撃を受けて傷ついたかのように飛び上がった。
――「見に行きましょう」彼女は言った。喉を締め付けられ、
二人は突然に、同じ力で立ち上がった!
驚くべき二人連れ、やせ細って青ざめている。
彼は、金釦のついた古い狩猟服を着て、
彼女は、古いショールの奇妙な絵柄をまとって!
III
二人は様子を窺いながら、見られるのを大変に恐れた。
それから、せむしのように丸まった背を曲げ、
全てが生き返ったかに見える中、年を取り過ぎているのを卑下しつつ
子どものように手を取り合って、
そして出発した、道をふさぐようにして。
それというのも、それぞれ酔っ払いのように揺れ、
時々肩をぶつけあいながら、
危なっかしい均衡をとりつつ、斜めに進んでいたから。
杖は自由なほうの手を支えながら、
木で出来た足のように、体の傍をうろうろしている。
けれども、息切れしながら休み休みに
彼等は庭に辿り着き、そして広い通りに出た。
過去が立ち昇り、二人の前を歩いていた。
湿った土の上に、ところどころ、見えるように思われた
愛し合う二人の、まだはっきりと残る足跡が
あたかも道が彼等の辿った跡を守ってきたかのよう
日々、いつもの二人連れが訪れるのを待ちながら。
すっかり衰えた二人は、巨木の傍までやって来て、
背の高い樫と楡の下へと消えてゆく
木々は二人の周りに永遠の夜を注いでいた。
そして古い書物の頁をめくるように
「ここだ」と一人が言った。もう一人が言った。「あそこだわ」
「あなたの指に口づけした場所?」――「ええ、あそこよ」
「唇には?」――「そう! そこだわ!」そして二人の
唇や指への接吻から接吻へと辿る巡礼は
十字架の道のように続いていった。
二人そろって過ぎ去った歓喜に満ち溢れ、
心は終わってしまった幸福へ向けて弾み、
思いやるのは、かつて、体を抱き合い
目の奥へと目で語り、指をからませ、
言葉もなく、未知なる熱狂に胸を震わせながら
自分達はこの道を進んだのだということ!
IV
ベンチは待っていた、苔むして、二人同様に年老いて。
「これだ!」彼が言った。「これよ!」彼女が繰り返す。二人は座った。
そして幸福な思い出の熱い反射の下
木々の深い漆黒が明るく照らし出された。
さて、草の中に二人は目を留めた
太った百歳のヒキガエルが近寄って来るのに。
広げた手脚で真似ているのは
まだ歩けない子供の動き。
痙攣するような嗚咽が彼等の息を喘がせた。
彼! 二人の遠い愛の最初の証人、
毎晩、彼等の誓いの言葉を聞きにやって来たものだった。
そして彼だけがこれらの恋人達の形見を認めたのだ。
それというのも、重々しくも辛抱強い歩みを急がせ、
腹を膨らませ、丸い瞳を潤ませながら、
萎びた恋人達の震える足元に
ゆっくりと、信頼の籠った太った体を引きずってきたのだから。
二人は涙を零した。―― 突然に、鳥の小さな歌声が
森の奥から発された。それは二人が
八十年前に耳にしたのと同じもの!
そして極度の高揚に慄く最中、
過ぎ去りし日々の底から、一飛びに目の前に
立ち現れる、激流の如く、絶えず増大しながら、
人生の全てが、その幸福、その酩酊、
情熱的な愛撫に休むことも知らなかったその夜、
疲弊しつつも甘美だった、二人だけのその目覚めとともに。
そして、夜、漂う影の下を流れゆく
掻き立てる樹液に満ちた森の香りは
接吻の時を絶えず引き伸ばしたのだった!・・・
二人が愛情に浸っている間に、道が
開け、激情に満ちた風を通るに任せた。
そして、かつてのように、香り高く、心を打ちつける
あの息吹が、木々の若さを運び寄せ
彼等の血に、死に絶えた芽生えの震えを目覚めさせた。
肌の熱気に焼かれながら、二人は感じた、
全身が震え、二人の手が押し付け合うのを
そして抱き合うように、お互いを見合った!
だが、年齢の隔たりを通して窺われる
消え去った欲望でかつては二人を満たしていた
輝くような額、若々しい顔の代わりに
見合わせているのは、二つの年老いた顔
醜悪なしかめ面で微笑み合っている!
二人は目を閉じた、憔悴し、急速に訪れる
大変な恐怖に絞めつけられた、さながら
死の苦悶のように!・・・
――「行こう!」男が言った。
だが二人は立ち上がれず、硬い
ベンチに嵌め込まれたようで、恐怖にかられる
余りにも遠くに来てしまい、こんなにも年老いて虚弱であることに。
彼等の体は余りにも動かないままなので
石人形と化したかのようだった。そして
二人は、突然に、一気に逃げ出した。
彼等は苦しみに呻いた。そして二人の背に天蓋は
一滴一滴、雨のように重たい冷気を注ぐ。
息を詰まらせ、氷のような息吹や、
地下室のような空気、黴臭い匂いに打たれた
百年も前からその下に芽生えていたのだ。
そして二人の心の上には、重荷のように、死に絶えた
詩情が、痙攣のような二人の努力に圧し掛かり、
遅く、息切れした足取りをよろめかせたのである。
V
切れたばねのように女は倒れた。
彼は、理解できずに留まり、彼女を待った、立ったまま、
不安気に、彼女はただ幾らか疲れたのだと信じて
それというのも、彼女の衣服はずっと震えていたから。突然に
突風のように恐怖が彼を襲った。
彼は身をかがめ、腕を取り、そして大変な
努力をして彼女を起こした、力は全然無かったにもかかわらず。
だがその哀れな体は垂れ下がり、不吉にもぐったりしていた。
彼は見た、息を詰まらせた彼女が死を迎えているのを。
助けを求めるために、彼は駆け出した
小さく跳ねる様はおぞましくもグロテスク。
その姿は、支えとなる手もないままに
杖に導かれながら、ぎこちない駆け足で
アラベスクのように複雑な道を描く。
息づかいは速く、咳のように激しかった。
だが彼はふらつく足がたわむのを感じた
足には力なく、膝の上で踊るかのようだった。
跳ねるような駆け足は、黒い幹へとぶつかった。
木々は彼を弄び、互い互いに
押しやり、突き返し、この苦悩を
意地悪くも楽しんでいるかのようだった。
彼は恐ろしい戦いが終わりを迎えたのを理解した。
そして溺れる者のように、小さな
嘆きの叫び声を発し、顔から地面に倒れた。
か弱い呻き声を、どんな風も運びはしなかった!
彼の耳にはまだ、どこかの空で
一羽の烏の長い陰鬱な鳴き声が聞こえ、
遠くのひび割れた鐘の音に混ざり合っていた。
そして一切の音が止んだ。厚く氷のような影が
彼等の上に圧し掛かった、墓石のように重たく。
VI
二人はそのまま。日の光は消えた。闇が
空一面を弔いの波で覆った。
二人はそのまま、二つの小さな落ち葉の塊のように
転がされたまま、執拗な熱に震えながら、
夜には姿もおぼろで、誰も二人を見つけなかった。
二人は障害物となって動物達を驚かせた
毎晩踏み行かれる小道を塞いでいたので。
あるものは立ち止まり、内気に眺めやった。
別のものは漂流物のように乗り越えて行った。
なめくじが上を這い、よだれの跡を引いた。
虫達は、二人の体の皺を探り、
他のもの等は、死んだものと思って上に居座った。
だがやがて道を震えが駆け抜けた。
驟雨が、産毛の生えた葉々を押し開き、
流れ行き、音立てて地面を打ちつけた。
そしてまだ震えていた二人の老人の上に、
雨は、厚い波となって、一晩中降り続けた。
それから、夜明けの光が現われる頃、
高い葉々から執拗に落ち続ける滴の下で
濡れた衣服の下にすっかり冷え切った
命の無い二つの体が拾い上げられた。おぞましく、硬直して
さながら海の底に見つかる溺死体のようだった。
「最後の逃走」(1876年)
Guy de Maupassant, « La Dernière Escapade » (1876), dans Des vers et autres poèmes, éd. Emmanuel Vincent, Publications de l'Université de Rouen, 2001, p. 76-84.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
(*翻訳者 足立和彦)
▲冒頭へ
▲『詩集』他作品へ
▲詩作品リストへ
Guy de Maupassant, « La Dernière Escapade » (1876), dans Des vers et autres poèmes, éd. Emmanuel Vincent, Publications de l'Université de Rouen, 2001, p. 76-84.
(画像:Source gallica.bnf.fr / BnF)
(*翻訳者 足立和彦)
▲冒頭へ
▲『詩集』他作品へ
▲詩作品リストへ
