「小説論」
« Le Roman », 1888
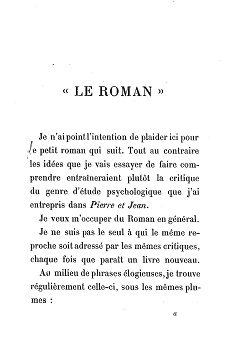 解説 1888年発表の長編小説『ピエールとジャン』の冒頭に置かれた評論。1月7日『フィガロ』Le Figaro 別冊にまず掲載されるが、この際に著者に無断の削除があり、誤解をもとにした批評家の反論を受ける羽目になり、作者を憤慨させた。3月18日『ラ・ヴィ・ポピュレール』La Vie populaire 誌にも再録。
解説 1888年発表の長編小説『ピエールとジャン』の冒頭に置かれた評論。1月7日『フィガロ』Le Figaro 別冊にまず掲載されるが、この際に著者に無断の削除があり、誤解をもとにした批評家の反論を受ける羽目になり、作者を憤慨させた。3月18日『ラ・ヴィ・ポピュレール』La Vie populaire 誌にも再録。冒頭にも断りのある通り、『ピエールとジャン』本文とは別に構想されたものであり、いわゆる「序文」ではない。「一般的」に「小説」(ロマンは、コント・ヌーヴェルと異なる、いわゆる「長編小説」を指す)について論じるという体裁になっている。
冒頭ではまず批評家の在り方について議論され、流派に捉われずにあらゆる創作の在り方を認めるべきだと主張し、芸術家にとっての創作の自由の必要性が強調される。ついで、歴史的観点からロマン主義とレアリスム(現実主義)・ナチュラリスム(自然主義)とを対比して相違を論じた後、アクチュアルな問題として、現代小説の二つの傾向を「心理分析」「客観主義」に二分して論じる。前者は自然主義に対抗して起こった流行で、ポール・ブールジェに代表される。後者はゾラはじめの自然主義者を指すものと考えられるが、デビューから数年のモーパッサンの短編も含まれるし、ここでの理論はフロベールについて語る言葉とも近しい。「本当らしさ」という観点からすればむしろ「心理分析」の小説には問題があるとしながら、しかし『ピエールとジャン』以降、作者は積極的にその方向へ進むのでもある。ユゴー、デュマに代表されるロマン派への評価は厳しいものであるが、おおむね、特定の立場に立たずに中立的に現代小説のありようを分析的に論じた一文となっている。
議論の中で、モーパッサンは、各個人がそれぞれ固有の現実を持っており、芸術家の使命は「個人的世界観」を提示することにあると主張する。「客観的真実」を唱えるゾラの主張への批判を含むと同時に、「客観性」を否定し「主観」を重視する点において、プルーストをはじめとする20世紀文学の先駆けともいえる表明となっている事実は、特に注目に値する。
小説家としてデビューして以来、モーパッサンはジャーナリストとして数多くの文芸時評も著し、とりわけフロベール、トゥルゲーネフらを論じる中で、自身の小説論を鍛え上げていった。もちろん『女の一生』、『ベラミ』、『モントリオル』といった実作の中で熟慮され、実践されたものでもあるだろう。本論はいわばその集大成の観を成すものである。
作者自身はルイ・ブイエ、ギュスターヴ・フロベールの指導のもとに文学修業を積んだのだったが、その教えの中心的なものが論の後半に明かされている。何よりまずオリジナルであることの大切さ。そしてオリジナルな物の見方を獲得するための観察の重要性。モーパッサンが終生、芸術家にとってもっとも重要と考えていたものである。
末尾に、簡潔、明快なフランス語の文章の理想が述べられている。「芸術的文体」の唱導者として暗に批判されているのは先輩の作家エドモン・ド・ゴンクール。ゴンクールは日記にモーパッサンに対する反論を記している。
最後に作者が主張する概念、フランス語の simplicité は、「単純さ」、「素朴さ」、「簡潔さ」などを表す。簡潔さ、明晰さは古典主義以来の文芸の一理想であったが、文飾を誇らない姿勢は作者の「誠実」を証拠だてるものであり、美学的理念は、ひいては作家の倫理性とも密接に結びついている点を見逃すことはできないだろう。
なお「才能とは長い忍耐に他ならない」の出典はシャトーブリアンではなくビュフォンが正しい(正確な引用ではない)。記事掲載後すぐに指摘を受けたが、初版ではそのまま掲載となった故、訳文でも訂正していない。
なお、「小説について」、『ピエールとジャン』(杉捷夫訳、新潮文庫、1952年初版、p. 5-26.)所収、などの既訳が存在する。
***** ***** ***** *****
小説論
小説論
私はここで、以下に続く小さな小説を弁護するつもりは全然ない。まったく反対に、私が理解してもらおうと試みる考えは、むしろ『ピエールとジャン』において企図した心理研究というジャンルへの批判をもたらすだろう。
私は、ごく一般的に〈小説〉というものを問題としたい。
新しい書物が世に出る度に、同じ批評家たちから同じ批判を受けるのは、なにも私一人に限ったことではない。
称賛の言葉の中ほどに、同じ筆になる次のような言葉を私は決まって見いだすのである。
――この作品の最大の欠点は、これが本来の意味での小説ではないということだ。
同じ論法でもって、こう答えることもできるだろう。
――名誉なことにも私を判断して下さったこの作家の最大の欠点は、彼が批評家ではないということだ。
実際のところ、批評家の本質的な性質とはどのようなものであろうか?
偏見なく、あらかじめ定まった意見もなく、流派の概念もなく、どんな芸術家の系列とも結びつきをもたずに、批評家とは、最も対立する傾向、最も相反する気質をも理解し、区別し、説明しなければならず、最大限に多様な芸術的探究をも認めなければならない。
さて、『マノン・レスコー』、『ポールとヴィルジニー』、『ドン・キホーテ』、『危険な関係』、『ウェルテル』、『親和力』、『クラリッサ・ハーロー』、『エミール』、『カンディード』、『サン=マール』、『ルネ』、『三銃士』、『モープラ』、『ゴリオ爺さん』、『いとこベット』、『コロンバ』、『赤と黒』、『モーパン嬢』、『ノートル=ダム・ド・パリ』、『サランボー』、『ボヴァリー夫人』、『アドルフ』、『ド・カモール氏』、『居酒屋』、『サッフォー』等の後で、「これは小説であり、あれはそうではない」と、まだ敢えて書きうる批評家はよほどの慧眼の持主であろうが、その慧眼とは無能さに大変によく似たものである、と私には思われる。
一般的に言って、この批評家が小説という語で理解しているのは、多かれ少なかれ本当らしい事件が三幕の芝居風に並べられたものであり、一幕目は提示、二幕目は行為、三幕目に結末となっているのである。
このような構成の仕方も絶対的に許されるものであるが、それ以外のあらゆる仕方も受け入れるという条件での話である。
それを踏み外せば、書かれた物語は別の名で呼ばれなければならないような、小説を作るための規則が存在するのだろうか?
もし『ドン・キホーテ』が小説なら、『赤と黒』もまた別の一つだろうか? もし『モンテ=クリスト伯』が小説なら、『居酒屋』もまたそうであろうか? ゲーテの『親和力』、デュマの『三銃士』、フロベールの『ボヴァリー夫人』、O・フイエ氏の『ド・カモール氏』、それにゾラ氏の『ジェルミナール』を比較することができるだろうか? これらの作品のどれが小説なのか? その有名な規則とはどのようなものなのか? それは何に由来するのか? 誰がそれを定めたというのか? どんな原則、どんな権威、どんな道理の名において?
しかしながらこれらの批評家たちは、ある確かな、疑いようのない方法によって、小説を構成するものと、その小説を、小説ではない別の作品と区別するものとを知っているらしい。そのことが意味するのはごく単純なことで、制作者ではない彼らもある一つの流派に加盟しており、小説家自身と同じように、自分たちの美学の外で着想され、実現されたあらゆる作品を拒絶している、ということである。
知性ある批評家とは、反対に、すでに書かれた小説と最も似ることの少ないどんなものをも探し出し、若者たちに新しい道を試みるように能うる限り勧めるのでなければならないだろう。
あらゆる作家は、ヴィクトール・ユゴーやゾラ氏のように、絶対的な権利、議論の余地のない権利を執拗に要求したものであるが、その権利とは、個人的な芸術観に従って制作する、すなわち想像し、観察するという権利であった。才能とは独創性に由来し、独創性とは、思考し、目にし、理解し、判断する際の特別な仕方である。さて、自分の愛する小説に従って作り上げた概念次第で〈小説〉を定義し、作品構成についてのある種の不変の規則を確立すると主張するような批評家は、新しいやり方をもたらす芸術家の気質に対して、絶えず戦い続けるだろう。絶対的にその名に値するような批評家とは、傾向も、特別な好みも、情熱も持たない分析家でなければならず、絵画の専門家のように、差し出された芸術作品の、芸術的価値だけを判断しなければならない。あらゆるものに開かれた彼の理解力は、彼の個性を完全に吸収してしまうことで、人間としては好きになれずとも、鑑定家としては理解しなければならないような書物でさえも、これを発見し、評価できなければならないのだ。
だが大部分の批評家とは、結局のところは読者でしかないが故に、彼らはほとんどいつでも間違って我々を叱責するか、留保なしの度外れたお世辞を言うかという結果になる。
読者とは、書物の中でただ自分の精神の自然な傾向を満足させようとばかりするものであって、自分の中心的な興味に応えるように作家に要求し、自分の理想主義的な、陽気な、好色な、悲しげな、夢見がちな、あるいは実際的な想像力のお気に召す作品や一節を、変わることもなく見事だとか「よく書けている」と評価するのである。
つまり、公衆とは、我々に向って次のように叫ぶ数多くの集団で構成されている。
――慰めてくれ。
――楽しませてくれ。
――悲しませてくれ。
――うっとりさせてくれ。
――夢を見させよ。
――笑わせよ。
――震えさせよ。
――涙を流させよ。
――考えさせよ。
ただ、幾らかの選り抜きの精神の持ち主だけが芸術家に要求する。
――私に何か美しいものを、あなたに最も相応しい形式で、あなたの気質のままに作ってください。
芸術家は試み、成功したり失敗したりする。
批評家は成果を、努力の性質に従って評価しなければならない。そして彼には諸々の傾向に気を配る権利はない。
こうしたことはすでに千度も書かれてきた。いつでもそれを繰り返さなければならないのだろう。
そういう訳で、人生についての歪んだ、超人間的で、詩的で、うっとりさせるような、魅惑的な、あるいは見事なヴィジョンを与えようと望んだ諸文学流派の後にやって来たのは、現実主義ないし自然主義の流派であって、真実を、ただ真実だけを、そしてあらゆる真実を提示すると主張したのだった。
公正な関心をもって、すっかり異なるこうした芸術の理論を認めねばならず、それらが産み出す作品は、それらが産まれたところの一般的概念をア・プリオリに受容した上で、ただその芸術的価値という観点からのみ判断されなければならない。
詩的な作品、あるいは現実主義的な作品を制作する作家の権利に異議を呈するということは、その作家の気質を修正するように強要し、彼の独自性を咎め、自然が彼に与えた視覚と知性とを彼が利用するのを許さないということである。
その芸術家が事物を美しく、あるいは醜く、卑小に、あるいは叙事詩的に、優美に、あるいは不吉に眺めたと言って彼を非難するのは、ある種の仕方に適合しているが故に、我々と同じヴィジョンを持たないといって非難するのと同じことである。
芸術家に自由に理解させ、観察させ、好きなように着想させようではないか、彼が芸術家である限りは。理想主義者を判断するためには詩的に高揚し、その上で彼の夢は凡庸で、平凡で、十分常軌を逸してもいなければ見事でもない、と彼に証明しようではないか。だがもしも自然主義者を判断するなら、どの点において人生における真実は、彼の書物の中の真実と異なっているかを示してやろうではないか。
あまりにも異なった流派は、まったく相対立する制作方法を用いたに違いないのは明白なことである。
常に変わらず、粗野で気を滅入らせるような真実を、変形させ、そこから例外的で魅惑的な事件を引き出すような小説家は、本当らしさについて度の過ぎた配慮をすることなく、好きなように出来事を操り、それを準備し、並べることで、読者の意に沿い、感動させたり、うっとりとさせたりしなければならない。彼の小説のプランとは、一連の創意に富んだ組み合わせでしかなく、巧妙に結末へと導くものである。エピソードは配置され、頂点に向って漸進して行き、そして中心的で決定的な出来事による結末の効果は、冒頭で掻き立てられた好奇心をすっかり満足させ、興味に対して柵を設け、あまりに見事に物語を語り終えるので、最も魅力的だった人物たちが、その翌日にはどうなるのかを知りたいとも思わせない。
反対に、人生の正確なイメージを与えると主張する小説家は、例外的に見えるような出来事の連続を注意して避けねばならない。彼の目的は一つの物語を語り、我々を楽しませたりうっとりさせたりすることでは全くなく、出来事の裏に隠された深い意味を考えさせ、理解させることである。大いに見て、大いに考えたお陰によって、彼は世界、事物、事柄や人間を、彼固有の、熟慮された観察全体から帰結されたある特定の仕方によって眺める。この個人的世界観こそ、一冊の書物の中にそれを再現することで彼が我々に伝えようとするものなのである。彼自身が人生の光景に感動を受けたのと同じように我々を感動させるためには、彼はその人生を綿密な類似さで我々の眼前に再現しなければならない。従って、彼は作品を大変に巧妙に、目立たない仕方で組み立てねばならず、表面はあまりに単純なので、そのプランを察知し、それと指摘したり、作者の意図を発見したりするのは不可能となるだろう。
一つの事件を組立て、結末まで興味を惹くように展開させる代わりに、彼は一人ないし複数の人物を、彼らの人生のある特定の一時期において捉え、自然な推移によって、次の時期にまで導いてゆく。このようにして彼が示してみせるのは、時には、精神は周囲の状況の影響によってのどのように変化するかということであり、時には、感情や情熱はどのように発展するか、あらゆる社会において、どのように人は愛しあうか、どのように憎みあうか、どのように争いあうか、ブルジョワの利害、金銭の利害、家庭の利害、政治的利害はどのように対立するか、ということであろう。
従って彼のプランの巧妙さは、感動や魅力、魅惑的な冒頭や心を揺るがす波乱には全くなく、不変の些細な事実を集める手際の良さにあり、そこから作品の決定的な意味が引き出されるのである。もし彼が三百頁の中に一人生の十年間を収め、その人物を取り囲む全ての存在の中で、その人生特有の、十分に特徴的な意味を示そうとするならば、無数の日常的で些細な出来事の中から、作家にとって無用なものをすべて取り除き、特別な方法によって、明敏ではない観察家には見落とされるままでありながら、書物にその射程と全体としての価値を付与するようなもの全てを明らかにする術を知らなければならない。
このような制作の仕方は、誰の目にも明らかな古い手法とはすっかり異なっているので、しばしば批評家を困惑させ、〈プロット〉という名を持つ唯一の太い筋の代わりに、何人かの現代の芸術家が用いる、とても細く、とても秘密で、ほとんど目に見えない筋の全部を、批評家たちが発見できないということも理解されるだろう。
つまり、昨日の〈小説家〉が人生における危機を、魂や心の激しい状態を選んで語ったとするなら、今日の〈小説家〉は通常の状態における、心と魂と知性の物語を書き記している。彼が求める効果、すなわち単純な現実のもたらす感動を生み出すためには、そしてそこから引き出そうという芸術的教訓、すなわち、彼の眼前にある現代人の真の姿の啓示を引き出すためには、彼は、非の打ちどころのない不変の真理を備えた事柄しか用いてはならないだろう。
しかし、これらの現実主義の芸術家の視点に立ったとしても、彼らの理論を議論し、異を唱えねばならないが、彼らの理論とは次の語に要約できるように思われる。すなわち「ただ真実を、そして全ての真実を」。
彼らの意図が、ある種の恒常的で不変の事柄から哲学を引き出すことだとしても、彼らはしばしば、本当らしさを優先するためには真実を犠牲にしても、出来事を修正しなければならないだろう。何故なら、
真実は時には本当らしくないこともありうる(1)。
現実主義者は、もし彼が芸術家であるなら、人生の平凡な写真を示すのではなく、現実そのものよりもより完全で、より驚くべき、より確かなヴィジョンを与えようとするだろう。
全てを語るというのは不可能であろう。そうなれば、我々の生活を満たす無数の無意味な些事を列挙するのに、一日当たり一冊の本が必要となるだろうから。
従って選択が課せられる。――そのことはあらゆる真実という理論に対する第一の攻撃となる。
加えて、人生とは、最も多様な、最も予測のつかない、最も矛盾した、最も雑多な物事で構成されている。人生とは荒々しく、続きもなく、繋がりもなく、説明できない、非論理的で、矛盾に満ちた、「三面記事」に分類されなければならないような惨事に溢れている。
そういう訳で、芸術家は自分の主題を選んだなら、偶発事と雑事の詰まったこの人生から、自分の主題に有用な特徴的な細部だけを取るだろうし、残りの全て、副次的なもの全てを排除するだろう。
無数の中の一例を挙げよう。
毎日、事故で亡くなる人の数はこの世で膨大な数に上る。けれども、事故も考慮に入れねばならぬという言い訳のもと、物語の途中で主要な人物の頭の上に瓦を落としたり、馬車の下敷きにさせたりできるだろうか?
さらに人生は全てを同一面に並べ、事柄を急がせたり、際限なく引き伸ばしたりする。反対に、芸術とは、予防線や下準備を用い、巧妙でうまく隠された推移を調整し、構成の巧みさだけによって本質的な出来事を前面に押し出し、すべて他の出来事は、重要さ次第でそれ相応に際立たせ、提示したいと望む特別な真実の深い感動を生み出すことの内にある。
真実を作るとはすなわち、事柄の通常の論理に従って、真実という完璧な幻影(イリュージョン)を与えることからなり、事柄を、それが継起するままにごちゃまぜに盲従的に書き写すことにはない。
そのことから私はこう結論づける。才能ある〈現実主義者〉とはむしろ〈幻影主義者(イリュージョニスト)〉と呼ばれるべきであろう。
そもそも、現実を信じるとはなんと子供っぽいことであろう。というのも、我々は各人、自分の思考や、自身の器官の内に自分の現実を持っているのである。我々の異なった目、耳、嗅覚、味覚は、この世に人間の数だけの真実を作り出している。そして、これらの器官から指示を受ける我々の精神は、異なった風に印象を受け、理解し、分析し、判断するのであり、あたかも各個人が一つの種に属しているかの如きである。
従って我々一人一人は、単純に、世界についての一つの幻影を作り出しているのであり、それは、それぞれの性質に従って、詩的な、感傷的な、陽気な、憂鬱な、汚れた、あるいは悲痛な幻影である。そして作家の使命とは、彼が学んで手中にするあらゆる手段を用いて、この幻影を忠実に再現することだけなのである。
人間的慣習たる美の幻影! 変わりやすい意見である醜という幻影! 決して不動ではない真の幻影! 多くの人を惹きつける卑劣さという幻影! 偉大なる芸術家とは、人類に自分特有の幻影を強制するもののことである。
従って、どんな理論に対しても腹を立てないでおこう。いずれも、ある気質が自らを分析して一般化した表明であるだけなのだから。
とりわけ二種類の論理が存在し、双方を認めるのではなく、しばしば両者を対立させあって議論がなされているが、それは純粋に分析的な小説の理論と、客観的な小説のそれである。分析の実践者が要求するのは、作家は精神の最も微細な進化も、我々の行動を決定する最も秘密な動機をも指し示すことに執心し、事柄そのものには全く副次的な重要性しか認めない、ということである。事柄とは到着点、ただの里程標、小説の口実である。従って、彼らによれば、心理学の著作を著す哲学者流に、想像力が観察と混じり合った正確かつ夢想的なこうした作品を書くこと、最も遠い起源に遡って原因を提示すること、あらゆる意思のあらゆる動機を述べ、利害、情熱、本能の衝動のもとに動く魂のあらゆる反応を識別することが必要となるだろう。
客観性(なんという見苦しい語か!)の実践者は、反対に、人生に起こる事の正確な再現を提示すると主張し、複雑な説明や、動機についての論議は一切注意を払って避け、我々の目の前に人物と出来事を過ぎて行かせるに留める。
彼らにとっては、心理は書物の中に隠されなければならず、それは現実において、心理は事柄の下、存在の内面に隠されているようにである。
このやり方で着想された小説は、それによって興味を惹き、物語の中に動きを持ち、色彩、躍動する生命を得る。
すなわち、人物の精神状態を長々と説明する代わりに、客観派の作家は、魂のそうした状態が、特定の状況においてその人物に宿命的に取らせるような行動や振る舞いを求める。そして彼らは、そのようなやり方で人物を書物の端から端まで行動させるので、その人物の全ての行動、全ての動きは、彼の内的な性質、あらゆる彼の思考、あらゆる彼の意志または躊躇いの反映となるのである。従って、彼らは心理を繰り広げる代わりに隠し、それを作品の骨格とする。ちょうど目に見えない骨が人体の骨格であるように。我々の肖像を描く画家は、我々の骸骨を示しはしないのである。
この仕方で実現された小説は、それによって誠実さにおいて利をもたらすようにも思われる。そもそもそれはより本当らしい。それというのも、我々の周囲に動いているのを目にする人々は、彼らが基づいている動機を我々に語ったりはしないのだから。
引き続いて、以下のことを考慮しなければならない。もしも人々を観察することによって、彼らの性質を十分に正確に決定することで、ほとんどあらゆる状況における彼らの存在様式を予測することができるとしても、もしも正確に「このような気質のこのような人物は、このような場合にこうするだろう」と言うことができるとしても、我々のものではない彼の思考のあらゆる秘密裡の進化や、我々のとは似ていない彼の本能のあらゆる謎めいた誘惑や、器官も、神経も、血液も、肉体もが我々のとは異なる彼の性質のあらゆる混乱した興奮作用を、一つずつ決定できるということにはならないのである。
脆弱で、優しく、情熱的ではなく、ただ科学と労働を好む人間の才能がどのようなものであろうとも、当たり構わず陽気で、官能的、乱暴で、あらゆる欲望や、あらゆる悪徳にさえも掻き立てられる男の心身に十分完全に転移して、すっかり異なるこの存在の最も内奥の衝動や感覚を理解し、指し示すことは決してできないだろう。彼の人生における行動は十分よく予測し語ることができたとしてもである。
つまり、純粋な心理学を行う者は、様々な状況に置いたあらゆる人物たちに自分が成り代わることしかできないのである。それというのも、器官を取り換えることは不可能だからであり、器官こそは外的生命と我々との唯一の仲介であり、器官はそれ自身の知覚を我々に押し付け、我々の感性を決定し、周囲の者たちのとは本質的に異なる一個の魂を、我々の内に造り出すからである。我々のヴィジョン、感覚の助けによって得られた我々の世界についての知識、人生について我々が抱く概念、そうしたものを、我々はあらゆる人物の内に部分的に移すことしかできない。彼らの内奥にある未知の存在を明るみにさらすと主張していながらもだ。従って、王、殺人者、強盗ないし善良な男、遊女、修道女、少女ないしは市場の商売女の体の内に我々が示して見せるものは、いつでも我々自身なのである。それというのも、我々は以下のように問いを提示するように強制されているからだ。「もし『私』が、王、殺人者、強盗、遊女、修道女、少女、あるいは市場の商売女ならば、『私』は何をし、『私』は何を考え、どんな風に『私』は行動するか?」従って人物を異なったものにするには、我々の「自我」の、年齢、性別、社会的地位、人生におけるあらゆる状況を変更することによってしかできないのであるが、この「自我」を、自然は器官という越えられない障壁によって取り囲んでいるのである。
腕の見せ所は、それを隠すのに役立つあらゆる多様な仮面の下にあるこの「自我」を、読者によってそれと認めさせないところにある。
しかしながら、完全な正確さという唯一の観点からすれば純粋な心理分析には異論の余地があるとしても、にもかかわらず、他のあらゆる方法と同様に、それも美しい芸術作品を与えることができるのだ。
今日、象徴主義者たちがいる。どうしていてはいけないものか? 芸術家としての彼らの夢は尊重すべきものである。そして彼らには、芸術の格別の困難さを知り、それを要求しているという特別に興味深い点がある。
実際のところ、すっかり常軌を逸しているか、大変に大胆であるか、格別に自信過剰であるか、まったくの馬鹿である必要があるだろう、今日なお文章を書こうとするには! 大変に多様な性質を備えた、大変に多重な才能を持ったたくさんの大家たちの後に、まだ成されておらずに成すべき何が残っていようか、まだ言われておらず言うべき何が残っていようか? 我々の内の誰が、似たような形でどこかにすでに存在しないような一頁、一行を書いたと自慢できるだろうか。我々はフランス語の書き物にあまりにも飽和しているので、自分が言葉で出来た生地であるかのような印象を体全体から受けるのだが、その我々が読書する際に、我々に親しくなく、少なくとも漠然とした予感を感じさせないような一行や、一つの思想を見つけ出すようなことがありうるだろうか?
すでに知られた方法によってただ公衆を楽しませようとするだけの人間は、自信をもって、凡庸という無垢さの内にありながら、無知で退屈した大衆のための作品を書く。だが過去の文学の全世紀に圧し掛かられ、何ものにも満足せず、全てにうんざりし、それというのもよりよいものを夢想するからだが、全てがすでに新鮮さを失ったように見え、自分の作品が無意味で平凡であるという印象を絶えず受ける者たちは、文学の技法を、何か掴み難く、謎めいているものと判断するようになる。最も偉大な大家の数頁がそれを僅かに明かしてくれるのだ。
二十行の詩句、二十行の文章を読むや、突然、驚くべき啓示の如くに心臓まで震え上がる。だがそれに続く詩句は他の全てと似たようであり、その後に流れ出る散文は、他の全ての散文に似ている。
才能ある者ならば、間違いなく、こうした苦悩や煩悶を抱くことはないのだろう。彼らの内には抵抗できない創造力があるからだ。彼らは自分を自分で判断するようなことはしない。別の者たち、ただ単に意識的で忍耐強い労働者である我々が、打ち克ち難い落胆の念を相手に戦うには、ただ努力を持続させるしかないのである。
二人の人物が、単純で光明溢れる教育によって、この絶えず試みる力を私に与えてくれた。ルイ・ブイエ(2)とギュスターヴ・フロベール(3)である。
ここで彼らと私自身について語るのは、数行に要約された彼らの助言が、恐らくは、文学の世界にデビューする時、普通以上に自分に自信を持てない若者たちの役に立つであろうからだ。
ブイエは、フロベールの友情を得る二年ほど前、先に幾らか親しく知ることになったのであるが、百行の詩句があれば、恐らくはそれ以下であっても、もしもそれが非の打ちどころなく、例え二流であっても一人の人間の才能と独創性との本質を含んでいるならば、一人の芸術家の名声には十分である、という教えを繰り返すことによって、私にこういうことを理解させてくれた。すなわち、継続的な労働と仕事に対する深い理解が、明晰かつ力に溢れ、鍛練を経たある日に、精神のあらゆる傾向によく調和した主題との幸運な出会いによって、短くも、唯一無二で、能うる限り完璧な作品のあの開花をもたらしてくれるだろう、ということを。
それから私が理解したことには、最も有名な作家であっても、ほとんど一冊以上の書物を後世に残してはいないし、何よりも、我々の手に入る無数の素材の中から、自分の持つ能力の全て、価値の一切、芸術的力の全てを吸収するようなものを、見いだし、識別するという幸運を得なければならない、ということであった。
後に、すでに何度か会っていたフロベールが、私に愛情を抱いてくれた。私は大胆にも幾つかの試作を彼にゆだねた。彼は善意をもってそれを読んでくれた上で、私に答えた。「君に才能があるのかどうか分からない。君が見せてくれたものは、ある程度の知性を証明してはいる。だがこのことを忘れてはいけない、青年よ、才能とは――シャトーブリアン(4)の言葉に倣うなら――長い忍耐に他ならないのだ。仕事をしたまえ。」
私は仕事をした。そして、しばしば彼の家へ赴き、自分が気に入られていると知ったのだが、それは彼が笑いながら、私を彼の弟子と呼ぶようになったからだ。
七年の間、私は詩を作り、コントを作り、ヌーヴェルを作り、唾棄すべきドラマ(5)まで作った。何も残ってはいない。師は全てを読み、次の日曜には食事をしながら批評を繰り広げてくれ、そして少しずつ、二三の原則を私に叩き込んでくれた。それは、彼の長く忍耐強い教育の要約となるものである。「もし独創性があるなら」と彼は言った。「何よりもそれを引き出さなければならない。もしそれがないなら、どうしても一つ獲得しなければならない。」
――才能とは長い忍耐である。――自分が表現したいと望むものを十分に長く、十分な集中力をもって眺め、まだ誰の目にも入らず誰にも言われていない一面を発見することが問題なのである。全てのものには、まだ探索されていないものがある。何故なら、自分の見つめているものについて自分よりも前に考えられたことの記憶だけを頼りに、我々は自分の目を利用するのに慣れているからだ。最も些細なものにも幾らか未知なものがある。それを見つけよう。燃えている火、平原の中の一本の木を描写するためには、その火やその木の前に、自分にとってそれらがもはや、どんな別の木、どんな別の火とも似ていなくなるまで留まりつづけよう。
このようなやり方で人は独創的となる。
さらに、世界全体において、絶対的に同じ二粒の砂、二匹の蝿、二本の手あるいは二つの鼻も存在しないというあの真実を示した上で、彼は私に、数行の文章で、一個の生物ないし一個の事物を、はっきりと個別化するような、同属あるいは同種の他の全ての生物、他の全ての事物と区別するような仕方で、表現することを命じるのだった。
「君が」と彼は言ったものだ。「扉の前に座った食料品屋の前を、パイプを吹かす門番の前を、辻馬車の駅の前を通った時には、その食料品屋やその門番を、彼らの姿勢を、身体の外見が、イメージの巧みさによって同時に精神の性質までも含むように、私に示して見せなさい。私がどんな他の食料品屋や門番とも見間違えることのないように。そして、たった一語で、どの点で辻馬車の一頭の馬は、その前後に並ぶ他の五十頭の馬と似ていないか、私の目に見えるようにしてみなさい。」
文体についての彼の考えは余所で述べた(6)。それは、今ここに説明した観察についての理論と大きく関係するものである。
述べようとするものが何であっても、それを表明するには一語しかなく、それを息づかせるには一個の動詞しかなく、それを形容するには一個の形容詞しか存在しない。だから探さなければならない。その言葉、その動詞、そしてその形容詞が見つかるまで。そして、決しておおよそで満足してはいけないし、たとえ上手くいってもいかさまには、困難を避けるためといって言葉の曲芸には、決して頼ってはいけない。
ボワローのこの一句を適用することで、最も繊細な事柄も翻訳し、指し示すことができるのである。
置かれるべき場所に置かれた言葉の力を教えた(7)。
思想のニュアンスの一切を定めるためにも、今日、芸術的文体(8)という名のもとに押し付けられている、奇怪で、複雑で、数多くの、意味不明な語彙を使う必要は全くない。だが最高度の明晰さでもって、一つの単語の価値が、それが占める場所によって変化するのを見極めなければならない。ほとんど意味の理解できないような名前、動詞、形容詞はなるべく少なく、けれども、異なっていて、多様に構成され、巧みに区切られ、響きと優れたリズムとに溢れた文章がより多くあるように。稀な言葉の収集家であるよりも、むしろ優れた文体家であるように努めよう。
実際のところ、文章を思いのままに操り、全てを言わせ、その文が表明してはいないことまで語らせ、言外の意味や、秘密で明言されてはいない意図で満たすことのほうが、新しい表現を発明したり、人の知らない古い書物の底から、その用法も意味するところも忘れられ、我々にとっては死語同然のあらゆる表現を探したりするよりも、一層困難なことなのである。
そもそも、フランス語は澄んだ水であって、気取った作家たちが決して濁らすことはできなかったし、決して濁らすことはできないだろう。各世紀はこの透明な流れに、それぞれの様式、もったいぶった擬古主義や気取り(プレシオジテ)を投げ込んだけれども、こうした無意味な試み、こうした無力な営為からは何物も、水面に浮かんで残ってはいないのである。この言語の性質とは、明晰、論理的で力強いことである。それは弱められたり、晦渋になったり、腐敗させられることはないのだ。
今日、抽象的な言葉を警戒せずにイメージを作る者、ガラスの「潔白さ」の上に雹や雨を降らせる者は、同僚の単純さに向けて石を投げることもできるだろう! 恐らくは肉体を持つ同僚には当たることはあっても、それを持たない単純さに当たることは決してないであろう。
ギィ・ド・モーパッサン
ラ・ギェット(9)、エトルタ、1887年9月
訳注
(1) ボワロー『詩法』 Art poétique (1674)、第3歌48行。ニコラ・ボワロー Nicolas Boileau (1636-1711) は詩人・批評家。古典主義文学理論の確立者として知られる。
(2) Louis Bouilhet (1822-1869) : 詩人・劇作家。ルーアン在住で、フロベールの親しい友人だった。詩集に『花綱と玉縁』(1859)、戯曲に『マダム・ド・モンタルシー』(1856)、『マドモワゼル・アイセ』(1872) など。モーパッサンは1868年にブイエと親交を持った。時評文「ルイ・ブイエ」(1882)などで思い出を語るとともに、ブイエの顕彰に努めた。
(3) Gustave Flaubert (1821-1880) : 小説家。精密な考証を基に、推敲に推敲を重ねて小説を執筆した。『ボヴァリー夫人』(1857)、『感情教育』(1869) などの作品は後世に大きな影響を与える。モーパッサンは1870年代を通してフロベールに師事し、文学について多くを学んだ。
(4) François-René de Chateaubriand (1768-1848) : ロマン主義の先駆的作家。『キリスト教精髄』(1802) など。「才能とは長い忍耐に他ならない」 « Le talent n’est qu’une longue patience. » の正しい出典は、18世紀の博物学者ビュフォン Georges Louis Leclerc Buffon (1707-1788) である。正確な引用は、「天才とは、忍耐に対して一層ふさわしい適性に他ならない」 « Le génie n’est qu’une plus grande aptitude à la patience. »(エロー・ド・セシェール『モンバールとビュフォンの城への旅』(1785) の中で報告されている)。
(5) 「唾棄すべきドラマ」:1877年執筆の韻文歴史劇『リュヌ伯爵夫人の裏切り』。翌年、改稿され『レチュヌ伯爵夫人』に改題。コメディー・フランセーズ等の劇場に提出されるが、上演には至らなかった。
(6) 「文体についての彼の考えは余所で述べた」:1884年、『ジョルジュ・サンド宛書簡集』に序文として掲載された評論「ギュスターヴ・フロベール」を指すと思われる。
(7) ボワロー『詩法』、第1歌133行。
(8) 「芸術的文体」style artiste : モーパッサンは暗にエドモン・ド・ゴンクール Edmond de Goncourt (1822-1896) を批判していると考えられる。ゴンクールは1888年1月9日に日記に記している。「新しい小説の序文で、モーパッサンは芸術的文体を攻撃し、名指しせずに私に狙いをつけた。すでにフロベールのための寄付金と『ジル・ブラース』の記事の際に、彼の率直さには不満を抱いていたのである。今日、攻撃が届くのと同時に、郵便で、彼は称賛と愛情の念を送ってよこした。こうして、彼はとてもノルマンディー人らしいノルマンディー人だと信じずにはいられない。そもそも、彼は嘘つきの王様だとゾラは言っていた……。/こんにち、彼はモニエ流の、とても巧みなノルマンディーの「小説屋」かもしれない。だが作家ではないし、彼が「芸術的文体」を貶める彼なりの理由があるのだ。ラ・ブリュイエール、ボシュエ、サン=シモン以来、シャトーブリアンを経てフロベールに至るまで、作家は自分の文章に署名を残し、教養人には、署名がなくとも彼のものと分からせたのであり、その条件によってのみ偉大な作家なのである。ところで、署名のないモーパッサンの一頁、それは率直に言って、全員に属するありきたりのよくできたコピーである。」
(9) La Guillette : ノルマンディー地方、故郷エトルタの町に建てられたモーパッサンの別荘。
