「ギュスターヴ・フロベール」 (II)
« Gustave Flaubert », 1884
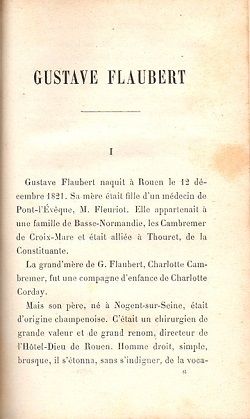 解説 1884年に刊行されたギュスターヴ・フロベールによる『ジョル・ジュ・サンド宛書簡集』(Lettres de Gustave Flabert à George Sand, précédées d'une étude par Guy de Maupassant, G. Charpentier, 1884) に「序文」として書かれたフロベール論、2章からなっている内の第2章。第1章は「ギュスターヴ・フロベール」 (I) に掲載している。
解説 1884年に刊行されたギュスターヴ・フロベールによる『ジョル・ジュ・サンド宛書簡集』(Lettres de Gustave Flabert à George Sand, précédées d'une étude par Guy de Maupassant, G. Charpentier, 1884) に「序文」として書かれたフロベール論、2章からなっている内の第2章。第1章は「ギュスターヴ・フロベール」 (I) に掲載している。第1章が主にフロベールの生涯を辿りながら、その作品を紹介・説明しているのに対し、第2章ではフロベールの文学観についてより詳しく説かれている。この章には先に書かれた評論の文章が頻繁に再利用されているが、その際、多くの加筆・修正が加えられている。
なおこの第2章については次の既訳が存在する。
ギー・ド・モーパッサン「ギュスターヴ・フローベール(抄)」、宮原信訳、『フローベール全集』、第10巻、1970年、筑摩書房、447-459頁。
***** ***** ***** *****
II
II
ギュスターヴ・フロベールは、何を差し置いても、何よりもまず、芸術家だった。今日の公衆は、文学者が問題となっている時にこの語が何を意味するのかをほとんど識別することができない。芸術の感覚、大変にデリケートで微妙で困難で、とても捉え難く、とても言葉に表しにくいこの嗅覚は、本質的に知的貴族階級の素質である。それはほとんど民主主義国家には属していない。
とても偉大な作家も芸術家ではなかった。公衆や大半の批評家も、芸術家とその他の者とを区別できない。
反対に前世紀には、公衆とは気難しく洗練された審判者であり、今日では消えてしまったこの芸術家的感覚を極端にまで推し進めたのだった。公衆は一つの文、一行の詩句、巧妙だったり大胆だったりする形容詞一つに夢中になった。二十行、一頁、一つの人物描写、一つのエピソードがあれば、一人の作家を判断し、分類するのに十分だった。言葉の下や中に含まれるものを探し、著者の隠している理由を見抜き、ゆっくりと読んで、何も見逃さず、文章を理解した後にも、もう知るべき何かが残っていないかを探したのである。それというのも精神というものは、文学的感興に対して準備ができるには時間がかかるものであり、作品の中に魂をあらしめるあの神秘的な力の隠された影響を受けるものだからである(1)。
何であれ才能を持った一人の人間が、語られた事柄にしか関心を持たず、文学の真の力は出来事にではなく、それを準備し、提示し、表現する仕方の内にあるのだということを理解しないならば、その者には芸術の感覚がないのである。
ある頁や、ある文章を前にして心へとのぼってくる深く甘美な喜びは、それが述べている事柄だけからやって来るのではない。それは表現と概念との絶対的な一致、大抵の場合に群衆の判断をすり抜ける調和と秘密の美の印象から来るのである。
ミュッセ(2)、あの偉大な詩人は、芸術家ではなかった。簡明で誘惑的な言葉によって彼が語る魅力的な事柄は、もっと高尚で、もっとつかみ難く、もっと知的な美の追求、探求、感動に心を奪われている者には、感動を与えることがない。
反対に群衆はミュッセの内に、いくらか粗野な自らの詩的欲求の充足を見出だし、ボードレール(3)、ヴィクトル・ユゴー、ルコント・ド・リール(4)の詩篇が与えてくれる身震い、ほとんど恍惚と呼ぶべきものを理解しない。
言葉には魂がある。ほとんどの読者は、それに作家でさえも、言葉に意味しか求めていない。この魂を見つけなければならないのだが、それは他の言葉との接触によって姿を見せ、炸裂し、噴き出させるのがとても難しい未知の光で特定の書物を照らし出すのである。
ある人たちによって書かれた言葉の結びつきや組み合わせの内には、詩的世界の全体的な喚起が存在するが、社交界の人士はもはやそれに気づいたり見抜いたりできない。そうしたことについて話すと、彼らは機嫌を損ね、理屈を並べ、議論し、否定し、叫び、それを見せてみろと要求する。そんなことは試みるのも無駄であろう。感じないのであれば、決して理解できないであろう。
教養があり知的な人間、作家でさえもが、彼らの知らないこの〈神秘〉について話されると驚くのである。彼らは肩をすくめてほほ笑んで見せる。どうでもいいことだ! 彼らは知らないのである。耳を持たない人間に音楽の話をするようなものだ。
この神秘的な芸術感覚を持った二人の人間の精神には、十語の言葉が交わされるだけで十分であり、あたかも他の者たちには分からない言葉を使っているかのように、互いを理解しあうのである。
フロベールは生涯にわたってこの捕まえがたい完璧さの追求に悩まされた。
彼の抱く文体の概念ゆえに、彼はこの語の内に、同時に思想家と作家とを構成するあらゆる性質を閉じ込めたのだった。だから彼が「文体しか存在しない」と言った時には、「言葉の響きや調和しか存在しない」と言おうとしたのだと思ってはいけないだろう。
一般的に「文体」として理解されているのは、自分の思想を提示するそれぞれの作家に固有の仕方である。そうであれば文体は人によって異なり、気質次第で華々しかったり地味だったり、豊かであったり簡潔だったりすることだろう。ギュスターヴ・フロベールは、著者の人となりは書物の独創性の内に消滅せねばならず、書物の独創性は、文体の奇抜さの結果であってはならないと考えていた(5)。
それというのも、彼は「文体」を、それぞれが作家の印をそなえていて、その中にどんな思考でも流し込めるような個別の鋳型の集まりのようなものとは考えていなかったのである。彼は〈唯一の文体〉の存在を、つまり一つの事物をその色合いとその強度の内に表現する唯一で絶対的な仕方が存在すると信じていた。
彼にとって、形式とは作品そのもののことであった。生物において血が、種族や家系にしたがって、肉体を生かし、その輪郭、その外見を決定するように、彼にとっては作品の内容が宿命的に、唯一にして正確な表現、拍子、リズム、形式の外観をもたらすのである。
形式無しに内容が存在しうるということや、内容無しに形式が存在するということは、彼には理解できなかった。
したがって、文体はいわば非人称的なものとなるだろう。そしてその性質は、ただ思考の性質とヴィジョンの力強さのみに由来することとなるだろう。
一つの事物を表現するには一つの仕方、それを言うには一つの語、それを形容するには一つの形容詞、それを息づかせるには一つの動詞しか存在しないという絶対的な信念に取り憑かれ、彼は一文ごとにその語、その形容辞やその動詞を見つけるために超人間的な労働に専念した。そうして彼は表現の持つ神秘的な調和を信じていたので、ある正確な語の口調がよく思われないと、不屈の忍耐心でまた別の語を探し、まだ真の語、唯一の語を手にしていないと確信しているのだった。
したがって、書くということは彼にとって恐るべきこと、苦悩と危機と疲労とに満ちたものであった。彼が自分の机へと座りに行く時には、この愛していると同時に苦しみをもたらす仕事への恐怖と欲望を感じるのだった。彼はそこに不動のまま何時間も留まり、忍耐強く注意深い巨人のものである恐るべき仕事に熱中した。この巨人は子どものビー玉でピラミッドを作り上げるのである。
背の高い樫で出来た肘掛椅子に埋まるようにして、頭は力強い肩の間に引っ込んだまま、彼は青い目で自分の紙を見つめていた。その瞳は小さく、いつでも動いている黒い穀粒のように見える。聖職者の被るのに似た絹地の軽やかな縁なし帽は、頭頂を覆いながらも長い髪の房を覗かせており、髪は先の方で輪を作って背中に広がっている。褐色のラシャ地の幅広い部屋着が全身を覆っている。先の垂れた立派な白い口髭が横切る赤味がかった顔が、高ぶった血の流入で膨れている。大きく暗い睫毛の影になっている目の視線が行を駆け、言葉を調べ回り、文をひっくり返し、集められた文字の様相を調べ、待ち伏せする狩人のように効果を見張っている(6)。
それから彼はゆっくりと書き始めるのだった。絶えず立ち止まり、再開し、書き直し、行を加え、余白を埋め、横向きに文字を綴り、一頁仕上げるために二十頁を黒く汚し、思考の痛ましい努力を続けながら、縦びき工のようにうめき声をあげるのだった。
時々、注意深く削られた鵞鳥の羽根ペンで一杯の東洋の錫製の大皿に、手にしていたペンを投げ出すと、彼は紙片を取り上げて目の高さへ持ち上げる。そして、肘をついたまま、鋭い大声で朗読を始める。彼は自分の散文のリズムを聴き、逃げ去る響きを捕まえるために止まると、調子を組み合わせ、半諧音を遠ざけ、知識に基づいてコンマを配置するのだが、それは長い途上の休止のようなものだ。
彼は言っていた。「一つの文が呼吸の必要性に対応している時には、十分な持続性がある。大きな声で読まれうる時には、その文は良いものなのだ。」
ルイ・ブイエの『最後の歌』の序文の中で彼は書いている。「下手に書かれた文はこの試練に耐えることがない。それは肺を息切れさせ、鼓動を妨げ、したがって生命の条件の埒外にある(7)。」
彼は無数の注意点に同時に悩まされ、取り憑かれており、彼の精神にはいつでも一つの確信がじっと留まりつづけていた。「あらゆる表現、形式、言い回しの中で、私が言いたいことを表すためには、一つの表現、一つの言い回し、一つの形式しか存在しない。」
そして頬を膨らませ、首を充血させ、額を赤くして、戦う闘技者のように筋肉を強張らせ、彼は絶望的なまでに概念や言葉と格闘し、それらを捕え、それらの意に反してでも結びつけ、彼の意志の力でほどけないようにし、思考を締め付け、超人間的な努力と疲労によって少しずつ屈服させ、捕えた獣のごとくに、堅固で正確なフォルムの内に閉じ込めるのである。
この並外れた労働から、彼には文学と文章に対しての極端な敬意が生まれた。これほどの苦労と苦しみによって一つの文をこしらえたからには、一語でも取り換えることが可能であるとは認めなかった。友人に『純な心』と題した短編を読み聞かせた時、十行からなる一節について指摘や批評がなされた。老嬢が自分のオウムと聖霊とを混同してしまう場面だった。そのような発想は農民の精神にとっては繊細すぎるというのだ。フロベールは耳を傾け、熟考し、その指摘は正当であると認めた。だが彼は苦悩に捕われた。「あなたは正しい」と彼は言った。「ただ……、文章を変えなければならないだろうね……。」
とはいえ、その晩から彼は仕事に取りかかった。十語を修正するために一晩を過ごし、二十枚の紙を黒くし、抹消した挙句、最後には、調和が完璧だと思われる別の文を作ることができずに、何も変えずに終わったのだった。
同じ短編の冒頭では、ある段落の最後の語が、次の文の主語となることで、多義構文の原因となりえていた。彼はこの不注意を指摘された。彼はそれを認め、意味を修正しようと努めたが、望むような響きを発見することができなかったので、意気阻喪して叫んだ。「意味にとっては残念なことだ。だが優先されるべきはリズムだ!」
この散文のリズムの問題が、しばしば彼を情熱的な議論へと駆り立てた。「詩句においては」と彼は言うのだった。「詩人には既定の規則がある。彼には分節、句切れ、韻、それに多数の実際的な決まり、職業的な学問的体系が存在している。散文においては、リズムに対する深い感受性が必要だ。リズムとは捉え所がなく、規則もなく、確実なものではないので、生まれつきの資質がなければならず、またさらに論理的思考能力、はるかに繊細で鋭い芸術家的感覚が必要で、それによって絶えず、言いたい事柄に従って文体の運動や色合いや音を変化させるのである。この液体的存在であるフランス語の散文を操ることができるなら、言葉の正確な価値を知っているなら、語に与える位置によってその価値を変化させることができるなら、一頁の興味を一行に惹きつけることができるなら、百の概念の内の一つを、それを言い表す用語の選択と配置だけによって浮き彫りにすることができるなら、一語、ある仕方で置かれたたった一語によって、武器によって打つように打つことがきるなら、読者の目の前に一つの形容詞を通らせるだけで、魂を揺るがし、喜びや恐怖や熱狂や悲しみや怒りで満たすことができるなら、その者は真に芸術家、芸術家の中でも最も優れた者、真の散文家である。」
彼はフランスの偉大な作家に対して熱狂的な賞讃の念を抱いていた。大家の作品の何章も暗記していて、雷鳴のような声で朗誦しては、散文に酔い、言葉を響かせ、区切って発音し、抑揚をつけ、文を歌うのだった。形容辞が彼の心を奪った。彼はそれを百度も繰り返し、絶えずのその正しさに驚き、宣言するのだった。「このような形容詞を見つけるためには天才でなければならない。」
自分の芸術に対する敬意と愛情、そして文学的尊厳の意識を、ギュスターヴ・フロベール以上に高くまで押し上げた者は存在しない。唯一の情熱、文芸に対する愛が、最期の日まで彼の人生を満たしていた。彼は熱狂的に文芸を愛し、その愛し方はほとんど絶対的で唯一のものだった(8)。
芸術家はほとんどいつでもある秘密の、芸術とは無縁の野心を隠している。人がしばしば追い求めるのは栄光であり、輝かしい栄光が、生きたまま彼を崇拝の対象とし、人々の頭を興奮させ、手を叩かせ、女たちの心を虜にする。
女性たちに気に入られること! それもまたほとんどすべての者にとって激しい欲望である。才能の全能ぶりによって、パリにおいて、社交界において、例外的な存在となり、賞賛され、誉めそやされ、愛され、我々が餓えているあの生きた肉体の果実をほとんど我が意のままに摘み取れること! 行く先々どこでも、評判、尊敬、追従を先導に入って行き、すべての視線が自分に注がれ、すべての微笑みが自分に向かって来るのを目にすること。そこにこそ、人工的な手段によって自然を解釈し、再現するという奇妙で困難な職業に専念する者の追い求めるものがある。
他の者たちは金銭を追い求めた。それ自体のためであったり、それがもたらしてくれる満足のためであったり。すなわちは、豪奢な生活と食卓の上の甘美な料理。
ギュスターヴ・フロベールは文芸をあまりにも絶対的な形で愛したので、この愛に満たされた彼の魂においては、他のどんな野心も場を占めることはできなかった。
決して彼は他の関心や欲望を抱かなかった。他のことについて話すことはほとんど不可能だった。彼の精神は文学的な関心に取り憑かれているので、常にそこに戻ってきては、社交界の人士の関心を惹くすべてのものは無駄だと宣言するのだった。
彼はほとんど一年中一人で過ごし、休息も中断もなく仕事を続けた。疲れ知らずの読書家で、休息は読書であり、調べたすべての書物から取ったメモが書棚一つ丸ごとを占めていた。そもそも彼の記憶は見事なもので、五年や十年前に、ほとんど知られていない作品の小さな細部を見つけた、章や頁、段落を覚えているのだった。こうして無数の出来事を知っていた。
彼は人生の大半をルーアンの近くのクロワッセの領地で過ごした。それは古い様式の愛らしい白い家で、セーヌの川沿い、素晴らしい庭の中央に立っている。庭は背後へと広がり、急な道でカントルーの丘をのぼってゆく。広い書斎の窓からは、ルーアンに上っていったり海へ下っていったりする大型船がすぐ近くを通って行くのが見え、まるで帆桁が壁に触れそうなほどだった。この幅広い川の表面を滑って、夢に見るようなあらゆる国へと旅立ってゆく船の無音の動きを眺めるのが彼は好きだった。
しばしばテーブルを離れると、巨人のような幅広い胸と古代ガリア人のような頭を、窓枠の中に映すのだった。左手にはルーアンの無数の鐘楼が空に鉄のシルエット、手の込んだ輪郭を描いている。少し右にはサン=スヴェールの工場のたくさんの煙突が空に煙を吐き出し、煙は花綱模様を描いている。紡績工場ラ・フードルの蒸気ポンプはエジプトの最も高いピラミッドと同じほど高く、対岸にある大聖堂の世界一高い鐘楼を眺めている。
正面に広がる牧場には赤毛や白毛の牝牛がたくさんいて、横になったり、立ったまま草を食んだりしており、右手の向こうには、大きな丘陵の上の森が地平線を塞いで、そこに流れる幅広い静かな川には、木の生えた島がたくさん浮かんでいるが、川は海へと下ってゆき、遠くで大きな谷間へと曲がって消えてゆく。
彼は幼少時代から見てきたこの見事な光景を愛していた。運動を恐れていたので、彼が庭へ降りてゆくことはほとんどなかった。それでも時折、友人が会いに来ると、一緒にボダイジュの立つ大きな並木道に沿って散歩した。その道は段々になっていて、重大かつ穏やかなおしゃべりのために作られたかのようだった。
彼の言うところでは、かつてパスカルがこの家に来て、この木々の下を同じように歩き、夢想し、話したに違いないのだった。
彼の書斎の三つの窓は庭に向き、二つは川に向いていた。その部屋はとても広く、装飾としては書物と、いくつかの友人の肖像と、旅行のお土産だけだった。そのお土産とは、幼いカイマンワニの剥製、純朴な召使がブーツのように蝋引きした黒くなっているミイラの片足、東洋の琥珀でできた数珠、黄金の仏像は大きな仕事机を見下ろしており、無窮の神々しい不動性の内に、その細長い目で、プラディエの手によるギュスターヴの妹のカロリーヌ・フロベールの見事な胸像を見つめている。彼女は若妻の時に亡くなったのだった。そして床には、一方にクッションを乗せた大きなトルコ製の長椅子、反対側には素晴らしい白熊の毛皮が敷かれていた。
彼は午前九時か十時から仕事に取りかかり、昼食のために立ち上がるが、すぐに仕事を再開するのだった。しばしば午後に一、二時間眠った。だが午前三時か四時まで眠らず、その時、夜のしじまの中、緑色の笠に覆われた二つのランプにわずかに照らされた静かなアパルトマンの中での瞑想によって、最良の仕事をなし遂げたのだった。川の上の水夫たちは「ギュスターヴさん」の家の窓を灯台のように利用していた。
彼は故国において周囲の者たちの伝説となっていた。人は彼をいささか頭のおかしい善人として眺めており、その奇妙な衣装は目や精神を恐れさせた。
仕事の時に彼がいつも着ていたのは、ベルトのところで絹の紐で結ばれた幅広のズボンと、地面まで届く大きな部屋着だった。この衣装は、気取りからではなく、そのゆったりさが好都合ゆえに採用されたのだったが、冬は茶色のウール、夏は軽い布地で、白地に明るいデッサンが描かれていた。ルーアンのブルジョア市民たちは、日曜日にラ・ブイユに昼食を摂りに行く時、蒸気船のデッキから、本物のフロベール氏がその高い窓枠の中に立っているのを見たいという期待が裏切られて、がっかりして帰ってゆくのだった。
彼のほうでもこの人々を積んだ船が通り過ぎるのを眺めるのを楽しんでいた。いつも机の端か暖炉の隅にかけてあるオペラグラスを目にあてて、彼のほうを向くすべての顔を興味深く凝視した。彼らの醜さを面白がり、彼らの驚きに心が晴れ晴れとした。彼は顔の上に各人の性格、気質、愚かさを読み取った。
彼のブルジョア嫌いについてはさんざんに話された。
彼はこの〈ブルジョア〉という語を〈愚かさ〉の同義語として、それを次のように定義していた。「誰であれ下品な仕方で思考する者を私はブルジョアと呼ぶ。」したがって彼が恨みを抱いていたのはブルジョア階級にではまったくなく、大抵の場合にこの階級においてお目にかかるある特殊な愚かさに対してだった。もっとも、彼は「良き民衆」に対しても完全な軽蔑を抱いていた。だが労働者よりも社交界の人士と接触することのほうが多かったので、民衆の愚かさよりも社交界の愚かさのほうに一層に苦しんだのだった。無知ゆえの絶対的な信念、不滅と言われる原則、あらゆる慣習、あらゆる偏見、一揃いの一般的だったり優雅だったりする意見が、彼を憤慨させた。大多数の普遍的な愚かさや知的劣等性に対して、他の多くの者のように微笑む代わりに、彼はひどく苦しむのだった。彼の過敏な脳の感受性ゆえに、各人が日々繰り返す平凡な愚かさによって傷つけられるように感じた。凡庸な会話が一晩中続くようなサロンから退出した時には、まるでめった打ちにされかのように衰弱し、打ちのめされ、自分自身が愚かになってしまったと彼は断言したものだが、それほどに、他人の思考にまで入って行くことの出来る能力を備えていたのである(9)。
いつも敏感で心を動かされやすく、彼は皮を剥がれた者に自らを譬えたもので、些細な接触でさえ痛みに震えるのであった。そしてもちろん人間の愚かさは、生涯にわたって彼を傷つけた。ちょうど内密の隠された大きな不幸によって傷つけられるように。
彼は愚かさを、いわば彼を苦しめることに躍起になっている個人的な敵とみなしていた。そして彼は、獲物を追う狩人のように執拗にそれを追い求め、最も偉大な者の頭脳の奥底においてまでそれを捕えた。彼にはそれを発見するに猟犬のような鋭敏さがあり、新聞の中や一冊の美しい書物の中に隠れていても、彼の素早い視線はそれの上に注がれるのだった。時にはそのためにあまりにも憤慨することになったので、彼は人類を種ごと破滅させたいとさえ望んだだろう。
彼の作品の人間嫌い的な面はまさしくここに由来する。そこから発する苦味とは、この凡庸さ、平凡さ、あらゆる形態の愚かさの恒常的な確認に他ならない。彼はその確認をあらゆる頁、ほとんどすべての段落に、一語によって、ごく単純な意図によって、ある場面や対話の調子によって書きつけるのである。彼は知的な読者を人生に対する悲嘆にくれた憂鬱さで満たす。『感情教育』を開いて多くの人々が感じた説明のつかない不快感は、脳内において裸にされた思想の永遠の惨めさについての理性を欠いた感触に他ならないのである。
その意図をもっとよく理解させるために、この書物を「ドライフルーツ」と呼べるだろうと彼は時々言っていた。それを読みながら、各人は不安な気持ちで自分もこの陰鬱な小説の悲しい登場人物の一人ではないかと自問する。それほどに、誰もが個人的で、痛ましい内密の事柄を、自分自身の内に見出だすのである。
ある日には、おぞましい書物を数え挙げた後で、彼は記した。「これはすべて、我が同胞たちに対して、彼らが私に催させた嫌悪感をぶつけるというだけの目的なのです! 最後には私は、自分の考え方を述べ、恨みをぶちまけ、憎しみを吐き出し、苦汁をまき散らし、憤りを洗い落とすことでしょう!(10)」
普通に見られる愚かさと一般的な平凡さに対して憤慨した理想主義者の軽蔑は、才能の種類や博識の性質が何であれ、優れた人物への激しい賞賛の念を伴っていた。〈思考〉しか愛したことがなかったので、そのあらゆる表現を尊重したのだった。そして彼の読書は、通常は文学芸術に最も疎遠と思われる書物にまで及んでいた。ルナン氏を不器用に批判した、ある親しい新聞に対して彼は気を悪くしたことがある。ヴィクトル・ユゴーの名前だけで、彼は熱狂に捕われた。彼はジョルジュ・プーシェ氏(11)やベルトロ氏(12)のような人物を友人に持っていた。彼のパリのサロンは、最も興味深いものの一つだった。
日曜日、一時から七時まで、六階にあるとても簡素な独身男性のアパルトマンに、彼は客を迎えた。壁は裸で家具は質素なものだったが、彼は芸術作品の置物を嫌悪していたからである。
呼び鈴が最初の訪問者を告げるや、彼は、文字で黒くなった紙片が散らばる仕事机を赤い絹の軽い布で覆う。布地は彼の仕事道具全部を包みこんで隠すが、それは司祭にとっての祭具のように、彼にとって神聖なものなのだ。それから、日曜日はほとんどいつも召使が外出しているので、彼自らドアを開けに行く(13)。
最初の客はしばしばイヴァン・トゥルゲーネフで、彼は兄弟のように抱擁した。フロベールよりもさらに背の高いロシアの小説家は、稀にみる深い愛情でフランスの小説家を愛していた。才能、哲学、精神の親近性、趣味、生活、夢の類似、文学的傾向、熱狂的な理想主義、賞賛の念や博識の一致が、二人の間に多くの絶え間ない接点をもたらしたので、再会するたびにそれぞれが、恐らくは知性の喜び以上に心の喜びを感じるのだった。
トゥルゲーネフは肘掛椅子に腰を下ろし、ゆっくりと話す。その声は優しく、少し弱くてためらいがちだが、言われた事柄に特別な魅力と興味を添える。フロベールは崇拝の念をもって彼の言葉を聞き、友人の大きな白い顔に、瞳の動く大きな青い目をじっと向けている。彼はよく響く声で答えるが、それはガリアの老戦士のような口ひげの下から、ラッパの音のように飛び出してくる。二人の会話は日常生活のことにはほとんど触れず、文学に関する事物や歴史からほとんど離れない。しばしばトゥルゲーネフは外国の書物を抱えていて、ゲーテ、プーシキンやスウィンバーンの詩をすらすらと翻訳した。
他の者たちが少しずつやって来る。テーヌ氏(14)、視線は眼鏡の奥に隠れていて、内気な様子をしているが、歴史資料、未知の事柄、ひっかき回した古文書の匂いと感触、哲学者としての鋭い視線によって掴まれた古代の生活の様子を伝えてくれる。
次にフレデリック・ボードリー氏(15)、学士院会員およびマザラン図書館の館長であり、ジョルジュ・プーシェ氏、自然誌博物館の比較解剖学教授であり、クローディウス・ポプラン氏(16)、七宝の達人であり、フィリップ・ビュルティー氏(17)、作家、収集家、美術批評家、繊細で魅力的な精神の持ち主である。
次はアルフォンス・ドーデ(18)であり、彼はパリの空気を運んで来る。それは生き生きとして、享楽的、活動的で陽気なパリだ。数語で大変おかしな人物の姿を描き出し、あらゆるものに対し、魅惑的な、南仏風でまた個性的な皮肉を振り撒き、才気あふれる精神の繊細さを、表情と身振りの魅力や、いつでも書かれた短編小説のように構成された物語の手腕で強調してみせる。愛らしい頭は大変に繊細で、黒髪の波に覆われている。髪は肩の上に落ち、カールしたあごひげとも混ざり、彼はしばしばそのひげの尖った先を丸めている。目は切れ長だが細く、インクのように黒い瞳を行き来させ、極端に近視のために、視線は時折ぼんやりとしている。声は少しばかり歌うようだ。生き生きとした身振り、機敏な様子、すべて南仏生まれの印である。
今度はエミール・ゾラが、六階まで上るのに息を切らしつつ、忠実なポール・アレクシ(19)を連れて入って来る。彼は肘掛椅子に身を沈めると、人々の顔の上を一瞥し、精神の状況、おしゃべりの調子や様子を追い求める。少しばかり脇に寄って座り、片足を下に敷いて踝に手をやりながら、あまり話さずに、彼は注意深く聞いている。時折、文学的熱狂、芸術家的な陶酔が話し手たちを駆り立て、生き生きした想像力の持ち主に親しい、あの極端で逆説に富んだ理論へと彼らを押しやった時には、彼は不安そうに足を動かし、時折「しかし……」の一語を挟むけれど、それは哄笑にかき消されてしまう。それから、フロベールの抒情的な興奮が静まると、彼は穏やかな声、平和的な言葉遣いで議論を再開する。
中柄で少しばかり太り気味、善良であるが頑固そうな様子をしている。多くの古いイタリア絵画の中に見られるような頭をしていて、美しくはないが、力と知性溢れる優れた性質を表わしている。短く刈った髪がとても広い額の上にそそり立っている。真っ直ぐの鼻は、鋏でばっさりといった風に、上唇の上できっぱりと切り取られていて、唇のほうはとても濃く黒い口ひげの陰になっている。このふっくらして、しかしながら精力的な顔の下の部分は、短く刈られたあごひげで覆われている。黒い瞳は、近視だが貫くようで、何かを探し求め、しばしば皮肉な微笑を浮かべ、一方で、ある特徴的な皺が上唇を巻くり上げさせると、ある種奇妙でもあり、からかっているようにも見える(20)。
また他の者たちがやって来る。次は出版人シャルパンティエ(21)だ。長い黒髪に混じった白髪がなければ、彼は青年と思われるだろう。細身の愛らしい男で、幾らか尖った顎が、濃いけれども丹念に剃られたあごひげの跡で青みがかっている。口ひげだけを生やしている。彼は若々しく懐疑家風の笑い声で心から笑い、それぞれの作家の話を聞いて彼らが求めるものを約束する。作家のほうでは彼を独占して壁の方へ追いやると、そこであらゆるものを彼に推薦するのである。次は魅力的な詩人カチュール・マンデス(22)である。官能的で誘惑的なキリストのような顔をしており、柔らかいあごひげと軽やかな髪がブロンドの雲で繊細な蒼ざめた顔を囲んでいる。比類のない話し上手、洗練されて繊細な芸術家、最も捉え難い文学的感興を捕まえる彼は、その言葉の魅力と精神の繊細さで特別にフロベールに気に入られている。次は彼の義理の弟のベルジェラ(23)、彼はテオフィル・ゴーチエの二番目の娘と結婚した。次はジョゼ=マリア・ド・エレディア(24)、傑出したソネの作り手であり、この時代の最も完璧な詩人の一人として名を残すだろう。次にユイスマンス(25)、エニック(26)、セアール(27)、さらにその他の者たち、気難しく洗練された文体家レオン・クラデル(28)、ギュスターヴ・トゥードゥーズ(29)である。
それから、ほとんどいつも最後に入って来るのは、背が高く痩せた男性で、その真剣な表情は、しばしば微笑んではいるが、尊大で貴族的な堂々とした様子をしている。
脱色したような灰色がかった長髪で、幾らかより白い口髭、独特の目は奇妙なほど広がった瞳に占領されている。
彼は貴族の外観、由緒正しい者の繊細で神経質な様子をしている。(人の知るとおり)彼は社交界、それも最良の社交界に属している。それはエドモン・ド・ゴンクール(30)である。進み出て来る彼の手には特別な煙草が一箱、いつでもそれを肌身離さずにいて、友人たちにはもう一方の自由な手を差し出す。
小さな客間は溢れてしまう。幾つかのグループは食堂へと場所を移す。
そしてとりわけこの瞬間にこそ、ギュスターヴ・フロベールを眺める必要があった。
大きな身振りで飛び立つかのように見えるのだが、彼は一人から別の一人へと一歩で移って部屋を横切り、長い部屋着は彼の後ろで荒々しい情熱に膨れ、さながら釣り船の褐色の帆のようで、興奮と憤慨と激しい炎と響き渡る饒舌に満ち溢れ、彼はその熱狂によって楽しませ、善良さによって魅了し、しばしば驚異的な博識ぶりで驚かせた。それには信じられないような記憶力が役立っている。そして明晰かつ深奥な一語でもって議論を終わらせ、思考の一飛びで数世紀を経巡っては、同類の二つの事柄、同種族の二人の人間、同じ性質の二つの教訓を結びつけ、そこから同種の二つの石をぶつけ合った時のように、光を発生させたものである。
それから、一人、また一人と友人たちは去って行く。彼は控えの間まで友人たちについて行き、そこでしばし一人一人と言葉を交わしては、力を込めて握手し、肩を叩きながら親愛の念のこもった笑い声を上げるのだった。そして、最後にゾラが、いつでもポール・アレクシを従えて部屋を出ると、彼は幅広のソファーで一時間ばかり眠り、それから燕尾服を着て、親しい友人のマチルド皇女(31)の館へと夕食に出かけるのだった。彼女は毎日曜日に客を迎えていたのである。
彼はそこで聞く会話に憤慨してはいたけれど、サロンが好きだった。離れている時には女性たちを厳しく批判し、「女性は公正さにとっての悲痛の種だ(32)」というプルードンの言葉を繰り返していたが、彼女たちに対して心を和ませた父性的な友情を抱いていた。これ以上ないほどに気取らずに暮らしていたが、見事な贅沢、豪華な優美さ、壮麗さを愛好していた。
内輪では、彼は陽気で善良だった。彼の力溢れる陽気さはラブレーの陽気さから直接に流れているもののようだった。彼は悪ふざけ、何年にもわたって続く冗談が好きだった。しばしば彼は満足して、率直な、深い笑い声をあげた。この笑いは、人間性に対する憤慨よりも彼にとってより自然で普通のもののように思われた。彼は友人を迎え、一緒に夕食を摂るのが好きだった。クロワッセまで人が会いに来ると、それは彼にとって嬉しいことで、彼は目に見える心のこもった喜びを抱いて、前もって接待の準備をするのだった。彼はよく食べる人であり、繊細な食事、美味しいものを愛していた。
人が大いに話題にしたあの悲しい人間嫌いは、彼にとって生来のものではなく、愚かさについての恒常的な確認から少しずつ深まっていったのだった。というのも彼の魂はそもそも陽気で、彼の心は寛大な感情のほとばしりに溢れていたのである。つまり彼は生きることを愛していたし、十分に、誠実に、人がフランス的気質を持って生きる時にそうであるように生きた。フランス的気質の持ち主にとっては、ドイツ人やイギリス人のように、憂鬱が嘆かわしい様子を見せることは決してないのである。
それに、人生を愛するためには、長く続く力強い情熱があれば十分ではないだろうか? 彼にはその情熱があり、それを死ぬまで持ちつづけた。子どもの頃から、心を文芸に捧げたのであり、決してそれを取り返すことがなかった。自分の存在をこの並外れて高揚した愛情の内に使い、恋人たちのように熱っぽい夜を過ごし、興奮に震え、消耗させる激しい愛の時間を過ごした後に、疲労に気が遠くなっては、毎朝、目覚めの時から、最愛の者への欲求に捕われるのだった。
ついにある日、彼は打ち倒されて、仕事机の足元に倒れた。いつでも情念に食い尽くされる偉大な情熱家たちが殺されるように、〈文学〉に殺されたのである。
ギィ・ド・モーパッサン
ギュスターヴ・フロベール、『ジョルジュ・サンド宛書簡』、シャルパンティエ書店、1884年、62-86頁。
Guy de Maupassant, Chroniques, préface d'Hubert Juin, U. G. E., coll. « 10/18 », 1980, t. III, p. 109-124.
ギュスターヴ・フロベール、『ジョルジュ・サンド宛書簡』、シャルパンティエ書店、1884年、62-86頁。
Guy de Maupassant, Chroniques, préface d'Hubert Juin, U. G. E., coll. « 10/18 », 1980, t. III, p. 109-124.
訳注
(1) この段落から「~互いを理解しあうのである。」までは評論「繊細さ」(『ジル・ブラース』、1883年12月25日の再録。)
(2) Alfred de Musset (1810-1857) : ロマン派の詩人・小説家。繊細な感性と憂鬱な気分に満ちた抒情詩は、後代の青年たちに大きな影響を及ぼした。モーパッサンも十代の一時期にミュッセの詩に傾倒した。
(3) Charles Baudelaire (1821-1867) : 詩人。『悪の花』(1857) でフランス近代詩に革新をもたらした。また、未完の散文詩集『パリの憂鬱』を遺し、象徴派以降の世代に大きな影響を与えた。
(4) Charles Marie Leconte de Lisle (1818-1894) : 詩人。『古代詩集』(1852)、『夷狄詩集』(1862) などを発表し、高踏派の中心的存在となった。
(5) この段落の途中より、「~力強さのみに由来することとなるだろう。」まで、評論「私生活のギュスターヴ・フロベール」(『新評論』誌、1881年1月1日)の再録。
(6) この段落から「~フォルムの内に閉じ込めるのである。」は、評論「一年前の思い出」(『ゴーロワ』紙、1880年8月23日)を大幅に加筆・推敲したものとなっている。
(7) Gustave Flaubert, op. cit., p. 30.
(8) この段落、および次の段落から「~場を占めることはできなかった。」まで、評論「書簡に見るギュスタ―ヴ・フロベール」(『ゴーロワ』紙、1880年9月6日)の再録(推敲あり)。
(9) この一文、および次の段落から「~最も興味深いものの一つだった。」までは、改めて評論「書簡に見るギュスタ―ヴ・フロベール」(『ゴーロワ』紙、1880年9月6日)の再録だが、大きく追加・推敲されている。
(10) 1872年10月5日付、レオニー・ブレンヌ宛書簡。
(11) Georges Pouchet (1833-1894):比較解剖学者。
(12) Marcellin Berthelot (1827-1907):化学者、科学史家、政治家。1865年よりコレージュ・ド・フランスで有機化学を講じた。
(13) この段落から、「~に客を迎えていたのである。」まで、再び、評論「一年前の思い出」(『ゴーロワ』紙、1880年8月23日)を大幅に加筆・推敲したものとなっている。
(14) Hippolyte Taine (1828-1893) 思想家、歴史家。実証哲学を継承し、科学的手法を文芸研究に取り入れた。『英国文学史』(1864-1869)、『知性について』(1870)、『芸術哲学』 (1882)、『現代フランスの起源』 (1875-1893)。
(15) Frédéric Baudry (1818-1885):言語学者。『言語科学とその現状』(1864)。
(16) Claudius Popelin (1825-1892):画家、七宝細工師、詩人。
(17) Philippe Burty (1830-1890):美術批評家。1872年雑誌記事に「ジャポニスム」の語を始めて用いた。日本美術の普及に貢献すると同時に、マネ等の印象派美術を擁護した。
(18) Alphonse Daudet (1840-1897) : 小説家。故郷プロヴァンス地方を叙情豊かに描いた。『風車小屋だより』(1866)、『プチ・ショーズ』(1868)、『陽気なタルタラン』(1872) など。
(19) Paul Alexis (1847-1901) : 小説家。『メダンの夕べ』寄稿者の一人。後にジャーナリズムの場で活躍する。
(20) この段落のゾラの描写は、評論『エミール・ゾラ』(カンタン書店、1883年)の再録。
(21) Georges Charpentier (1846-1905):出版者。ゾラと親しく、自然主義文学者の作品の出版を多く手掛けた。
(22) Catulle Mendès (1841-1909) 詩人、小説家、劇作家。1860年、『ルヴュ・ファンテジスト』を創刊し、パルナス派の詩人として出発。詩集に『フィロメラ』(1863)等。オペラ『グゥエンドリン』 (1886) (エマニュエル・シャブリエが音楽)、『イゾリーヌ』(1888) (アンドレ・メサジェが音楽)でも成功を博した。ワグナーを擁護したことでも有名。1866年、ジュディット・ゴーチエ Judith Gautier (1845-1917) と結婚。後に離婚。
(23) Émile Bergerat (1845-1923):詩人、小説家、劇作家。『地方の女たち』(1871)、『アンゲランド』(1884)、『凌辱』(1885)、『カリバンの書』(1887)等。1872年、エステル・ゴーチエEstelle Gautier (1848-1914)と結婚。
(24) José-Maria de Heredia (1842-1905) : キューバ出身の詩人。高踏派の一人で、唯一の詩集『戦利品』(1893) がある。1894年アカデミー会員に選出。
(25) Joris-Karl Huysmans (1848-1907) : 小説家。『メダンの夕べ』寄稿者の一人。自然主義から後に神秘主義に転じた。『さかしま』(1884)、『彼方』(1891)、『大伽藍』(1898)。
(26) Léon Hennique (1850-1935) : 小説家。『メダンの夕べ』寄稿者の一人。ゾラと親しかった。『エベール氏の災難』(1883)、『ある性格』(1889) 等。
(27) Henry Céard (1851-1924) : 小説家、批評家。『メダンの夕べ』寄稿者の一人。『美しい一日』(1881) 等。
(28) Léon Cladel (1835-1892):小説家。『滑稽な殉教、パリ小説』(1862)、『浮浪者』(1873) 等。
(29) Gustave Toudouze (1847-1904) 小説家。『オクターヴ、19世紀パリ生活情景』(1873)、『ランベル夫人』(1880)、『誘惑女、パリ小説』(1883) 他多数。評論に『アルベール・ヴォルフ、パリの時評文家の物語』(1883)。
(30) Edmond de Goncourt (1822-1896) : 小説家。弟ジュールと二人で(後に一人で)小説を執筆した。『ジェルミニー・ラセルトゥー』(1865)、『娼婦エリザ』(1877) など。美術収集家として日本美術にも詳しかった。長年記した日記が名高い。
(31) La Princesse Mathilde (1820-1904):ナポレオン一世の弟ジェロームの娘。1841年に結婚するが早くに離婚。パリでサロンを開き多くの文人を招いた。
(32) « La femme est la désolation du justice. » : プルードン『革命と教会における正義について』(1858)、第11部「恋愛と結婚 続」の中の言葉。Pierre Joseph Proudhon, De la justice dans la révolution et dans l'Église, « Onzième étude. Amour et mariage. Suite », Chapitre premier, XIII. (Œuvres complètes de P. J. Proudhon, tome, XXIV, Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven, 1869, p. 158.)
